September.24,2007 夏の終わりに読んだホラーじかけのミステリ
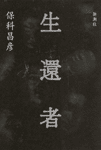 秩父の山中の旅館が、おりからの台風で土砂崩れにあい、泊り客や従業員が生き埋めにあう。数日後に救出されるが生き残ったのは七人だけ。主人公は図書館員の男。同僚の女性と泊まりに行って自分だけが助かった。傷が癒えぬままに日常を過ごしていると、生き残った人々が次々に死んでいくという事件が起きる。男の元にも、いたずら電話ともとれる不気味な電話がひっきりなしにかかってくる。自分では覚えのないミスを図書館の職員たちから指摘され、いったい何事が起こっているのか不安になっていく。
秩父の山中の旅館が、おりからの台風で土砂崩れにあい、泊り客や従業員が生き埋めにあう。数日後に救出されるが生き残ったのは七人だけ。主人公は図書館員の男。同僚の女性と泊まりに行って自分だけが助かった。傷が癒えぬままに日常を過ごしていると、生き残った人々が次々に死んでいくという事件が起きる。男の元にも、いたずら電話ともとれる不気味な電話がひっきりなしにかかってくる。自分では覚えのないミスを図書館の職員たちから指摘され、いったい何事が起こっているのか不安になっていく。
著者はホラー作家なのだそうだが、これはホラー仕立ての本格ミステリだとの書評を目にして読み出したのだが、なかなか結末が読めない。これ、ひょっとしてただのホラーなんじゃないかと思い、ゾッとしはじめたころ真相が明かされる。作者の巧妙に仕掛けたトリックでうまくミスリードがなされていて読者の思い込みを誘う手法がわかったときは、「う〜ん、やられた」と思った。さて犯人はと読み進めていくと、ひょっとしてという思いもサラリとかわし、なるほどという犯人像が現れる。ただ、動機はというと「それはないだろう、いかになんでも」という思いがする。これだったらもうホラーで押し通しちゃったほうがよかったかも。でも、そうなったら本当に怖い話だし、私は最初から手に取らなかったかもしれない。
September.15,2007 もうひとつの意外な結末
 映画『キサラギ』は、今年公開された日本映画の中でも屈指の出来だと思う。なんといっても脚本がよくできている。もうこの脚本が書き上がった時点で、面白くならないわけがないというくらい、できが良かった。もっとも中には、これは芝居向けの脚本で映画向きではないと言っている人もいる。確かにひとつの部屋の中だけで進行する話だから、そういう意見も出てくるのだろう。でもまあ、芝居を映画にしたりしている映画もあるんだから、これもありじゃないだろうか。それに、芝居向きというわれる脚本を精一杯、映画という表現手段で描いているという気がする。
映画『キサラギ』は、今年公開された日本映画の中でも屈指の出来だと思う。なんといっても脚本がよくできている。もうこの脚本が書き上がった時点で、面白くならないわけがないというくらい、できが良かった。もっとも中には、これは芝居向けの脚本で映画向きではないと言っている人もいる。確かにひとつの部屋の中だけで進行する話だから、そういう意見も出てくるのだろう。でもまあ、芝居を映画にしたりしている映画もあるんだから、これもありじゃないだろうか。それに、芝居向きというわれる脚本を精一杯、映画という表現手段で描いているという気がする。
いつか、芝居として上演されるのではないかという噂の中、これを落語にした噺家が現れた。落語ファンならご存知、柳家喬太郎だ。今年、7月7日の中野ZERO小ホールで行われた『柳家喬太郎独演会 みっちりナイト 七夕+愛+ミステリアス=』で口演された。このときのチケットは私は手に入らず諦めてしまっていたのだが、直前になって都合で行かれなくなった人からチケットが回ってきたと思ったら、もうそのときは他の予定を入れてしまっていたのだ。他の予定をキャンセルして喬太郎を聴きに行くか、それとも予定通りにするか散々迷ったあげく、泣く泣くこのチケットを別の人物に転売することにした。いつかまた喬太郎版『如月』を聴く機会はあるに違いない。そして、その機会はナマの落語ではなく活字という媒体で、あっけなく素早く実現した。『別冊文藝春秋9月号』。この号に喬太郎が口演したものを採録して、自身が加筆修正したものが掲載されたのだ。
映画では、あまり売れないアイドルが自殺した一周忌にインターネットのファン・サイトの呼びかけで、彼女を偲ぶ会が開かれ、ファンだったという男が集ってくる話だった。喬太郎は思い切って時代を江戸時代にして、アイドルを花魁という設定に置き換えた。さて、ここからが喬太郎の腕の見せ所である。元になった映画は現代だったので、インターネット、電話、写真、アロマキャンドルなど話の進行に重要な道具が出てくる。いったいどうしたのか、それが私の最大の関心事。活字になったものを一読してわかったのは、喬太郎は元になった映画を参考にして、まったく別物を作り上げたという事だった。そこが喬太郎らしい。映画をそのまま落語にしても成立しないし面白くもならないと決断したに違いない。映画版でのアイドルの死の謎と、集ってきた男たちの彼女との関係といっ部分は大鉈を振るってバッサリと切って捨ててしまった。どこかユーモラスだった映画の雰囲気も捨てて、喬太郎はまったく美人ではないのに、なぜか絵草子で見ただけの如月花魁に惹かれてしまった男達をしみじみと描き出す。そして、ラスト。喬太郎は映画にもなかった大ドンデン返しを用意している。これはもう本当にあっと驚くもので、おそらく映画『キサラギ』を観てからの人の方がよりびっくりするだろう。これはもう、映画『キサラギ』のストーリーを追って落語にする作業を放棄したところからでなくては生まれなかった結末で、これこそまさに落ちのある話、落語というものになっていたのだ。喬太郎、恐るべし。
September.8,2007 1ページで3回笑える
 『復讐はお好き?』(Skinny Dip)は、カール・ハイアセン(Carl Hiasen)の作品の中でも、今までで一番デキがいいのではないかという気がする。前作の『ロックンロール・ウィドウ』(Basket Case)は、なぜか初めて一人称小説になっていて、内容もこれはまずいなあと思っていたのが、今回は大復活を果たしてくれた。例によってテーマは環境問題だが、声高に掲げるわけでもなく、ギャグ連発の中で、自然と問題意識を読者に植え付けるという落ち着きを感じた。
『復讐はお好き?』(Skinny Dip)は、カール・ハイアセン(Carl Hiasen)の作品の中でも、今までで一番デキがいいのではないかという気がする。前作の『ロックンロール・ウィドウ』(Basket Case)は、なぜか初めて一人称小説になっていて、内容もこれはまずいなあと思っていたのが、今回は大復活を果たしてくれた。例によってテーマは環境問題だが、声高に掲げるわけでもなく、ギャグ連発の中で、自然と問題意識を読者に植え付けるという落ち着きを感じた。
いや、ハイアセンの笑いは、ますますエスカレートしていて、本作では、そうですね、1ページで3回笑えるくらいのギャグが詰まっている。電車の中で読んでいると何回も吹き出して恥ずかしい思いをすること間違い無し。例によってマトモな登場人物はほとんど登場しない。夫に海に投げ捨てられるヒロイン、ジョーイの個性も笑えるが、その犯人たる夫チャズの存在は大笑いだ。医者になりたかったのに果たせずに生物学者になり、海シラミ(そんなのいるの?)の研究で学位を得たという人物。汚染物質を垂れ流す農園主からの以来で水質検査のデータを改竄する悪徳学者。生物学者のくせに生物が大嫌いという設定だ。その農園主から派遣されたボディガード、トゥールが凄い。全身毛むくじゃらでおよそ人間とは思われない容貌。実際、動物と間違われて猟銃で撃たれて尻に銃弾が入っている。その痛みで痛み止めの膏薬を求めて病院に忍び込み、患者から剥がして張り付けるという行動を続けている。なぜか十字架マニアで、墓地で十字架を見つけると引っこ抜いて自分の庭に差すのが趣味。それでいて妙にモラリストで、両親は大切にするものだとか、殺した生物は食べなくてはならないとか主張する。事件を捜査する刑事はニシキヘビを飼っていて、そのヘビが逃げ出して騒ぎになる。などなど、、あいかわらずヘンな人物ばかりが出てくる。
ハイアセンという作家は、ストーリー・テラーというよりは、おかしな人物を創造しては、それを動かすことで笑いを作り出すタイプの人のようで、あいかわらずモタモタした話が続いていく。それでも、今回締まった印象を受けるのは、殺されかけた妻の夫への復讐譚という設定が良かったからだろう。それと怪人トゥーイと死期が近い老婦人モーリーンとの挿話がいい。
しばらく毎回のように出てきていたスキンクは、今回は小さな役回り。スキンクに頼らなくなったのはマンネリ打破か。でも、いったいスキンクはどうなってしまうのだろう。だんだん老化現象なのか頭はおかしくなっていっているみたいだし・・・・・。
このコーナーの表紙に戻る
ふりだしに戻る
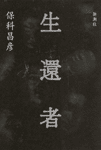 秩父の山中の旅館が、おりからの台風で土砂崩れにあい、泊り客や従業員が生き埋めにあう。数日後に救出されるが生き残ったのは七人だけ。主人公は図書館員の男。同僚の女性と泊まりに行って自分だけが助かった。傷が癒えぬままに日常を過ごしていると、生き残った人々が次々に死んでいくという事件が起きる。男の元にも、いたずら電話ともとれる不気味な電話がひっきりなしにかかってくる。自分では覚えのないミスを図書館の職員たちから指摘され、いったい何事が起こっているのか不安になっていく。
秩父の山中の旅館が、おりからの台風で土砂崩れにあい、泊り客や従業員が生き埋めにあう。数日後に救出されるが生き残ったのは七人だけ。主人公は図書館員の男。同僚の女性と泊まりに行って自分だけが助かった。傷が癒えぬままに日常を過ごしていると、生き残った人々が次々に死んでいくという事件が起きる。男の元にも、いたずら電話ともとれる不気味な電話がひっきりなしにかかってくる。自分では覚えのないミスを図書館の職員たちから指摘され、いったい何事が起こっているのか不安になっていく。 映画『キサラギ』は、今年公開された日本映画の中でも屈指の出来だと思う。なんといっても脚本がよくできている。もうこの脚本が書き上がった時点で、面白くならないわけがないというくらい、できが良かった。もっとも中には、これは芝居向けの脚本で映画向きではないと言っている人もいる。確かにひとつの部屋の中だけで進行する話だから、そういう意見も出てくるのだろう。でもまあ、芝居を映画にしたりしている映画もあるんだから、これもありじゃないだろうか。それに、芝居向きというわれる脚本を精一杯、映画という表現手段で描いているという気がする。
映画『キサラギ』は、今年公開された日本映画の中でも屈指の出来だと思う。なんといっても脚本がよくできている。もうこの脚本が書き上がった時点で、面白くならないわけがないというくらい、できが良かった。もっとも中には、これは芝居向けの脚本で映画向きではないと言っている人もいる。確かにひとつの部屋の中だけで進行する話だから、そういう意見も出てくるのだろう。でもまあ、芝居を映画にしたりしている映画もあるんだから、これもありじゃないだろうか。それに、芝居向きというわれる脚本を精一杯、映画という表現手段で描いているという気がする。 『復讐はお好き?』(Skinny Dip)は、カール・ハイアセン(Carl Hiasen)の作品の中でも、今までで一番デキがいいのではないかという気がする。前作の『ロックンロール・ウィドウ』(Basket Case)は、なぜか初めて一人称小説になっていて、内容もこれはまずいなあと思っていたのが、今回は大復活を果たしてくれた。例によってテーマは環境問題だが、声高に掲げるわけでもなく、ギャグ連発の中で、自然と問題意識を読者に植え付けるという落ち着きを感じた。
『復讐はお好き?』(Skinny Dip)は、カール・ハイアセン(Carl Hiasen)の作品の中でも、今までで一番デキがいいのではないかという気がする。前作の『ロックンロール・ウィドウ』(Basket Case)は、なぜか初めて一人称小説になっていて、内容もこれはまずいなあと思っていたのが、今回は大復活を果たしてくれた。例によってテーマは環境問題だが、声高に掲げるわけでもなく、ギャグ連発の中で、自然と問題意識を読者に植え付けるという落ち着きを感じた。