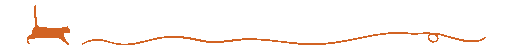
アームチェア
| 浅田次郎『霞町物語』(講談社文庫) 入院中は、自分が持ち込んだ本、見舞客が差し入れてくださった本でベッドの脇の棚は本棚と化してしまい、ちょっとした図書館状態になってしまった。普段なかなか読書時間が取れなかったから、入院中は読書三昧ができるぞと、能天気にも内心喜んでいたのだが、実際に入院生活に突入してみると、やはり一日中、本を読んでいるというのは飽きてくるという事が、すぐにわかった。 約二ヶ月間の入院生活で読めるだけは読んだが、それでも半分は読み残してしまった。いよいよ退院が近付いて、残った本は家に持って帰ってもらっていたのだが、「さあ、今週早々にも退院だ」と踏んだ週始め。一冊だけ残して、あとは全部家に持ち帰ってもらってしまった。ところが担当医は「大事をとって今週末まで入院してもらって様子をみましょう」と言い出すではないか。がっかりしたのは言うまでもないが、手元にもう読む本が無い。 そこで思いついたのが、病棟のロビー。ここには、どうやら入院していた患者さんが読み終えて置いて行ったらしい本が置いてある。ここから一冊拝借しようかと思って選んだのが、浅田次郎の連作短編集『霞町物語』。麻布の写真館の息子を主人公に、三代の家族が同居した写真館を舞台にした話が八篇。『小説現代』に発表したものを発表順に並べているのだが、一編目の『霞町物語』で、大学受験を翌年に控えた主人公の秋の話から始まり、最初のうちは少しずつ、そのちょっと前の話、そこからまたちょっと前の話と遡っていって、五編目の『雛の花』から、その次の『遺影』は主人公が小学生のときにまで遡る。 どの話も面白くてよく出来ているが、私のベストは『雛の花』。主人公の祖母が出てくる話は、これ一編なのだが、この祖母の話が実によく出来ていて、これ一本では惜しいくらい。小学生の主人公を歌舞伎に連れていく導入部の面白さと、そこで仕込む伏線の見事さ。歌舞伎座を出てからの、ある種ほろ苦さ。なにより鉄火肌の江戸っ子という祖母の造形が見事だ。そして驚きの展開。これは都合上書いてしまうが、祖母は自分が喉頭癌だと知り、ひとりで築地の国立癌センターに入院してしまう。同じ喉頭癌で入院中の私の驚きを、お察しいただけるだろうか。 ここに癌に対する悲壮感はまったくない。これを病院のベッドで読んでいたときに、この祖母の粋な行動の数々に、「これこそ江戸っ子よ!」と心の中で快哉を叫んだものだが、最後には涙が止まらなくなって困った。もし、この本を読んだことが無い人でも、この一編だけは是非読んで欲しい。歌舞伎好きの人、江戸っ子だと自任している人、小説好きの人、そして癌の宣告を受けた人。必ずや感銘を受けるだろうから。 主人公が高校生のころという設定の時期は、どうやら1960年代後半。実際にあったディスコ、青山のパルスピードから最初の短編は始まるが、解説でそのパルスピードでDJをやっていた人の解説があって、これも楽しい。 「私はいつも、始めにオーティス・レディングの『ドック・オブ・ザ・ベイ』をかけた。次にオーティスのバックバンドをやっていたバーケイズの『ソウル・フィンガー』、アーチー・ベル&ザ・ドレルズの『タイトゥン・アップ』あたりで盛り上げていき、クライマックスはやはりオーティスの『トライ・ア・リトル・テンダーネス』で決める。(中略)そしてこれもお決まりのパーシー・スレッジ『男が女を愛する時』でチークタイムに入るのだった」 この解説を読んで、「うんうん」とうなずける人は、ほぼ同世代だろう。『雛の花』『遺影』を挟んだあとの六篇は、その時代の高校生の話。私はこの主人公みたいに、夜のディスコに繰り出すわけでもなく、進学校の生徒だったわけでもないが、『すいばれ』あたりの、ひと夏の思い出とかは、「ああ、そういえば私には、あんな経験があったなあ」と思いだすこともあり、今から思えば恥ずかしくもある青春の日々を思い出したり。 退院してから最後の二編を読み終えて、さて、ロビーから持って来てしまったが、これは返しにいかなくてはいけないのだろうかと迷っている。読み終えた自分の本の何冊かはロビーに置いてきたんだから、まあ、いいのかな・・・と。 2012年1月26日記 静かなお喋り 2012年1月26日 このコーナーの表紙に戻る |
 ふりだしに戻る
ふりだしに戻る