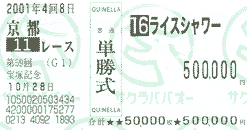
November.25,2001 競馬ファンのロマンをかき立てるコメディ
11月18日 『サクラパパオー』 (PARCO劇場)
明治座を出て、今度は渋谷へ直行。競馬を題材にしたコメディと聞いて見る気になって前売りを買っておいたのだ。ラッパ屋が以前に上演して好評だったものをキャストを大幅に入れ替えて大劇場での公演に持ち込んだ。
『サクラパパオー』は競馬場を舞台にした8人の人物のドラマだ。競馬が初めてだという彼女を連れてきたカップル。冴えない中年男。長年競馬をやり続けてきたオバサン。会社の金を使い込んでしまって何とか競馬で取り戻そうとしている男。謎のセクシーな美女。悪質なコーチ屋など。競馬はドラマであるとはよく言ったもので、競馬そのものもドラマであると同時に、そこへ集まる人の数だけのドラマが存在する。
私が初めて競馬場に足を運んだのはそんなに昔のことではない。10年くらい前だったろうか。競馬はそれほどの経験もなかったが、人に誘われて行ってみて緑の芝を走る競走馬の姿に圧倒されてしまった。それからだった。一時期、ものに憑かれたように競馬場に足を運んでいたことがある。中山競馬場、東京競馬場だけではあきたらず、中京競馬場、阪神競馬場にまで行ったことがある。最初は単に競走馬が走る姿に夢中だった私も、ギャンブルとしての競馬にはまっていった。競馬場はやはり鉄火場でもあるのだ。1レースから始めて、ずーっと負けっぱなしで、最終レースに帰りの電車賃だけ残して有り金すべて賭けたこともあった。やがて徐々に熱が冷め始め、今や『G1十番勝負』のコーナーを見ていただければわかるのだが、あのコーナーは漫才のコーナーになってしまった。
グランドホテル形式で進んでいたドラマが、中段から登場人物たちが一体となっていく。メインレースに出場するサクラパパオーの名前が出るあたりから、一瞬展開が読めそうになった。サクラパパオーに勝負をかけた登場人物たちが、一攫千金を得るか、大損をするかという展開だと誰しもが思うだろう。こういう展開はいままで映画でさんざんやられてきた。しかし、しかし、この『サクラパパオー』は誰も予想もつかない展開が待っているんですね。まさに大穴。はあー、こういう手があったのかと感心してしまった。これは詳しく書いてしまうのはルール違反だろうから書かないでおく。しかし、競馬ファンならばサクラパパオーのこういう結末、何回も目にしているはずだ。これも予想のつかないドラマなのだ。
芝居の途中で馬券が舞台上に大量に散る場面がある。帰り際にその馬券を何枚か拾ってきた。これがその一枚。ほかにもメジロパーマーだのビワハヤヒデだのテンポイントだの、競馬ファンが見たら喜びそうな名前の単勝馬券があったが、みんな偽物。JRAのマークがよく見ると・・・。
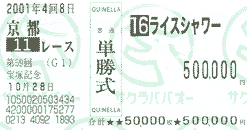
November.23,2001 時間来るまで明治座見物
11月18日 杉良太郎公演『遠山の金さん〜江戸のわらじ唄』 (明治座)
明治座の招待券をもらうことがよくある。大抵ひとにあげてしまうのだが、今月は久しぶりに行ってみることにした。古今亭志ん駒さんと古今亭志ん五さんが出ているからだ。もっともこの日は午後に一本もうひとつの芝居を見に行く予定があり、ギリギリまで明治座にいてから脱け出す計画。まあ『遠山の金さん』なら、いつでもパターンは同じだから最後まで見なくてもストーリーは最初から知れている。
履物問屋の主人が殺される。南町奉行は犯人として、この問屋にわらじを収めているわらじ職人(石橋正次)を逮捕するが、金さん(杉良太郎)はこれに疑問を感じる。なぜ疑問に思ったかというと、この職人が作ったわらじが実に丁寧な仕事をしているのを見たからで、こんないい仕事をする人物が人殺しをするわけがないと思ったから―――って、これは強引なんじゃないの? まあいいか・・・お決まりなんだから、そういう細かいところは気にしないでおこう。
こちらのお目当てはふたりの噺家さんというヘンな客だから、第一部は主に話の起こりを説明するのに費やされ、町人役のおふたりのコメディー演技が少ないのにやや不満。別にコメディーではないのだから、そんな場面が少ないのはしょーがないか。コメディー的な要素で盛り上がるのが第二部のアタマ。葉山葉子にほのかな恋心をつのらせる志ん駒が、黒紋付の格好で彼女の家に行きプロポーズをしようとするのだが、打ち明ける前に彼女は金さんに惚れていると告げられてしまう場面。もっとも葉山葉子がとても跳ねた演技で、志ん駒さんは食われちゃったかなあ。これに続く、裏口での金さんと同心(高松しげお)とのやりとりを盗み聞きしようとする志ん駒、志ん五らの演技は、寄席で演っている落語の登場人物そのままの可笑しさ。
このあと、わらじ職人の無実を証明しようと南町奉行の面々を現場に呼んでの実地検証で、不自然なところを指摘してみせるところでも、ふたりの噺家さんはいい演技をしていた。さあ、このあといよいよお白州でのクライマックスとなり面白くなるところではございましたが、ちょーど時間になってしまいました。第三部の歌謡ショウを楽しみにしている杉様ファンのおばさまで一杯の明治座をあとにしたのでございます。―――なんだか、いいところで終わっちゃう講談みたいだね。
November.20 前から聴きたかった『バールのようなもの』
11月17日 志の輔らくごのごらく (国立演芸場)
春にもあった、国立演芸場と立川志の輔という組み合わせの企画の2回目。志の輔が二席演って、ほかに色物が入る。
前座はいつものように立川志の吉。「ちゃんこ鍋を食べに行ったら、後ろで食べていた子供が言っていました。『お相撲さんのお肉って美味しいね』」 ネタは『寿限無』。頑張ってね。
女流講談の神田茜は薄オレンジとでもいうのだろうか、きれいな着物を着て出てきた。林家彦いちと5年前に結婚して出産。私はこの人の高座をまだ知らない。どんな講談を聴かせてくれるのか楽しみにしていた。この日のネタは『小さな恋のメロンディ』と題された新作講談。ある会社のオフィス、26歳のOLが15歳だったときに好きだった卓球部のカレのことを思い出している。カレのことはある事件がきっかけで嫌いになってしまうのだが・・・。一方現在の彼女は結婚適齢期を迎え、少々焦りが・・・。と言っても出会いのチャンスがあるわけでもなく、社長ひとり社員ひとりの小さな会社の身。いつしか社長のことが好きになってしまう・・・。いかにも女性らしい切り口の噺で、私などはついて行けないところがあるなあ。女性なら喜びそうな噺かもしれない。
志の輔一席目。まずは茜のフォロー。結婚して子供をもうけていたので、四年ぶりの高座であることを説明し、「子供を持つと芸人も落ちついてくるものなのですが、どんどん面白くなっている。芸人としてはいいのですが、主婦としては・・・心配になる」 飛行機のマクラをいくつかして、ネタに入る。
熊さんが、物知りだというご隠居にものを尋ねている。へえー、これは『やかん』かなあ、それとも『つる』かなあと思いながら聞いていると、質問の内容が面白いのだ。「エイのヒレってどこまでがヒレなんですか?」 「切っていって『痛い!』ってとこまでがヒレだな」 「爪みたいなものですか」 「深く切りすぎたものは、これをフカヒレと言ってな」 「キリンってなぜ首が長いんですか?」 「あんなに高いところに首があるんだ、繋ぐしかないだろう」 「蚊に刺されるとどうして痒いんですか?」 「痒くなかったらどこを掻いていいかわからないだろう。教えてくれてるんだ。親切だろ」 「新聞で死体とか遺体とか書いてありますよね。死体なんですか遺体なんですか」 「・・・・・それはまあ、二つあるんだよ」 「二つ? どういうことで?」 「男と女だな」 「男と女?」 「男がシタイで、女がイタイ・・・」 隣の席に座っていた小学生らしい男の子と女の子がゲラゲラ笑っている。ほっ、本当に分っているのだろうか・・・!
この噺、何かと思ったら清水義範の『バールのようなもの』だった。志の輔は、清水義範に自由に自分の作品を落語にしていいという許可を貰っているらしい。この人で『緑の窓口』を聴いたこともある。『バールのようなもの』は演っているとは聞いていたが、ぶつかったのは初めて。これは『オール読物94年5月号』に載ったもので、当時、志の輔がパーソナリティーとしてやっていたラジオ番組で、『バールのようなもの』を読んだという話をしていたのを憶えている。あのあと、これを本当に落語にしたとは驚きだ。なにしろ原作はエッセイ風のもので、これを落語にという発想が私には見当がつかなかったのだ。ようやく耳にして納得し、感心してしまった。前半のご隠居にものを尋ねるところは、まったくの志の輔の創作。中段の[バールのようなもの]論議は、原作を元に会話体で作りなおし、そして最後のオチに向かっていくところは、これまた落語として成立させるためのオリジナル。なあるほど、志の輔はうまく清水義範の原作を換骨奪胎して自分のものにしている。というよりも、もうこれは原作を離れたオリジナルのものと言ってもいいだろう。志の輔の代表作としてこの『バールのようなもの』を挙げる人がいるが、その理由がようやく分った気がする。
仲入り後は、岡田修の津軽三味線。暗く照明を落とし、ミラーボールで雪が降る様を表現した舞台で、息を飲むような『津軽じょんがら節』を演奏してみせた。
一曲終えて発せられた岡田修の声は、その風貌に似合わず優しい声だった。「三味線を二本用意してありますが、別にダテではないんです。こちらの三味線は音色がまったく違うんです」と脇に立ててあったもう一本の三味線を弾いてみせる。「どう違うかというと、皮の張りがちがうんです」。なるほど、今まで弾いていたものよりも皮をゆるく張っているために、音が柔らかくなっている。「こういうのは、我々の仲間では音が出ていないというのです。本来の津軽三味線は限界まで皮を張っています。ですが七十年くらい前、私たちの先輩は雪の降る中、門づけをして弾いていたものでございます。三味線の皮は湿気に弱くて、強く張っていて湿気に当たると翌日は破けてしまいます。それで昔はゆるく皮を張っていたものでございました。この音色を聞いて昔の先輩を忘れてはならないと思っています」 沁み入るような岡田の言葉を聞いて、次の曲はこのゆるく張った三味線で、『津軽音頭』。普通の津軽三味線がダイナミックな音色だとすると、こちらはどこか優しい音色がする。目をつぶって聴いていると、雪景色の北国の情景が頭の中に浮かんできた。
最後の三曲目は一世風靡SEPIAのために書いたというダンスナンバー『嵐』。太鼓と三味線、あとおそらくシンセサイザーで作られたカラオケをバックに、現代的な音楽と津軽三味線の融合に見事に成功した、燃えてくるような面白さだ。
志の輔二席目は『ねずみ』。志の輔の『ねずみ』は今年の正月以来。あのときも感じたことなのだが、志の輔の『ねずみ』は以前のものと変化しているのではないだろうか。以前に志の輔の演っていたものは、もっと人情噺的な色合いが濃く、もっと重いものだったような気がする。それが、ずっと軽い噺になり、笑いの要素が強くなっている。甚五郎の扱いも、名人のくせに酒飲みでぐうたら、それでいて人の前に出るのを嫌うというのではなく、明るく活発な様子になってきている。志の輔の中で何があったのだろう。この明るく軽い『ねずみ』、私はだんだん好きになってきた。
November.17,2001 泣きに走らない純正爆笑コメディ
11月11日 『バッド・ニュース☆グッド・タイミング』 (PARCO劇場)
去年の夏の『オケピ!』以来の三谷幸喜の芝居だ。その千秋楽のチケットを手に入れ、この日をどんなに待ったことか! そこへ小学校時代のクラス会の通知。今回はわけあってどうしても出席しないといけない事情がある。しかしこの日を逃すと三谷の芝居を見逃してしまうことになる。クラス会は12時から。三谷の芝居は2時から。少しだけなら顔を出せないこともない。会場になっている帝国ホテルのスカイラウンジで担任だった先生やクラスメイトと1時間ほど歓談してから、会場を脱け出して渋谷へ向かう。旧友たちには「ちょっと仕事がらみで用があって」とウソをついてしまったが、どうしても見たかったのだよ、この芝居。ごめんね。
前説で出演者のひとり、八嶋智人が出てくる。オープニング・ジョークをかまして笑わせたあとはお馴染み、携帯電話の注意だ。芝居の会場では様々な方法でこの注意をやっているが、今回の方法はかなり効果的だと言える。切り忘れによる開演中の呼び出し音を、まず100%無くせる。「音の出るもの、携帯電話、PHS、ポケット・ベル・・・こんなのいまだに持っている人っているんですかねえ・・・・」 目の前にいた男性を標的にして、「今一度、お確かめください・・・・今一度お確かめください・・・・」 本当に切れているか確かめるまでジッと待っている。「はい、プリーズ・リピート・ミー。もうケータイは鳴らさない」 男性が繰り返すと、「はい、ご褒美です」とみかんをひとつ手渡した。
「では、予告編に続きまして本編をお楽しみください」と八嶋が引っ込むと幕があがる。舞台の照明は消えたまま、ところどころでパッ、パッ、パッとスポットが当たる。スポットが当たったところにいる役者が芝居のワンシーンを演じてみせる。中でどこからか矢が飛んできて役者に当たるという演技をした人がいたと記憶しているのだが、このあとの本編に入ったらそんなシーンはなかった。これは三谷一流のジョークなんだろうなあ。
舞台に照明が点き、芝居が始まる。ここはホテルのスカイラウンジという設定なのだろう。たった今脱け出してきてしまったクラス会のことが頭をよぎる。ごめんね、みんな。上手はエレベーターホール。下手がラウンジ。奥に上の階に上がる大きな階段がある。今回は上手の前の方の席だった人はちょっと気の毒だったかもしれない。ちよっと見にくかったと思う。
生瀬勝久と沢口靖子のカップルは、きょうが結婚式の当日。新婦は落ちついているように見えるが、落ちつかないのが新郎。一生に一度の晴れ舞台を前に緊張しているのかと思い気や、とんでもない事態にうろたえているのだ。式はこれから2時間後。しかしこの結婚の話、新郎の父にも新婦の父にもまだ伝えていないのだ。というのもふたりの父は10年前に喧嘩別れした漫才コンビの息子と娘だからだ。新郎は両方の父親には内緒で式をあげてしまおうと思っていたのだが、新婦が両方の父親を呼んだというのである。それも結婚式ということは伏せておいて。2時間後に犬猿の仲である漫才コンビの息子と娘が結婚するのを説得して、ふたりを式に参列させてしまおうというのである。それはどう考えても無理だと思うのだが、これが沢口靖子という能天気なキャラクターが巻き起こしてしまった騒動の始まりとなる。
生瀬勝久の父は伊東四朗。コンビ解散後も、いろいろな相方と漫才を演ってきたのだが、どうもうまくいかない。喧嘩別れしたとはいえ、昔の相方が一番良かったと今でも思っている。一方の沢口靖子の父親は角野卓造。漫才コンビを解消後、市会議員として活躍しているが、近く選挙を前にして心に動揺があるようだ。ふたりに説明してくれと新婦は新郎に任せっきり。頭はもう式のことしかないようだ。式のことしかないといえば新婦の母親の久野綾希子も式に着る衣装と化粧に余念がなく、父親たちを説得することなど頭になく、自分のことしか考えていない。
バラバラに呼んだはずのふたりの父親は、何回かのすれ違いの笑いのあとに10年ぶりの再会を果たす。なんでここに呼ばれたのかは知る由もない。よーく事情を知っているのは、ここのラウンジのウエイターの八嶋智人。客の話などには関心を持ってはいけない立場なのだが、よーく耳をすましているらしく、すべてを知っている。いわば客席の客の代表的な立場にある。このウエイターのリアクションは観客の反応でもある。見終わって一番印象に残っているのがこの人で、得な役まわりだなあと思うが、三谷が書いた『古畑任三郎』の第3シリーズでも、このウエイター役で出いたから、三谷はこのキャラクターをどうしても使いたくなったのだろう。
かつての漫才コンビが揃ったところで話が進むかと思いきや、ここで話は伊東四朗の一方的な[勘違い] [思いこみ]で、また笑いが大きくなる。結婚式などということは端から頭にない。上の階では何やら宴会の準備が進んでいるようだ。しかもなぜか伊東と角野用に揃いの衣装まで用意されている。「ははあ、コンビを再結成させようという、それぞれの息子と娘の計画なんだな」と思い込んでしまう。それでは、時間もないことだからネタをさらっておこうと、ふたりが稽古を始める。これが、娘の父親と娘の婚約者のネタだから話がややこしくなる。「娘はやらん!」と叫ぶ角野に、ホテルの結婚コーディネーターが驚き、「私も一緒に参加させてください」と割り込んでくる。漫才をやっているのに何で知らない人が入ってトリオにならなきゃいけないんだと思いながらも、ここで繰り広げられるコント風の部分は、腹を抱えて笑ってしまった。伊東四朗やはりコントの達人だなと思う。伊東が中心になって笑いを引き出していく。
新聞の批評で、笑わすだけのためのわざとらしい脚本だという文章を見かけたが、まさに三谷のこの芝居はそれを目的にして書かれているものだから仕方ない。そういうコメディって今まで日本になかったんだもの。ともするとこのコメディ、ラストで泣かせる藤山寛美調のものになりかねない。それをあくまでコメディだけで押しきった三谷幸喜の腕に、私は惜しみない拍手を送りたいと思う。
千秋楽に行ったのは訳がある。きっと三谷がカーテンコールで出てくると思ったからだ。案の定出てきました。2回目のカーテンコールで一番上手に立った。八嶋に「あっちにいけ」とばかりにエレベーターホール側に突き飛ばされながらも、中央に戻ってきていた。それと芝居の途中にも出てきた。エレペーターが開くと、新郎の友人達が乗っているという場面。中から三谷が出てきて、新郎と踊りだし、エレベーターに再び乗ろうとするともうエレベーターは行ってしまっている。慌てて新郎に付き添われて階段を駆け上がっていく。伊東四朗が、絶妙の間で「なんだ、あのヒゲの濃い男は?」
November.14,2001 幻の落語家では終わらないでよ、円龍さん!
11月10日 三遊亭円龍の会 (浅草ゴロゴロ会館)
インターネットで[三遊亭円龍]を検索してみたら、[幻の落語家]という表現が出てきた。そう、この人の高座を見るというのはけっこう難しい。なにしろ寄席では見かけないのだ。円生の弟子だったのだが別に円楽一門ではなく、落語協会の所属である。円生が協会を脱退したときには、師匠に反対した立場にいた。「師匠、それは敗者の論理です」と言って円生を怒らせたという話も残っている。それがなぜなんだろう、寄席に出ていない。
円龍さんの方は私のことを憶えていないかも知れないが、私と円龍さんはその昔、円龍さんがまだ旭生という名前で二ツ目だったときに逢っている。私の十歳以上年上のイトコが円龍さんの高校時代の同級生で、二ツ目時代に開いた落語会を何回か見に行っている。その後、円龍になってからも何回か聴きに行っているし、円龍さんの著書『円龍の下町味めぐり』の取材で私の店に立ち寄られたときに、話をしたこともある。
そんな円龍さんがCDを出した。『風流艶くらべ』(キングレコード)という艶笑小噺を集めたものである。それを記念して三年ぶりに落語会を開いた。三年ぶりというのも驚きだったが、このあと今度はいつ見ることが出来るか分からない。昼間に叔父の葬式があったのだが、葬式から帰って喪服から普段着に着替えて、急いで浅草へ向かう。
前座で出来たのは、橘ノ百円なるひと。前座? 前座にしては歳がいっている。何者なのだろう。『寄席芸人年鑑』にも出ていない。「商船大学を出た友人が教えてくれたんですがね、豪華客船に乗ったら非常脱出用のボートがいくつあるかチェックしておけというんです。『どうして?』と訊いたら、『あのボート、十人と乗れない。救命(九名)ボート』」 ネタは『道灌』。
円龍一席目。「志ん朝師匠が亡くなったことは大変な損害でした。六十三歳。二十年早いですよ。私の師匠の円生は名人といわれていました。噺も上手いし、その噺の数もたいへんに多い人でした。しかし、滑稽噺、長屋ものには弱かった。そこへいくと志ん朝さんは何でもできた」 自分の師匠を差し置いちゃっていいのかなあとも思うが、確かに円生は重々しい感じがする。それはそれで円生落語として完成されたもので、世の中にはいろんなタイプの落語があっていいんだと思う。同じ噺でも演る人によって、こんなにも違って聞こえるのかと思うのが、落語を聴く楽しみなのだから。
志ん朝さんに『鰻の幇間』の稽古をつけてもらった時のエピソードなどを語り、ネタの『大久保彦左衛門』へ。これは大久保彦左衛門のエピソードを集めてきて語ったもの。なかなか興味深い。よく調べたなあと感心しながら聴いていたのだが、ひとつ注文をつけさせていただくと、調べたものを一度自分の中で消化して落語として出すというのがまだ不足しているような気がした。ナマの資料をそのまま出されてしまったような印象が残るのだ。彦左衛門のエピソードはそれだけでも大変に面白かったのだが、さらにプラス・アルファがあったほうが聴く側としてはより楽しいと思うのだ。
一席終えた円龍自ら百円、舞台監督と高座の台の片付け。このあとは奇術の前田奈美の出番だ。超ミニスカートで踊りながらスカーフの中から鳩を出してみせたりする。踊りがうまくて、足がきれいな人だなあと思っていたら、なんとこの人西野バレー団で16年も踊ったのちにマジッシャンになったそうだ。どうりでスタイルがよくて踊りも上手いはずだ。最後は上着を脱いでスカートを外すと下はレオタード姿。すっかり悩殺されてのマジック。これなら何演っても騙されちゃいそう。
円龍二席目は、立ったままでの『世界の小噺』と題したジョーク集。CDにも『江戸艶ばなし』というのが入っていたが、彦六、円生、森繁らの物真似で、当人が好んで演っていたという艶笑小噺を演ってみせた。この人は器用な人で物真似が本当に上手い。以前はテレビに出て、誰も演ることのない人のようなレアな物真似を演ってみせていたものだ。談志の物真似ジョークが良かった。「談志好みのジョークっていうのはね、ひとひねりもふたひねりもしたのなんです。わからない奴はわからなくていいってやつ」 ほんと、談志好みのジョークって確かに面白いんだけど爆笑には至らないんだよね。
そのあとは、どこで集めてきたのか世界の小噺をズラーッと並べていく。アメリカ、中国、ロシア、アラブ、フランス、スペイン、ユダヤ・・・・・。ただ、ちょっと日本人を前に分かりにくいのも多い。イギリスのジョークなどは、イングランド人、アイルランド人、スコットランド人のそれぞれの性格が分かっていないと何のことだか分からない。ズラーッと並べられた小噺はどれも面白かったのだが、ただ並べられただけでは次第に頭が疲れてきてしまった。これも一席目の『大久保彦左衛門』と同じなのだが、集めてきた小噺を一旦自分の中で消化して、構成を立てなおして語れなかったものだろうか? 最初の物真似小噺が面白かっただけに、後半がややダレてきてしまった。
仲入りのあとは、櫻川七好(しちこう)さんという幇間さんのお座敷芸。「私の芸は酔っ払って見るもんなんです。こういうところで素面のお客さんの前で演るもんじゃないんですが・・・」と、まずは都々逸。♪久しぶりだな何から先に お燗つけよか 帯とこか・・・・・・。拍手がくると「うれしいですね、我々、座敷で演っても拍手はきませんからね」とうれしそう。
なにしろお座敷で酔っ払い相手に演る芸だけあって、ちょっとネットには書けないネタもある。それを知りたい人は、やっぱり七好さんをお座敷に呼ぶしかないかなあ。『深川』を踊ってみせ、あてぶりの『かっぽれ』。落語ファンにとって楽しかったのは屏風芸。なんと『たいこ腹』を屏風を使った一人芝居で演ってみせてくれた。屏風の陰にお旦がいるという設定で、屏風に引きずり込まれて腹に針を刺される幇間を見事に演じきった。
円龍のトリのネタは『淀五郎』。前回(と言っても3年前)に『中村仲蔵』を演ったそうで、そのつながりでこの演目となったという。つまり、中村仲蔵が功なり名を遂げて立派な役者になったあと、若い淀五郎という役者にアドバイスをするというつながりがある話なのだ。これは私も円生でも聴いた記憶がある。円龍は円生のものを引き継いだ感があって、なかなかのデキだった。力演である。さすがに円生が弟子にとっただけあって、いい筋をしていると思う。ただし・・・ただしなのだ。家に帰ってよく考えてみると、この『淀五郎』、何かが足りないような気がしてならない。上手さは認めるものの、客を噺の中に力ずくで引きずり込んでいくような迫力が不足しているような気がしてならないのだ。それが、客の前であまり噺を演らないことから来ているとしたら・・・・と、ふと思ってしまったのだが違うだろうか。
円龍さんに何があって寄席に出ないのか(あるいは出られないのか?)知らないが、もっと人の前で頻繁に落語を演って欲しい。だって本当にいいものを持っている人なんだもの。円生直系の弟子としているんだから、円生から学んだ落語の真髄を伝えていって欲しいのだ。落語は演者と客がいてこそ成り立つもの。誰かが言っていたが、客がいないで落語を演ってもそれはひとり言でしかない。今回はちょっといつもとは違って噺家さんに酷なことを書いてしまったかもしれない。でもこれは私が円龍さんにもっと人前で落語を演って欲しいという願いからのことだ。せっかく『淀五郎』という芸道ものをトリネタに持ってきた円龍さんだ。芸人の凄まじさを、是非見せて欲しい。
November.5,2001 スミさん、いつまでもお元気で!
11月3日 国立演芸場十一月上席昼の部
玉川スミ芸能生活80周年記念公演
「来ないとブツよ!」 おん歳83歳になられる玉川スミさんから、こんなことを高座の上から言われたら、行かないわけにいかない。とは言え、玉川スミ芸能生活八十周年記念公演は、浅草演芸ホールで、十月の余一会昼夜二回興行。平日は仕事で身動きがとれない身としては、スミねえさんには悪いが行くことができない。ところが国立演芸場でも11月上席では玉川スミの記念公演をやってくれるではないか! ねえさん、こっちにはいくからぶたないでねー。
というわけで行ってきました、国立演芸場。窓口でチケットを買おうとして並んでいて驚いた。窓口のおねーさんがお客さんに「大分混雑していますので、もう残りの席が少なくなっています。よく捜して座ってください」と言っている。浅草演芸ホールでも昼夜超満員だったっていうから、やっぱり人気なんだなあ。私の番が回ってきて千円札を二枚窓口に入れると、おねーさん、何やら内線電話を入れている。電話を切ると、「申し訳ありませんが、もう立ち見になってしまいました」 やったー! なんといういいタイミングなのだろう。国立演芸場は立ち見だと入場料を割り引いてくれるのだ。1900円の入場料が1200円になるのだ。「いいです、いいです。立ち見でもいいです」 800円のオツリをもらい、客席へ。もう前座の春風亭昇七が『子ほめ』を演っている。下手前方の壁にもたれて、もう大分慣れてきて落ちついた感のある話ぶりを楽しむ。頑張ってね。
昇七の噺が終わると、一旦幕が下りた。噺を終えたばかりの昇七が幕の前に出てきて、「たいへん混んでまいりました。隣の座席に荷物などを置かれている方、あとからお出での方のために席を空けてくださるようにお願いします」と言った途端に最前列に座っていた若い女性の隣の席の荷物がどかされた。すかさず、その席へ。わーい、1200円で最前列。もうけもうけ。
幕が上がると、まずは玉川スミの獅子舞からだ。後ろ足を曲芸の翁家喜楽が務め、前足を玉川スミが演る。女性には教えないという方針だったのを、無理に頼み込んで教わったのだという。客席からご祝儀が届けられ、スミねえさん、お礼を言って投げキッス。
コントD51は休演。トラは新山ひでや・やすこの漫才。ひでや「昭和四十年の秋でした。私は玉川スミねえさんに弟子入りしようと思ってました。四十四年前ですよ。そのときはすれ違いで弟子入りできなかったんですが、そのときの師匠は綺麗だったですね」 やすこ「その時はじゃないでしょ、失礼な! その時もと言いなさいよ!」 漫才の方はいつものタクシードライバーのネタ。「元お寺さんだった運転手がいましたよ」 「何で分かったの?」 「『お客さん、ボチボチ着きますよ』って言ってた」 こんなのがドンドン出てくる。「千葉県出身の運転手さん、ボウソウするんですよ」 「栃木県出身の運転手さん、運転がイマイチ」 「津軽出身の運転手さん、メーターを倒して『よーし、いくぞう』」 ところどころでトチると相手の突っ込みが入るのが夫婦漫才らしい可笑しみが出て楽しい。どこまでがネタでどこまでかトチリなのか分からないのだが。
目がチカチカするようなまっ黄色の着物を着た古今亭寿輔が出てくると、客席がそれだけで笑いに包まれる。「何も喋らないうちに何で笑うんですかねえ」 ネタは『地獄めぐり』だ。「さあさあ亡者ども、早く船に乗らねえか!」と演っているうちにも、続々とお客さんが入ってくる。「ほうらほらほら、あとから来たお客さん、早く座れってんだ。演りにくくってしょーがねえ」 そう言われてもねえ、もう客席は空席なんてないよ。見世物小屋では、幽霊のキックボクシング(?)やら骸骨のストリップなんてやっているし、高橋お伝のおでん屋さんやら、坂本九のスキヤキ屋やら、田中角栄のピーナツ屋やらがズラーッと並んでいる。笑った笑った。この人、面白いねえ。
奇術の松旭斎すみえ。レコードの色が変わる手品、スカーフ、トランプの手品などを演ってみせたあと、「玉川スミさん、83歳ですってね。寄席も高齢化。私、いくつに見えます? 近くに座っている人には無理だけど、遠ーくの方に座ってる方、28くらいに見えるでしょ。本当は38。芸歴は48年」 いったいいくつなんだあ?
春乃ピーチクと玉川スミの即興漫才。「化粧に何時間かかるんですか?」 「十五分・・・何笑ってるのよ!」 「十五分? どうみたって三時間はかかるでしょ」 「何てこと言うのよ!」 「真後ろから見ると、16歳くらいに見えますね。それが斜め後ろからだと28歳。真横からだと45。真正面に回ると・・・ああ、なるほどな―――っと」 即興とは思えない絶妙の間だ。「野球なんて見ます?」 「あれはイヤだね。アタシはお灸」 「長島さん引退しちゃいましたね。すべてを水にながしましょう―――ってね」 「あとはハラの底まで考えて」 「今年はスワローズの優勝でしたね」 「来年から歌が変わるの知ってます?」 「えっ! 『東京音頭』じゃなくなるの?」 「そう、来年からは『花笠音頭』 ♪めでためでたーのー 若松監督」 このへんは打ち合わせありそうだなあ。
仲入りを挟んで、口上だ。幕が上がると下手から柳亭痴楽、古今亭寿輔、翁家喜楽、玉川スミ、春乃ピーチク、春風亭小柳枝の順で頭を下げている。司会は痴楽。「本来なら、司会のものは目上のものがする決まりになっておりますが、玉川スミさんよりも先輩のものが誰もいません。僭越ながら、私が司会を勤めさせていただきます。まずは寿輔より挨拶を願います。黒紋付を三十年以上着ていないそうで、出してきたらシワだらけ」 さっきの黄色い着物から黒紋付に着替えている。「地獄から戻ったチンドン屋でございます。黒紋付を着ると、どうしたことかお客さんを見下したような気になってしまう」 さっきの寿輔とは大違いの印象。寿輔、似合ってるよ、その黒紋付。「長生きといえば、きんさん、ぎんさん。スミ師匠はその上を行ってますよ。金だの銀だのじゃない。この人の入れ歯はダイヤモンド。まず107歳以上は長生きするはずです。長生きの人はみんな似ています。体がみんなチビ・・・・いや、小さな人が多い」
喜楽はさっきの獅子舞について語る。「20年前、スミ師匠の芸能生活60周年のときに、是非教えてくれと言われましてね、それまで女性に教えたことはない。それでも、どうしてもということで・・・なにしろ大先輩ですからね。20年前はお若かったですから完璧でした。そのあとの70周年では若くなくなっておられましたから、70%くらいのデキ。今回また稽古したんですが、20年前のものを30%くらいの長さに削ってのものになりました。さすがにキツいんですよ」
ピーチクはいまから20年前に、寄席でアトの出番の人が到着せず穴が空きそうになったとき、スミさんとふたりで突然に高座に上がり、即興で漫才をやったときの話をした。それから、ときどきふたりで即興漫才を演るようになったとのこと。「あるときね、スミさんが私にネクタイをくれたんですよ。それからわたしらの仲はネクタイ(肉体)関係」
小柳枝。「つつしんで口上を申し上げます。本来ですと師匠の柳昇がここにおりますところでございますが、師匠このところ出費が多かったようで、他の儲かる仕事に行ってしまったようでございます。成り代わりまして、弟子の私が出てまいりました。スミ師匠、芸歴80年。初高座が3歳。えっ? 15歳でございますか?」 ハハハハハ、初舞台が15だったら今95? スミさん、ジロッと睨むけど目が笑っているよー。「小さな体に大きな芸。いつまでも生き残って芸を見せてください」と締めて、その小柳枝の音頭で三本締め。
口上が終わって再び幕が上がると、浪曲の用意がされている。なんと65年ぶりにやる浪曲だという。昔は女浪曲師として活躍していたこともあるという。玉川という名前はその名残なのかと思ったら、当時の名前は東家女楽燕(あずまやおんならくえん)とのこと。演目が『一本刀土俵入り』。歌い出したその声の張りのあること! 獅子舞は六十の手習いで憶えたというだけあって、ちょっと・・・という感じではあったが、こちらは65年のブランクを感じさせないなかなかのもの。「しがねえ男の土俵入りでござんす!」とミエを切って一旦引っ込むと、藤色の着物に早代わり。カラオケが流れて三波春夫の『一本刀土俵入り』を熱唱するサービスぶり。これがまた上手いんだ! ♪化粧回しは夢の夢 今じゃカッパに三度笠・・・・・・
「上野駅のミルクスタンドで『おばちゃん、牛乳ちょーだい』と言って牛乳をもらったら、それが美味しくないんですよ。『おばちゃん、これ何? 何の乳? 牛乳にしてはやけに水っぽいね』と言ったら、『じゃあ、水牛でしょ』だって」。柳亭痴楽と聞いて思い浮かべるのは、どうしてもまだまだ先代のイメージ。痴楽つづり方教室の印象が強烈に残ってしまっている。今の痴楽が先代のイメージを超えるのは並大抵のことではないだろう。そんな痴楽のこの日の演目は『先代一代記』。病に倒れて二十年。八年前に亡くなった先代の話を、先代の物真似を交えて語ってくれた。
春風亭小柳枝が蕎麦のマクラを振っている。こりゃ『そば清』かなあと思っていたら、今度は昔の時の数え方を詳しく解説し始める。こりゃあ『時そば』しかないやね。始めの旨い方の蕎麦屋での食いっぷりがいい。蕎麦屋を商売にして毎日食べている私でも食べたくなっちゃうもの! そして後半の不味い蕎麦屋だ。しっぽくの丼を持ち上げた男、「たまには洗ってるの? ひびが入っているぞ! フチが欠けてる。ありゃ、ここも欠けてる。かけそばってやつだね。いい丼だねえ、ノコギリにも使える」 「なんでダシとってるの? ゴキブリなんか出てくるんじゃないの?」 「蕎麦ってのは細くなきゃいけない。そこへいくとお前んとこは・・・・・・・太いねえ、よく太っちゃったねえ。ただの太り方じゃないねえ。むくんでるぞ、こりゃ。お蕎麦の脚気だね」 しっぽくの中に入っているチクワを捜す仕種が長ーい! 「チクワ、入ってないよ! これだけの空間だよ、さっきから大々的に捜査しているのに見つからない・・・・・・ああ、あったあった! 丼のミミかと思ったよ」 不味い蕎麦なら不味い蕎麦なりに、食べてみたいなあと思わせるこの話、当店としては大歓迎!
さあ、玉川スミのトリの時間だ。「人生わずか五十年という時代に生まれて、あっという間に八十三歳」 いつものように ♪久しぶりだねお前の三味で と歌って三味線をひとしきり弾いてみせる。「終わったんだよ! おとっつぁん、一番前に座ってたら、一番先に拍手しなきゃダメじゃないか!」 場内割れんばかりの拍手に包まれる。この標的にされたおじさんもうれしそう。 ♪この袖で ぶってやりたい もし届くなら 今宵の二人にゃ 邪魔な月
「始めのころの松づくしというのは五本くらいの扇子でやっていたものです。でもそれじゃあつまらない。すこしづつ増やしていって百二十本で演ったこともあります。でも、今じゃそんなに持てない」 この日の扇子の数は九十本。人が、その上でようやく立てるくらいの大きさの箱を五段積み上げて、その上にたくさんの扇子を背負ったスミさんが乗る。片足の指で扇子を挟んで片足立ちになってみせたり、小さな箱の上をグルリと回ってみせたり。なにしろ八十三歳の女性が演ることだ。見ていてヒヤヒヤしっぱなし。ところがご本人、いたって自信がおありのようだ。すべての演技が終わって深深と頭を下げるスミさんに、また割れんばかりの拍手。そこへ、さっき標的にされた最前列のおじさんが立ちあがり、ご祝儀袋をスミさんに手渡す。スミさん、満面の笑顔だ。
すごいものを見ちゃったなあ。老人が絶対にしてはいけないこと―――それは転ぶこと。弱くなっている老人の膝は、それで取り返しがつかなくなることが多い。杖をついて、ようやっとの思いで歩いている老人のなんと多いことか。スミさん、体に気をつけて、いつまでもその粋な毒舌を聞かせてくださいな。