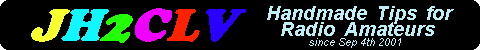
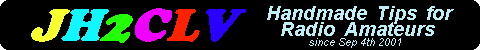

|
ゼンハイザーの超指向性マイクMKH-416シリーズは、2025年で発売から今年50周年を迎えるらしい。スタジオのブームに吊り下げて役者のセリフを追ったり、屋外の自然音の収録にもその姿をよく見る。もう50年も経ったのかと思うと感慨深い。その昔はRCA/BK-5Bだったが、隔世の感があった。 ところで、MKH-416/816シリーズには末尾にP又はTの文字を付けて、MKH-416Pは48Vファンタム(Phantom)、MKH-416Tは12V/ABファンタム(Tonader)とする製品が存在する。一般的にはファンタムと聞くとほぼ48Vなので、その中にABファンタムマイクが混在すると話が厄介になる。そのままでは使えない。 先日どうしてもMKH-416Tを48V系ファンタムと共存させなければいけない事態が発生したため、簡易的に48Vファンタムから12V/ABファンタムへの変換器を製作してみた。T1のDC磁化が懸念されるが聴感では分からない。 音源はクラシック系の女性ボーカルで、これをPAしてピアノとバイオリンとのバランスをとると言うもの。手持ちや仕込みマイクは使いたくないとのことで、ややオフ気味でもそれらしい収音が行え、ハウリングマージンの稼げる超指向マイクの選択となった。写真はその様子。 なおファンタム電源についてはAbout 48V Phantom & AB-12V Power for Condencer Microphonesとして拙作HP内で記している。 |
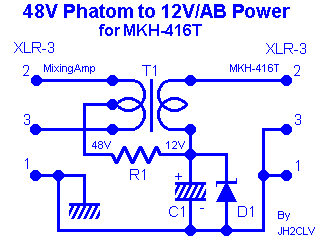
|
ミキサーが供給するファンタム電源のパワーは、メーカーによって異なるので、ここでは一例として記している。また48Vファンタム電源は、チャンネル毎、複数チャンネルのグループ、全チャンネルなど、供給方法もミキサーやメーカーよって様々だ。 今回はやや急場しのぎ的な感が強いので、極力簡単で手持ち部品で対応できる回路とした。左図がそれで、入出力にXLR3タイプのコネクタをオスメスで配し、間に1:1のマイクトランスを挿入。ミキサー側のトランス1次側CT(センタータップ)よりR1を経由し、C1(ケミコン)とD1(12Vツェナーダイオード)で12Vを生成する。この1Vをトランス2次側のコールド側に供給し、ホット側を出力させる。 AB方式のファンタムは、マイク電源と音声が重畳され、かつコールド側は接地される不平衡回路である。したがってこの装置の挿入場所は、なるべくMKH-416Tの近くが好ましく、ミキサ側の近くへの挿入はノイズを拾い易い。 |

|
写真はアイデアルのP-5アルミケースへ実装した様子。XLRコネクタは基板用実装してあった小型のモノを取り外して利用。トランスはタムラ製600Ω(CT):1.2kΩ。その他CR類等を含め手持ちをかき集めた。 図には電圧を記してあるが、ツェナーダイオードは無い状態で、R1=1.2kΩの時にMKH-416Tを接続すると電圧は12.4V程度に収まった。ミキサー側の回路(電源Z)が様々だと思うので、心配な場合はやはりD1を挿入し電圧を飛び出しを押えた方が無難だろう。ただしダイオード自身でノイズを発生する場合もあるので、特性は可聴域外を含めてチェックした方が良い。 普段は殆ど出番は無いと思うのだが、不平衡側をギターアンプの不平衡出力へ繋げばダイレクトボックスとしても使えそうだ。 |
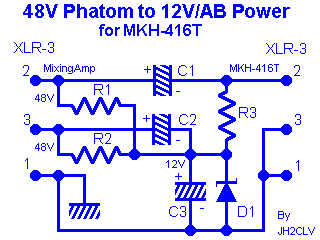
|
磁気シールドされたトランスは大きく高価とか、前述のDC磁器飽和が気になるとかの向きには、左図のトランスレス回路が良いかも知れない。 XLR3のオスメス弾丸に組み込んだ製品は、トランスは使わず、この回路の様に抵抗R1/R2により48Vを導き、R3で分圧して平滑するか、もしくはMKH-416を負荷した時に12V付近に電圧が落ち着く量にR1/R2値を決めているのかも知れない。ご存知の方、ご教示下さい!。 平衡ラインのコールド側をC3経由で接地しているが、直接接地しても良い。チップ部品で基板上にまとめてしまえば、2平方cm程度には収まってしまうだろうから、鉄砲玉にも組み込み易い。 |