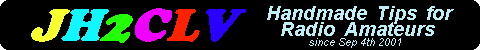
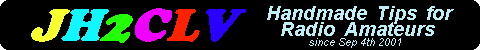

|
�ɖ�̑��c�|���J�����̑����L�тė����B���낻��S�}�_���J�~�L���̏o�����\�z�����̂ŁA�̍����̊Ď����Ƃ����Ղ��悤�ɑ�������n�߂��B���p�������A�א�̋��Ԃ������p���Ă��邽��29������31���܂Ŋ|�����Ă��܂����B31���͉J���~��o���A�v���U��ɍ��H�p�̑�����ɂȂ����B�ɖ�̐����͖̎��ӂ݂̂�29���Ɋ���グ���B30���͓���������o�������A�̖肪�傫�����߁A���ǑS�ʊ���ɂȂ����B������31���͐����Ŏc���Ă����̊ԂƁA����܂łɊ���c����(�Y�ꂽ)����������S�Ă̍�Ƃ��I�������B �ʐ^�͊��������ɓ]�����������@�B�n���h���o�[���ŁA�茳�ɃX���b�g�����o�[������B�����Ԃ̑�����ł́A���������߂č�Ƃ���ƍ���ɂ߂邽�߁A�������č�Ƃ���`���̂��Ă���B�I���}�E�X�͑������ɑ��ނ��肵�����c�|���J���̍����B�S�}�_���J�~�L�����o�����A�����ɂ���ė��ĎY������̂ŁA���̑O�Ƀ��X�s����SL��Z���ڂɍ����̎���֎U�z����B�ނ炪�U�����Ɏ�������ݐ�ہA���X�s���������ɂ���ƃR�����ƂȂ�B��N�̎��тł͈���30�C�ȏオ���ՏI�ƂȂ����B���N�̂��Ƃ����A�ނ�͑��c�|���J�����{���ɍD���ȗl���B |

|
���m���b�N�̒��q���p�����Ă��邩���J�Â֍s���̂��y���݂������B��肭�s�����̂܂I�_�܂ŏオ��ÉĂ̒����ɉ����悤�ƁA29��8���O�ɐ��J�Â��������B�ԈႢ�͂Ȃ��Ǝv���Ă��Ă��A���Ԃ��o�Ƃƌ��ɖ߂��Ă���o�������x�����Ă����B�`���[�N����A���R�C�������鋰�������2�E3��ʼn�����B�X���[��Ԃł����肵�ĉ���Ă���B�����ŏ��߂ă��b�^�@�I�ƐS�̒��řꂢ���B�\��ʂ�A���̂܂ܐ��J�Òi�X���̍ŏ�i(�I�_)�܂ŏ��B�����߂Ƀ^�P�m�R�|���ɗ��Ĉȗ����������A1�������炸�̊ԂɊ��̃c������|�̐L�т��X�S�C�B�e�L�g�E�ɑ|���Ȃ���ÉĂ̖܂ŒH�蒅���B�C�m�V�V���@�����@�ʂ̉����A�J���Ő�ɂȂ�y������Ă���̂��C�ɂȂ�B���X�ɃR���e�i2�t�������n�������A�����B��������1�`2�g���͗L�肻���Ȃ̂ŁA�Еz�ē����Ă��̓s�x���n�ɒʂ��\�肾�B �Ƃ���ʼn��~�I��ŘA�����I���������Ă���B���~��ɂ���M�q�̖ɑ傫�ȖI�����o���A�I�����������̂�҂��ăr�j�[���܂֗��Ƃ��B�����A�M�q�̖̃g�Q�⏬�}���ז�������̂Ő�ɐ藎�Ƃ��Ă����B��������I�Q�͐V���������ɏ悹�A������������Δ��ɓ�������B�ނ炪�V���ȏZ�܂��ƔF�������OK�����A����܂ł͐Â��Ɍ����B29����30���̒��߂��ɔ����B�I����O�ɌQ���Ԗ��I�̒��ō�Ƃ���̂̓X���������邪�A�ނ�ɑ���D�����͏�Ɉӎ����Ă���B |

|
�����A�����̃~�J�������3�w���\�����B���ꂪ�~�J�����̍ŏI���B����ȍ~�̓~�J���̉Ԃ����S�ɂȂ��Ȃ邽�߁A�x���܂ʼnԂ��������Δ������_���̓�{���̖I�ꂪ�~�J�������̍ŏI�ɂȂ����B�����Ƃ��A��{���͏b�Q�̉\���������A�I�������X�ɕ��ֈړ����n�߂Ă������߁A���͈��|�I�ɏ��Ȃ��B���ʂȂ�4�����J�n��6���J�n�ƂȂ�A���H���Ƃ��Ă���̃X�^�[�g�ƂȂ����B�������Ȃ��̂ŒZ���Ԃő��g��������A6��45�����ɂ͍�Ə�ō��o���Ă����B�ʐ^�͉��S�����@�֊|����O�̑��g�ŁA���W���i�C�t�Ő藎�Ƃ��Ă���l�q�B�~�J���̉Ԃ̌�̓��`�m�L��J���X�U���V���E�ւƃ~�c�o�`�͓]�킷��B����ȊO�̉Ԃ��炭�̂ŁA�~�J�����܂ߕS�Ԗ���ԂɂȂ邪�A���n�̎���͂�͂�J���X�U���V���E�B����̖�����7�`8�������B �Ƃ���ʼn��~�̂�瑁���̗t�ɁA�I���}�E�X�̗l�ȁu�������a�v���ڗ��B�t�悩��̔_��U�z�ł�����{���Ă���̂����c�B����Ŗ{���A���Z����(x750)�̃f�����t���A�u�����U�z�����B�����łɒx���̊��������̂����A���ق��Ċ���o�������Ɋ��������Ȃ����߂̍�킾�B�������n�ɂ��鑾�c�|���J����Z�g�J�ɂ͑S���������Ȃ��̂ɁA�ǂ����ĂȂ̂������ɒl���������B�������͐��o�Ȃ̂ŁA�_���ȏꍇ�͑��߂ɓE�ݎ��A�t���藎�Ƃ����Ƃɂ��Ă���B |
| �Ƃ���Ő��J�Ẫ��m���b�N�A5��5���ɃL���u���^�[�̐��ŕ������Ă������A�����O�A�ÉĂ̎��n�ŕ��������B�G���W���͂����邪�p��������~���Ă��܂��B�������߂̌��ۂ��Ĕ����Ă���c�L���u���^�[���R���𐁂��Ă��Ȃ��B�����Ă͋��Ȃ������̂��B��X�K�˂�S�_�@��X�̃I���W�ɑ��k������A���ʂ̃p�[�c�N���[�i�[����_�������ƌ����A�z�[���Z���^�[�ŃN���[�i�[�L���u���Ă����BHONDA1300����ɐ����Ƃ����b�ɂȂ����i�ŁA���̓Ɠ��̓�����45�N�o�������ł������ʼn��������B������L���u���^�[�̃t���[�g�o���u��m�Y�������t�����B����Ō��������������Ɍ��������A�ғ������J�Â̒����Ŏ~�܂��Ă��܂����B�����܂Ŏ��R�����ʼn���L���u���^�[���O���ƃr�b�N���A�R�����L���u���^�[������A�t���[�g��m�Y���W�̕��i���O���L���b�v�ɗ����ė����B���������I�B�f��ƃt���[�g�̃V���t�g�������ČŒ肷��r�X(3mm)���A�傫���ɂ݃V���t�g���O�ꂽ�͗l�c���N�̐U���̉e�����B�F�X�Ȉ��������d�Ȃ�A���܂��ܕs��Ƃ��Ď��ʂ���Ă��܂����Ɛ����B����Ō����ɕ��������c�Ǝv���邪�A�����ȍ~�̓��삪�y���݂��B���łɍŋߊÂ��Ȃ��Ă����u���[�L�������s�����B�F�X�Ɗy���܂��Ă���邱�̃G���W���ɂ́A���ՓI�ȃ��m�������Ă��܂��B��Ƃ̓��m���b�N�Ɋ��y�g���̉ב�ōs�������A�o���u�̈ꕔ���]����ב�̌��Ԃ���n��֗����B�͑��̒���T����鎞�̓��h�A���Ƃ������o�������̊����B����J�ɋ����������������B |

|

|
�����17���߂�JA0TU�^�L������d�b���������BJA-EME�S���~�[�e�B���O���Q���R����̋A�蓹�炵�����A���ƌ�O��܂ŗ���ꖾ���ߑO���ɂ��ז��������Ƃ����B��Ԏ����������A�l�̕�����������͍�낤�ƁA���������ƍH�[��������B�����߂ɗ���ꂽ���q����̑Ή��ł�����x�͕Еt���Ă��ėǂ������B10���߂��ɓd�b�������̂ŁA�����߂��܂ŗ����̂��Ǝv���ďo��ƁA���ɓ������Ă��čH�[�̓�����Ɋ���o���ꂽ�B���R����2�����Ă̌䓞���������B�����ĉ��Ɖ��l�������Ńr�b�N���B��������J�~�T�����o�|���钼�O�ŁA�b���v�w�Ԃ̃A�C�{�[�������������B���l���̓S�~�̎R�ɍ��f����Ă�����l�ŁA�������������Ȃ��ƒU�ߓ��m�řꂭ�B�^�L���Ƃ�30�N�߂����t�������ŁA�A�C�{�[������̂̓n���t�F�A���w�ǂ������B���[���ł͓���I�ɋZ�p�I�Ȃ����������Ē����Ă��邪�A��͂蒼�ڂ̕������e��������Ղ����Z���B���������ł͍�����������LDMOS-SSPA�����^3kW�d���ʼnғ������A�o�͂�R�A���x�̊m�F�ȂǂŘb������オ�����B�ʐ^�͖��������Œ�J�����̉f���c�U�炩���Ă那�I�B�I���}�E�X�̓~�[�e�B���O�ŕ��ꂽ�A�^�L�������LDMOS�ɂ��50MHz/kW-SSPA�B�^�o�R����ɁA�������̈�i���I�B�n���h���C�h���Ė{���ɑf���炵���B1���Ԓ��x�����������Ɋy�������Ԃ��߂������Ē������B |

|
�Q�n��3�j��Ƃƌ�a��̎��V���ŁA���܂�|���ʼn߂������ƂɂȂ����B������킹��̂͐����ȗ��̂��ƂŃJ�~�T���̓E�L�E�L�������B ���V���ƌ����A2006�N5��27���AFEDXP�ESDXRA�����~�[�e�B���O���s���A���j�A�A���v�̍u�����˗����ꂽ�BGU-74B(2m)��GU-84B(6m)�̃A���v�������ĕ�������������̂��Ƃ̗l���B�֓���OM�w�Ƃ̃A�C�{�[�������̌�̃n�����C�t�ɑ傫�ȉe����^���Ă��ꂽ���Ƃ��v���o���B�����͐É��P�g���C���ŁA�J�~�T����q�������͂���Ȃ��Ƃ�m��R���Ȃ��B ���č���́A�w��3�j�v�w�̃v���f���[�X�ŁA������͑S���̂��q�������B�������̒a���j������ƌ������ƂŁA�o���O�܂ŃJ�~�T���ƃv���[���g�̏����ɖz�������B���V���ɂ͋�������{�݂�X�܂��~�n���ɗ��̓I�ɓW�J����B�����͂��������Ȃ���y���݁A��̓R�e�[�W�Ŏ������ޗ���BBQ�A�����ĉJ�Ȃ������������[�U�[�V���[���y���݁A�Ō�ɒa����B�ʐ^��25���̌ߑO���ɗ��������AQUARIUM�̃v���N���ŎB�����W���ʐ^�B����ɂ��Ă��݂�ȗz�C�Ɍ�����B������A�O�����ɓ�������Ă��鑷���������Ȃ���A30�N���O��3�j�̎p���d�Ȃ�v�킸���ށB�����ƌ��C�ł��ė~�����B |

|
����P�g���C�����2008�N12��23���A�s���̃n�[�h�I�t����A�A�i���O�J�Z�b�g�̃f�W�^�C�Y�ړI�ōw������KENWOOD�̃~�j�R���|RXD-SG3MD�B���ÂŁ�2100�������B���̌�16�N�A����ɓ��삵�Ă�������N���A���ɓd��������Ȃ��Ȃ����B�J�Z�b�g�������f�W�^�C�Y����P�[�X�͍��ł����X����r���ɕ��Ă����BAC�R���Z���g�Ɍq���ƃI�����W�����v���_�����邪�A�d��SW�����Ă�ON(�O���[�������v�_��)�ɂȂ�Ȃ��B���������艽�Ƃ��������Ȃ���ƁA���N�ɂȂ��ĉ����̉��݊��ŗl�q�����邽�߂ɕ������n�߂Ă����B�A���v����ʂɁAC630A�ƌ����p�[�c�i���o�[�̃R���f���T�̏đ����B�d������ɂ͊W�Ȃ���Ȃ��Ǝv�����A���~�̖]�݂������đ�֕i�𓊓��B�������ɂ͕ω��Ȃ��B3�����ȏ���X�J���������ǂ��Ȃ����A�W�������܂Ƃ܂������Ԃ����҂ł��Ȃ����A�l�b�g�������ďC�������肢�ł������T���n�߂��B���Íw������m��ʊԂɎ��Ԃ��o�߂��Ă��܂������A������Ƃ����v�����ꂪ���艽�Ƃ��������������Ǝv���Ă���B�ʐ^�͉����̉��݊��ň�U�X���܂����Č��̏�Ԃɖ߂���RXD-SG3MD�B���̃V�A���F�����X�O�b�h���B |

|
�~�J�������̑�2�w��������A21���͗��ي��̔_��U�z���s���B�莝���_����ۂ��������Ƃ�O��ɋC�t���A������JA�z���Z���^�[���J��8������҂��Ĕ_����w���B6���߂��ɂ͊|���n�߂����������A���̎��ԃ��X�͎��ɑ傫���B1���d���̂��肪2���ɋy��ł��܂����B�_��̊�߂̓��X�s����x3000�A�i���Ax2000�A�G���_�C�t�@�[x600�A�t��x500�B�J�~�T���̎x�������A���~���c��ځ�(���H)���`���J���ɖ쁨���䑁���Ə����ɐi�ނ��A���䑁���̓r���Ŕ_��1500(500x3)���b�g�����s�����B500���b�g�����̒lj��w���ɑ��邪�A����16����������Ƃ�Ő�B��22���͖�����4�o���x�̉J�B����̎U�z�͊������Ǝv�����A���ʂ������Ă��Ȃ����Ƃ��肤�B�J�I�������ߌ�A�Ăѕ��䑁�������R�����~�쁨����G���K���g���U�z���ďI���B �Ƃ����21���AJA����J�����V��ň�ĎU�z�̎w�����������B�����A18���ȍ~�̎U�z�ł���Α�ւł���ƋL����A�䂪�Ƃł͍���̎U�z�ő����Ƃɂ����B���N�͍�N�ȏ�ɃJ�����V���ڗ��B���n�ʼnz�~�����J�����V�������A���N�̍앿���뜜�����B��N��Q�����ɍ������������A�����Đ��͗v���ӂ��B�ʐ^�͏`���J�̂͂�݁A�I���}�E�X�͈ɖ�̑��c�|���J���֎U�z���̗l�q�B |
| 5��20��7�������A������̊R�����ꂽ�B���߂̂���ł̓h�X���Ƌ���ȉ����������炵���B���������͒�����I�����̂��ߕ��ō�Ƃ����Ă����B�J�~�T���͂��̉����������l�Ȃ��Ƃ������Ă������A�����ɂ͕����炸�܂�������ȏɂȂ��Ă���Ƃ͎v�������Ȃ������B���ǂ��̎�����m�����̂͗[���ɍs��ꂽ�^�Ƃ̂��ʖ�̐Ȃ������B���̏��ʐ^�Ɏ��߂Ēu�����ƒ��H��Ɍ����`���Ă݂��B�m���ɃX�S�C�B�R�̖@�ʂ��A����Ă�����Џ@�|�ƈꏏ�ɁA�h�X���Ɛ�(�R�ؐ�)�܂ŗ������Ă���B�������̗v���ɂ��A�s�����Ή����Ă��邪�A�܂��|�ꂽ��|���������Ă���i�K�������B��J���~�����琅�̗��ꂪ���������̂Ń`�g�S�z���B���̍Œ����߂�K��炲��l�Ƃ��q��������A�R�����Ȃ���u��������I�v�ƙꂢ���B�G�b�Ǝv�����ʂɉ��Ɖ��ƊR�̒����Ɍ��\�ȑ傫���̃J���V�J�B������������ƌ��Ă���B���ꂽ��ɂ���ė���Ȃ�ė]���������D���Ȃ̂��ƎG�k���Ă���ƁA�ǂ���犋�̍���H�ׂĂ���l�q�B���x���H�Ŏ���ɖ߂��������狏��炵���B�J���V�J�͎R�ɓ���Ǝ��ܑ������邪�A�o�X�ʂ�̑Ί݂ɏo�v����Ȃ�āc�l�Ԃ̐��������߂Ɍ����Ă��A�l������Ȃ��k������n�͔ޓ��̐������Ȃ̂��B |

|

|
���N���ĊO�ɏo��ƁA�����v�[���Ƌk�̍��肪�Y���Ă���B���N�̓��n�̃~�J���̉Ԃ͗�N��蒷����������B�����̒J(���E�V�O�J����)�ł͖w�ǂ����ق��A�Ԃ̎����͏I�������̗l�Ɍ����邪�A���[�J�������ɂ���Ă͖����Ԃ�t���Ă���������B�܂������̒J(�Δ�����)�ł͕W��������\���ɉԂ��c���Ă���B�����A���̍�Ƃ�T���̉Ƒ��\��A�����ēV�C���������肷�邩��A�~�J�������̑�2�w�������ɂ��邩�͔Y�܂����B�ƌ������ƂŎ�Ɏ҂̃J�~�T���͍���20���̖̍�������B��4�����������Ƃ��n�߂邱�ƂɂȂ����B�Ԃ̊��Ԃ������A�V����܂��܂��������̂ŁA�O��̖̍�����1�T�Ԃ����~�c�o�`�B�͑����̓��������Ă��ꂽ�Ǝv���B���̌���~�J���̉Ԃ͎b�������A�~�c�o�`�͖����W�߂邾�낤���A�~���o�����ɂ��̂܂܂ɂ��Ēu�����ƂŁA�Ă̕S�Ԗ��ւ̔��f��A�~�c�o�`�B�̉c�݂̎x���ɂ��Ȃ���ƃJ�~�T���͍l���Ă���l���B���̗D�������~�c�o�`�B�Ƃ̋����Ɍq�����Ă���̂��낤�B�ʐ^��6���߂��A���̖I��̗l�q�B4���������Ƃ��n�߂Ă��A������I���̂�8�����B���̌㒩�H������Ə�Ŗ����ɓ��邪�A�J�~�T���͉��~�̖I�ꂩ�瑃�g������������A���H��14�����B���Ǎ�Ƃ��I������̂�16����������Ă����B |

|
�{�삵����ɉJ���~��A�c��ڂł͑����đ�������s�����B��n�ɎT�����z���엿�ɁA�����������ォ��W�J���邱�Ƃɂ����ʂ����҂��Ă���B�ƌ����Ă�����Ȃɂ��ꂢ�ɂ͎U��߂��Ȃ��̂ŁA�����͋C�����̖�肩�B���������Ă���ƁA�C�\�q���h���������~��ė��āA��������ɏo�Ă���~�~�Y�⒎�����ɂ��邩��ʔ����B������̓x�ɂ���ė��Ėڂ������̂Ŋ����̗l���B�ʐ^�͓c��ړ�����o�X�ʂ肩��B�������́B�l�ڂɐG���ꏊ�Ȃ̂ŁA������ɂ͗͂�����B �Ƃ���ŃI���}�E�X�B�F�l��N������͂����l�b�g�I�[�N�V�������ŃQ�b�g�����AELTEK���̓d��Flatpack2_48V_3.3kW_FE_RECT_HE�B�}���c�ʔ̂���M�{�V�[�q���͂����̂�AC200V���q���A����m�F�����Ă���l�q�B���j���ŏo�͐�����|����ƁA�Q�b�g����4��S�Ă����삵�z�b�Ƃ���B�o�͓d����4�䋤52.2V�ɒ�������Ă����B���̑傫����3.3kW������Ȃ�āA��̑O�Ȃ�M���ĖႦ�Ȃ����낤�B������96.5%�������Ėw�ǔM�ɂȂ�Ȃ��������Â��BIC-PW1��VL-1000�J�������ɂ��̗l�ȓd������������A���肪�ς���Ă��������m��Ȃ��B����1����g���ALDMOS��SSPA�����������Ɉڂ��v��ł��邪�A�ʂ����āB |

|
VL-1000�̎蓮�o���h�ؑւ����C�}�C�`�ǂ������炸�r���ɕ��Ă����B�C����蒼���ă}�j���A����ǂݒ�������A�l�b�g�����{�����Ēm�b��t�����BF_SET�t�́AVL-1000�����͐M��(50W���x�̃L�����A)����ƁA���̎��g�������m���Ď����I�Ƀo���h�ؑւ�������@�\�炵���B����̓A���v����(OPERATE)��Ԃł��X���[��Ԃł����삷��B�����t��������3�b���x�����`�����X�������̂Ńm���m�����Ă���ƃ`�����X���c�܂�������x�����Ηǂ��̂����BElecraft��KPA500�́A��Ƀo���h���m�@�\�������A�G�L�T�C�^�[���L�����A���o���Ώu���ɒǏ]����BSSB�ł�PTT�����������ŒǏ]����B�܂��o���h�֖ؑt���p�l���ɏo�Ă��邵�A�G�L�T�C�^�[�̃f�[�^�ł��A������B���������̌��ɂ�����ς��L�����̂��낤�A�o���h�ؑւ��̍l�������͂߂��`�g��蓹�����Ă��܂����B����ŁA�蓮�Ȃ���S�o���h�ւ̐ؑւ��\�ɂȂ�A�o���h���ɃX�y�b�N�ʂ�̏o�͂ł��邱�Ƃ����������B�ʐ^�͍H�[��IC-7300���G�L�T�C�^�[�ɂ��ăe�X�g���̗l�q�B�I���}�E�X��50MHz�ł̏�Ԃ�\������LCD�c50MHz�͏o��1kW���C�@�������B �Ƃ���ŁA�G�L�T�C�^�[�̃o���h�ؑւ��ɘA�����Ȃ��A���v�͖{���Ɏg����B���S�ʂł��ۑ�ƂȂ�B���̂��߁Aicom/CI-V��Yaesu/BCD�֕ϊ��������������x���Ői�߂Ă���B���ICT-Kuwa��LIF-59���g�킹�Ē������B����x�������X�g���X�̂Ȃ��o���h�ؑւ����������Ă���B |

|
�V�肪�o��O�̏t��Ɏ{�삵���������̂����A�m��\����N�x�ւ��̏���Ƃɉ����A�s�c�I��ً}���@�Ȃǂ����Ď���C�����Ȃ������B���Ԃ��o���Ă��C���U��A���̋C�Ɋ���Ȃ������̂������ȂƂ���B�~�J���̉Ԃ��炫�A�I�����i���Ă���ƃ~�J���̖ɐ\����Ȃ��Ǝv���Ă���B����ŖI����肪��i����������A�ӂ������Ēx��y���Ȃ���̔z���엿(�݁[�����A)�̎{����n�߂��B20kg��30�܋߂��͂��Ă��āA��������~���c��ځ��`���J�����R�����䑁�������~��Ə��ԂɎ{��B�����č���16���͈ɖ쁨����G���K���g�Ɖ��A��ʂ�̎{����I�����B�J�~�T����2�l�ł���1���ŏI���̂����A���I�̃P�A�ł���ǂ���ł͂Ȃ��A�ƂĂ��w���v�o����ɂȂ��B�ڂ��ڂ��}�C�y�[�X�ŁA�̗l�q�����Ȃ���A���{�̑��ނ���s���čs����2���ɂȂ��Ă��܂��B���n�ɂ���Ă͍Ăё����L�тĂ���̂ŁA�엿���ǂ������l�ɑ����������B�����܂Ǝ{��ł͓����Ȃ����ʂ�_���Ă���B VL-1000�̓d�������c�͂����肵�Ȃ��̂����A�d��SW�̒��������Ԃ��C�����Z�������͗l�B14���̐[��A������Ǝv�����ɏA���Ă���N���オ��A���ڂɉ������猩����LCD�p�l���̏Ɩ����_�����B����Ȃ��ƂŃ��N���N���邩��ʔ����B����������̓C�}�C�`�c���o���Ă��Ȃ��B7MHz�̕\������蓮�̃o���h�ؑւ��Ăǂ����́cF_SET�t�炵�����ǁBicom(CI-V)����BCD�ւ̕ϊ���쒆�����B |

|
4���A�T�C�����g�L�[�ɂȂ�ꂽOM����A��i�̐��X��������点�Ē������B���̒���Yaesu��VL-1000/VP-1000���������B�b���H�[�ɕ��u���Ă��������ASPE/2K-FA��f����ł�200V/AC�v���O����t���铙�̏��������Ă������B�����Ė{���A���ɒʓd�����݂��B�t���P�[�u����VP-1000��VL-1000���q�����鋰��VP-1000�̓d���𓊓��B�J�`�ƃ����[���c�e�X�^�[��48V�o�͂�}12V�o�͓����m�F�B������VL-1000�̓d��SW������B�Ƃ��낪�E���ł��X���ł��Ȃ��c����̓��[�J���Ȃ̂ɉ��́H�B ���̍Œ��A�J�~�T�����y���S���̃G���W�����~�܂����Ⴄ�ƃw���v�B�A�N�Z�����瑫������ƃX���[��Ԃ��ێ��ł��Ȃ��B�M���҂��Œ�~���Ă��܂��A����o���x�ɃG���W���N������K�v����B�̂̊��ŃX���[�������H�Ǝv���V�[�g�������グ�G���W�����[��������ƃr�b�N���B�L���u���^�[�Ȃ郂�m�������A���ˎ��̓d�q����ł܂���������グ���B�v���O�����Ă�낤�Ɣ��Α��̃V�[�g�������グ����_�Όn�����B�C�O�j�b�V�����R�C����f�B�X�g���r���[�^�[�������B�F�X���ׂ�ƁA���͌ʂ̃C�O�j�b�V�����R�C�����v���O�ƈ�̉�����A�����̈����͂��Ȃ��炵���B�m���Ƀm�C�Y�����x�^�[���Ɣ[���B��������̃S�~��o���R���v���b�T�Ő�������A�Q�[�W�M���M���������I�C�����[�A����ɃA�N�Z���y�_���ƃX���b�g���̗V�т����A��̕�����Ȃ��܂ܕ����ƂȂ����B�v���������A�Y�����Y�������Ƃ��������B ����ȏň�����߂��čs���B |

|
4��12������~�J������肪�n�܂����B��5���ɂ͖I��֏o�|���A�I������~�c�o�`�����𗭂ߍ����g��I�щ������B�����ɂ�9���̑��g�������Ă��邪�A�S�Ă��������̂ł͂Ȃ��ꖨ�̗ʂŔ��f���Ă���(�ʐ^)�B��������g������̍�Ə�։^�э���ł悤�₭���H�Ƌx�e�ɂȂ�B�����āA���H������ō�Ə�Ŗ����ڂ肪�n�܂�B���ɂ̓~�c�o�`�ɂ��W������Ă��郂�m�����邽�߁A���i�C�t�ł��̊W��藎�Ƃ��Ă��牓�S�����@�֑��U����B���S�����@�͍�N����d�������J�͌y���ɑ劈�Ă���B�E����ƍ�����𐔕��ԍs���A��ɔ�ׂ��爳�|�I�ȍ̖����ɂȂ��Ă���B���āA�I�q�����鑃�̏ꍇ�͒��J�Ɉ��������֖߂����A�����ƒ��ɑ�����o�Ă��邱�Ƃ�����B�J�~�T���͂�����܂߂đ����֖߂����D�����Ɋ��S����B���܂ꂽ����̗c�I�́A�ǂ̑����ɖ߂��Ă����Ȃ��炵���B���͈�l�ʂ֖�20kg�����e����B�Ⴂ����25kg������Ă������A����ɂȂ������ςȂ̂Ōy�����Ă���B�ŏI�I�ɖI�ꖼ��d�ʂ��L�����tⳂ��ʂɓ\��b���n������B����̓~�J��������1�w�B3�����̖I���3���Ԃň��肵���B�~�J�����n�ɕW������n�`�̈Ⴂ�A�����č��N���L�̋C�����A�J�Ԏ��Ԃ��������ߗ��ي��ɑ�2�w�̖�����\�肵�Ă���B�Ƃ���ŏ���12���ߌ�A�̖���̎���I�ꂩ�番�I������߂��̊`�̖ɖI��(�I���}�E�X)���o�����B�H�Ɍ���傫�����������A�J�~�T���Ƌ�����ƂŖ���������Ă���B |

|
5���̘A�x���Ɋ��k�ނ͖��J���Ǝv���Ă����炻���Ȃ�Ȃ��B�C�����オ���Ă��Ȃ��B��������������̗ǂ�����A���[�J�������A�܂��i��ɂ���Ă͊J�Ԃ��i��Ŗ��J�̏�������B���������ꉀ�n���̓����ԁA�����͓������ؓ��ł��J�����傫���B��̉��Ȃ낤�ƍD��S���N���B�܂����n�ʼnz�~�����J�����V���₽��Ƒ����c���̂��璃�F�̓z�܂ŕ��ʂ͋��Ȃ����B������ƍ��N�̃~�J�����n�͗�N�Ƃ͖��炩�ɗl�q���قȂ�B�ƌ������ƂŁA3���炫�̔_��U�z�̃^�C�~���O��A�x������f���Ă����̂����A���̃^�C�~���O��͂߂Ȃ��B�����������扄�����o���Ȃ��̂ŁA���9���A�ӂ������ċɑ����E��������ɎU�z���n�߂��B���~�Ə`���J�̂�瑁���A����Ɠc��ڂ̑������C���[�W���Ă������A�`���J�̐��͊J�Ԃ��i�݁A�c��ڂ̐����ɂ���Ă͐i��ł���B�ʂ̊Ǘ��Ȃǂ���Ă��Ȃ�����A���Lj�ĎU�z�ɂȂ��Ă��܂��B�C�t����16�����A�c��ڂ�삩�甼���U�z�����Ƃ���ŁA�J���|�c�|�c���č�Ƃ𒆎~�B�J�������Ȃ���̔_��U�z�Ȃ�čŒႾ�B�����č����A�J���Ŗڂ��o�߂���̏B����̎U�z�͂�����x�������Ǝv�����A��̃I���͉�������Ă���̂��Ƌ����B�ʐ^�͖I��̋��͎����U�z����Ɛ錾�����J�~�T���B�I���}�E�X�͊J�ԏ����A���ɂ͖����Q�B |

|
2�E3���O�ɁA�F�l����SPE��2k-FA�̓��삪�����̂Ō��ė~�����ƃ��[�����������B�l�q�����邾���Ȃ�Ɠ�Ԏ����������A���X�ɖ{������ȉו����͂����B�d����30kg���邽�߁A�^�����܂Łu����v�����肢�������ƑŐf���L�������A�ߋ��̎���������o���ĉ��Ƃ��u�z�B�v�ɑ��������炵���B���Ԃ��o�����猩��ƕԎ������Ă��������A����Ȓ��q���Ɖ����ɂȂ邩������Ȃ�����A�[��ɂȂ��ďd�������グ���B�d���v���O���������AIC-7300��d�͌v�ƃ_�~�[���[�h���q��(�ʐ^�c����IC-PW1)�B���͂���2k-FA�A2�N�U��̑Ζʂʼn����������h��B���鋰��d�������`�F�b�N�����邪�AATU���܂ߓ���͐��킾�����B�[��Ƃ͒m��Ȃ���A���́u�g��v���˗���g�ѓd�b�Œm�点���B�����ė����A���X�ɔ��l�߂������ƂȂ����B�˗����PC���܂߂��V�X�e���I�Ȗ�肪�����̖͗l�B �Ƃ���ŕ����J�n100�N�Ɠ��₩�����A���N12���œ��ǂ�55���N���Ȃ��ƋC�t�����B50���N���x�X�g�Ȃ낤���ǁA�C�t�����̂��x�������B�x��y���Ȃ���L�OQSL�J�[�h���v�悵�Ă���B�I���}�E�X�͎b��łŃN���b�N�Ŋg�傷��B�w�i�͐É��s�M�ؒJ�ÎR��JOPK�t�����̃A���e�i�S���z���x�m�R�B |

|
�c�ɂ𒆐S�Ƃ������������Ă��Ă��A�V����L��ȂǏ��̑����ɋ����BTV�͓d�������Ă��邾���ŁA�������ȊO�ɁA�f���̒��ɕ�����×����Ă��āA���̒�����������B������̈ӎv�Ŏ��ɍs���d�|���Ȃ�ǂ����A���W�ɏ��𗬂��ꂽ���̉���������ǂ��́H�ƂȂ�B�N����������珈���\�͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ͎������낤���A�����������A���^�C���ʼnf��f��������̂ɁA�K�v�ȏ�ɕ�������ꂽ��ڂ̂��ǂ���ɍ���B�������肾�Ƃ���A�ŋ߃L�b�`���̗①�ɂ̏�Ƀ��W�I��u�����B����TV�͌��Ȃ����Ƃɂ��āA6���O���烉�W�I�����Ă���B���̐���������1�����������Ă���B���ł͂��ꂪ�����p�^�[�����B���N�͕����J�n100�N�Ɠ��₩�����A�ŏ���30�N���x�̓��W�I�����������B�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�ƌ������A�ߓx�̏��͍����������A�l�̕\���͂⓴�@�͂�D���B100�N���@�ɁA�����\���̐��E�ɐZ���āA���̒��̐��|�����Ă݂����BHam�E���f�W�^�����[�h��FT8�������ĂȂ��ŁACW��PHONE�������Ɖ^�p���Ȃ���Ɣ��Ȃ��Ă���B�ʐ^��30�N���O�̖��É�����A�J�~�T�����q����p�ɔ�����SONY��CD���W�J�ZCFD-33�B�����Ɠ�������債�����́B�I���}�E�X�͌��ւ̎���1tube�X�[�p�[�B���색�W�I�ł�郉�W�I�̑����O�b�h���B |

|
4��5���ɐ��J�Â̗l�q�����悤�ƃ��m���b�N�̃G���W��(�O�HT430)���|�������N�����Ȃ��B������g���C���邪�S���_���ŁA����Ȃ̏��߂Ă̑̌��B4��28���A�Ăуg���C���邪�ꎞ�͋N�����邪������~���ă_���B��Ƃ��Ղ����H�ۂ܂ŏd�͗����ňړ��A�ăg���C���邪���l�B���̎��A�O�������������̘R��o�������Ăы����B�����Ė{��5��5���A�ÉĂ�^�P�m�R�̐L�т��C�ɂȂ�A�{�i�I�ȏC���̐��ŗՂށB�G���W���̔r�K�X�L��v���O���m�F����ƁA�ǂ����R�����z���Ă��Ȃ��B����ł̓L���u���^�[���H�ƂȂ�A���O������֎����A��B�U���Ă��t���[�g�������Ă���C�z���Ȃ��B��������Ǝʐ^�̔@���������̖������j���L���u���^�[�̒�Ōł܂��Ă���B�t���[�g�������������R���o���u���J������ԂŌł܂��Ă��銴���B�p�[�c�N���[�i�[�ʼn���𗎂Ƃ��A�v����CRC�𐁂��B���H��A�Ăь���֕������p��������ƈꔭ�N���������B���������̂��Ă���Ă��Ċy�����A�܂�ŏ��N����ɖ߂����l�������B����Ŕ��o����1�����őS�ʕ����ƂȂ����B���X�ɒi�X���̏I�_(�I���}�E�X)�܂ŏ��B�ÉẴ`�F�b�N�ƐL�т��^�P�m�R�̔��̒��A���߂Č���b�Q�ɑ����c�܂��ۑ肪�o���Ă��܂����B |

|
���N�̓~�J�����̑O�ɏt�̕S�Ԗ�����ꂻ�����ƘA�x�O���ɃJ�~���ꂢ���B���s���ăo�b�e���[�d�≓�S�����@�̓���m�F�A�����Ă�����̏������s���Ă����B�V�C�⏊�p�Ƃ̊W�����邩��ƍ�Ɠ����������Ă������A�O���u�������I�v�Ɛ錾�B���̖��21���O�ɂ͏��ɏA�������ɔ������B5��5��5���N���B���̂Ƃ���閾�����O���Ƒ����Ȃ�A�ڊo�܂��Ȃǖ����Ă����R�ɋN���Ă��܂��B���H�͌�ɂ��āA�����p�ӂ��ĕ��̖I��������B���g��8����������A�����ĉ��~�̖I��}��4��������B�����܂�1���Ԓ��̍�ƁB���H��̐��𐮂��A���悢��t�̕S�Ԗ���肪�n�܂����B���̃^�C�~���O�ł̖����́A�S�Ԗ���r�����邱�ƂŁA�J�Ԃ��n�܂��Ă���~�J�����̏��x���グ�邽�߁B �ʐ^�͉��S�����@��萂���t�̕S�Ԗ��B�T�N���ⓡ�̉Ԃ���ɁA�̉Ԃ�^���|�|�Ȃǂ̖쑐�̖����������Ă���B���x�͑z�肵�Ă������l��y���ɏ���79%��������r�b�N���B�I���}�E�X�͉��~�̖I��ō�Ƃ���J�~�T���B�����ɉ��𗁂т��~�c�o�`�̓����������č�ƁA��Ԗ��̗����Ă��鑃�g���������B�S�Ă��������̂ł͂Ȃ��A�~�c�o�`�̐����p�Ɏc���~�J���̊J�Ԃ܂ł��q���B |

|
5��1���A�F���̗F�lT�������C�؍s�r���ɗ������ƌ������ƂŁA�O���̔ӂ��瑫�̓��ݏ�̖�������������H�[�̕ЂÂ����s���Ă����B���̓����A���������Ԃ̊m�F������Ɓu������10�����v�ƕԎ����������̂ŁA�ۋC�ɍ\���Ă����B�����9��������������������낤���A�ˑR�p�������r�b�N���B�l�����牺����R1�𑖂�ƌ����Ă������A���Ԃ��S�z�ɂȂ�V�����ɕύX������z��ȏ�ɑ��������炵���B���ꂩ�璋�H�������18�����܂ŁA�n�v�j���O(�p���N)������Ȃ���y����������߂����B���ΖʂƂ͂ƂĂ��v���Ȃ������BT���Ƃ�PC-VAN��SIG�A�������[�U�[�Y�N���u�̃����o�[���ォ��̂��t�������B��������35�N�߂��ɂ��Ȃ�BSIG�ɏW�܂����Z�p�w(�_)�ɂ̓X�S�r�̌�m�������A�������[�v����MS-DOS�}�V�������A�n�[�h�E�F�A�Ɏ����ꎩ��SCSI�{�[�h��g�ݍ��݁AHDD��MO������CD�����q���A������PC�ȏ�̊�������Ă����B��X�͂��̉��b�ɗa����A���ł����ꂼ��ɓƎ��̃V�X�e�����\�z���Ă���B�v�͕��D���Ȃ̂����A�A�v���݂̂ɋY���̂ł͂Ȃ��A�����ɍ������d�|������ɗ��ł���B�ʐ^�͎���֑O�ł��낮T���Ƃ̃c�[�V���b�g�B�I���}�E�X�͎��͂ŕ��������A�H�[�Ɏ�����������������Mini7HR���I����T���B�c�u����CRT��DTP�\�t�g��2HD�f�B�X�N�������������B��O���X�����A�E���HDD/MO���q����Mini7RX��2��������Ă���B35�N���̂̃��[�v�����A�O���X�g���[�W���q���ō����œ����Ȃ�āA�����̐l�͐M������낤�c�B |

|
4�����A�����B�����̓~�J�����֑͔����(�ʐ^)��z���엿�T���ɒǂ��Ă���B�̒����C�����e�L�g�E�ɂ���Ă���ƁA����ς�d�����x���Ȃ��B �NjL�����O���Ă����m��\�����̌�BE-Tax���}�C�i�|�[�^���̃��b�Z�[�W�ɁA�ҕt���̐U�������ɃG���[���o�Ă���ƒm�点���������B�����܂����ƕ�����l���Ă���ƁA4��11���Ɏw������Ɋҕt�����U�荞�܂�A�G���[���������B�ꌏ�������B���N�͐헪���������āA���߂Ƀf�[�^���͂��ĕs���̎��Ԃɔ����悤�Ǝv���B����͋ꂵ���ꂾ�����B ������3���̓��@���̕ی��B�F�X�ƌ_����e�ׂ������̏ꍇ��OK�ł��A�a�C�͔�Ώۂ̕ی�����B���t�������ʼn������A�_����e���ǂ�������Ȃ����m���B����ōŌ�ɒH�蒅��������ې����̕ی����a�C��OK�Ɣ����A�X�ǂŕی��؏��������܂葱���B���@�����ɉ��������z��4��22���U�荞�܂ꂽ�B70������ی����e�̌��������K�v���낤�ƃJ�~�T���Ƌc�_�B�M�����ɂ��Ȃ��ƖY�ꂿ�Ⴄ�ƌ����Ȃ���������肪�߂��Ă����B 5�N�O�ɕ�o�^�����������h�Љ�̃f�W�^���ȈՖ����B�����J�ɍēo�^�𑣂��n�K�L���͂���(�I���}�E�X)�B5�N�O���v���o���������Ə��ނ��쐬�A5��12���ȍ~�ɓ��C���ʂ֓͂��l�ɔ�������B |
| �O�シ�邪�ʐ^�͎���̗��R�u��v�̌�������(����)�Ɉʒu����Δ��̒r�V��H������B2�{�̓S���͎���̗��R�ɂ��т������́B�����͓�ΎR���Ɍ����̂ŏ��a30�N��Ɍ��݂���A���������ɑ��d���s���Ă���B�E���͕���10�N�ォ�痠�R�̎R���߂������Ă��āA�L���̓������ϓd��(���g���ϊ�)����k���ʂL�сA�g�����獂�R�`���ܕ��ʂ������Ă���B��ł͂����2�n�����������Ă���B4��4���ɎR�ؑ�����Δ���֔�����H���p���H�̐�����s���ɂ��s��ꂽ(�I���}�E�X)�B��J�̓x�ɍH�����ꂪ��������H�����������A�悤�₭���H��������R�،o�R�ŖΔ�(�r�V��)�܂łȂ������B�܂��H���p�ŁA��ʓ��H�Ƃ��ĊJ�ʂ���ɂ͍X��3�N���|����炵���B�R�ؐ�͉����ɏZ����T������J���������A���Q������邽�߂ɓ��H�ɗ��ꍞ�ސ��̓K���Ȕr�o�����߂���B������ł͒n���̏d���B���A�����ɔ������X�N�ւ̔z�����d�˂Đi�����Ă����B�I����A�߂����ɂȂ��@��Ƃ���A������W�҂͌y�g��4��ɕ��悵�R�ؑ�����Δ����֎������A�s��(���_�Ɠ��H)�ɏo�ċA�H�ɏA���B |

|