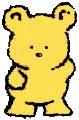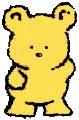|
|
| 「第 71-11 章」 |
|---|
 『子育ちは 失敗見つけ 越えていく』
『子育ちは 失敗見つけ 越えていく』

■子育ち12標準■
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『子育ち第11標準』
【失敗を発見しよう?】
《まえがき》
この子育て羅針盤では,子どもの育ちを6つの視点と2つの領域から理解することを目指しています。6つの視点とは,誰が育つのか,どこで育つのか,いつ育つのか,何が育つのか,なぜ育つのか,どのように育つのかという問に沿うものです。また,2つの領域とは,自分自身の育ち(私の育ち)と他者と関わる自分の育ち(私たちの育ち)という育ちの領域を想定しています。6つの視点にそれぞれ2つの領域を重ねると,12の論点が生じます。これが羅針盤の針路構成となります。
この第71版では,「子育ち」が獲得しなければならない必須の項目を,確認していきます。日々健やかに育っている子どもたちは,人間として豊かな能力と感性を備えていくことが期待されています。育ちのエネルギーは絶え間なく吹き出しているので,導きを誤ると不都合な育ちに向かう恐れがあります。友だちをいじめて喜ぶような子どもに育ってほしくはないはずです。親も本人も後悔しないように,12の必須の標準を再確認していきましょう。
《失敗を発見しよう?》
積み木遊びをしている子どもが積み上げていても倒れてしまいます。それでも飽きずに繰り返して積み上げています。手伝って積み上げようとすると嫌がります。自分の手で積み上げたいからです。そのためには,失敗するところがどこか,見つけなければなりません。失敗するということは,嫌なことや悪いことではないのです。ゲームで遊んでいる子どもも,簡単にクリアできるゲームは面白くないはずです。失敗があるから,成功した喜びがあり,面白いのです。
植物には生長の芽があります。芽を摘むと,生長できなくなります。子どもの成長の芽は,失敗するところです。失敗しなくなることが,成長することです。失敗をさせないことは,成長の芽を摘むことになります。失敗は成功の元と大人は思っていますが,失敗は成長の元と子どもは知っています。一方では,危ない失敗をすると痛い目に会います。それは当面危険として回避すればいいでしょう。高い所から飛び降りることは怖いと感じることで,身の安全性を確保していきます。
親として,子どもが失敗を発見することにどのように関わっていけばいいのでしょう。もう一人の子どもが失敗に遭遇できるように,親が子どものしたことがないことをしてみせることです。親が立って歩いているから,子どもは立って歩こうとします。して見せて,言って聞かせてさせてみることで,子どもは未知の失敗を発見することができます。しつけはさせることではなく,してみせることです。また,ほめてやるには,失敗という前提が必要なのです。
東京都目黒区で,しつけという言い訳で虐待されていた5歳の女児が亡くなりました。大学ノートに字を書かされていたのでしょうが,その文面がとても哀れです。「じぶんからきょうよりか もっともっとあしたはできるようにするから もうおねがいゆるしてゆるしてください ほんとうにもうおなじことはしません ゆるして」。死ということで解放されたというのでは,あまりにひどい人生です。失われた人生を天国で取り戻せるようにお祈りします。
★落書き★
足元を見られるとつけ込まれます。この足元とは何のことでしょう。昔は旅をするときに自分の足で歩きました。山道などで疲れ切ってしまうと,そこから一歩も動けなくなることもありました。そんな旅人の弱った足元を見ていた駕籠かきは,普段の何倍もの料金をふっかけました。そこから,人の弱みにつけ込むことを指す「足元を見る」という言葉が生まれました。足元を見られても,普段どおりの適正な価格であれば,問題はないのですが。つけ込むか労るか,心情次第です。
|
|
|