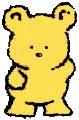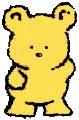|
|
| 「第 96-01 章」 |
|---|
 『子育ちは 思い思われ 自我共に』
『子育ちは 思い思われ 自我共に』

■子育ち12視標■
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『子育ち第1視標』
【自我あり】
《まえがき(毎号掲載)》
子育て羅針盤では,こどもの育ちを6つの方向と2つの領域から考察します。6つの方向とは,「誰が,どこで,いつ,何が,なぜ,どのように育つのか」という問題視座です。また,2つの領域とは,「自分の育ち(私の育ち)」と「他者と関わる自分の育ち(私たちの育ち)という育ち」の領域を表します。6つの方向にそれぞれ2つの領域を重ねた12の論点が「子育て羅針盤」の基本的な考察の構成となります。
この第96版でも,これまでの流れに沿って,子ども自身や親が育ちの確認をしていくときに,見えて感じることができる視標という面から育ちを考えていきます。それぞれの完成度に違いがあってもそれは個性になり,一応の評価ができるようなら,幸せに育っているということができます。子どもの育ちは見えにくいものですが,羅針盤としての全方位を見届けることができることを再確認していただけたらと思っています。
《誰が育つのか(私の育ち)?》
デカルトによる「我思う故に我あり」という有名な言葉があります。ものを見て感じて思っている自分は確かに存在しています。その思っている自分が自分を意識しているから,自分という我も存在していると言えるというのです。赤ん坊が育っていくと,やがて物心がつきます。自分のことを名前で呼ぶことができるようになります。思う我という子どもが育ったのです。この思う子どもを,もう一人の子どもと呼んで,「育っているのはもう一人の子どもである」と考えていくことにします。
「おしっこが出そう」と言葉で言える,それはもう一人の自分が自分を感じ取ることができるからです。育っているのは子どもではなく,もう一人の子どもであると考えることができます。このもう一人の子どもの誕生には,父親の関与が必要です。生まれて以来一心同体であった母親が,自分を離れて父親という人とつながっていることを感じ取ります。この母親離れを促すのが,父親による母親の夫婦という別の関係への誘いです。子どもはこの三角関係の中で,否応なく自分を意識するもう一人の自分の誕生を迫られるのです。
子どもはやがて反抗期を迎えます。それは成長の大切なステップです。自分のことは自分でする,つまり,もう一人の自分が自分のことを決めるという表明,それが反抗という形になっているのです。「考えて決めるのはもう一人の子どもである」ということが,子育ちの第1針路です。もちろん子どもは未熟ですからすべてを決めさせることはできませんが,育ちに合わせて,もう一人の子どもに決定権を委ねていかなければなりません。親の言うことを聞いていればいい,それはもう一人の子どもをないがしろにすることです。
子どもに決めさせるとわがままになるのではないかと心配ですね。もっと遊んでいたい! そんなとき,ダメというか,言いなりにさせるか,どちらが最終決定をするか? どうすればいいのでしょうか? 例えば,あと10分だけよ,という提案をします。それを承諾するかどうかを,もう一人の子どもに決めさせるのです。10分だけということをもうひとりの子どもが決めることができます。頭ごなしではなくて,子どもの意向を聞き入れることができる形にするということです。
★落書き★
大正時代に街中を流す交通手段は人力車が幅をきかせていて,タクシーは外車で珍しく,車高も高いものでした。客は着物姿であり,乗り降りには手助けが必要でした。また,地図を見て道を指示する人が同乗する習わしでした。彼らは助手さんと呼ばれ,運転席横を助手席と言っていました,その後,助手さんが同乗する慣習がなくなっても,助手席の名前は残っているのです。
|
|
|