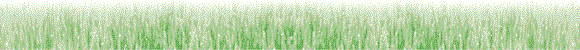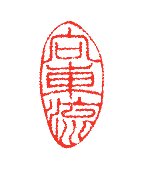
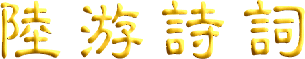
漢詩 龍興寺弔少陵先生寓居
南宋 陸游
|
中原草草失承平, 戍火胡塵到兩京。 扈蹕老臣身萬里, 天寒來此聽江聲。  |

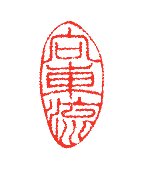
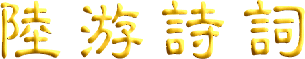
|
中原草草失承平, 戍火胡塵到兩京。 扈蹕老臣身萬里, 天寒來此聽江聲。  |
龍興寺に 少陵先生の寓居に 弔ふ******************
中原 草草として 承平を 失ひ,
戍火 胡塵 兩京に 到る。
扈蹕の老臣 身 萬里,
天 寒きとき 此こに來りて 江聲を 聽く。
| 『宋三大家絶句』より |
| 2004.1.3完 2009.4.4版 |
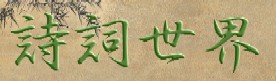
********** |
メール |
トップ |