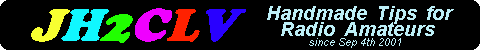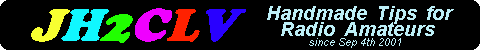制限増幅器(LB/Limiting Buffer Amplifire)試作・・・Original Circuit Desinged by JA2QXY
2008年8月、ハムフェアでTopGunのブースを訪ねると、JA2QXY川村氏からのプレゼントだと言われJH2AMN川上氏より制限増幅器の基板を頂戴した。この川村氏設計の基板は何人かに頒布された模様で、既に製作を完了し運用に供しているOMも多い。
ところが当局は相変わらず気が多い性格で、製作に取り掛かるまで何と5ヵ月を経過しその最中に新年を迎えてしまう有様。さすがにバツが悪いので、早々に組み上げオリジナルケースに組み込んでみた・・・やる気になればすぐじゃん!。以下これまでの概要を紹介する。
 オリジナル基板と回路
オリジナル基板と回路
このLBは現在は生産完了の松下電器AN5285Kを1個とデュアルOPアンプを2個使用している。AN5285KはTV受像機のAF回路用に作られたもので、2系統(ステレオ)のVCAが内蔵され両系統同時に制限動作する。またリニア動作との切替も可能。更に無音(微小)入力時、VCAの利得を低減させるノイズゲート的な機能もあり興味を引く。川村氏の回路は、2系統の制限増幅がカスケードに接続され、確実に制限が掛かるように工夫されている。
周辺は前段にデュアルOPアンプ2段のスピーチアンプと、後段にデュアルOPアンプ1段のバッファアンプが配置されている。またOPアンプのバイアス用にOPアンプ1個を割り当てている。写真は部品の実装が完了した基板のトップビュー。中央がAN5285K、左右は私の大好きなNJM5532DD。
 内部構成
内部構成
オーナーの運用形態は、IC-756背面にあるACCコネクタの変調入力へ直に入力する。この変調入力は、出力100Wを得るために約400mV(最大値)を必要とする(1KHzで実測)。このためオリジナル回路定数の場合レベル不足になるので、出力バッファの利得を-20dBから0dB(利得=1倍)に変更している。
また運用状態を確認するためにVU計を取り付けレベル監視が行えるようにしている。
写真はTKACHIの傾斜型アルミケースST-1Sのパネル側に組み込んだ基板とVU計、及び入出力JackにモードSWとDC-Jack。
基板上のVR(制限レベル・出力レベル)はパネル面の小穴からドライバーを挿入し調整する。
電源は外部の12~14VのACプラグ式SW電源としている。ケース内に無理して組み込むより簡単でSWノイズの被りからも逃げられる。
VU計はDC電流計なので、Geダイオードによるブリッジ回路で整流して振らせている。ダイオードの整流特性の関係で完全なスケールにするには工夫が必要だが、ここでは目安程度に考えている。
Jackは6mmΦの3極フォーンJackだが、GNDは浮かせて基板まで導いて接地しノイズの影響を嫌っている。
 フロントパネル
フロントパネル
傾斜型アルミケースTS-1Sならではの味が出ている。
VR調整は大胆にもパネル面に空けた小穴2個で行なう。間の抜けたパネル面はレタリングで補完し雰囲気を出す。
モードSW(制限OFF/ON)は、見た目はやや大型のトグルSWで、余りトルクが必要ない物を選んだ。この状態でSWを左右に切替えても本体が動いてしまう事は無い。
基板は25mm/3mmネジの6角金属ポストで行なっているが、そのポストを固定しているのが上下に見える3mmのトラスネジ。これは本当は見せたくなかったが、そこまで凝ると細工が面倒なのでこれで我慢している。皿ビスにしても良いかも知れないが、レタリングとの兼ね合いでバランスをとると良い。
マイクJackは3極フォーンJackでポリ製絶縁リングネジ(青色)で浮かせている。平衡受けが出来るようにチップはHotリングはColdとして取り扱い、後者をスリーブ(シールド)へ接続している。
 リアパネル
リアパネル
リアパネルにはDC-Jackと出力Jack(赤色)が取り付けてある。
出力Jackは2極フォーンJackでポリ製絶縁リングネジ(赤色)で浮かせている。シールドは前述のマイクJackと同様の処理を施し、ここでは接地せず基板で接地している。
特性試験と考察
 AN8285K:2段カスケード動作・・・LimVR:最小、OutVR:最大
AN8285K:2段カスケード動作・・・LimVR:最小、OutVR:最大
Vcc:12V Vctl:2.6V 最大利得G:47dB(リニア動作)
残留N:-75dBm(リニア動作) 入力換算ノイズ:-75-47=-122dBm(リニア動作)
Audio Tester:AH979G/Shibasoku(Filter:Flat)
①リニア特性(1KHz)/制限特性(1KHz)/歪率(1KH)
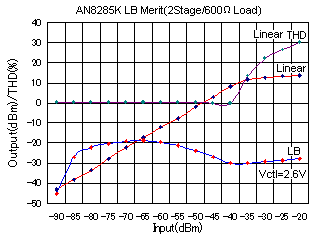
1KHzによるリニア動作と歪率は問題無く大変良好である。600Ω負荷時の飽和出力が+10dBm程度まであるので、リニア動作基準としては-10~-8dBm付近が適当と思われる(ヘッドルーム18~20dB確保)。
ところが、制限動作(2stage)させると-18dBmを最大として-30dB程度まで出力が抑えられる。また-18dBm出力時の入力レベルは-70dBmと言う低レベルで果たされる。この数字をどう診るかであるが、使用するMicの出力レベル、制限を掛けるポイントが重要になってくる。
AN8285Kの場合は、制限開始点と傾斜は独立して変えられないので、入力利得により「らしい所」に設定するしかない。という事で-70dBm入力で既に制限域に達している状況を、全体に下方に約10~15dB程度シフトさせた運用がベターかと思われる。このためにはMicアンプの利得を抑制し、出力低下分は出力アンプの利得を補正する。
VU計については、-70dBm入力時に0VU振れるようにレンジ修正する。
オリジナルのレベル配分はオフMic(Micを離す)運用のイメージで、ハンドMicやオンMicでガナル運用には全く不向きだろう。常に制限域内で動作するLBになってしまうから・・・。
個人的な意見だが、リニア動作には広いマージン(入力換算SN=120dB以上)があるので、それに合わせて、例えば-10dBm~+10dBの出力を2~1dB傾斜に押さえ込んでくれるのが有難い。
②周波数特性(リニア時)
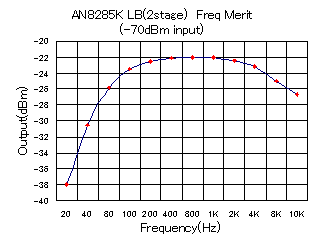
マイクアンプは程ほどの帯域に押さえられ無線電話目的として自然である。むやみにf特をDCやハイフレまで伸ばす事を好まれる向きもあるが、総合的なIMの増加を招くのでこのような程々の帯域制限は歓迎だし必要と思うが、如何だろうか・・・。
上図でリニア動作で1KHzにおけるTHD曲線も示している。全く問題は無い。制限時のTHDについても同様で全く問題ない。
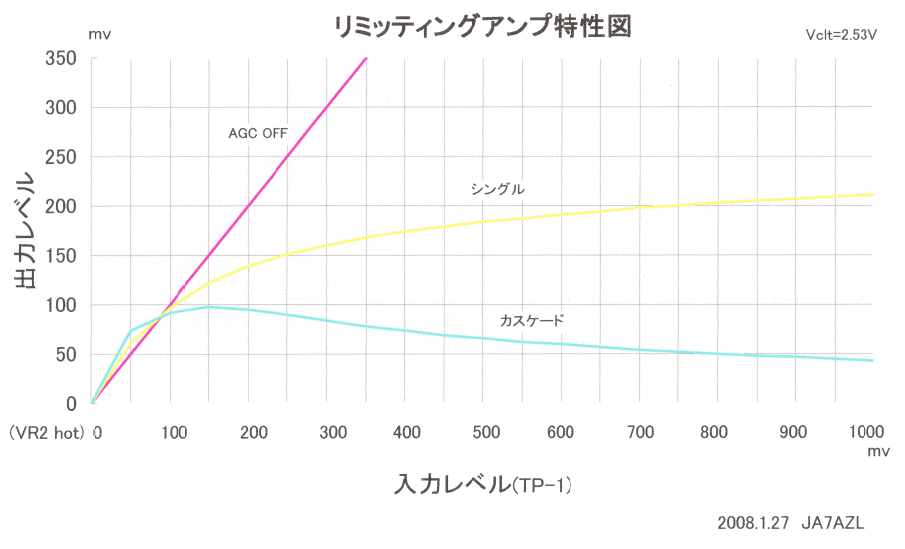 JA7AZL富樫OMの御好意で、左に測定された入出力特性を暫定的に掲示させて頂きました。
JA7AZL富樫OMの御好意で、左に測定された入出力特性を暫定的に掲示させて頂きました。
クリックするとオリジナルサイズで見られます。
2段カスケード接続だと大入力時の抑え込みが大きく、制限傾斜が右下がり(マイナス傾斜)になるのが良く分かります。片から約20dBの増加を-6dB程度に抑え込んでいます。
この傾斜はフラットまたは1~2dBのプラス傾斜に、個人的にはしたいと考えています。
課 題
①AN5285Kの2段カスケード接続と1段との比較
・・・前項のJA7AZL富樫OMのデータをご参照下さい。
②VU計の精度向上と自照ランプ追加


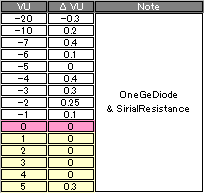 ・・・VUメーター用(兼ヘッドフォンアンプ)アンプを追加し、メーター曲線の校正を行い表示誤差を0.5dB程度に抑えた。
・・・VUメーター用(兼ヘッドフォンアンプ)アンプを追加し、メーター曲線の校正を行い表示誤差を0.5dB程度に抑えた。
アンプはエレキットのPU-2101を使用した。利得調整VRやビス締めの入出力&電源端子付きで汎用アンプとして使い易い。
整流はGeダイオード(1N60)のブリッジは止め1個の半波整流とし、リニアリティは倍率抵抗(≒3.3KΩ)で補正した。得体の知れないメーターを相手だと中々根気が要る作業になる。VUメーター背面にランプを仕込んだ・・・随分と雰囲気が変わるものである。
正直な所レベルメーターが無いとどうなっているのか動作状態が分からない。これで各段階のレベルダイアを合わせておけば、全体の動作状態が掴める。
測定機としてのVU計は旧BTS等で詳細(レベル・インピーダンス・整流方法・立ち上がり時間etc)な約束事が規定されている。ここでは簡易のdBレベルメーターとして、たまたま手元にあったVU目盛が書き込まれたDC電流計を使用している。シングルトーン程度が表示できればOKとし、針の振れは必ずしもVU(VolumeUnit)とはならない。あくまで目安である。
③スタンバイ(送信制御)系統の組み込み
・・・前面に8Pinマイクコネクタ、前面と背面に8Pinマイクコネクタを追加。電圧の異なるエキサイタ間で逆流しないように、前面8PinコネクタのマイクPTT-SWを、背面の8Pinマイクコネクタと6mmΦ-PhoneJackへダイオード分配(Diode-OR)した。
④コンデンサマイク対応
・・・前後に8Pマイクコネクタを配し、ICOM系の電源供給を行なう。12V電源から3端子Regで8Vを生成し、1KΩ経由でPin①(マイク)へ供給。同時にPin①からC(10μ/25V)でマイク出力を取り出し、ダイナミックマイク回路へ接続(前面6mmΦ-PhoneJackへパラレル)する。このAFとDCの重畳方式は、業務機で使われているAB(Tonader)方式とほぼ等価と見なせ、変換ケーブル(8Pin-XLR3)による直接接続が可能である。
⑤出力複数分配とレベルADJ-VR設置
・・・最終形態で実施。8Pinマイクコネクタ(IC-756)と、6mmΦ-PhoneJack(KWM-2A)へ2分配。レベル調整は、エキサイタ・マイクアンプのレンジとマイクVRに依存しようとしたが、マイクアンプのヘッドルームを考慮し5KΩVRを背面に取り付けた。
⑥2ToneGen内臓
・・・IcomのDTMFマイクロフォンHM-14を使えるようにした。マイクに依存するがkey2個押しでシングルトーンも発生できる。制限動作レベルの設定などに便利。
⑦簡易ミキサ機能
・・・これは中止。PhonePlug(マイク)をJackに挿入した時に8Pinマイクは遮断される構造にした。
⑧その他
・・・随時。
 最終形態・・・暫定
最終形態・・・暫定
前項で紹介したように、前面と背面に8Pinマイクコネクタを追加、TRCV(IC-756とKWM-2A)へマイク出力とPTT制御を分配した。
当初予定していたIC-756変調段への直接入力は確認のみ行い、コネクタ出力はマイクレベルとした。f特はワイドになるが、通信用としてはフィルタ処理が必要と考えている。
なおAN5285Kはカスケード接続を止めシングル接続とした。このためにC17とVR2は直結、R14とC20は取り外した。制限特性は富樫OMのデータ参照。
さらにマイクアンプゲインを下げ、制限開始レベルを下げられるように、R6を22KΩから2.7KΩへ変更した。
なお出力アンプは前述の如く、帰還抵抗を変更(R18/19パラ=5OKΩを4.7KΩへ)し利得を-20dBから0dBに変更している。
この状態で制限ON時にVU計フルスケールに納まるようし、0VU以下では制限OFF/ONでも概ねレベルが揃うようにした。これにより制限の状況が把握できる。この調整は出力の絶対レベルを意識しないで、先ずマイク入力に応じた好みの制限レベル(カーブを)を決定し、それをVU計アンプの利得でメーター上に展開させる。最終的に出てくるレベルを抵抗ATT(VRなど)でTRCVのマイク入力レベル(例えば-40dBm前後)に減衰させコネクタ出力させる。
写真は運用中の本機。3.5MHzでJA1ADD中島OMと1st運用(Jan17.08)。
川村氏の回路図(PDF)のコピーをとって修正した回路を参考のためアップしました。基板上の回路のみです。フロントパネルのPhonJackにマイクを差し込むと、8Pin側がカットされる仕掛けにしてある。ただしPTT等の系統は生きている。
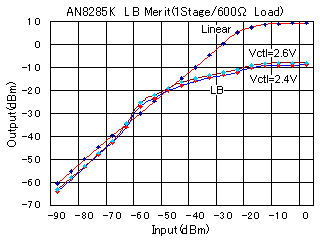 最終形態の入出力特性
最終形態の入出力特性
最終形態の入出力特性をとった。グラフはリニア動作とVctlの違いによる制限動作2種類を表示している。Vctlは2.6Vと2.4Vであるが、その違いは後者の方が最終的な制限レベルが2dB弱低く押さえ込んでいる。LimVRはAN5285Kの前段OPアンプの利得なので、増加すればグラフが左方向に動く。またOutVRは出力アンプの利得なので絞ればグラフが下方に動く。
この特性の何処を使うかが次なる課題である。オーナーは常に制限領域で動作させるのは不自然で好まない。程々に直線域と制限域がつながる辺りを基準点とすると自然になる。リニア曲線と制限曲線がクロスする辺りがその目的に合いそうだ。20dBの入力増加を6dB程度に抑え込んでいる。VU計はクロス点を0VUとして校正、TRCV側はガナッた時にALCが動作しないギリギリにMicGainを合わせる。或いは制限曲線がリニア曲線より上に膨らんでいる辺りを基準点にするのも良い。20dBの入力増加を9dB程度の変化に抑え込んでいる。聞こえ方はこちらの方が自然だろう。基準点以前のレベルは逆に10dBの入力変化を18dBと伸長しているのが面白い。これで相応にトークパワーが上がり、安定した運用が実現する。なお、AMは搬送波でSSB はサイドバンドでAGCが働くから、受信側は同じ回路でもAMとSSBとは違った聞こえ方になる。RxのAGC特性を含むと更に様子が変わる。受信状況で全く異なるエンベロープを聴いている事を忘れないようにしたい。
 AN8285K:1段動作・・・LimVR:最小、OutVR:最大 Vcc:12V Vctl:2.6/2.4V 最大利得G:30dB(リニア動作) 残留N:-85dBm(リニア動作) 入力換算ノイズ:-85-30=-115dBm以下(リニア動作) Audio Tester:AH979G/Shibasoku(Filter:Flat)
AN8285K:1段動作・・・LimVR:最小、OutVR:最大 Vcc:12V Vctl:2.6/2.4V 最大利得G:30dB(リニア動作) 残留N:-85dBm(リニア動作) 入力換算ノイズ:-85-30=-115dBm以下(リニア動作) Audio Tester:AH979G/Shibasoku(Filter:Flat)
Vctlの調整は、R13(10KΩ)に抵抗を抱かせカット&トライする。R13のみの場合はVctl=2.6V、47KΩを抱かすとVctl=2.4Vで約1dBの制限増加。47KΩ2本並列で2.24Vだが制限は変化なし。これで47KΩが適当と判断した。
*入力換算ノイズ:アンプのS/Nは利得や運用レベルで数値が変わるので本当の評価がし難い。高S/Nを謳っていても飽和までのマージンが明確でないアンプもある。それでS/Nをダイナミックレンジも考慮した客観的数字で示す必要がある。それが入力換算ノイズ。入出力を規定負荷で終端し、出力の残留ノイズレベル(dBm)から利得(dB)を減じた数字で表す。ただこれも入力をショートして残留ノイズを測っている場合もあるので注意したい。
左は最終状態での内部写真。
測定機の違いで取得データの特徴に違いがありましたので、測定機を統一してデータを取り直し、同一スケール上にプロットました。
 その後の変更と課題
その後の変更と課題
本日2008年3月15日までの状況を写真に示した。
その後TRCVの送信制御(PTT)はTRCV側にスタンバイモードが無いので、プラグの抜き差し等の操作に依存する事になり不便なため切替機能が必要である事が分かった。
それで今まで制限ON/OFFに使用していたトグルスイッチをこれにあてた。制限ON/OFFはパネル左下に小型のトグルスイッチを取り付けここに移した。
さらにハンドマイクを差さない時のPTT動作が出来ないのでパネル中央下にスタンバイスイッチを取り付けた。
以上により運用性が大幅に改善された。
その他・・・KWM-2Aの筐体とエキサイタ(LBアンプ)間にアース処理をしても若干の電位差が発生する。普通の音声では分からないがツートーンを入れると先端に揺れが乗る。KWM-2Aの分配ケーブルを抜けば改善されるが・・・後日対策する。
COFFEE BREAK①・・・LBの語源(LBのBはBuffer-ampのBかB-ampのBか)
ここでの記述は目的を直接的に示す意味で「Limiting Buffer」としていますが、これについては色々議論があります。別の語源を豊橋の知人N氏からお知らせ頂きました。古い送信関係の資料によれば・・・AFアンプの呼称を用途に応じアルファベットで行っていました。AとかCとかHとかetcです。ちなみにBアンプは「制限増幅器を前提にする(直線増幅器を使用することもある)」と定義されています。そのBアンプはTxの過変調を防ぐリミッタを兼ねていましたから、「リミッタ機能を持ったBアンプ」の意味でLBと呼ばれるようになったそうです。ちなみにB以外の使途は、A:調整アンプ、H:前置アンプ、C:送線路アンプ、D:受線路アンプ・・・等がありました。
LBはTx設備に限らず、録音や伝送設備をはじめとする音声レベルの抑制に広く使われるようになって行きます。予期せぬ大入力に備える目的とダイナミックレンジの狭い装置への送り込みで必須の装置なのです。
COFFEE BREAK②・・・制限増幅器について
制限増幅器は別名LB(LimitingBuffer)アンプとも呼ばれる。業務用Txの変調器送りには必ず挿入され、過変調やオーバーロードを抑える。基準レベル前後から始まる利得制限カーブは、各社のノウハウでもある。受信状況(ノイズ・混信・フェージング)を考慮し、いかにして明瞭なプログラムを届けるかが、この選定にかかっている。場合によっては低レベル時のカーブを持ち上る場合もある。ラジオ放送を聞くと各局のトーンに差を感じる事に気付く。同じ局でもメディアで異なる場合もあり、歴史的ノウハウの蓄積の結果とも言える。
制限増幅器の仕組みは、直線増幅器の利得を出力から得た制御DC電圧で制御するものである。人間がVRを回して利得を調整する動作を、電気的にかつ瞬時に行う一種の帰還回路である。急な入力レベル変動や多系統のレベル調整はどうしても制限増幅器に依存する事になる。急な大入力には素早く反応し、引き続く信号へ自然につなげる処理が求められる。また制限特性を意識的に変えることにより、AF信号のエンベロープが変わり、平均変調度(音量)を上げたり聴感を変えたりする事が出来る。
SSB送信機では、RF系アンプのダイナミックレンジにAF信号を効率的にレイアウトすることで、ピーク入力時の歪みを抑え平均変調度を上げた運用が可能になる。AFエンベロープとRFエンベロープの整合性をとるのも、アマチュア無線の楽しみ方の一つである。そこには周波数特性の改善では見られない味が待っている。
COFFEE BREAK③・・・真空管式制限増幅器について
昭和30年代に使用されていた真空管式LBをご案内する(前述N氏より資料提供)。
リモートカットオフ5極管6BA6のプッシュプルアンプのCgバイアスを、DC制御して利得を制限する方式。Rxで使われるAGCアンプと同じ考え方である。制御電圧は、最終段6V6プッシュプルアンプのプレートから導いたAF信号を、双2極管6AL6で両波整流して得る。
この6BA6のSgは、定電圧放電管VR-105MTで安定化した電源を供給、動作点の変動を抑えている。Cgバイアスはカソード抵抗による自己バイアスであるが、カソード抵抗(100+50/VR_Ω)にバイパスCは無く自己NFB効果を狙っている。後段(6AU6/6V6)も同様で、自己NFBによる低歪を狙っている。
時定数は1.5MΩと0.2μFの並列回路をベースに、2MΩと0.5μFの直列回路を装荷してリリース特性を変更できる。
制限動作点の設定は、6AL5のカソードにVR-105MTで安定化したDC電圧を抵抗分割し、1MΩ経由で供給して行なっている。しかし微調VRなどは見当たらない。
初段を含めて4段構成であるが、2段目以降は全てプッシュプルで構成され直線性が考慮されている。最終段は6V6プッシュプルで、ラインアンプなのにパワーアンプの作りになっている事に驚く。また全段トランス結合と言う作りにも驚かされる。DC電流によるトランスの磁化から逃げるために、磁化を相殺出来るプッシュプルは当然の選択だったのかもしれない(初段除く)。
温故知新・・・現在でも十分通用すると思われる。デバイスは違っても、やっている事は今と変わらないなぁと頷く。ただしトランス結合は現在では大変かもしれないが・・・。
COFFEE BREAK④・・・マイクロフォンの出力レベル(感度)について
無線用のハンドマイクから業務用のマイクまで数種類を、同じ音源に同じ距離で向けた時の出力レベルを測定しました。参考にしてください。