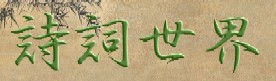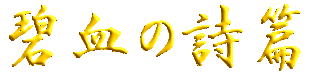
@ZB̪
@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìv@£FË
@@@@@@@@@@@@@@@
|
·Ì]ÐC èÇäÍR½B ªoÃC ¤C ç²ãßB ê~ç÷ÃB ÇzácNC wVÉC ñlÍB ªãC ¼ÌnC ã½äHB u û¸C úrºC ½EãsúîB ż¤ªàØC RÎêì¾C âÛßÂC lÁB OÔûC ¸C óºåÃC èí½¬I Õ¸C SkáC ÎëB Ûû~C ±ûûåC èÎààC xºB ¥WgC ´yêNC áà¨îH ·¹´âVC íì]C ûäÜè½ÕB gslC ®Uä^C LÜ@XB 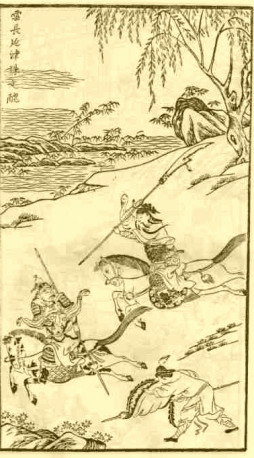 |

 V½AÐVð\µAcéAcºðÛ¥µÄ¢éB
V½AÐVð\µAcéAcºðÛ¥µÄ¢éB