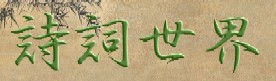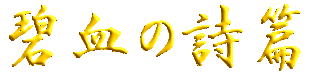
@@@@ @@@@@@@ @@@@
qå

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@é°¥
´C M^¬B ãsúîvsAC ËSuP¶B ñôyVqC é{noèåB ¿ãqìzC ßçgºËB Tâüè «C o]½´B Ãئ¹C óReéB ùç¢ÚC ÒÁãÜ°B æ¯sÝä è¨C [å m¶B Gz³ñøC ò嬴dê¾B l¶´ÓC ÷¼N_B  |