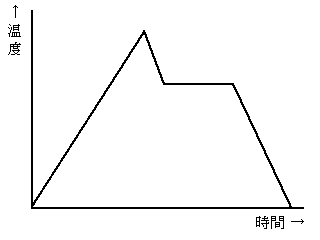

結晶釉について
結晶釉にも色々種類があり、チタン、コバルト、マンガン、亜鉛結晶などがあります。現在取り
組んでいるのは亜鉛結晶釉です。
聞かれることが多いものに結晶生成のメカニズムがあります。なぜこのような大きく、きれいな
結晶が出来るかというと一定温度での保持がポイントです。通常の焼成でもねらしと称して最
高温度到達後、幾分温度を保持します。結晶釉の場合には最高温度から100〜150℃程度
下がった点で2〜3時間保持して結晶の成長を行います。焼成の温度パターンはだいたい以
下の図のようになります。
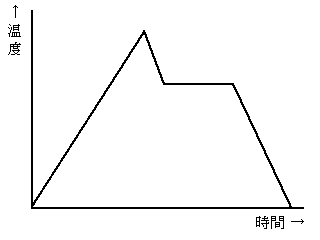 |
|
| 焼成前の状態 | |
 |
|
| 焼成後の状態 |
また釉薬にも秘密があり、結晶の基となる原料が大量に含まれ非常に流動性の高い状態に
なっています。このように釉薬成分と焼成条件がうまく一致したときに大きな結晶が成長しま
す。しかし実際の焼成は教科書通りには行きません。一番の原因は長石一つとっても産地
により成分が微妙に異なり、窯についても大きさにより昇温時間に違いがあるため自分に合
った成分や焼成条件を見つける必要があります。
失敗例としては最高温度が低いと結晶は小さくなり大きく発達しません。また高すぎたり保持
時間が長すぎると逆に結晶は消えてしまいます。それに釉薬が薄いとその部分の発達は小さ
くなります。それに最大の問題点は非常に流動性が高いのでうっかりすると棚板まで流れて
しまうことです。作り始めた頃はいつもグラインダーで後始末をしていました。今でも1回の窯
でいくつかは失敗しています。
 |
|
| 結晶拡大画像1 | ニッケル含有結晶釉 |
今後も焼成条件や配合比率を調整する必要があると思われますが、出来た作品の結晶を拡大
してみました。
なにも入らない状態では結晶は白くなり、着色金属を加えることにより変化します。しかし金属が
加わることにより結晶生成条件が異なってきます。現在のところ含有率により3パターン程度の
プログラムを設定しています。
一番おもしろいのはニッケルで詳しい理論はあるようですが結晶の色は水色、母体の色は茶色
になります。この結晶も好みの分かれるところですが、私は好きでこの結晶のぐいのみを愛用し
ています。理由は透明な液体が入ると屈折率の関係でよけいきれいに見えてきます。ただ色が
付いた液体は汚く見え、特にワインを入れることは絶対におすすめしません。