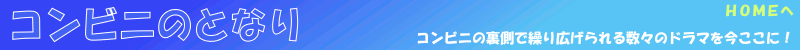
|
最後の仕事
|
|
| 掲載日 | 2003年2月3日 |
| 情報提供者 | AKILA |
|
柔らかな日差しがガラス越しに差し込む。 2日間降り続いた雪もすっかり姿を消し、今では歩道の隅へ僅かに残滓を残すのみであった。 穏やかな風は、だがしかし冬の季節を感じさせるには充分に冷たく、弱々しい太陽の光は人々の纏うコートを脱がせようとするにはあまりにも頼りない。 「7年……か……。」 誰に話し掛けるでもなく男はつぶやく。 昼下がりのなだらかに流れる時間の中、男は小さなお店の中に立っていた。 見渡せば狭い店内の商品棚には様々な食品や日用品が並べられている。 ありふれたデニムのシャツを着た男は、さらにその上に重ねるようにして多少派手な色の服を羽織り、左胸の部分には顔写真付の名札をつけている。 おそらく誰もがすぐに気付くであろう。その服が全国展開をしている大手コンビニエンスストアの制服であること、そしてその男がこのコンビニの店員であるという事に。 男の名はAKILA。 3年前この店がOPENしたときからのスタッフであった。 それ以前にも別店舗で働いていた経験をもつAKILAは、初めてコンビニで働いた時のことをひどく懐かしい記憶のように感じていた。 7年間。 決して長いとは言えないが、AKILAにとってこの7年間は多くの思い出が詰まった日々だった。 商品の発注をしていた手を止め、存外に天気の良い表を眺めた時、心の中に生じた思いがつい口からこぼれたことに彼自身も多少驚きを感じていた。 (思ったより感傷的なんだな、俺も) 幸いなことに、昼のラッシュを終えて閑散としていた店内には客もまばらで、先ほどの呟きを耳にとめた者も居ないようだ。 「どうかしましたか? AKILAさん。」 不意に声をかけられ、AKILAは我に返った。 「あ、……あぁ、Tさんか。」 Tさんと呼ばれる女の子は、不思議そうな面持ちで先輩店員を見ながら尋ねた。 「珍しいですね。ずいぶんボーっとしてましたよ?」 「え? そうか?」 とぼけるAKILAの返事を聞くやいなや、女の子の表情にいたずらっ子のような笑顔が浮かぶ。 「あ、まさかぁ〜。今日が最後のシフトだからって、感傷に浸ってたとか?」 「えっ!? ……いや、そんな…、まさか。」 笑って誤魔化したものの、彼女の勘の鋭さと観察力の前には無駄な努力であることは間違いない。 まいったな。 前々から彼女の感性の鋭さには驚かされていたが、最後の最後になってまでそれを実感させられるとは。 「ま、いいですけどね♪ それより早く発注済ませてくださいね。この後トイレの掃除しないといけないんですから。私がトイレ掃除行くと、レジに誰も居なくなっちゃうでしょ?」 「わかったよ。もう終わるから少しだけ待ってて。」 見た目こそ幼く見えるが、彼女の仕事ぶりは店内の誰もが認めるところであった。 AKILAがコンビニを辞める決断をしたのも、彼女をはじめとして頼もしい後輩が何人か育ってきたからこそだ。 後顧の憂いなく旅立てるということが、どれだけ歩みを力強くさせてくれることか…。 (発注の残りを片付けなきゃな。) そう思いつつも、やはりいまいち身が入らない。 今日で最後という現実に満足感よりも寂しさを感じてしまうのは、まだ未練が残っているということなのか。 思えばいろんなことがあった。 店長の失踪、幽霊騒ぎ、ヤクザとオーナーとの壮絶な戦い。 それに、たくさんの変わったお客さんも見てきた。 店の駐車場にたむろするヤンキーを追い払うために、110番通報した回数もゆうに100回は超えているだろう―――。 「AKILAさん。は、や、く、してください。」 「あぁ、ごめんごめん。」 後輩に急かされつつ発注を終え、レジに入る。 時計を見れば針はすでに3時を告げ、彼の勤務時間が残り僅かであることを教えてくれる。 相変わらずまばらな客足。 住宅街の午後は、まるでそこだけが別世界のように穏やかに時を刻む。 店の外に目をやれば、風景画さながらの静かな景色の中を幾人かの人が通り過ぎる。 吐いた息はすぐさま粉雪と同じ白に塗り替えられ、その白が歩行者の後ろにぴったりとついて行くさまは、蒸気機関車の煙のようだ。 その白さだけが唯一、この風景画の中で時間の流れを感じさせてくれていた。 最後の日をこんなに落ち着いた気持ちで過ごせるとは……。 か細くも暖かい陽の光―――。 緩やかに流れる時間―――。 パタパタパタと走り寄ってくる人影―――。 ………………? 人影? 見ればトイレ掃除をしていた後輩の女の子が、狭い店内を駆けて来るのが目に入った。 彼女はAKILAのそばまで駆け寄ると、泣き出しそうな顔をしてこう言った。 「AKILAさん! トイレが詰まっちゃいましたぁ〜〜〜!!」 ………………………………………。 結局最後までネタまみれかよ、オイ。 |
|
|
|
|
|
□ □ 広 告 □ □ |