「文学横浜の会」
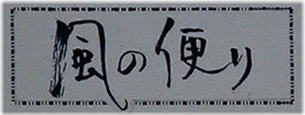
随筆(城井友治)
「文学横浜の会」
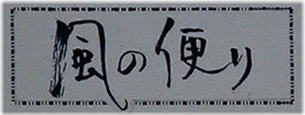
随筆(城井友治)
2003年06月15日[掲載]
〔 風の便り 〕ー残年記ー
<71>
近ごろどういう訳か思いがけない人の夢を見る。 夢は五臓六腑の疲れというが、それなら以前から見ても当り前と思う。 五臓六腑の疲れは今始まったことではないからである。 どうせお前さんのことだから、夢に現れるのは女の人か、なんて言いたいだろうが、 残念ながらむくつけき男ばかりだ。 会議をやっているところに、のこのこ遅れて入ってくる男がいた。 しょうがねぇなと見ると、学生時代の後輩だった。
「おい、なんだって来たんだ?」 言われてみると、なんの会議だったか首をかしげ、返事につまったところで目が覚めた。 なんで彼が夢の中に現れたのか分らない。あるいは病気でもしているのかと気になったが、 そんなことを言ってやれば、先方がかえってびっくりするだけだ。 社会人になってから数年は、試験に遅刻する夢をよく見た。 これは現実的で、恐怖のしるしだったから分る。 そう言えば女性の夢は見なくなった。こっちが枯れてしまったせいなのか。寂しいことである。 ◇ ◇ 私がこの街に住みついたのは、昭和29年(1954)で、 保土ヶ谷区川辺町の義父の家への同居だった。 戦後アメリカ軍が占領統治のために厚木に降り立って、 横浜のニューグランドホテルを司令部にする時に、くねくねした道をやめて、 新たに厚木と横浜を結ぶ直線道路を作った。それが一時期MSA道路といわれたもので、 今日の16号線である。 義父の家はこの16号線と旧八王子街道にまたがっていた。 旧道に面した方が正面で、玄関はこっちにあった。家の真向かいには、 さくらんぼ印の『日本精糖』のコンクリートの塀が帷子川沿いの道まで伸びていた。 ところがわが家の塀はアメリカ軍の払い下げの梱包材を広げたものを繋ぎ合わせたものだった。 道を歩く人には、その隙間から凸凹した地面とがらくたが山積みされた庭が覗けた。 当時砂糖は貴重品であった。そのせいか、暫くしたら、 『日本精糖』の塀の上には盗難よけの鉄条網が張られるようになった。 恐らくは塀を乗り越えて、泥棒に入った輩があったに違いない。 時折、風の具合でプーンとカラメルの匂いが漂ってくることがあった。 あれは瞬間だったら砂糖にあやかったような気分になるが、長時間嗅いでいると、 あまり良い匂いとは言えない。 引っ張り凧で好景気を続けた砂糖業界も、やがてズルチン、サッカリンと人造甘味料に押され、 また格安の輸入製品に追われるという憂き目にあう。 そして健康上の理由で、砂糖の消費は落ち込んで行った。 去年、砂糖を山積みにしていた巨大な倉庫が壊され、整地されると、 そこにホームセンター『こうなん』と『ワットマン』という電器販売の会社が入った建物が出現した。 開店日には16号線が車の列で渋滞を極めた。 『日本精糖』の会社名はどこにも見当たらない。ここになにがあったのか、 そのうちに知る人もいなくなるだろう。 そう言えば、わが家の工場敷地も『崎陽軒』の寮と駐車場になり、 日用品市場のあったところはパチンコ屋になっている。 昔の面影は、義父が毎日手を合わせていた末広稲荷が残っているだけだ。 ◇ ◇ 5月25日(日)から奄美大島に行っていた。 初日は雨だったが、後は天気に恵まれた。関東地区はずうっと雨だったらしいが……。 奄美大島は仲間のイッちゃん(若林一郎)が民話のケンムンを元に児童劇を書いたり、 紙芝居にした作品もあるから懐かしかった。 残念ながら伝説や民話の探索に行った訳ではなく、 バードウォッチング仲間が行くというので便乗した。 泊まったところが、海浜近くのリゾートホテルだったから、 珊瑚礁の海の青さと輝くばかりの白砂の浜に都会の喧騒を忘れることが出来た。 時期的に客はほとんどが釣客で、目の前のプールで泳ぐ美女もなく、 ビーチパラソルは閉じられたままだった。 ご承知の通り、隣の喜界島をも含めて、流人の歴史の舞台になったところだ。 今も鹿児島県だが、昔も薩摩藩の統治下で苛酷な生活を強いられたようだ。 ホテルに着いたのが、午後1時を回っていたから、まず昼食をとろうとレストランを覗くと、 5、6人の男たちが、鍋を囲んでいっぱいやっていた。 ビールの立て看板のところに、鶏飯(けいはん)980円と張り紙がしてあった。 鳥飯、そぼろの乗った三色弁当、あるいは鳥のテリ焼き丼、もしかしたら親子丼の形変りか。 くるくるっと想像の矢が飛び交う。
「俺、あの鶏飯にする」 隣のテーブルに置くと、別の女性がお盆の上に、一人用の鍋料理に使うコンロを置いた。 見ると、それは、丁度中華の冷やしそばに使う具のような、 鳥肉や玉子、椎茸の千切りが皿にのり、御飯のお櫃がそばにある。 小さな鍋には、スープとおぼしきものが湯気をあげていた。 「あれっ、頼んだのは、鶏飯だけど……」
丼が出てくるものと思っていた私は思わずただした。 なんのことはない、お茶漬けのようなものだった。 後で聞いたことだが、昔鹿児島藩の侍が役目で島にきて、仕事を終えた後で、 「腹が減ったので食う物を出せ」と、 いきなり言った。接待をするところでなかったから用意はなにもしていない。 断る訳にもゆかない。 それで残っていたものを千切りにして飯の上にのせ、スープをかけて出した。 余程腹が減っていたものと見え、「これは旨い」と舌鼓を打った。これが鶏飯の始まりとか。 郷土料理になったのか、車で走っていたら、方々の食堂に、 「鶏飯あります」の看板が立っていたし、土産物屋の店頭でも、箱入りの「鶏飯」が売られていた。 これならなにも土産に買うほどのものでもない。 家人が旅にでも出て、留守番をしている時の食事には格好である。 冷蔵庫に残っているものを千切りにし、コンソメをかけたら出来上がる。 「冷蔵庫整理飯」。これは全く味気ない。
「鶏飯」は、おそらく庭に放し飼いされていた鶏をつぶして食事に供したものだろう。
スローライフの時代のことだ。客人は薩摩焼酎を飲みながら、待っていたに違いない。
奄美大島に行くと言ったら、カミさんは目を輝かせた。 「大島紬、お父さんがお母さんに買ってくれたことがあったわ。 それよりどこへ行った時だったかしら、銀座を歩いていて、 お母さんが突然ウインドウに飾られていた大島紬を買うと言い出したの。 びっくりして、お金持ってるの? って訊いたっけ」
父は贖罪の意味があってか、時たま驚くようなプレゼントを母にしたようだ。
残念ながら私はそんな甲斐性のある男ではない。
また幸いなことに、今度のグループは紬には関心が薄かった。
県道沿いの「大島紬村」の案内板を横目で見ながら車は走った。
三月に行った沖縄の久米島絣が大島絣の源流らしいとは、家に帰ってから知ったことだった。
ナイト・ウォッチングというのに申し込んであった。 夜7時半にホテルを出発し、原生林のガタガタ道の林道を四駆のバンがゆっくりゆっくり走る。 車のライトに照らされて、動物が逃げて行く。猪の子供。 近くに親がいるかも知れないと言うが、その姿は現れなかった。 ここの猪は本土にいるのと違って、小振りなんです。となると、あるいは親だったのか。 なにしろ逃げてゆくお尻しか見えなかったのだから、なんとも言えない。 車を止めてサーチライトで高い木の枝を照らすと、アカショウビンがいた。 次々と照らし出されてもじっとしている。ストロボが光っても、瞬きもしない。 リュウキュウコノハズクが二羽、こちらはライトが眩しいのか、枝の陰に顔を隠した。 クロウサギと会えるかも知れない。少し歩きますか、と言われて車を降りたが、 みんなおっかなびっくり。 奄美大島はハブがいるからステッキは必ず持参のことと言われて来たからだ。 「ここだけだったらステッキはいりませんよ」 懐中電灯で足許を照らさなければ、鼻をつままれても分らない真の闇。 案内人は杖らしきものを持っている。ハブの頭を引っ掛ける丸い輪がついていた。 やはりハブが出るかも知れないのだ。 「掴まえれば、一匹5000円貰えます」 島にハブが繁殖し危険極まりない。ハブの駆逐のためにマングースを三十匹入れた。 それがあっという間に万の数に増え、天然記念物のクロウサギをも食い散らすことになってしまった。 生態系が変ったことを憂えているが、壊しにかかったのは人間だろうに……。 「道の脇のところどころに小さな蘭があるの見えますか。鶴蝶蘭という品種で、珍しいものです。 新聞記者が、この可憐な花を絶滅種と新聞に書いたら、 絶滅するのなら今のうちに採ってしまえと山へ入って来た連中がいたんです。 情けないったらありゃしない」
野の花は、野にあってこそなのに、嘆くのも無理はない。
一体人間の心はどうなってしまったのか。
薩摩藩と琉球王朝の狭間に揺れ動いた歴史の街、奄美大島。 昭和28年(1953)12月24日、奄美群島が米軍から日本に復帰した。 今年が丁度50年目にあたる。 ◇ ◇ 去年、半年に一度会うことにしようと提案した「くまそう会」が、 新宿の高層ビル街のセンタービル53階のDINING OUTで6月5日にあった。 「くまそう会」については何度も書いているが、 都立二中(立川高校)44期生のA組のクラス会です。 奇妙な会の名前は、立川の先の拝島に「熊川倉庫」という燃料倉庫があった。 俗称「くまそう」と言った。ここに勤労動員された中学生の我々が集まって旧交を温めている。 担当の先生はすでに亡く、同級生も年々欠けて来ている。 今度は、松井英雄君が思いがけないものを持参してくれた。 ミリタリズムの思想を叩き込まれた少年たちは、進んで軍人の道を志願した 。中学3年になると、予科練に入ることを許された。入隊が決まった時、 支給品の中に首に巻く絹のマフラーがあった。 飛行機上で颯爽となびかせるマフラーに、生徒のみんながサインをした。 それを大事に持っていた。60年間も……。 「こんなにうまく字が書けたのかなぁ」 貴重な記念品をじっと見入り、誰もが15、6歳の少年に戻ってしまった。 戦争が1年長びいていたら、 我々はこの世に存在していなかったという実感がふつふつとわいて来た。 03/6.13 城井友治 |
[「文学横浜の会」]
禁、無断転載。著作権はすべて作者のものです。
(C) Copyright 2000 文学横浜