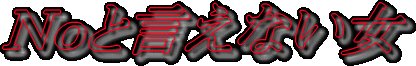
第一話
ここは横浜。横浜西口からラブホテル街の方面へ徒歩で5分ほどの場所。そこのテナントビル五階のクラブであたしはホステスをしている。今日も夕方に出勤して、今店を開けたところだ。
店を開けてすぐ、常連の安浦さんがカウンターに座った。ボトルキープしてある「山崎」をちびちび飲みながら、奥さんや子供の話をしている。仕事が忙しく、いつも帰るのは終電ぎりぎりみたい。なかなか家族と話す時間もないみたいだけど、家庭を愛してらっしゃるのがひしひしと感じられる。この方は週一ぐらいのペースで来てくださる。笑うと笑顔の可愛いおじさま。
15分ぐらいして、常連の岩下さんが若い連れの方と一緒にボックス席へ。指名で恭子と瞳の二人が接客に行った。
開店して30分ぐらいして、新規のお客様がいらっしゃった。スーツ姿の若い男だ。若いけど品のいい。
「いらっしゃいませ〜!!」
みんなで笑顔の挨拶をすると、そのお客さんは小さく「どうも」といってボックス席に座った。
ママの指示で彼の席へといった。
「いらっしゃいませ。美緻と言います。宜しくお願いします。何にいたしましょうか?」
「・・・カティサークにしてください。シングル、ロックで」
カウンターからカティサークとグラスとアイスボックスを取ってきた。グラスに琥珀色の液体をゆっくりと注ぎ込む。アイスボックスから氷を三つ入れる。グラスの中で氷に細かいひびが入る心地よい音。
「どうぞ。・・・お客様はこの辺でお勤めの方?」
「ああ、東口の方で会社をやっとるんや」
そういいながら美緻に名刺を差し出した。(株式会社 葛城商事 代表取締役社長 葛城雅也)と書いてある。
「すご〜い。お若いのにすごいですね」
「いや、オヤジから会社をもろうたからこんなに若うて社長なんかやれるんや。たかが、若造や」
「それでもすごいわあ」
「去年オヤジから引き継いだばかりや。美緻さんは?」
「あたしは高校を出てすぐこの店で働き始めて、今年で三年目です」
「ほー、それだけやってると慣れたもんやな」
「やだあ、そんな風に言わないで下さいよ。まだまだ新米と言って下さいよ!」
かれこれ二時間ぐらい話し込み、葛城さんはお帰りになった。
それ以来、一回来店するだけで最低二万円になる店に、葛城さんは時には花を携えて、毎日通ってくるようになった。指名するホステスは、必ずあたしだった。しょっちゅういらっしゃるにも関わらず、同伴出勤も求めない。それでいて、それなりのお金を落としていってくれる。ありがたいお客さまだ。
葛城さんが初めて来店されてから半月ほど経った頃、休みを二日取って旅行に行ってきた。休み明けに店に出勤すると、店にいらしたお客様におみやげのハンカチを配った。みんなに同じハンカチを。
開店して30分ぐらいして、いつものように葛城さんがいらした。
「いらっしゃいませ〜!!」
「美緻さんを宜しく」
私は必要なものを持ってすぐ葛城さんの席へ。
「葛城さん、いらっしゃい。ところで、月曜から旅行に行ってくるってあたし言ってたでしょ。これ、おみやげ」
おみやげのハンカチを葛城さんに差し出すと、葛城さんの目つきが少し変わった。
第二話
横浜市・西区のマンション。夕方。今日はどんより曇っている。今にも雨が降りそうだ。バルコニーのガラス戸をゆっくりスライドすると、少し肌寒い空気が、起きたばかりのネグリジェの中を浸食する。ランドマークタワーが小さく見える。
車の音が遙か遠くにかすむ。生活の雑音も聞こえない。まるでこの世界に自分しか居ないような、そんな錯覚さえ起こしそうになる。贅沢な孤独を楽しめる。
紅茶をゆっくりとカップに注ぎ終わった。そのとき、この静けさを携帯電話の着信音が破った。この時間帯にかけてくる人はまず居ないはずだけど?
「はい、相沢です」
「よう、出勤前に電話して悪いな」
聞き覚えのある関西弁。このひとは!
「ええ!!」
「わしや。葛城や」
「!!」
「どうしてもあんたの声が今聞きとうなってな〜。ははは」
「あたしの番号をどうやって知ったんですか?」
「内緒や」
「店の誰かが喋ったんですか?」
「ちゃうちゃう。なんでそうかりかりするんや。今夜も頼むで」
ぶつり。ぷーっぷーっ・・・。すぐ切られた。
誰から聞いたんだろう?でもうちの店にそんな事する人は居ないと思うしな。他のルートから聞き出したとすると、一体どういう・・・?気味が悪いな。
今日もまた店に行ったらあの人と顔を合わせることに・・・。いやだな。
いつも通りに出勤。そしていつも通りに開店。開店して30分後にまたあの人が来た・・・。
「いらっしゃいませ〜!」
たとえそれが嘘でも、精一杯の笑顔で葛城さんを迎える。目を合わせるのがいやだ。
「どうも。・・・おい、美緻!今夜も頼むで」
いつから呼び捨てになってんのよ。心の中でむっとしながら、それは顔には出せない。
必要なものを持って、葛城さんのとなりへ(行きたくないけど)。いつもだとお客さんの左側にべったりくっついて座るのだが、2cmほど離れて座った。ボトルキープのカティサークをいつも通りに注ぐ。
「どうぞ」
グラスを葛城さんの前に置くやいなや、太い腕が背中を這い、あたしの左肩をがしっと掴んだ。
「美緻、なに離れて座っとるんや。つれないやないかぁ」
そういうなり、ぐいっと引き寄せられ、スーツの脇に押しつけられた。言葉も出ず、固まってしまった。
「初々しいのお。好きやで、美緻」
第三話
今日もあの人から電話がかかってきた。それも一日に7,8回。私が今何してるのか、どこへ行くのかしつこく訊く。明日はオフだがとても不安だ。とりあえず寝てしまおう。疲れ切っていたので吸い込まれるようにぐっすり寝てしまった。そして・・・午前4時。
突如、ベッドのそばの電話が鳴った。誰だろう、こんな時間に。不愉快さがなるべく声に出ないように努めながら、電話に応じた。
「はい。和光ですが」
「美緻!飲みに行こう!」
「え?」
「飲みに行こうっつっとるんや」
「今午前四時なんですけど?」
「なに冷たいことゆうとるんや。常連の安浦さんも来てくださっとるんやで。すっぽかすんか」
「あたし安浦さんを呼んでくださいなんていってません!なんで「すっぽかす」事になるんですか!」
「わからん女やな〜。とにかく下まで降りてこい!」
「下?」
「玄関前のロビーで待っとる」
ええ!!どうやって家まで来たの!オートロックなのにどうやって中に入ったの!
「あたしの家をどうやって知ったんですか!オートロックなのにどうやって入ったんですか!」
「オートロックのマンションゆーのはなあ、正面はがちがちにロックされとっても、裏の出入り口には鍵がかかってなかったりするもんや」
「・・・」
あまりの気味悪さに電話を切った。しかしすぐ電話がかかってきた。
「おいこら。電話切るな!!殺すぞオラ!」
すぐに受話器を置いた。また電話がかかってきたが、絶対に出なかった。朝になっても何度も何度も電話がかかってきた。
布団にくるまったまま、窓を見ることさえ怖かった。
第四話
今日はいつものように一人で出勤するのは怖い。信用できる男友達・杉田君に同伴出勤のふりをして職場まで同行してもらった。開店一時間半前に横浜駅に到着。人混みに潜んでいないか充分に注意しながら、店までついた。
杉田君は近くで働いてるバーテンダー。うちの店長と懇意にしている関係で知り合った。とってもいい人。出入り口で感謝を伝え、仕事の準備。
開店して30分。葛城さんは来なかった。
言葉にこそ出さなかったが、その場にへたり込みそうになるぐらい安心した。本当に安心した。10分ほど後、私は泰子ちゃんと新規のお客さんの応対についた。
小一時間ほど話しただろうか。肩を叩かれたので後ろを振り向くとあの人が立っていた。あたしが応対していたお客さんに対して葛城さんはあたしを「ちょっと話があるので借ります」と断ってあたしを店の隅へと連れて行った。
「葛城さん・・・何なんですか?」
彼は涙を浮かべていた。
「美緻・・・他の人になんで優しくできるんや?」
「ええ!?」
「俺はこんなにも美緻のことが好きやのに・・・」
そんなこといわれたって・・・。あたしはこれが仕事だからしょうがないじゃない。仕事で疲れたお客さんをいやすのがあたしの仕事なんだから。
「・・・美緻は絶対俺のことが好きや!好きなんや!」
「どうしてですか?」
そう思う根拠は何よ?
「美緻は・・・俺のことが好きなんやっ!絶対!」
そういうと彼は涙をこぼしながら店を飛び出していってしまった。
その翌日には更にエスカレートした。仕事に行く前に近くのスーパーに買い物に出かけたのだが、その少し前に葛城さんから電話があった。今何してる?これから何をする?と細かく訊いてくる葛城さんに対し、適当に答えていたのがいけなかったのかも知れない。一体どうやって調べたのか、あたしの友達の所に彼は電話をかけまくり、
「美緻をどこに隠した!」
と怒鳴りまくったというのだ。
第五話
買い物から帰ってきたら早速葛城さんからの電話。やはりその剣幕はものすごいものであった。事情を全く知らずに平和な気分で帰ってきたあたしにとっては、何でこんな事になってるのか状況をすぐにはつかめなかったほど。独占欲の強い恋人とか、いつまでも娘を子供扱いする父親とか、そういった部類以上のものだ。
葛城さんの猛攻撃を受けている間、テーブルの上に置いた携帯電話(買い物には持っていかなかった)はひっきりなしに鳴り続けた。葛城さんの電話が終わった後、電話をくれた友達にかけ直すと、葛城さんの執拗で激しい脅しの電話に怯えたみんなが起こった出来事を説明してくれた。受話器の向こうで泣いてる人も少なくなかった。ただただ謝るしかなかった・・・。
やばいと思った。でも、もう手遅れ。離れたくても、店に来れば会わないわけにはいかないし、外で待ってたら振り切れない。だってお客さんですからね。
そんなストーカーまがいの脅迫客、警察に訴えるべきよという友人もいる。しかし仮にそれで彼が刑務所行きになったとしても、それで終身塀の中から出てこないわけではない。出てきたら葛城さんはきっと復讐しに来るに違いない。それが恐ろしい。だからなおさら、Noとは言えない。
そんな恐怖の日々が続く中、開店前の店に警察が来た。杉田君が殺されたというのだ。
第六話
写真も見せてもらったが、間違いなく杉田君本人だった。胸を鋭利な刃物で何度も刺されたらしい。カッターシャツの胸にはいくつも穴があき、真っ赤に染まっていた。
警察の方は10分ほどいろいろと質問すると帰っていった。
開店して30分後、あの人が来た。何も証拠はないけど、あたしのカンでは葛城さんが杉田君を殺ったと思う。あの日あたしが杉田君に頼まなければ、あんな事にならなかったろうに・・・。
葛城さんのグラスにカティサークを注ぐとき、ボトルが小刻みにふるえ、グラスが神経質にカタカタと呼応した。・・・この人が恐ろしかった。
翌日からはテラスから見える風景にいつもはないオブジェが混入した。あたしの住むマンションの敷地内からあの男が見上げているのだ。出勤するときには店の出入り口までついてきた。そしていつものように、開店して30分後に店に現れ、あたしが帰宅するときには暗闇の中、マンションまでつけてきた。しかも、あたしと足音をそろえてつけてくる。暗い夜道にそろえた足音が反響する。振り返っても葛城さんを見ても、彼は何も言わない。マンションに入ると、相変わらずマンションに敷地内のどこかからあたしをじっと見ている。そんな日が何日か続いた。
葛城さんがあたしを四六時中監視するようになって5日たった日、あたしは研修旅行で家を留守にした。帰ってくると、あたしのドアののぞき窓はくりぬかれ、1センチほどのただの穴になっており、ドアのすぐ前の廊下にはポテトチップスを食べた後の袋や、コンビニの弁当の食べ後などが落ちていた。・・・同じフロアに住む主婦が通りかかり、怪訝そうな顔であたしに問いかけた。
「あなたが留守の間、あなたのドアの前に立ってた男性ってだ〜れ?」
「ドアの前で何してたんです?その人」
「ドアののぞき窓をくりぬいて外からも見えるようにして、ポテトチップスとかを食べながらず〜っとあなたの部屋を覗いていたのよ〜。何日も」
「!!」
「気持ち悪くって警察に通報しようかとも思ったんだけど・・・」
翌日の朝にはもっと常軌を逸したことが待ち受けていた。
あたし宛に差出人のかいてない小包が届いたのだが、その中身が問題だった。中には白い化粧クリームのようなジェル状の物が入ったガラスの瓶(イチゴジャムの瓶の中身を詰め替えたもの)と手紙が入っていた。
手紙には大阪弁でこう書かれていた。
「美緻、いつだっておまえのことが好きや。
邪険にせんといてえな。
おまえのことを想像しながら少しずつ何日もためた物を今日は美緻に送るで。
俺の『愛のジャム』とでも思ってくれや」
その白いジェル状の物は、化粧クリームなんかよりはるかにベットリしていて、イカのような臭いがした。
第七話
開店前の店内。あたしたちはいつものように客を迎え入れる準備をしている。愛子ちゃんが近づいてきた。
「美緻〜、昨日は大変だったわね」
みんなが手を動かしながら、心配そうにあたしに視線を向ける。
「うん・・・」
「今日もずっと監視されてたの?」
「うん。・・・愛子ちゃん、何日かかくまってくれない?」
「え・・・あたしは・・・今夜から親がしばらく泊まるからまずいけど。誰かみっちゃんを泊められる人は居ない?」
愛子ちゃんがみんなに話を振っても、クビを縦に振る女の子は居なかった。みんなの顔はこわばっていた。
その日のうちに、実家に電話。親に事情を話して、明日からかくまってもらうことにした。友達もみんなあたしを助けてくれない。選択肢はこれしかない。
朝一番で母親に車で迎えに来てもらい、静岡の高地にある実家へと向かった。早朝だけに、道もがらがら。市街地から遠ざかるにつれ、葛城さんどころか車なんかなくなった。うまくあの人をまくことが出来た。
久々の実家を見ると涙が出そうだった。昨日まで続いた恐ろしい日々を懐かしい生家が、そして母親が癒してくれた。去年亡くなった父親も、仏壇でにっこりほほえんでいた。
すき焼きを囲みながら、母に怖かったことすべてを吐き出し、安らかになれた。何でもっと早くここに来なかったのだろう。
その日の夜は母の部屋に布団を二つ敷いて、一緒に寝た。
夜2時。突然電話が鳴った。
第八話
ぷるるるる・・・・。ぷるるるる・・・・。こんな時間帯に誰だろう?そう思いながら布団から半身出して受話器を取った。
「はい、相沢です」
「・・・今すぐここから出た方がいい」
「は?どなたでしょうか?」
「今すぐ逃げなさい!」
そういうと相手は電話を一方的に切った。発信元を見ると、杉田君の携帯の番号になっている。確かに杉田君の声に似ていたような気がするが、杉田君はもうこの世にいないはずでは?
頭の中でいろいろと考えられる可能性を推測してみるが、答えを特定できない。とにかく今日は寝ようと思い、布団をかぶった。
午前2時半。再び電話が鳴った。母が電話を取ると、何か言う前に怒気に満ちた声が受話器の向こうから聞こえた。
「どらぁ。おまえ何しとんじゃ。美緻をかくもうとるやろ!」
「!!」
どうしてここの電話番号がわかったんだろう。
「何とか言えよコラァ!!・・・美緻を出さんかい!何で美緻を隠すんや!」
「・・・」
「美緻はそこにおるんやろ!はよだせぇ!」
母はこの時点で強引に電話を切った。とりあえず、電話での脅しの電話がかかってきたら無視しようということにした。
その話し合いが終わるやいなや、誰かが家のドアをバーンと蹴る音がした。
「出てこい!こらぁ!隠し立てしたら、この家に火ぃつけるぞ!ああ!」
そこからは近所の迷惑などお構いなしの怒号とドアの蹴り上げの連続。20分ぐらい続いた。近所の人は誰も出てきてくれなかった。
次の日の朝、玄関のドアをチェックすると無数の蹴り傷が付いていた。
その日の夜も翌日の夜も、執拗に葛城さんが家に来て大声を上げながらドアを蹴る、窓を叩く、を繰り返した。
三日目の夜、葛城さんの襲撃が終わった後に完全に怯えきった母はこういった。涙を浮かべながら・・・。
「お願い。勝手にどこへでも行って。もう私に関わらないで。出ていって!」
友達はもとより、たった一人の母にまで見放されてしまった・・・。
もうどうしていいか分からなくなった。どうしていいかわからないまま、あたしは荷物をまとめ始めた。
第九話
荷物をまとめると、朝の始発電車で実家のある街を出た。見慣れた風景が朝焼けの中を流れていく・・・。今こうして列車に座っているこの瞬間も、きっとどこからか私を見てる・・・。どこからか見られている感覚が常にしていても、そっちの方を見ないようにした。
自宅近くの駅に着き、マンションへと向かった。まっすぐ前だけを見て・・・。後ろを振り向けばきっとあの人がついてきてる。
自分の部屋にはいるとき、あの人が部屋に入ってこないように気をつけてドアを閉め、部屋の真ん中にへたり込んだ。
これから先どうするのか?どうするのが一番いいのか?考えなきゃいけない。考えなきゃ・・・。でももう頭が真っ白で何も考えられなかった。
常にどこからか見られている恐怖。どこにいても何をしていても見られている恐怖。一睡も出来なかった。
その日の夕方、久しぶりに横浜の店に出勤した。
「おはようございます」
「あら、みっちゃん。久しぶりねえ」
「美緻さん、おはようございます」
みんな一応笑顔で挨拶してくれたが、誰も目が笑っていなかった。それからは、仕事上の最低限の話の時しかあたしに話しかけることもなくなった。何人かで固まって雑談するときも、あたしがまるでその場にいないかのようにあたしには誰も話を振らないし、あたしが何か言っても聞こえないふりをされた。
開店後30分。あの人は来なかった。
仕事を終えて、自宅マンション近くの駅の改札をくぐった。駅の階段を下り、横断歩道を渡り、ろくに街灯もついてない真っ暗な道を歩いた。いつも通り、あたしの足音以外にもう一つの足音がついてくる・・・。
第十話
自宅マンションへの真っ暗な道。他に誰もあるいていない寂しい道。あたしのハイヒールがアスファルトを叩く音と、あの男の革靴がアスファルトを叩く音だけが暗闇にこだまする。・・・後ろから何をされるか全く分からない。でも後ろを振り向けない。あの男はあたしのすぐ後ろにいる・・・。
足を止めた。それにあわせてあの男も足を止めた。後ろを振り向かないまま、涙をこらえて訊いた。
「葛城さん・・・あたしをここまで追い込んで、あたしに何をして欲しいの?」
「・・・」
「もうどうしていいかわからなくなった・・・。もうどうでもいいわよ・・・」
「・・・」
「どうでもいい・・・。何も考えられない・・・。あなたの望むようにするから・・・。好きなようにしてよ・・・」
彼はしばらく黙っていた。1分ほど後、彼の足音があたしに近づき、あたしの手首を掴んであたしのマンションへ・・・。
あたしのベッドの上で、彼に抱き寄せられながら・・・あたしはうわの空だった。もう本当にどうでもいい。自暴自棄。無気力。彼に一番近い位置にありながら、何だか自分はここにいないような気分だ。
一番キスされたくない男にキスされ、汚らわしい舌で口内をまさぐられても、そんなあたしを他人事として傍観している自分が居た。
夜明け前、あたしは抵抗もせず、この男に貫かれた。涙も出なかった。
事が終わると、男はあたしに背を向けていびきをかいて眠り始めた。あたしはベッドから起きあがると洗面所に向かった。体を縦にした途端、子宮から膣へ、あの男の精液が逆流するのが分かる。洗面所で何度も口をゆすいだ。何度も何度も・・・。
あたしの気持ちの何パーセントかは理性の灯がともっているのだろうか。仮にそうだとしても、そうだと思いたくない。
失意の果てのこの宴は、あたしという人間に案外お似合いなのかも知れない。
その日からあたしは、日を追うごとにそう鬱状態になっていった。
第十一話
鬱の時には「あたしに構ってモード」全開。なりふり構わずあの男に甘え、もたれた。「あなたが居なくちゃ生きていけない」と・・・。軽躁になると相手をぐいぐい引っ張り、重症鬱で誰にも会いたくない!!外に出られない!!となった。
あの人の”言葉”が怖かった。あの人にいつか拒絶されるのでは?会いたいと思っても外へ踏み出せない。電話もかけられない。あの男に依存できない時間は、薬に依存することで紛らわせた。
「好き」という感情が理解できない。きっと自分は魅力的じゃない。あたしは精神分裂気味でもない。でも、会うのは怖い。あたしはあの人に疑似恋愛してるのかも知れない。否、元々そうだったのでは?現象が必要だから?
躁から鬱へと足を浸し始める頃、喫茶店でぼうっとするのが習慣となってしまった。悩んでいるのか。悩んでないのか。多分、No。普通にホットを頼んで窓際に座る。トレイをテーブルの上に置こうとしているときにはすでに同じ議論パターンが頭の中で何度も無限繰り返し実行されてる。湯気の上がってる珈琲に手をつけることもなく、頭の中では同じように議論が持ち上がり、同じように論戦。同じように決着を見る。そしてまた、同じように議論が持ち上がり・・・。
無限再生の途中でふと気がつくと、いつも女の髪の毛がテーブルにこんもり積まれてる。あたしは無意識のうちに髪を抜いているのだろうか?
とてつもなく不安。とてつもなく怖い。あんなに厭なあの人に依存することでこの思いを紛らわすことが出来ない日・・・。髪、切ってみた。肩や腕に血が出るほど爪あとをつけてみた。せめて大声で叫べる場所があったなら良いのに。自分を傷つける事でしか、この苦しみを紛らす事が出来ないの。
・・・高校時代に友達だった、佳代子に電話で呼び出された。彼女の部屋にあがるなり、単刀直入にいわれた。
「遠方の病院に強制的に入院させます。有無をいわせない!」
「あたし、大丈夫よ」
佳代子に手首をぐいっと引っ張られ、袖をまくられた。
「じゃあ、この手首の傷は何?このままじゃあなた、本当に廃人になるわよ!」
「・・・」
その日のうちに無理矢理旅支度をさせられ、アイマスクをさせられて車に乗せられた。どこまで走ったのか分からない。車から降ろされアイマスクを取った目の前には、うっすらと雪化粧したとてつもなく寒い見知らぬ街が広がっていた。
佳代子とそのだんなに両脇を抱えられ、病院の中へと連れて行かれ、そのまま入院させられた。窓もない病室だった。朽ち果てた古い天井が、なおさら気分を陰鬱にした。
第十二話
美緻は無事退院した。自傷癖も躁鬱もどうにか抑えることができるようになった。薬の助けも借りながら。
翌日、店にも今まで通り出勤。今まで通りにお客さんをもてなした。
ホステスとお客様の和んだ会話。グラスに琥珀色の液体をゆっくりと注ぎ込む。アイスボックスから氷を入れる。グラスの中で氷に細かいひびが入る心地よい音。お客様の言葉の隙間にかいま見える他人の人生・・・。この仕事にやっと戻ってこられた・・・。
午前二時半。少し押したが、営業を終了。今日は結局あの男は来なかった。こなくていいけど・・・。明日くるのかな?
いつものようにお店の片づけが始まった。あたしは洗い物から始めたんだけど、始めてすぐに同僚のメグちゃんが声をかけてきた。
「みっちゃん、ごめんあたし、今日風邪で体調悪いんだ。あたしの分をやってくれない?」
この子、早退や休みがやけに多い。その度にあたしに代わってくれと言ってくる。しょっちゅう。いいように利用してるんだろうな。多分。わかるもん。ほとんどの場合、仮病だって事。
「うん、わかった。おだいじにね」
また断れなかった。断ろうかと一瞬逡巡したんだけど。断った後のことを考えると・・・。
店を出て横浜駅へ。駅に入るあたりで、あの男がまたつけてきているのがわかった。西口の人混みの中でもちゃんとわかる。あの男の姿。
家に帰るとまたセックスを求められた。あの男に抱かれている間中、いつものように心はここになかった。うつろな表情をしたマグロ。
一時間ほどの行為が終わると、あの男は帰っていった。薄汚い。気持ち悪い。
寝室へ戻ると、いないはずの人が立っていた。・・・杉田君。え?
大声を出す寸前に彼はあたしの口を塞いだ。
「みっちゃん、おどかしてごめん。声は出さないで」
声を出さないでったって・・・
「杉田君・・・死んだんだよね?」
「そうだよ。僕は生きてない。幽霊♪」
「・・・」
怖いというより、初めて霊を目の当たりにして、頭の中は真っ白だった。今自分がどういう状況にあるのか、感覚でつかむのにものすごく時間がかかっていた。
杉田君があたしの口を塞ぐのに、足を動かさずにそのまま横移動してあたしに近づいた。生きてる人間だったらそんなことはできないはず。
「みっちゃん・・・美・緻・さん?大丈夫?」
「・・・」
「いいに来たことがある。・・・葛城さんが君を愛してる事はよくわかってると思う。だけど、みっちゃんの葛城さんに対する気持ちは・・・違うんだろ?」
「・・・」
「みっちゃんが今のまま、Noということもできず、何か葛城さん対策の積極的な行動に出ることもできないんじゃ、いつまで経っても状況は変わらないよ?別にどうにかなるのを待ってるつもりじゃないんだろうけど、客観的に見て、そうだよ。君の今の姿勢は」
「・・・」
「いきなり大幅に変えることは無理でも、小さいところから少しずつ変えていきなよ。・・・このままの状況を続けたくないだろ?」
「・・・うん」
「君がいい判断をするのを期待してるよ。じゃあね」
彼はそういうと消えてしまった。・・・小さいところから少しずつ、か。
次の日の営業終了後。いつものようにお店の片づけが始まった。始めてすぐにまたメグちゃんが声をかけてきた。
「みっちゃん、ごめんあたし、昨日から『お客様』で体調悪いんだ。あたしの分をやってくれない?」
「イヤ!」
My will. My courage. My revolution. 結果がどうあれ、なりふり構わず動いてみることにする。
第十三話
どれだけ長い間自分はこの泉に沈んでいたんだろう?透明で心地よい何かに包まれたまま、瞼を開けることすら容易くない。目覚めることなく、いくつの夢を見たのか?いや、これ自体が夢なのかも知れない。
瞼を開けてはいけない。今すぐには。夢にありがちな、奇妙な強迫観念が意識を拘束していた。違う。眠っている私のすぐそばに、誰かの気配がする。”誰かに見られている。”
瞼をあげて、それが誰であるかを確かめる?
今この状態で他にわかることは、ある方向の狭い範囲から光が射し込んでいること(窓がそこにある?)、私を見ている誰かは私の顔から右へ40センチほどのところにいるみたい。
怖い。目を開けてその人の方向を見て何が起こるかわからなくって・・・。
体を横たえたまま、眠ったふりをしてこの場をやり過ごした方がいいのか?意識的に息を整え、眠ったふりを続けてみた。部屋は見えない。窓や扉の隙間から流れ込む大量の血液。うち寄せる邪気に腐食する傍観者。この閉じられた空間に沈殿する恐怖が、真偽の判別もつかないイメージを瞼裏に描く。
「おら、美緻。何寝たふりしとんのや。アホな芝居すな。わかっとんのやぞ」
声はしないはずなのに、意識にははっきりと注ぎ込まれた。声も音もしない空間で、聞き慣れた大阪弁が直接脳にロードされた。いったい何がどうなっているのか?
寝たふりしていたが、もはや怖さで声も出ない。そこへ追い打ちをかけるようにあの男の声が伝達された。いや、今度ははっきり聞こえた。
「怖くて声が出えへんのか。出さんでええ。とりあえず目ぇ開けぇや」
しばらく逡巡したが、勇気を振り絞って少しずつ目を開けてみた。
第十四話
は?夢かあ・・・。
時計を見るとまだ午前3時半。そこへ音がした。玄関のドアポストにコトリと。誰かが郵便物を投函した音だ。こんな時間に誰が?
ゆっくりとベッドから抜け出て、部屋の敷居から玄関の方をチェックする。暗くてよく見えない。・・・警戒心を解くことなく(ほどける訳ないか)ゆっくりと音を立てないように玄関のドアに近づく。冷たい土間に素足が触れる。音を立てないようさらに注意を払いながらドアの前まで接近した。
ドアに聞き耳を立ててみる。・・・何も聞こえない。そっとドアポストを開いてその郵便物を手にした。
と、その時! 誰かにガッと手首を掴まれた!!ドアポストの差込口から男の手が急に出てあたしの手首を掴んでいるのだ。掴まれたその感触は明らかに女の手ではない事はわかる。葛城さん??
その男は急に手を離した。もちろんあたしはバランスを崩して玄関の土間に倒れ込んだ。廊下から階段へと走り去ってゆく足音を耳で見送りながら、少し安堵を覚えた。
郵便物には次のように記されていた。
「はあ?Noと言える女になる?
アホかっ!! 人間そんなに簡単に
変われるわけがないやろ!」
この人はあたしの行動だけでなく、心まで監視しているの?
今日も夕方に家を出た。今までのように葛城さんがあからさまにつけてくることはなかった。だが、どこかからあたしの出勤を見ている男がいる。
第十五話
どういうわけか、その日から葛城さんがあたしの前に現れなくなった。店への往復で尾行されることもない。営業中のお店に現れることもない。そんな日が何日も続いた。そんな異変に気づいた同僚たちはこそこそと噂していた。
「いったいどうなってんのかしらね〜・・・」「ねえ。あんなにしょっちゅう来てたのに・・・」
そんな彼女たちを横目に、淡々と毎日の業務をこなした。
寝てるときだろうと何だろうとお構いなしにかかってきたあの電話もぴたりとやんだ。気にかかりながらもこの機会にぐっすり休んだ。いや、休めるほど安心はしていなかったのだが、それ以上に疲れていた。久しぶり、本当に久しぶりの休息。休息といえる休息。
そんな日が数日続いたある日。その日は珍しくこの横浜でも雪が降っていた。積もるほどではなかったが、この港町にたおやかに降り注ぐ雪は、音のないリズムをあたしの心に投影した。この雪のように生きられたらいいのに。
一階の集合ポストの中身を改めると、見たくない速達が一通入っていた。郷里の静岡の叔母からのもので、母が急死したことを告げていた。文面に踊っていたその知らせの意味を理解できても、気持ちになかなか浸透しない。
母に見放されたあの事件以来、久しぶりに目にする母の消息。よりにもよってこんな形で・・・。いくらあんな薄情な母とはいえ、親は親。行かないわけにはいかない。明日通夜、明後日葬儀・告別式。ちょっと急だわね・・・。文章にどんな事情で急逝したのかは書いていなかった。そんなことより、母の実の娘であるあたしに速達ってのはちょっとあんまりなんじゃ・・・。電話一本よこせなかったのかしら。
叔母の家に何度が電話してみたが、何度かけても留守だった。葬儀の支度で家にいるどころじゃないんだろう。
職場に電話を入れて、事情を話して三日間フリーにした。今日はたまたま休暇だったが、明日と明後日はシフトインしていたので。
横浜から車に乗って、母の遺体の待つ生家へと旅立った。雪の舞う横浜が視界から離れてゆく。
見込みが甘かった。横浜市を発つときにはぱらぱらとまばらに降っていた雪が、故郷に近づくにつれ次第に本格的に。横浜では積もっていなかったのに、積雪量が実家への距離と反比例して深くなっていく。途中チェーンを装着し、スリップしないよう気を遣いながら走った。カーラジオからは、「50年ぶりの豪雪」とクールにしゃべる女性アナウンサーの声が流れていた。
雪に四苦八苦しながら夜遅くにどうにか郷里の村に辿り着いた。山間部に注ぎ込まれた黒いリキッド。液中に沈降する白雪。元々民家がまばらな土地だが、尚更まばらに見えた。
実家の玄関の前にたち、合い鍵を使った。扉をそっと開け、中の様子をうかがった。奥の部屋の方に明かりがともっているのがわかる。時間も時間なのだが、少し待っても誰も出てくる気配がない。ま、自分の家なんだし、いいかと思って靴を脱ぎだしたとき、後ろに人の気配を感じた。
振り向くと、あの人が立っていた。なんでここに?
第十六話
葛城は無表情で私を見下ろしている。この人と母の通夜との関連がまったく推測できない。まさかこの人が通夜を手伝いに来たとは思えないし、呼ばれることはもっと有り得ない。じゃあ他に何の用!?
「あっ、あっ、あの、あの、なんでここに、あたし、その」
「な〜にシドロモドロになってんのや。毎日しつこー会いに来とったやつが急に出てこんなって、それが急に目のまん前に、それも思いもかけん場所で出てきたもんやから動転しとんか。情けない女やのう」
「・・・」
「まあええ、来い」
ぐいっと腕を引っ張られて中へと引っ張り込まれた。葛城は私を牽引しながらどかどかと無神経に廊下を歩いて明かりのほうへ・・・。
暗い廊下を進んで、明るい部屋の入り口が近づく。部屋の入り口にさしかかるなり、私の体はふわりと宙に浮いた。中が見えるか見えないかのタイミングで部屋の中に投げられたのだ。いったぃぃ・・・。
視線を水平に戻して、もっと驚いた。
・・・母が生きていた。
第十七話
母が生きていた。しかも、叔父と叔母と母の三人がこの部屋でロープで縛られていた。三人とも相当折檻されたらしく、顔や体にその痕跡が残っていた。中でも叔父のそれは特にひどかった。なぜ叔父が一番傷ついているのかは問わずもがな。
古ぼけた室内灯のせいもあるだろうが、三人とも折檻されたこと以上に元気がないように見えた。折檻されたことだけが元気がない理由ではなさそうだ。
後ろに振り向きながら、これはどういうことかと訊きかけたそのタイミング。葛城が真後ろで思いっきりビール瓶を振り上げているのが視界に入った。よける暇もなく、脳天に激痛が一閃。記憶が真っ暗に途切れた。
ガンガンに痛む頭とサイッテーの気分で目覚めたのはお昼。ヤニで茶色に汚れたデジタル時計を見ると、2時過ぎ。ますます雪が降り積もっているのが窓から確認できた。
ビール瓶で殴られるのはこんなに痛いものだったのか。頭を触れば、きっと一番痛む辺りがカサブタになっているであろう。
触れば・・・という言い方になっているのは、今さわれない状況にあるから。・・・あたしも縛られてしまったのだ。失神している間に。迂闊だった。三人の有様に気を取られて、今の自分に充分あり得る危険から注意が離れていた。
今、部屋に葛城は居ない。他の三人は縛られた状態のままで眠っている。三人が座らされている向こうには、黄色いビニール袋に包まれた何かが置かれている。何が入っているかはわからない。
葛城の目的は何なんだろうか。あたしたちをこんな風にして。あたしたちに何をして貰いたいんだろう?叔母夫婦と母は、いつから縛られているのだろうか?彼はこれからあたしたちをどうするつもりなんだろう?
一時間ぐらいして、二階から誰かが降りてくる音がした。音、歩き方で、ほぼ間違いなく葛城だと思った。
予想通り、その男が現れた。この29歳め。こんな犯罪行為をしておきながら、あくびをし、ぼりぼりと背中をかきながらのご登場には呆れた。
「いろいろ訊きたいことがあるけど、その前にあたしたちに水を飲ませて欲しいのと、トイレに行かせて」
第十八話
「水?この雪のせいで水道水は凍結して出ないし、今呑めるものはジュースとビールだけ。これは貴重だからおまえらにはやれん」
「ええ!?」
「あと、食いもんもおまえらにはやれん。この豪雪のせいでうかつに外にも出られない状況だしな。車は勿論動かんし」
「ちょっと、それじゃあたしたちは」
「トイレはその黄色いポリ袋の中にせえや」
「・・・」
呆気にとられて何も言えないあたしを残して葛城はまた戻っていった。彼はいったい何がしたいのだろう?
叔母が唇だけ動かして元気なく教えてくれた。
「あたしたちはこの三日ほどこの状態のままよ・・・。水も食べ物も与えられないまま監禁されてる。もうこのまま死にたいよ・・・」
「・・・」
「三日前にあの男が来て、その時この家にいたあたしたち三人が殴られるは蹴られるはで縛られて監禁されたんだ。そしてあんたをおびき寄せるために、智佐子(母のこと)を死んだものとして通夜・葬儀への招待状を書かされたんだ。まさか葬儀がニセモノで罠だとは誰も思わないだろ?ましてあたしの字で書いてあるわけだし。電話で伝えようとしなかったのもそれが理由よ」
「・・・」
「あの男は「まんまと罠に引っかかりやがって、アホな女や」とせせら笑っていたわ」
「・・・」
「それに加えてこの何十年ぶりかのこの豪雪。逃げるに逃げられない。隣家に逃げるにしても、こんな田舎じゃ隣家まで相当距離がある。吹雪で迷ってそのまま凍死する可能性も充分あるわ。その上、三日間飲まず食わずで逃げる元気もない」
「・・・。あの人はこの先どうするつもりなの?」
「知らないよ・・・。何が目的なのかさっぱり見当もつかない。それがわかったらねー」
「・・・」
お腹すいた・・・。水のみたい。
その夜、またあの男が来た。
「どうやおまえら。結構もつのう」
叔母が毅然としてくってかかった。
「なにいってんのよ!!クソ監禁男が!いったい何が目的なのよ!」
叔母は葛城に思いっきり蹴飛ばされ、後ろの壁に叩きつけられた。
「やかましいわ、クソババア」
あたしがキッと睨み付けると、葛城はますます逆上した。
「何やその目は!!」
あたしを押し倒すと、みんなが見てるその前でブラウスを引き裂いて覆い被さってきた。やっ!!!
葛城の唇があたしの唇に触れようとしたその瞬間、彼の体がガクンと跳ね上がった。すぐ彼は足の方を向いて怒鳴りつけた。母が彼の足にがぶりと噛みついていたのだ。手も縛られているし、娘を助ける手段といえばこれしかなかったのだけど、そんなことより、母が、あんな薄情な母が体を張ってあたしを助けたことに驚いた。
葛城は体を反転させて母に立ち向かっていくと、母を大きい拳で殴り始めた。何度も何度も殴ったが、母は離さない。やがて彼は人差し指と中指を母の目の前に立てた。
「離さんかこらぁ!!離さんと目ぇつぶすぞ!」
母は微動だにせず葛城を睨め付けた。
「離さんか!!」
母は毅然として動かなかった。ひるむ様子すら微塵もなかった。その雄々しい母の両目にあの男の指が突き刺さった。角膜からダークグレーのゼリー状のものがねっとりと漏れだしていくのがはっきり確認できた。
母が噛む力を失ったところで、足から母を振り払って男はよろめきながら立ち上がり出血している左足を引きずって隣の部屋に行った。押し入れを開け閉めする音がした後、こちらの部屋に戻ってきた彼の右手には大型の猟銃が握られていた。無言で母の口の中に猟銃を荒々しくつっこみ壁に押しつけると、何でもないことのような顔をして引き金を引いた。
ドオオォォ・・・ン
母の後ろの壁に、血と脳髄と脳漿で紅の絵が描かれた。・・・母は、処刑された。
第十九話
葛城は一度振り返って我々に一瞥をくれるとまた部屋を出ていった。
「おまえらもあんまり逆らうとこうなるでー。ヒヒヒ」
二階から何かを取って戻ってきた。チェーンソーだ。刃に光が反射して眩しい。・・・そのチェーンソーが母に牙をむいた。
母の首に当てられると耳をつんざく悲鳴を上げて食い込んでいった。刃がめり込むにつれ、弾け飛ぶ鮮血。脂肪と筋肉を切断しているうちは比較的刃の進む速度も速かったが、中程に到着すると進みが鈍った。体重をかけて骨を押し切る葛城の後ろ姿。返り血が彼の服の脇に滲んでいく。
チェーンソーが突き抜けると、血まみれの母の首がごとっと床に落ちた。人の形をしたそのオブジェは、未練がましく切断面から真っ赤な唾を吐いていた。
葛城はそれを黄色いポリ袋にぽいと捨てた。ポリ袋を開けるとき、糞尿とともに強烈な腐敗臭が吹き出した。原形をとどめていないが、腐敗の進んだ動物の遺体が三体ほど入っているようだった。見た感じ、多分そうだ。
その日の夜、葛城に二階の寝室に呼び出された。上半身裸、トランクス姿であの男はベッドに腰掛けていた。やっぱりそうなのねと思いながら着衣を脱ぎ始めると彼が遮った。
「そういう意味やない。そのままこっちへ来いや」
第二十話
招かれるままベッドに近づき葛城の横に座った。真っ暗な部屋。部屋の隅で紫色に浮かび上がる水槽。窓の外にはゆっくりと降りてゆく小雪。背景には夜に弱々しく浮かび上がる銀世界。
葛城が足を組み替えるとベッドが軋んだ。五分ぐらい沈黙が続く・・・。なに考えてんの?
「どうしたの?今日は」
葛城は何も言わずに分厚い大学ノートを渡してくれた。そこには彼の今までの半生と精神医の分析レポートが綴られていた。長々と克明に・・・。
要約すると、こうだ。葛城がまだ4歳の頃、父の連日の暴力に耐えかねた母が家を出てゆき、離婚した。どういう経緯があったのかは分からないが、子供をどちらが引き取るのか決まらなかった。
ある日のこと、母は葛城少年を家から遠く離れた24時間保育園に預けた。「あとで迎えに来るから」と言い残して・・・。二度と迎えに来ることはなかった。父も。両親に捨てられたのだ。
父からも母からも保育園への入金はないまま、二年が過ぎた。24時間保育へ児童が置き去りになったのだ。当然の事ながら、様々な冷遇を受けた。愛情を感じることはなかった。
そのままの状態で、小学校の入学式も迎えた。新品のランドセルを背負って母親と幸せそうに学校の門をくぐる子供たち。そんな情景を羨望の目で見つめながら、近所の子のお下がりのランドセル・服を身にまとって入学式に参加した。
三年目からは親戚の間をたらい回しにされながら育てられた。愛情を感じることはなかった。うまく甘えることもできなかった。実質的な「家庭」のないまま育った彼は。
『人並みに愛される』術を知らないまま育った葛城雅也少年は、『人並みに愛せない』青年に成長したのだ。
「・・・せめて、あんたを”普通に”愛したかったわ。ほんまは・・・」
「・・・」
「あんたを精神的にいくら追いつめても、結局あんたの心を振り向かせることなんか出来ひんかった・・・」
「・・・」
「明日、俺は自殺する」
「!!」
「生きとる資格がない。ただ・・・」
「ただ?」
「死ぬ瞬間を見届けて欲しいんや。迷惑やってわかってる。勝手な願いやって分かってる。ほやけどな・・・」
・・・人が死ぬところなんて見たくない。誰もがそうだと思う。あたしも・・・。
「でも・・・」
「ごめんね」
「ごめんね」のセリフが突き刺さった。
「わかったわ。最後に立ち会う」
自殺幇助。あたしも犯罪者だわ。
「おおきに。好いとる女に・・・甘えとるな、俺」
その夜はほとんど眠れなかった。夜空を流れ落ちる星をずっと眺めていた・・・。
足音で目が覚めた。白みかかった夜空からうっすらと伸びた足が、目の前に立つシルエットを逆に見えにくくしていた。
「葛城さん?」
夜明け前の青黒い明度に目が慣れてくるのにしたがって、葛城の姿が徐々に形を成した。
「美緻・・・」
「何ですか?」
「死ぬ瞬間を見届けてくれと言うたけど・・・そうじゃなくて・・・」
「・・・」
「俺と一緒に死んでくれ」
「えええっ!!!」
青天の霹靂、どころじゃない。
「・・・」
「・・・」
「・・・どうして私があなたの自殺の道連れにならなきゃいけないんですか?」
「・・・」
問いかけてから何分も経っていった。普段の毅然とした態度とはかけ離れたリアクション。かといって心の舵を失いかけている感じにも見えない。心情の読みとりにくい表情をしている。
この物静かな彼が彼本来の姿なのだろうか?・・・その静かな表情に、悪魔のような微笑が差し込んだ。見慣れたあの顔。
「体を無理矢理奪うても、おまえの心は手に入らんかった。殺す寸前まで追いつめても、手に入らんかった。一番欲しかったおまえの気持ちが・・・」
あたしの顎をがしっと掴んで怒鳴りつけた。
「ほやから、代わりに命をもらうで!他の男には渡さん!!おまえは俺のもんや!!」
「!!」
「明日俺と一緒に来い!俺と一緒に死ね!!それまでに逃げたら許さんぞ!妙な真似をしたらどうなるかわかっとるやろうな!!ああ!?」
・・・どうしよう・・・。
第二十一話
曙から朝に遷移するまでの間、目を閉じることなくベッドの中にいた。カーテンの隙間から差し込むオレンジの朝日。眠ることなどできようか。
逃げるか?行くか?どうやって?
朝。私、叔父、叔母の三人は雪を肌で暖めて溶かした水で喉を潤した。食事を何日も与えられていない私たちにとって、この水だけが命を繋ぎ止める糸だ。水道水は相変わらず凍結していて使えない。
閉じこめられているのにどうやってやってるか?台所に窓が二枚ついている。施錠されている上に防犯柵がついているため、開けることも割って外に出る事もできないのだが、右の窓の右隅が元々割れていて、その位置のすぐ下に棚が付いている。その棚にビーカーを置いて、割れた穴から漏れ落ちてくる雪を集め、その後ビーカーを抱え込んで暖めて溶かすのだ。
・・・これは使える、と思った。
第二十二話
回し飲みされているビーカーを見据えながらあたしは言った。
「今日、逃げようよ。この家から」
叔父と叔母の動きが止まった。
「どうやってえ?」
「家中の窓がどうなってるか知ってるだろ?どうやって出るのさ?」
「盲点があるわ」
「どこに??」
あの男が近づいて来ないよう気をつけながらプランを説明していった。
正午前になって、あの男が降りてくる足音が階段から聞こえてきた。台所にいたあたしにあの男は”二度と戻らない外出”への同伴を指示した。あたしの体中をチェックして凶器を所持していないのをチェックして、あたしの体を縛っていたロープを外した。縄が床に完全に滑り落ちたタイミングで、居間に居た叔父がわめき出した。
「どらぁ!!美緻をどこに連れて行くつもりじゃあ!!」
叔父に背を向けたまま葛城が毒づいた。
「おまえに関係ないやろ」
「葛城!おまえの好きにはさせんぞ!!」
葛城が怒って叔父の方に振り向くそのタイミングに・・・台所の窓によろけた振りをして倒れ込み、体を支えるために手をついたような演技をして、右の窓の右隅に手を突っ込み、手の平大のガラスを折り取った。折り取ったらすぐ普段ビーカーを置いてあるあたりに(割れないように)落とした。叔父の方に向かい掛けていた葛城は顔だけこちらに向けて
「うるせえ!!」
とだけ吠えて居間の方に向き直り、どすどす叔父に迫っていった。
怒りにまかせて叔父を猛烈に蹴りつける後ろ姿。自分以外を全て見下したその背中。何様のつもりなんだろう。
叔父が蹴られている間に、気づかれないように折り取ったガラスをハンカチで素早くくるんだ。いつの間にか手が震えていた。葛城の暴力への恐怖の為か?今からしようとしている事を思って怖じ気づいているのか?・・・その震えがなるべく小さくなるように気持ちを自制しながらその凶器を右手に握った。
葛城のまだ蹴り続けていた。その後ろから音をなるべく立てないようにして葛城の背後に忍び寄る。叔母はあたしに気づかない振りをしてくれた。
あの男の真後ろに到達したところで、一気にガラスを葛城の右目に突き刺した。日本語として判別できないようなもの凄い声をあげながら床に崩れ落ちていく葛城。今度はその左目に突き刺した。床に着地する前に。
床の上をのたうち回って痛がる葛城。切れた両目の角膜からゼリー状の何かがブニョブニョと漏れ出していた。
第二十三話
みんなに合図して階段へ向かう。のたうち回る葛城を残して。玄関前にある階段は暗い明かりが一個あるだけ。三人で急いで駆け上がる。目をやられた葛城はすぐには追ってこられないだろう。
二階の葛城の部屋の扉を開くと、明かりさえつけていない真っ暗な部屋。部屋の隅で紫色に浮かび上がる水槽。窓の外は激しい吹雪になっていた。
「あ!ここは窓に防犯柵も何もついとらんわ!」
「そう。この部屋はついてないの。だから葛城はここを自分の部屋に選んだのだと思うわ。まさか自分の部屋から逃げることはないだろうとね。これが盲点よ」
「でも外はすごい吹雪じゃない。こんなんで逃げられんの?」
「もう限界じゃ。暴力も飢えも」
「三人で逃げましょ」
凍えないよう葛城の部屋にあるコート・ジャンパーを三人でそれぞれ着て、窓を開けた。しばらく味わっていない猛烈な寒さが顔や手や耳を突き刺した。
夜の闇とこの吹雪に遮られて視界はすこぶる悪い。風上の方を見ないようにして窓のすぐ下の車庫の上に滑り降りて、他の二人についてくるよう促した。下の地面がクッション代わりになるとはいえ、一度に降りると怪我する可能性があると判断したからだ。まず叔父が滑り降り、最後に叔母が滑り降りたのだが、その時に雪でつるつるになりすぎている瓦のせいでバランスを崩して横向きに落ちてしまった。肩を強打した叔母が痛っと叫んだ声に誰かが反応した。
「そこにおるんやな!!」
部屋からすーっと人影が現れた。葛城だった。手には斧を持っている。
やばい!!私と叔父と叔母は急いで下へ着地。葛城はやはり目がちゃんと見えないらしく、車庫の上に転がり落ちた。
「おまえらー!」
もう死にものぐるいで逃げるしかなかった。雪に足を取られながらとにかく逃げた。後ろから葛城が追ってくるのが見える。寒さで全身がかじかんであっという間に触覚も痛覚もなくなった。
「美緻、もう走れない。ちょっと休もうよ」
叔母が音をあげた。葛城が追ってくる姿は見えなくなっていた。
「分かった。木陰でちょっと休もう」
雪に足を取られることで予想以上に体力を消耗していた。その上、この寒風が体力と気力をそいでいく。雪が三人に容赦なく叩きつけられているのだけど、それも今では肌で感じ取ることは出来ない。葛城は今どこまで来ているのだろう。
第二十四話
どこかからエンジン音が近づいてくる。キャタピラの回転音のような音もする。・・・北東方面から雪上車が近づいてくるのが見えた。助けてもらおう。
走って近寄っていくと、車窓から警官が顔を出した。
「おお、どうしました?」
「助けて!!」
「?」
「追われているんです!殺されそうなんです!」
乗っていた二人の警官は半信半疑の表情で顔を見合わせた。まあ、とりあえず乗れと促されて後部座席に乗せてもらった。
叔母夫婦の待つ場所へと雪上車を進める。曇天のため、轍を刻みつけている雪原に星明かりすら差さない。
そこへ車のルーフ(天井)にドン!!と鈍い音がした。車内の三人が何か声を発するのとほぼ同時にすぐにフロントガラスが砕け散った。葛城が来た、と思った。
飛散したガラス片でひるんだ警官に猟銃が向けられた。
「・・・さっさと止まらんかい」
三人とも固まった。
「美緻はシートの後ろに隠れろ」
葛城が何をしようとしているのか悟った助手席の警官が、美緻がシートの後ろに隠れたのを確認してからピストルを抜こうとしたのだが、間一髪早く葛城が銃身でピストルを叩き落とした。
「どらぁ」
警官の口に銃口を突っ込むと、
「誰がそんないらん事せぇゆぅた?」
銃声と共に血と脳漿が車の後ろ半分に飛び散った。
「キャーーーーー」
血塗られた車窓に脳の破片がゆっくりと滑り降りていた。
第二十五話
警官は慌てて急ハンドルを切り、葛城が雪上に振り落とされるのが見えた。後ろから二、三発発砲してきたのだが、それは幸い人体には当たらずに車体にヒットした。異常はないようだ。
そのまま車を走らせ、叔父と叔母が待つ木陰へ着いた。
「ああ!!おまわりさん!!」
「よかったあ。助かるんやな」
助手席の遺体を毛布でくるんでトランクに積み、叔父と叔母を加えたメンバーで雪上車に再び乗り込んだ。だがエンジンがかからない。何度やってもかからない。
「さっき撃たれたので故障したんでしょうか?」
「だろうねー。ちょっと応援を呼びます」
警官は無線で連絡を取り始めた。
「この付近に同じ署の車が走っとるはずです。じきに我々を見つけてくれると思いますわ」
雪上車の中からあたりを見ても、今のところ漆黒の空と雪原しか見えない。心細い。怖い。不安だ。警官がそばにいるとはいえ、殺人者がじりじりと後を追ってきていることに変わりはない。この夜景に沈殿する雪が視界を悪くしていることも、不安を募らせていた。
そこへ、雪上車のライトらしき光が南できらめいた。ほんの一瞬の出来事だが、林の向こう側にキラリと。
光は林を迂回して、我々の前にと姿を現した。警官は応援者を迎えるべく、車外へと出て走っていった。
だが、車から現れたのは応援に駆けつけた警官ではなかった。走って出迎えた警官をその場で処刑する銃声が雪原に鳴り響いた。
第二十六話
銃を構えたまま、こちらににじり寄りながら脅してきた。
「美緻以外、外に出ろ」
みんな顔を見合わせて、一様に動揺の表情を見せた。
「はようせぇ!!」
苛立った葛城が真ん前でバンパーを蹴り上げた。……諦めてみんな車のドアを開けた。これから我々をどうしようというのか。
葛城はみんなに手を頭の後ろに組んで後ろを向くよう指示した。何をしようとしているのか、誰の胸にも感じたことだろう。
雪原に乾いた銃声がこだまする。白いキャンバスに血の抽象画が描かれた。警官の頭を銃弾が貫通したのだろう。額と後頭部からどす黒い血が壊れた蛇口から安っぽく吐き出されては雪に滲んでる。
「美緻は俺の乗ってきた車に乗り換えろ。運転席だ」
もう一方の車に歩いていき、キャタピラに足をかけたところで葛城に訊いた。
「叔父と叔母はどうするの?」
「やかましいわ!置き去りや!!」
「でも……」
怒った葛城がこっちへ走ってきた。
第二十七話
あたしを突き飛ばし運転席に乗り込み、叔父と叔母に向かって突進していく。逃げまどう叔父と叔母を一人ずつはね飛ばすと、倒れた彼らの体を何度も何度も執拗に轢き殺した。人の命をなんだと思っているのだろう。あまりのことにその場にへたり込んだ。こんなに簡単に殺されるなんて。
葛城はもう一度あたしの所に戻ってくると、降りてきてあたしに再度乗るように促した。……運転席に乗り込むと、「このまま横浜へ帰れ」と指示された。雪上車は適当なところで乗り捨てていい、このまま横浜へ帰れと。
「あなたはどうするの?」
「横浜の時と同じように、どこかからおまえを見続ける」
さんざんあたしたちを追いつめておいて、あたしだけ逃げろってどういうことなのだろうか。彼の思惑が分からなかった。この数日間は、葛城にとって何だったのだろう。これから本当にあたしを見続けるだけなのだろうか。
アクセルを踏み、雪上車を発進させた。葛城がバックミラーの中で小さくなっていく。彼は何を考えているのか。
丸一日ほどかかって山を下り、雪上車を乗り捨てた。静岡駅付近の健康ランドで体を洗い、服をまともなものに着替えた。せめて職質されないように。静岡駅前の雑踏を歩きながら、奇妙な感覚を味わっていた。何だか異世界から戻ってきたような気分だ。
静岡駅からこだまに乗り、新横浜を目指した。
こだまのなかでしばらくうたた寝したあと、目覚めるとテーブルに手紙が挟んであった。文面にはこう書いてあった。
「好きだよ。君をいつでも見ている」
第二十八話
……以前と同じように、どこかから見ている目。あいつはどこかからあたしに欲情している。……足許の床を叩く落ち着きのない走行音や窓外を慌ただしく駆け抜ける夜景すら、あたしの精神状態を不安定なものにした。すぐ後ろを見る勇気も出ない。
一時間強ほどで新横浜駅に降り立ち、西区のマンションへと急いだ。久し振りの横浜を楽しむゆとりなど無かった。電車の車中の男性全てが怖かった。電車を降りた後の相模鉄道のプラットフォームですれ違う男たちですら、あたしに何をしてきてもおかしくない気がした。
マンションに到着し、玄関でパンプスを脱いだ。その時、部屋にあがる前、それどころか部屋の電灯をつける前に携帯電話にメールが届いた。真っ暗闇の中でバイオレットに浮かび上がった画面に無機質な文字が並んでいた。
「オカエリ、ミッチャン。新幹線ハ疲レタカイ?」
第二十九話
考える余裕もなく、ただただ怖くて近くにあった毛布にくるまって目をつぶった。……外に逃げる勇気も出ない。その内に視界から消えてくれるのを願った。毛布の外から聞こえてくる音は、窓に吹き付ける風の音だけ。
10分ぐらい経っただろうか。鍵をして出かけたはずの窓がすーっと開く音がした。そして窓の敷居をまたぎ、閉めたのが分かった。10秒ほど間があいて、フローリングをゆっくり踏みしめる音がこっちへ向かってくる。
葛城は毛布の前に立ち止まると、かがみ込んだようだ。毛布をかぶったあたしをじっと見ているのだろうか。……30秒ほどして、毛布越しにあたしをなめ始めた。
第三十話
あたしをいやらしくなめ回す。舌がナメクジのように這う。あいつの吐息が生暖かく吹き付けてくる。なめ回しながらあいつは徐々に興奮していた。
ひとしきり楽しんだあと、奴は立ち去っていった。みしみし床を軋ませて。
その夜のニュースで杉田君殺人事件の続報が流れていた。捜査の手は確実に核心へと及んできているのだろう。私に気づかれないよう私を見張っているでしょうし、葛城にも同様に刑事が張り付いているであろう。
翌日の晩、ベッドでうとうとしかけたタイミングで電話が鳴った。
第三十一話
電話を取ると、怒気を帯びてかすかに震えた葛城の声が聞こえた。
「オマエ、警察ニタレ込ンダダロウ?」
「そんな事してません」
「ウソヲツケ!警察ニペラペラ何デモシャベットンノヤロ?アア!?」
「……」
「オマエノセイデ、四六時中刑事ニ張ラレトルワ!!」
「……」
「イラン事シトッタラドウナルカ、モウイッペン ワカラセナ アカンナ」
ほとんど一方的にまくし立てると、葛城はがちゃんと電話を切った。キレた葛城は、明日からどういう行動に出るのだろう。
第三十二話
その夜、葛城の部屋に眼光鋭い男たちが訪問した。ついに、というか、今日逮捕状が出ていたのだ。逮捕状を見せられた葛城は逃走を図ろうとしたが、あたりを封鎖している警察にすぐ取り押さえられた。
店の女の子から電話で一報があり、テレビをつけると両脇を刑事にがっちり固められ、パトカーに乗り込む葛城の姿があった。手にはカーキ色のジャンパーが掛けらていたが、顔には何もかけず、少しうつむき加減で黙っていたその表情は、間違いなくあたしを苦しめ続けたあの葛城の顔だった。
悪魔が逮捕された。とうとう彼は居なくなった。つい数時間前まで恐怖に苦しめられていたのに。……しかし、彼の眼差しの呪縛からなかなか解放されない。降り落ちてくるはずの安堵感はなかなか私に降りてこず、ふわふわと遊離していた。
とにもかくにも、あたしは自由になったのだ。自由を実感しな!美緻。
店長からも電話があり、しばらく店は休んで休養しなさいと言われた。店の女の子からは……さっきのコ以外からは無かった。
確かに彼は逮捕された。でも、窓のカーテンを開けたり、外出したりする気にはなれなかった。カーテンも開けず、ドアも開けず、何日も自室に閉じこもっていた。
最終話
今まで住んでいたマンションを引き払い、新しいマンションへ引っ越した。また、勤め先も変更した。葛城が逮捕されたとはいえ、やっぱり怖かったのだ。葛城の残像は、私の心に深く爪痕を残している。今でも。
あんな事件があったとはいえ、あたしも生きていかなければならない。日々の生活は待ってはくれない。働いて収入を得なければならない。いつまでも仕事をしないわけには行かない。……新しいお店で、あたしはこれまで通り接客に励んだ。
そんなある日の夜、寝ていたあたしの枕元でメール着信音が響いた。携帯電話を手に取り、暗闇の中ぼうっと光る画面を確認すると、カタカナの大阪弁の文面が書かれていた。
「ミッチャン、ヒッコシタンヤナ。ドコイッタンヤ?」
……葛城だ。あたしが引っ越したことを誰から聞いたのだろう。……どうして留置所の中からメールが打てるんだろう。
「ヒッコストキニ カーテンヲ オイテイッタンヤナ」
確かに、カーテンはいいやと思ってそのままにして引っ越したのだが、何でそんなことまで知ってるんだろうと驚いたところへ、
「イマ、ミッチャンノ ヘヤノマエニ オルンヤ。ズット ツカットッタ チャイロノ カーテンガ ソノママニナットルネ。アタラシイヒト マダ スンデヘン ミタイヤネ」
とのメールが来た。ぞっとした。留置所を抜け出して、あの部屋の前に立っているのだ。
「ミッチャン、イマ、ドコニオル?」
怖くなって携帯電話の電源を切り、戸締まりを大急ぎで再チェックしてベッドに潜り込んだ。
眠ることなどできなかった。体中の血が逆流しているかのように感じられた。
一時間ほどして、ベランダの方で物音がした。そちらを見ると、見たことのある人影が映っていた。葛城だ。間違いない。
コンコンコン……。
爪の先でガラス面を軽くたたいているのだろう。あたしは声を潜めて存在を悟られないようにした。
コンコンコン……。
その叩き方に相手の苛立ちを感じる。怖い、怖い、怖い。お願い、早く去って!
バンバンバン!
扉がサッシからはずれそうなぐらい強打してきた。声を出しちゃいけないのに、もう泣きそうだった。
……あの人は、男なのだ。そう、男なのだ。
怖くて、よりいっそうベッドに沈んだそのとき、葛城は力ずくでベランダのガラスを割って侵入してきた。葛城の姿を直視することなどできなかった。
葛城に布団を引き剥がされると、みぞおちを強く殴られた。沸き上がってくる吐き気に耐えきれず、ベッドの上に嘔吐した。みぞおちに差し込まれた激痛が、手足に痙攣を否応無しに与えていた。抵抗する力も失った。胸ぐらを捕まれ、壁に押しつけられた。
「俺のキリストになってくれ」
あたしの右手を横に押しつけると、太い釘の先をあたしの右手の平の中央に口づけさせた。そして金槌を振り下ろした。釘が壁に刺さる音と共に、あたしの手の平に穴があいたのを激しく感じた。
そして左手も釘で壁に固定され、右足と左足も釘で固定された。キリストの最後のように、磔に処せられたのだ。
血みどろの手足にそれぞれ接吻すると、葛城は愛おしそうに呟いた。
「美緻、今のおまえは最高に綺麗やで。たまらんわ」
葛城が猟銃をあたしの口に押し込む様がスローモーションのように感じられた。
ドン!!
銃声が響いてすぐ、あたしの霊魂は自分の体から遊離していった。白い壁に血と脳髄と脳漿で抽象画を描き出し、口からは夥しい血を吐き出し、頭を垂れたあたしの体は、喩えようもなく美しかった。
処刑の直後、部屋に警察が踏み込み、「最後の芸術」を刑事たちも鑑賞できた。この猟奇殺人はスキャンダラスに報道され、やがて時と共に人々から忘れ去られた。葛城の行方は、誰も知らない。
−終−