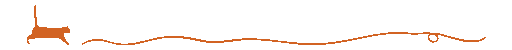
| 映画『ランナウェイズ』を観て 映画『ランナウェイズ』は、1970年代後半の登場したガールズ・ロック・バンドのヴォーカリスト、シェリー・カーリーの自伝を基にして、ギターとヴォーカル担当だったジョーン・ジェットが制作したもの。 これを観ると、ランナウェイズの成り立ちがよくわかる。どうしてもシェリー・カーリーとジョーン・ジェットの視点から描かれているのは仕方のないことなのだが、ハイスクール時代から暗さを秘めていたシェリー・カーリー、男に負けないロックをやりたがって突っ張っていたジョーン・ジェットの様子が描かれて行く序盤部分は痛快。 シェリーとジョーンの視点から描かれているせいか、ウィキペディアなどとの記述とやや異なっている。映画ではやがてふたりがプロデューサーのキム・フォウリーを介して出会い、女性だけのロック・バンドという企画が進行しだす。つまり、女性だけのロック・バンドが存在したのではなく、ロック・ビジネスが生み出したのがランナウェイズだったというわけだ。 私らがロックというものに理想を抱いていたころには、もうとっくにロックはビッグ・ビジネスになっていたということだ。1969年のウッドストックを愛と平和のコンサートだと定義したのも、ある意味まやかしのようなもので、あれだってロック・ビジネスの一環だったわけだというのに気付くのに、長い時間がかかってしまった。 それはそうだろう。ロックで食べて行くとなると、それなりの収益は必要だ。だからレコード会社も売れそうなバンドにしか契約しないし、事務所だって所属させない。それはそのバンドがいかに音楽的に優れていても、なんたってビジネスなんだから。 今でも、音楽が大好きな若者がミュージシャンの道を選ぼうと、街中で演奏している姿をよく見かける。ミュージシャンになろうというのは勝手だ。でも、もし仮に自分の作り出している音楽が、こんなに素晴らしいのにレコード会社はどうして振り向いてくれないのだろうと思っているなら、それは、あんたじゃ売れないということなのだ。会社はビジネスをして成り立っている。会社は慈善事業団体じゃないのだ。 ランナウェイズに話を戻そう。ウィキペディアによるとプロデューサーのキム・フォウリーはギターとヴォーカルのジョーン・ジェットとドラムスのサンディ・ウエストを引き合わせ、さらにギターのリタ・フォードを加え、ベーシスト(当初はコロコロ変わった)を入れてバンドを結成したのだという。さらにもうひとりバンドの花(?)をと思ったのか、シェリー・カーリーを入れたということになっている。 映画はバンドでシェリーに歌わせようとして、キム・フォウリーが『チェリー・ボンブ』を即興で作詞作曲するシーンがある。キムはシェリーに女性であることを強調させるような演出を加えていく。「男の生理で考えろ」といった意味の、かなり難題を15歳の少女に押しつけるのだから無茶だ。 映画ではこのあと、レコード会社と契約してデビューする様が描かれる。1976年ファースト・アルバムがリリース。1977年セカンド・アルバム『クイーン・オブ・ノイズ』リリース。その後のワールド・ツアーで日本で公演した様子が映画でも再現されている。 私もランナウェイズのライブを新宿厚生年金会館で観た。この時にウドー音楽興業は上手いことを考えた。厚生年金会館を一日借り切って、昼はランナウェイズ、夜はロキシー・ミュージック解散後のブライアン・フェリーの興業を行ったのだ。私? もちろん昼夜とも行きましたとも。ブライアン・フェリーのバックにはロキシーからの流れでギターにフィル・マンザネラ、ドラムスにポール・トンプソン。ベースがジョン・ウェットンでサックスにメル・コリンズがいるという豪華版。しかも凄腕ギタリスト、クリス・スペディングがいるという、凄いバンドだったのだが、今回はランナウェイズだ。 ランナウェイズの日本公演の模様は後に、『ライブ・イン・ジャパン』というライブ盤が出ることになる。 映画でも描かれているように、彼女たちは熱狂的に日本に迎えられる。それは当時のマスコミ媒体と、レコード会社との異常な繋がりがもたらしたものだと思う。当時、おそらくクイーンが若い女性ファンを獲得したことから、レコード会社各社の、ティーンエイジャーの女性に対する海外のロック・ミュージシャンの売り込みが激化していくことになる。 レコード会社が売り込みをかけたのは、ロック専門誌だけではなかった。ティーンエイジャー向けの女性誌(例えば『セブンティーン』など)、それに『週刊平凡』や『週刊明星』といった歌謡曲雑誌にも猛然とタイアップ記事を持ち込んだのだ。おかげで、クイーン、キッス、エアロスミ、チープ・トリック、それにいささか色合いの違うベイ・シティ・ローラーズまでごったにされ、それにランナウェイズまで影響を受けたというのが真相だろう。 ラジオ媒体だってそうだ。野球中継のないストーブ・リーグの夕方は海外ロックの番組が結構あったし、テレビでも夕方の若者向け番組では取り上げられることもあった。 ランナウェイズ来日直前には、確か『ミュージック・ライフ』が増刊号を出して、ランナウェイズの写真集を出していた記憶がある。それにはシェリー・カーリーのコルセット姿で歌っている写真もあり、局部が見えていると内輪で話題になったこともある。また日本の媒体はライブ以外のオフの様子の写真を欲しがった。映画の中でシェリー・カーリーが自宅の庭でポーズをとる写真が掲載された日本の雑誌を巡って、メンバー間が険悪になる様子が描かれているが、これも事実なんだろう。あくまで自分たちはミュージシャンなのだと思っているメンバーとの間で亀裂が入ったのは、日本のマスコミのせいなのかもしれない。 しかし、彼女たちも幻想を抱いていたのかもしれない。ロックというものはビジネスになってしまっていたのだ。事務所、レコード会社、マスコミ、興業会社が一体となり、金儲けの手段にもなって行ってしまったのだよ。 ショッキングだったのは、シェリーたちが日本へ向かう飛行機の中でドラッグをやっているシーン。彼女たちにしてもドラッグに負けてしまっていたとは、やや残念な思いがした。 さて、1977年の日本公演の途中でベースのジャッキー・フォックスが脱退してしまう。このときの 公演を観ていた感想からすると、確かにバンド自体がギクシャクしていたなあという印象。シェリー・カーリーは出ずっぱりではなく、ジョーン・ジェットがヴォーカルをとって四人編成になる曲が多くて、実際、シェリーの見せ場はコルセット姿で『チェリー・ボンブ』を歌うところ。それもジョーンと比べると声が細くて、ロックにまるで向いていない。 なにしろ、リタ・フォードのギターは聴きごたえあるし、サンディのドラムスも凄い。そこにシェリーである。バンド内部で軋轢が出来るのは当然だったのではと想像される。現実にシェリーは脱退。このへんは映画での描写でも辛いところだ。 この私も70年代後半、ロックに夢を抱いて、業界の片隅で仕事をしていたひとりだった。そして業界の裏を覗いてしまうと、夢と現実がまったく別だったことに愕然とすることになった。そんなあの時代を思い出させる映画ではあり、また日本のロック・ビジネスもなんかおかしな方向に向かっていた時代でもあったんだなあと、この映画を見ながら思いだしたのでありました。 2011年4月29日記 このコーナーの表紙に戻る |
 ふりだしに戻る
ふりだしに戻る