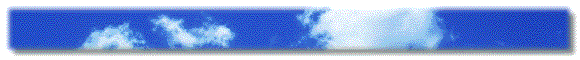- 子どもの社会力 門脇 厚司著
- 「いじめ」「学級崩壊」など、子どもたちをめぐる深刻な状況の原因は何か。他人への愛着・関心・信頼が失われていく背景を追うことで、人と人がつながり社会を作る力としての「社会力」の意味と重要性を示し、成長過程で必要な大人の働きかけや、「冒険遊び」などの地域での実践を訴える。 (岩波新書 660円)
- 子どもの危機をどう見るか 尾木 直樹著
- 続発する少年事件、いじめや不登校、学級崩壊への心配。子どもの危機は、社会の危機である。どう打開すればよいのか。危機をもたらした背景を丹念に解明し、子育てと教育を再生させる考え方と実践例を示す。 (岩波新書 660円)
- 「学級崩壊」をどうみるか 尾木 直樹著
- 小学校低学年の学級崩壊は、なぜ全国的に広がっているのか。子育て調査と教師体験の実績を踏まえ、一人担任制の強制的な一斉授業から、子どもが納得し共感するゆとりある授業への転換などを提言する。 (NHKブックス 970円)
- 学校は再生できるか 尾木 直樹著
- いじめ、不登校、普通の子のナイフ事件、援助交際…。その背景とは何か。優れた教育実践家が、学校荒廃の現状と学校内外の要因を見る。「子どもを主役に」を旗印に従来の子ども観の一大転換をはかって、子ども自己決定力の確立と学校再生の道を展望する。 (NHKブックス 1070円)
- やわらかな脳のつくり方 吉成 真由美著
- 脳の専門家が頭の特効薬を処方する。「子どもをキレさせない処方箋」「学級崩壊を斬る」「日本の若者の老化現象」など教育への新しい視点を提供してくれる。 (新潮社 1600円)
- 学校を創る―茅ヶ崎市浜之郷小学校の誕生と実践 著者代表 大瀬 敏昭 監修 佐藤 学
- 子どもと教師と親と市民が育ち合う「学びの共同体」づくりを推進する茅ヶ崎市のパイロットスクールとして誕生した、浜之郷小学校。堅実な教育実践を基調とした学校づくりの3年間の歩みが描かれている。浜之郷小学校は、これからの公立学校の可能性を示している。 (小学館 1700円)
- 「学校」が教えてくれたこと 山田 洋次著
- 著者が、映画『学校』を製作する中で、いろんな校長、教師、生徒たちや親たちに出会う。その出会いで考えさせられたこと、教えられたことを綴る。「授業というのはクラス全員が汗をかいて、一生懸命になって作るものなのだ」 著者からのすてきなメッセージである。 (PHP研究所 1300円)
- 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト レイチャル・ハリス著 石井千春訳
- 巻頭の詩「子は親の鏡」をいつも心に留めておきたい。子どもの個性と長所を伸ばしていくのが親の役目である。この本は、父母に子育ての知恵を授けてくれる。 (PHP研究所 1500円)
- 教師の感性をみがく 佐久間 勝彦著
- 著者が、すてきな教師に出会うためにつづった報告である。出会った人たちは、教師としての感性をみがきつづける大切さを教えてくれた。読み終えて心洗われる。 (教育出版 1800円)
- なぜ学校にいかせるの? 寺脇 研著
- 現役の文部省の官僚が世間の教育に対する疑問に答える。教育では「夢を持たせる」ことが大切だと強調する。「学校が変われば生徒も変わる」 教員が本気で考えなければならないことである。 (日本経済新聞社 1400円)
- 教え方のプロ・向山洋一全集 12 家庭教育の指針 向山 洋一著
- 著者の主張は一貫している。それは「子どもの事実」と「実践の手応え」を大切にしてきたからである。「伸びる子のタイプ」や「子どもを育てるポイント」の章は頷ける内容である。「努力と成長の法則」を証明したい。 (明治図書 1800円)
- 学力崩壊 和田 秀樹著
- 日本中の子どもを巻き込んでいる変化は、学習時間の減少とそれに伴う学力低下である。学力低下で国が滅びる。間違いだらけの教育論議を指摘しながら、読者に「わが子」の勉強を勧める。 (PHP研究所 1300円)
- 大衆教育社会のゆくえ 苅谷 剛彦著
- 大衆教育の社会の成立とそのゆくえ―教育が、戦後日本社会の形成にどのようにかかわったきたのか、日本の将来にどのような影響をに及ぼしうるのか。これらの問題に、日本と外国の社会を比較することによってアプローチする。 (中公新書 700円)
- 教育改革をデザインする 佐藤 学著
- 学校を内側から変えるための明確な指針と具体的な道筋を提案する。「学びの共同体」としての学校づくり。子どもたち、教師たちが学び育ち合う場所だけでなく、親や市民も学校教育に参加して、教育行政の人々も学校の改革に協力して学び育ち合う学校改革を提言する。 (岩波書店 1700円)
- 「まなび」の時代へ 地球市民への学び・30人の現場
- ワークショップ・ミュー編著
- 環境教育、ボランティア学習、体験学習、ワークショップなど「新しい学び」を実践する30人のファシリーテーターたち。混迷する教育への「代案」。教育への未来が本著に示される。 (小学館 1800円)
- 教育改革 ―共生時代の学校づくり― 藤田 英典著
- 個性を生かす教育の実現、いじめ・不登校の克服など学校の諸問題に、新たな角度から光をあて、学校週五日制や公立中高一貫校の導入等が子どもや社会に与える影響を検討する。真の教育改革の指針を提示し、学校・家庭・地域の連携による教育の再生を考える。 (岩波新書 700円)
- ニッポンの学校ってどんなとこ? ゲイル・R・ベンジャミン著 佐藤由紀訳
- アメリカの母と二人の子が体験したニッポンの小学校。母は文化人類学者。一人の外国人研究者の視線に、自分たち日本人が教育システムについて、つい見落としてしまいがちな部分への批判を読み取ることができる。母国の教育を日本の学校から見直そうとしている。 (白揚社 2300円)
- 総合学習の思想と技術 加藤 幸次著
- 「今なぜ、総合学習なのか」の問いに明確に答える。「まず、子どもありき」と学習活動の中心に「子どもたち」を置く。総合学習をめぐって、児童中心主義の思想を吟味し、実践をふり返るべきと提言する。第一の総合学習の源流をデューイ・スクールと考え、記述した部分が興味深い。 (明治図書 1160円)
- 野口流・硬派学校づくり論 野口 芳宏著
- 国語の優れた実践家が、校長としての4年間の実践を著す。校長は、例えれば、機長であり、船長であり、司令官である。学校の決定権は、責任者である校長にある。校長は、その決定について部下職員を納得させるだけの力量、識見、信頼を身に付けるべきだと、著者は説く。 (明治図書 2000円)
- 学校って何だろう 苅谷 剛彦著
- 全国3万人の大学生が選んだ№1.ティーチャーが中学生にメッセージを贈る。「どうして勉強するの?」「校則はなぜあるの?」の疑問をいろいろな角度から見直し、読者と共に考えていく。「学校と社会のつながり」の章は、学歴社会と学校の関係を考えさせられる。 (講談社 1400円)
- みんなの学校問題 池上 彰著
- どうして学校は崩壊するのか? みんなと違うことで生まれる「いじめ」、偏差値と通知表におびえる子どもの実態は? PTAは誰がやる
?など、学校の「大疑問」を、NHK「週間子どもニュース」キャスターが分かりやすく解説する。
(講談社 1500円)
- 学校崩壊 河上 亮一著
- 学力は低下、外界に全く無関心、他人との関係が作れない、授業中に私語しても悪いとも思わない生徒が続々と登場しつつある。著者は学校の実態を報告するとともに、学校が崩壊寸前に至った原因を示し、再生への道を探る。 (草思社 1500円)
- 学校の失敗―誰が子供を救うのか 向山 洋一著
- こうすれば学校は甦る! 「自由」という名の「放任」が″学校崩壊″を生んだ。子供のやる気のツボを押さえれば、子供たちに笑顔が戻ってくる。父母、教師必読のその方法とは― (扶桑社 1500円)
- 教育のみらい 学校のゆくえ 下村 哲夫著
- 少子化の進行する中での教育と学校の実態を検証し、いかにして教育の未来を開き、そのために学校をどう変えていくかを具体的に示した、教師必読の一冊である。 (教育出版 2000円)
- 学校の条件―いま学校が問われていること 下村 哲夫著
- 学校は各方面から厳しい問いかけを受けている。本書は、学校が当面する諸課題を取り上げ、どうしたらよいか、新しい学校の在りようを提言する。 (学陽書房 2200円)
- 21世紀を築く学校 下村 哲夫監修 原崎 茂・小杉 康裕編著
- 岐路に立つ日本の教育を切り拓く。実践を踏まえて追求した新しい学校の創造を提言する。新世紀を切り拓く子どもの育成を目指して。 (学陽書房 1900円)
- 学校って、なんだろう 産経新聞「じゅく~る」取材班
- なぜ学校はここまで信頼を失ったのか。ニュースではわからない教育現場の苦悩ぶりを丹念に描きつつ、学校再生の道を探る。 (新潮社 1300円)
- 今どきの教育を考えるヒント 清水 義範著
- みんなの「教育問題」を根本から深く追究。子どもたちの問いに答えようとしない、先生・親・文部省のお役人、そして世間の大人に成り代わり、清水博士が答える。 (講談社 1500円)
- 学校はなぜ変われないのか―その理由を探すあなたへの処方箋 中野 重人著
- 子どもが行かない学校でよいのか―客が来ない店はつぶれる―いまや横並びの学校ではない―同じような品物ばかりで客は来るか―叱られるだけの学校でよいか―小言をいわれて客は寄りつかない―子育ては学校だけの専売特許ではない!―学校と家庭と地域社会と 「生活科」の生みの親が、学校の変革を訴える。 (明治図書 1200円)
- いじめと不登校 河合 隼雄著
- 日本人の生き方が問われている。子どもと学校に関心のあるすべての人に。中学生から大人まで一読損をしない人生処方箋。欧米の教育を参考にしつつ新しい日本の教育のあり方をつくり出そうという自覚と決意が日本の教育改革に必要だと提言する。 (潮出版社 1500円)
- 学校の先生には視えないこと 藤井 誠二著
- 学校に先生や生徒の他に養護教員や事務職員、図書館司書、学校現業職員などいるのは比較的知られているが、スクールカウンセラーやボランティア学校相談員などの存在はあまり知られていない。しかし今、学校では、これらの人々が教育に新しい息吹を入れ、学校再生を果たそうとしている。本書は、学校で働く「先生」以外の人たちのインタビュー・ルポである。「学校の先生には視えないこと」を視ることができる。 (ジャパンマニシスト 1600円)
- 子どもの心が見えますか 梶原 千遠著
- 不登校、引きこもり、学級崩壊、キレる子、落ち着かない子……そのとき子どもは何を思っているのか? 親や教師はどうすればいいのか? 問題行動の奥にひそむ本当の「こころ」を、学校カウンセラーが読み解く!(マガジンハウス 1500円)
|
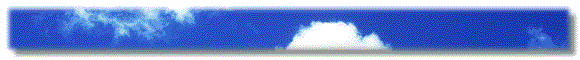 ・
・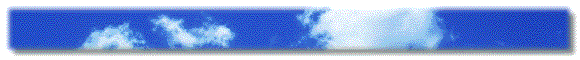
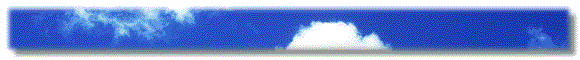 ・
・