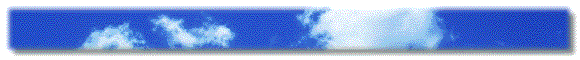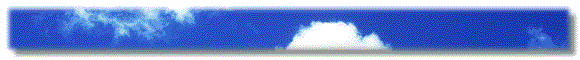
|
1 発掘調査が行われて (1)いつ 平成11年(1999年)9月から発掘調査が始められ、 平成13年(2001年)3月まで行われました。 (2)どこで 高崎市下滝町(高崎市の東部)に下滝 天水遺跡はあります。 (3)だれが 群馬県埋蔵文化財調査事業団が調査 しています。 (4)なにを 高崎伊勢崎線の南から井野川までの 地域を発掘調査します。 調査面積は、約9,700㎡です。 (5)どうして 主要地方道前橋長瀞線が建設される ためです。 (6)どのように 道路や水路を境にして調査をする地域を区に分けました。 南(井野川)からA区・B区・C区・D区・E区と名付けました。 2 遺跡の位置と周りには 下滝天水遺跡は高崎市下滝町にあります。現在、遺跡の周りには水田や畑が広がり、家々も建ち並んでいます。この遺跡は井野川の左岸段丘上にあり、標高約79mに位置します。井野川は、榛名山の南側山腹を水源とする河川です。井野川は北西から南東に流れ、この遺跡の南東1.5kmで烏川と合流し、これをさらに5km下り、利根川に合流します。 井野川の左右両方の段丘上には、弥生時代以降の遺跡がたくさん分布してます。特に左岸段丘上には、周りよりわずかに高い土地が帯状に伸びています。この小高い土地にあり、下滝天水遺跡の近くにある主な遺跡を紹介します。 下滝天水遺跡の北西には、群馬県の古墳時代初期の古墳、全長が90mの前方後方墳、将軍塚古墳があります。井野川の上流には、中・近世の城館址の元島名遺跡、弥生時代から平安時代にわたる大規模な住居址群、方形周溝墓、古墳群が発見された、鈴ノ宮遺跡などがあります。 慈眼寺付近には、全長約30m、横穴式石室をもつ前方後円墳、御伊勢山古墳を始め、10m~20mの小さな円墳が数多く見られます。また、井野川と烏川の合流する付近には、直径70m、竪穴式石室をもつ円墳の若宮北古墳と古墳時代後期の小さな円墳が集まる若宮古墳群があります。 井野川の右岸には、前方後円墳である観音山古墳、不動山古墳などがあります。 将軍塚古墳 史跡整備された観音山古墳 3 調査日記 今年度は(2000年)、D区、B区、A区の順に調査を進めています。 まずD区の調査内容を紹介します。D区の基本の土層は下のようです。 D区の土層 ← 表土 ← As-B混土 (1108年に浅間山の噴火で降下した軽石を を含む。) ← 黒褐色土 ← Hr-FP・Hr-FA泥流 (6世紀に榛名山の2回の大噴火に ← 黄色砂質シルト による泥流層。) ← As-C混土 (4世紀初めに浅間山の噴火で降下した軽石 ← 黒色土 を含む。) 4月26日(水)に2つの面の全景写真を撮影しました。一つは、Hr-FA泥流下水田面で、一段高くなっています。もう一つはAs-C混土水田面です。わずかながら水田の畦の痕跡が認められます。いずれも古墳時代の水田跡と考えられます。 As-C混土水田面では、大きな溝が見つかりました。 から南東へ向けて走っています。水田の畦の方向と合わせて考え ると、当時の地表面の傾斜に沿って、水田の畦や溝が作られたよ うに思われます。 また下のような遺構が出てきました。もしかしたら人の足跡か馬 の蹄跡かもしれません。 続いて5月31日(水)にD区の最終面の全景写真 を撮影しました。ここでは数条の溝が見つかりました。 風倒木痕も数箇所で確認されました。4世紀以前の 遺構と考えられます。 B区は、現在の道路によって1区と2区に分けられました。 B1区では、中世の掘立柱建物の柱穴跡が見つかりました。 また、しっかりと掘られた数条の溝が見つかりました。溝は、 中世以前に起こった洪水によって運ばれた土砂で埋められ ていました。 さらに調査を進めると、古墳時代の竪穴住居跡が1件、発見されました。この住居跡では多数の土器が出土しました。住居の床に貼り付いていた厚手の土器や、祭り用に使われたとされる土器(「坩・かん」と言います。)が出てきました。土器は古墳時代のものです。土器や炉(ろ)から見て、4世紀代の住居跡と考えられます。 調査中の竪穴住居跡 出土した厚手の土器 祭り用の土器(上) 後の調査で古墳時代の住居跡は、B1区の南側にあるA1区でも30件ほど見つかりました。ただ、同じ時期に何件の住居が建てられていたのかはわかっていません。 B2区では、中世以前の畠が見つかりました。写真から掘り込んだ溝の様子がよくわかります。当時の畠では、溝と溝の間に盛られた土のところ(「畝・うね」と呼びます。)で作物が栽培されていたのだと思われます。 A区の調査の様子を見ましょう。A区を現在の農道によって、1区と2区に分けました。南側を東西に流れる井野川に近い区を1区、農道をはさんで北側を2区としました。 A1区では、中世と古墳時代の溝が発見されました。 中世の溝は4mの幅があり、直線部分が80mある大きな 溝です。中世に掘られた溝が、江戸時代になって埋められた と考えられます。そのため、溝の中にはたくさんの石と共に 陶磁器の破片が投げ捨てられていました。この溝は、遺跡の 東側にある中世の館跡の下滝館に関係する施設の一部と考 えられます。  古墳時代の溝は幅3mほどの直線的な溝です。断面は台 古墳時代の溝は幅3mほどの直線的な溝です。断面は台形を逆さにした形をしていて、底が平になっていました。5世 紀代を中心にたくさんの土器が出土しました。中世の溝の掘 り方の違いがよくわかります。 た。写真の住居跡の奥の壁には、カマドに使用された部分 がくぼんでいます。カマドの使用は古墳時代の5世紀代に始 まり、奈良・平安時代に引き継がれていきました。 |
メールはこちらへ |
トップページへ |