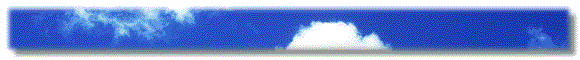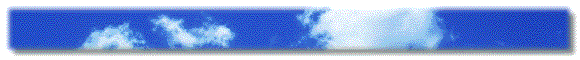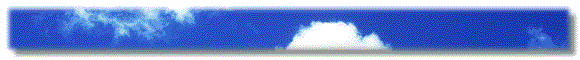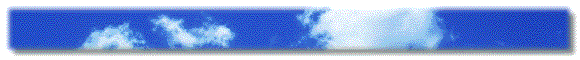1 発掘調査が行われるまで
(1)いつ 
平成13年(2001)年4月から1年間を発掘調査を行いま
した。
(2)どこで
北群馬郡子持村大字吹屋(ふきや)小字糀屋(こうじや)
に遺跡があります。
(3)だれが
群馬県埋蔵文化財調査事業団が調査をしました。
(4)なにを
道路建設予定地で小字名が「糀屋」の地域を調査しました。
(5)どうして
国道353号(鯉沢バイパス)道路が建設されるため、事前に調査を行いました。
(6)どのように
調査区を現在の道路を境にして区に分け、東からⅠ・Ⅱ・Ⅲ区と名付けました。
2 遺跡の場所の周りには
吹屋糀屋遺跡は、群馬県のほぼ中央、北群馬郡子持村に位置します。現在、本遺跡の周辺にはコンニャク畑が広がり、家々も建っています。子持村は、東に赤城山、北に子持山、西に榛名山があり、三方を山に囲まれています。北からは利根川が南流し、北西から吾妻川が流れ、村の南側で合流しています。子持村は、子持山の扇状地と利根川・吾妻川による大小いくつかの河岸段丘からなっています。本遺跡は、下から2番目の河岸段丘上(「白井面」と呼ばれています。)に位置します。調査区の標高は約208mです。
子持村の大部分は、古墳時代に2度の榛名山の噴火による火山灰や軽石、泥流に覆われた地域です。火山灰や軽石を取り除くと、榛名山の噴火直前の地表面が出てきます。そこには当時の人々の生活した痕跡が現れます。軽石で埋もれた代表的な遺跡として、国史跡の黒井峰遺跡や、西組遺跡があり、竪穴住居跡や平地住居跡などからなる集落が見つかっています。吾妻川を挟み、渋川市では火山灰に埋もれた竪穴住居跡や祭祀場跡などが中筋遺跡で見つかっています。また、住居跡以外でも水田跡や畠跡や放牧地など生産に関係する遺構も見つかっています。白井北中道遺跡では畠跡や数多くの馬の足跡が発見されています。本遺跡に隣接する北牧大境遺跡では、軽石の下から一辺が1〜1.5mの区画のミニ水田が見つかっています。
3 発見されたもの
Ⅰ 軽石層(Hr-FP)上の調査
* 榛名山二ツ岳降下軽石(Hr-FP)の噴出年代 6世紀中頃 
中〜近世 掘立柱建物跡 井戸 土坑
平安時代 住居跡
Ⅱ 軽石層(Hr-FP)下の調査
古墳時代後期 水田跡 畠跡 放牧地跡
Ⅲ 火山灰層(Hr-FA)下の調査確認できなかった。
*榛名山二ツ岳降下火山灰(Hr-FA)の噴出年代 5世紀末
古墳時代中期 水田跡 放牧地跡
Ⅳ 黒色土層中
古墳時代 竪穴住居跡 掘立柱建物跡
4 Ⅰ区のおおよその調査内容
① 軽石上の調査 土坑、竪穴住居跡
(奈良時代〜近代) 土坑は貯蔵穴、近代か? 竪穴住居跡を3件検出。平安
時代の羽釜の破片が出土。鉄くずも出土。小鍛治に関係
する遺構か?
② 軽石下の調査 水田跡、畠跡、放牧地跡、道跡、溝
(古墳時代後期) 畠跡は東側の台地上に作られていた。水田跡は低地に作
られいた。放牧地跡では馬蹄痕跡や道跡が見つかった。
③ 火山灰下の調査 水田跡、土坑、溝
(古墳時代中期) 水田跡は低地に作られていた。軽石下水田に比べ、畦畔
が低く、区画が不定形であった。
④ 黒色土中の調査 竪穴住居跡、土坑
(古墳時代初頭) 台地から見つかった。土器を中心に遺物が出土した。
勾玉や臼玉が出土した住居もあった。
⑤ ローム層上面の調査
(縄文時代) 土器が少量出土したが、遺構は確認できなかった。
Ⅰ区 軽石下水田跡 火山灰下全景 竪穴住居跡
|