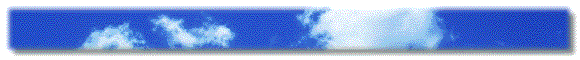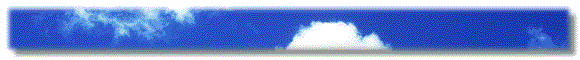
|
1 発掘調査が行われるまで
(1)いつ
平成14年(2001)年6月20日から平成14年8月31日まで
(2)どこで
前橋市大手町1丁目1番地、県庁敷地内に遺跡はあります。
(3)だれが
群馬県埋蔵文化財調査事業団が調査をしています。
(4)なにを
県庁敷地内で前橋城の城跡を調査しています。
(5)どうして
県民広場を整備するため、事前の調査を行っています。
2 前橋城とは…
中世、前橋には廐橋(まやはし)城がありました。その築城は、15世紀末、長野氏に
よるといわれています。近世に入ると、廐橋城(前橋城)は前橋藩の城として整備され、 本遺跡付近は城内に入り武家屋敷や堀として使われていました。城の東側には城下 町が整備されました。現在、前橋市はその城下町として発展しています。前橋城跡は、 明治9年に県庁が置かれた後は、官庁街として利用されています。
3 遺跡の位置と周囲には
(1)地理的環境
本遺跡は、前橋市大手町にある群馬県庁の敷地内に所在し、前橋台地の北端部に
位置します。前橋台地は榛名山南東に広がり、利根川旧流路と井野川とに挟まれた 台地です。標高は約108m、利根川との比高差が約12mです。現在の利根川は、前橋 台地中央を流れていて、15世紀後半頃に流路が定まったものとされています。それ以 前の利根川は、大手町の北側で現流路を離れ、前橋市街地北東部を通って南東方 向に流れていました。利根川流路変化前、大手町周辺は現在の利根川対岸とは台地 上に一続きでした。
本遺跡周辺の主な堆積層は、次のようです。
表 土 (上層)
総社砂層 (榛名山を起源とする)
前橋泥流堆積物(約2万年前、浅間山の山体崩落による)
前橋砂礫層 (利根川によって運ばれた)
(2)歴史的環境
中世になると、上野国守護に上杉氏が任命されました。上杉氏から上野国守護代
に任命された長尾氏が、国府の地に蒼海城を築き拠点としました。15世紀中頃にな ると、内乱や一揆が各地で起こり、長尾氏の勢力は次第に衰えました。やがて、西 上野で勢力を伸ばしてきた箕輪の長野氏は、利根川沿いの石倉の地に城を築きま すが、利根川の変流により壊滅してしまいます。変流した利根川の東側に残った郭 を利用し築いたのが、厩橋城(前橋城)とされています。
戦国時代、東国では小田原の後北条氏、越後の上杉氏、甲斐の武田氏を中心とす
る武士団が勢力を争いました。上州においても三つ巴の争いを繰り返し、戦乱の中で 厩橋城は戦略拠点として重要な役割を担っていました。
近世になると、厩橋城(前橋城)は前橋藩の城として整備され、城下町もそれに引き
続き整備され、各地の産物・商品が盛んに流通しました。
明治時代になると、前橋城は廃城となり、やがて前橋城跡には群馬県庁が置かれ、
前橋は県都として発展を遂げることになります。
4 発見された遺構と遺物
調査区内で、幕末の再築前橋城本丸「本城門」の土橋と堀の一部が確認できまし
今回、確認できた再築前橋城「本城門」に伴う堀は、再築前の前橋城三の丸「三た。土橋の幅は約11mです。調査の結果、今回発見された土橋の石垣は、明治以 降に修築されていることがわかりました。また、本丸を区画する堀の立ち上がりが 北側で確認され、堀の深さは3mを超えました。 ノ門」の堀に相当します。今回の調査箇所は、再築前の前橋城絵図によると、三ノ 門東側の枡形と堀、堀に架かる木橋の部分に当たります。土橋の部分を掘り上げ ると、枡形の西側の一部に再築前の石垣が残っていました。しかし、堀に架かると される木橋の痕跡は、調査区が狭く発見できませんでした。
|
メールはこちらへ |
トップページへ |