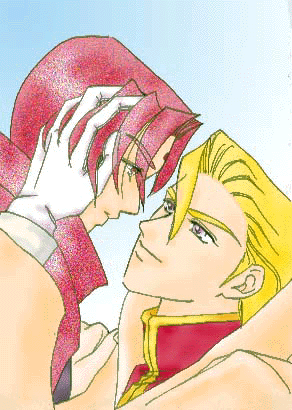
| Too Sweet Honeymoon |
「こーゆーのって何て言うんだっけー…」
ぼんやりと視線を泳がせていたシグナルが、ぽそりと呟いた。
「…何の話だ。」
長身の体を心もち屈めるように弟の顔を覗き込んで、男は訝しげに眉を上げる。ロボット特有の端正な容貌に、自信に満ちた余裕のある表情が浮かぶ、身内の欲目(があるとも思えないが)を差し引いても余りあるいい男ぶりに眩暈を感じつつ、少年は突っ伏した姿勢からオラトリオを睨み付けた。
見下ろす紫の瞳は透き通る朝焼けの色。はらりと一筋落ちた金の髪は、鈍く陽の光を宿して。戦闘型にも劣らぬ運動性能、桁違いの演算能力。そして何より、『最強』と称して憚らぬ守護者としての実績とプライドを持つ、音井ブランドの一人であるということ。
「そりゃあね、かっこいーと思わなくもないよ、ぼくだってオラトリオのことは!」
ふてくされた様子でじろりと見上げられた男が、意外そうに瞬きをした。
「…お前、何か悪いモンでも食ったんだろう?」
「う゛ー…何かそれに近いかも…」
の、割には押さえてるのは頭だ。のっそりと体を起こしたシグナルが頭を抱える。動きにつられて、プリズムの波がふわりとうねった。
「おーい、大丈夫かシグナル?」
いつになく具合の悪そうな弟に、オラトリオの瞳が僅かに曇る。よしよし、と撫でてくれる白い手袋の優しい動きに素直に目を細めて、シグナルが溜息をついた。
「…そーだよなぁ、優しいトコだってないわけじゃないんだよ。」
「さっきから何気持ちの悪りぃこと言ってんだお前は…」
呆れたように後頭部をぺしっ、と叩かれて、少年がかみついた。
「オラトリオが悪いんだからなぁっ!」
「だーかーらー、何の話だって。」
ん?と面白そうに覗き込んでくる悪戯っぽい表情も似合っている。似合ってはいるがしかし。
「だからって、これはセクハラだと思う!」
「───はぁ?」
何じゃそりゃ。
シグナル少年が持ち出したセクハラとは、セクシュアル・ハラスメントの略称である。性的嫌がらせ、という訳語が当てられることが多く、一般には男性が女性に行うとされているが、ごく少数女性から男性に対して行われることもあるし、実は同性同士でもごく普通に見られたりもする。大は刑事犯罪から、小は日常的な会話までに適応される言葉ではあるのだが。
ここで出てくるかそれが?
自分が入ってきてからの一連の会話を思い返して、オラトリオは首を捻った。疑問を乗せた視線を投げる兄に、シグナルは憤懣やるかたなし、といった様子でまくし立てる。
「オラトリオは格好いいし、優しいトコだってあるし、ぼくから見たってそりゃあいい男だけど!」
「…ほー…」
何だか珍しい物でも見るように上から下までを眺め回している男に、さすがに照れたのか顔を真っ赤にした少年が続けた。
「『オラトリオってかっこいいよね』とか『誰にも負けないくらい強いし』とか『弱点なんかないよ』とか聞かされるのはともかく!」
「…まだあんのか。」
オラトリオは呆れたような視線を、カウンターの向こう側でのんびりとお茶を楽しんでいる相棒に向ける。前述の美辞麗句の数々は、まず間違いなく彼の口から出たモノだろうということが容易に察せられたので。
一方、シグナル少年に対して彼言うところのセクハラ発言を遠慮なくかまして下さったオラクルはというと、あくまでおっとりと首を傾げた。
「ええと…どうしてあんなにキスが上手いのかな、って…言ったかな?」
「『ついその気になっちゃうんだよね』とも言ってたよ…」
すごくきもちいいんだよ、知ってるかい?とかさー、と、しくしくカウンターに懐いたシグナルが補足する。
「ああ、そうそう。」
にっこり笑ったオラクルが手放しで称讃した。
「すごいね、シグナル。ちゃんと覚えてるんだ♪」
「…忘れたいよぼくは…」
今にも泣き出しそうなシグナルを気の毒そうに眺めやり、オラトリオは苦笑してオラクルを手招いた。ほてほてとカウンターの内側から出てきた青年が、窺うようにおずおずと口を開いた。
「何かまずかったかな?」
世間知らずのゆえに、時折言わなくても良いことまで口にしては窘められていることを多少は気にしているらしい。ちょっとだけ雑音(ノイズ)の瞳が不安そうに揺らめくのに、オラトリオの手がすい、と差し伸べられる。
「…まあ、まずいと言えなくもないな。」
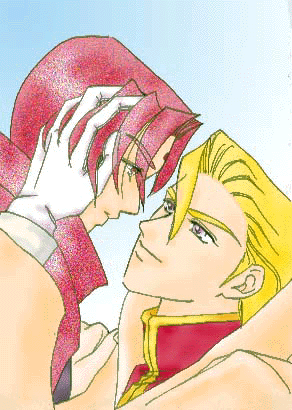
白い手袋の指が、千々に色を変える雑音の髪を甘く絡め取る。引き寄せられる体を肩に置いた手で支えたオラクルは、もの問いたげに薄く唇を開いて僅かに首を傾げた。それへ微笑んでやりながらその瞳を柔らかく煙らせた男は、極上の美声を惜しげもなく披露する。予測した少年の両の掌を貫通したその声、その言葉がシグナルの聴覚構築(ヒヤリング・コンストラクション)及び言語中枢を直撃して、彼の思考回路が一瞬真っ白く溶け落ちたことは言うまでもない。
「あんまり可愛いから、今すぐキスしたくなった。」
ダメか?
唇をふわりと掠めた熱の気配に、くすくすと笑ったオラクルが額や鼻先を男のそれへ擦り寄せながら囁いた。
「…馬鹿。」
すっかり忘れ去られてしまったシグナル少年が果たしてセクハラを訴えたのかは不明だが、どのみちこのありさまをどこやらで証明しなければならないとしたら、それはそれで精神的苦痛は計り知れないだろう。
…とある午後の、ごくありふれた《ORACLE》の光景であった。
Illastrated by Mikan