| 余呉湖の珪藻 原口和夫 |
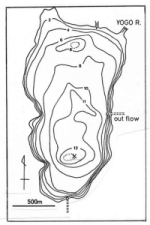 ×印 採集地点 |
| はじめに 余呉湖は琵琶湖の北10kmに位置し,琵琶湖と同一の地溝帯の中にある湖で琵琶湖と同様に陥没によって生 じたものと考えられている。湖面の海抜は134m,面積1.64平方㎞,最大水深14.5mである。湖に流入する河川 はなく,排出河川として北東端に余呉川があり,湖の水は周辺耕地の潅漑に使われている。1967年に余呉湖の 水位低下を防ぎ,水質保全を目的に琵琶湖の水をポンプアップしての保水が図られ現在に至っている。 余呉湖の珪藻類について根来(1956)は湖底泥から25属69分類群を報告し,その後,平野(1979)が16属44分 類群,田中(1992)が9属14分類群を報告していて,これらを合計すると25属85分類群になる。また、根来(1956) は他の水質関係の報告(吉村1937,山口1955)と合わせて,余呉湖は中栄養型~富栄養型の湖に属するとして いる。 試料と方法 試料は1999年8月余呉湖の最深部の底泥をエックマンバ-ジ採泥器で採取した。試料は濃硫酸で煮沸して有 機物を分解,水洗の後プレウラックスで封入してプラパラ-トを作成した。標本は写真撮影の後、2,000倍に拡大 して同定を行った。 試料について出現種ごとに被殻数を計数し,総被殻数1,000個をもって相対頻度(%)を求めた。 結果と考察 観察の結果珪藻類30属180分類群を確認した。これらのうち根来(1956)と共通するものは49,平野(1979)とは 27,田中(1992)とは8分類群で合計58分類群であった。既報告分類群85中,再確認されたものが58分類群で,残 る27分類群が未検出であったことについては,これらが余呉湖の希産種であることによるものと思われるが,さら に検討の余地がある。今回122分類群を新分布として報告するものである。なお,当水域から認められた珪藻類 で琵琶湖から検出されている分類群(Skvortzow 1936, Watanabe & Houki 1988,辻 1995)と共通するものは107 分類群であった。 優占種は浮遊性種のAulacoseira granulata, A. ambigua, Stephanodiscus carconensis, Cyclotella stelligera, Asterionella formosa で,これらの合計が80%に達した。Aulacoseira granulata 及び A. ambigua の合計が60% に及び、共に富栄養性種と位置づけられているところから、余呉湖の富栄養性が推測され根来(1956)の報告に 一致する。平野(1979)はStephanodiscus carconensis は余呉湖及び琵琶湖に特徴的な分類群と報告しているが、 三方五湖からの報告(濁川・長谷川 2000)もあり主に西日本に分布する分類群とみられる。 今回観察された珪藻群の中から特徴的な分類群について図版を掲げた。検出された180分類群についての記 録は、容量の関係から掲載を割愛した。全種の記録が必要な方は筆者まで連絡されたい。 図版の珪藻について 1 Achnanthes obliqua (W.Gerg.) Hust. ; K. & L. 1991b. p.33. f.18/18,19. (N) Fig. 7 Skvortzow (1936) によってEucocconeis onegensis Wislouch & Kolbe の名で 琵琶湖から報告されている。希 産種である。 2. Geissleria yogoensis (nom. nud.) Figs 11,12. 殻形は楕円状皮針形で殻端が頭状に突出している。殻長43-48μm、殻幅20-21μm。条線は10μmに8-9本で 放射状、殻端付近ではほぼ平行。中心域は小さく円形、中心域の片側に2個の点紋を有す。殻端部に縦溝を挟 んで大きな縦条紋をもつ。近縁種のG. tectissima (Lange-Bert.) Lanbe-Bert. は、中心域の点紋が一つであり、 殻端部の縦条紋が小さく、殻形が線状皮針形である点で区別される。 3. Navicula angustissima Hust. in Schmidt et al. 1934. pl.399. f.19. Fig. 15. ところどころ胞紋が欠落する分類群で、各地にときどき出現する。筆者は青木湖(1997)、山中湖(1998)で本種を 記録している。殻長57μm、殻幅7μm、条線は12/10μmで胞紋は粗く17/10μm。 4. N. hasta var. gracilis Skvorzow 1936. p.275. pl.7. f.9. Figs 8,9. 承名変種より小型で条線密度が高い種類である。記載では殻長51μm、殻幅10μm、条線は放射状で9/10μm。 当水域で得られた個体は殻長42-68μm、殻幅9-11μmであった。 5. N. nipponica (Skvortzow) Lange-Bert. 1993. p.126. pl.45. f.9-15. (0.1%) (N) Fig. 14. Skvortzow (1936) が琵琶湖から N. radiosa Kutz. var. nipponica として記載した分類群である。 6. N. undulata Skvortzow 1936. p.275. pl.4. f.2, pl.7. f.6. Fig. 13. 琵琶湖から記載された種類で、殻面は楕円状ひし形、殻縁が僅かに波打つのが特徴である。殻長54-64μm、 殻幅13-15μm、条線は10μmに7-8本、軸域は狭く、中心域は小さな皮針形。Skvortzow は記載の中で N. hasta Pantocsekに酷似すると述べているが、殻縁部の形状で区別される。 7. N. virgata Hust. ; Hustedt 1966. p.743. f.1720. Fig. 10. 青木湖から記載された種類である。条線が粗く10μmに10本、胞紋は17/10μm。 8. Pinnularia hilseana Janisch var. japonica H.Kobayasi in Kobayasi & Ando 1977. p246. pl.6. f.44,45. Fig. 2. 殻は線状で殻腹が僅かにふくれ、殻端は幅広の頭形。軸域は広い。中心域は広く殻縁に達する。殻長55μm、 殻幅8μm。条線は11/10μmで、中心部では放射状、殻端部では逆放射状。 9. P. polyonca var. nipponica Skvortzow 1936. p.278. pl.6. f.3. (0.1%) Fig. 3. 殻面は皮針形で殻縁は3回波打ち、殻端はやや尖形。殻長50μm、殻幅7μm。条線は中央部で放射状、殻 端でほぼ平行11/10μm。承名変種とは、殻幅が狭いことと殻端が頭状に丸くないことで区別される。 10. Stephanodiscus carconensis Grunow ; Skvortzow 1936. p.256. pl.1.f.19, pl.6. f.2. (9.6%) (N, H) Figs 4,5. 殻面の点紋の間に放射状の間隙をもつ特徴的な分類群で、当水域の優占種の一つである。 11. S. niagarae Ehrenb. ; K. & L. 1991a. p.67. f.68/1-3. (2.3%) Fig. 6. S. neoastraea Hak. に酷似する分類群で、本種は殻面の周辺部に刺が無いことで区別される。 余呉湖関係の文献 平野 実 1979. 日本の湖の珪藻堆積物についての研究.梅花短期大学研究紀要 28:113-130. 根来健一郎 1956. 余呉湖の湖底堆積物中の珪藻類.陸水学雑誌 18:134-140. 濁川明男・長谷川康雄 2000. 福井県三方五湖の珪藻群集と水環境.Diatom 16: 45-62. Skvortzow, B. W. 1936. Diatoms from Biwa Lake, Honshu Island, Nippon. Philippine Journal of Science 61: 253-296. 田中正明 1992. 余呉湖,478-482. In:田中正明(編) 日本湖沼誌.名古屋大学出版会.名古屋 辻 彰洋 1995. 琵琶湖沿岸帯における付着性珪藻群集(1).Diatom 11:17-23. Watanabe, T. & Houki, A. 1988. Attached diatoms in Lake Biwa. Diatom 4:21-46. 山口久直 1955. 余呉湖の湖底堆積物と高等水性植物. 陸水学雑誌 17:81-90. 吉村信吉 1937. 湖沼学.439pp. 三省堂,東京. |
|
| 図版へ 表紙へもどる | |