3-500Zは直熱管です。フィラメントを直列にして交流点火で使用する場合、直熱管の宿命でグランドに対してバランスした状態を保たないと、プレート側でHumが発生します。フィラメントを点灯する交流電源により、一次電子が変調されるのがその原因です。高周波でドライブする場合も同様で、2管を同じ条件で動作させるには若干の工夫が必要です。参考までに、3-500Zの通電時のフィラメントは電圧は5V、電流は14.5Aですから、その抵抗値は約0.345Ωになります。またフィラメントの形状はらせん型です。
フィラメントはPin番号で言えば①番と⑤番の間につながっています。一般に、回路図では①番でも⑤番でも等価のようにしか書いてないので、気にしなければ配線ルートを優先してつないでしまうでしょう。
しかし球の中を良く見ると、図のように①番は球の上部までリードされそこで初めてフィラメントにつながります、⑤番は最短でフィラメントにつながっており、両者が等価でない事は明白です。また、フィラメントはらせん状ですので、一定のインダクタンスを持ちますから、RFで影響が出てくるものと考えられます。
さて、ここからが本題です。フィラメントの接続を(*はフィラメント、-は配線)・・・
(1)「-⑤^①-⑤^①-」とした場合・・・図1
(2)「-⑤^①-①^⑤-」とした場合・・・図2
(3)「-①^⑤-⑤^①-」とした場合・・・図3
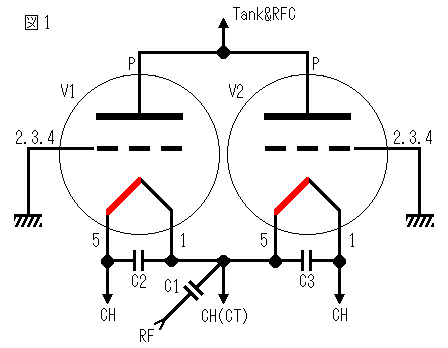
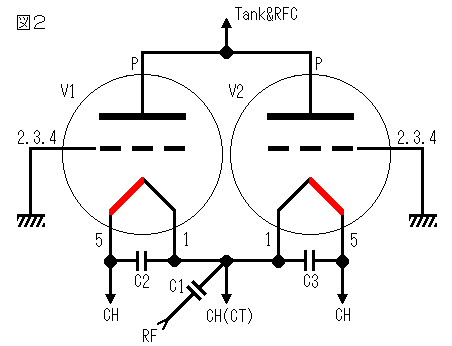
・・・でどのような違いがあるか考察してみます。
(1)の場合はフィラメントの中点からみてフィラメントの配置が機構的にバランスせず、結果として電気的にもバランスしません。
(2)の場合は電源側にフィラメント、中点側にリードが来ますが、グランドに対し機構的・電気的にバランスが保たれます。
(3)の場合は電源側にリード、中点側にフィラメントが来ますが、グランドに対し機構的・電気的にバランスが保たれます。
次にフィラメントの中点(対Grid&GND間)に高周波を加えてみます。
(1)は片方が①番でもう片方が⑤番ですから、2管が均等にドライブできません。フィラメント上を通過する高周波電流の向きが一致しません。また周波数が高くなるとこの状況は顕著になり、場合によってはIg/Ipの位相が2管でずれる可能性もあります。この対策として、コンデンサにより①番⑤番をバイパスする手法がありますが、管内でのリード部分まではバイパス出来ません。
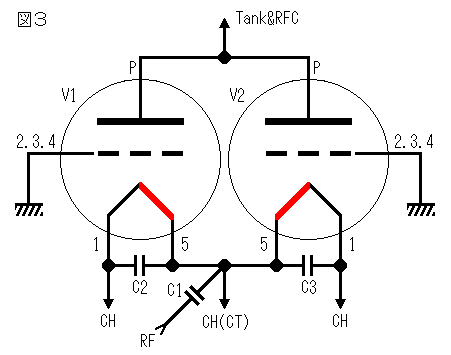 (2)は均等にドライブ出来そうですが、リードがまずありますのでハイフレではf特の低下が考えられます。フィラメント上を通過する高周波電流の向きは一致します。また(1)のように①番⑤番をバイパスすれば、バランスを保ちながらf特の改善が出来るものと思います。
(2)は均等にドライブ出来そうですが、リードがまずありますのでハイフレではf特の低下が考えられます。フィラメント上を通過する高周波電流の向きは一致します。また(1)のように①番⑤番をバイパスすれば、バランスを保ちながらf特の改善が出来るものと思います。
(3)は直にフィラメントをドライブし、かつバランスしていますのでよりベターな方法だと言えます。フィラメント上を通過する高周波電流の向きは一致します。さらに①番⑤番をバイパスしておけばより完全でしょう。
こうした考察の上に既製品のリニアアンプを見ると、必ずしも考慮したものばかりではありません。片管ばかり痛みやすいアンプや、均等に劣化していないアンプには、こうしたフィラメントの配線に考慮の無いものが散見できます。
「微々たるもの」とお考えの方もあろうかと思います。しかし理にかなってますし、必ず効果があります。一度お試しください。
よりベターなフィラメント回路は、上記(3)の接続に併せ、フィラメントチョークはトリファイラにしてフィラメントと中点に、トランス側もフィラメントとCT端子につなぎ、高周波的に完全にフィラメントを浮かす方法が良いと考えます。このやり方は、直列回路によるフィラメント電圧のアンバランスも回避できます。
Ampは一つの高周波電源ですから、均等に動作しない限り、片方がもう片方の負荷になることも予想されます。バイアス状態や低ドライブ時は揃っていても、高ドライブ時の出力が揃うとは限りません。3極管の場合は、グリッドバイアスかこのフィラメントの輻射バランスに頼るしかありません。
 左は、参考までにIgの位相差のデータを取ったものです。これはTL-922のGrid回路に発生する高周波電圧を、オシロスコープでベクトル表示したものです。
左は、参考までにIgの位相差のデータを取ったものです。これはTL-922のGrid回路に発生する高周波電圧を、オシロスコープでベクトル表示したものです。
 なお各管のGrid回路にRFC・C・Rの「並列ネットワーク」をグランド間に入れ、NFBをかけIMDを狙った回路がありますが、2管の動作が本当に同じ状態であるか常に注意したいところです。
なお各管のGrid回路にRFC・C・Rの「並列ネットワーク」をグランド間に入れ、NFBをかけIMDを狙った回路がありますが、2管の動作が本当に同じ状態であるか常に注意したいところです。
写真は各社の3-500Z、左からFAL、EIMAC、AMPELEX・・・この他にCHINA製など様々な3-500Zがある。
ゼロバイアスで使える三極管として最も手頃な球と言えるが、パラ運用は慎重にやりたい。
