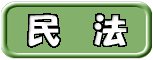
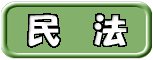
【午前の組・2番クジ】
Otomo |
「1組2番です。よろしくお願いします。」 |
主査 |
「はい、それじゃ、かけて下さい。」 |
Otomo |
(優しそうな主査なので少し安心しつつ、席につく) |
主査 |
「うん、それじゃ、私の方から、民法についてうかがいます。まず、左のパネルを表向けて下さい。」 |
A ――――― B
|
|
主査 |
「Aは建物を所有しており、これをBに賃貸しています。他方、Bは、Aの承諾を得た上で、これをCに転貸しています。この場合、まずAC間の法律関係はどうなりますか?」 |
Otomo |
「はい。えっと・・・・CはAに対して、賃借人と同様の義務を負います。」 |
主査 |
「同様の義務? たとえば?」 |
Otomo |
「たとえば、CはAに対して直接、賃料支払義務を負います。」 |
主査 |
「賃料支払義務ね。他には?」 |
Otomo |
「他に、ですか・・・? えー、目的物の用法を守って使用する義務も負うと思います。」 |
主査 |
「なるほど。では、その後、AB間の賃貸借契約が合意解除されたとします。このとき、Cの地位はどうなりますか?」 |
Otomo |
「えー、AB間が合意解除されますと、・・・AC間に直接の賃貸借関係が発生し、Cは賃借人の地位に立つと思います。」 |
主査 |
(少し驚いた様子で)「えっ? AC間に直接賃貸借が成立するんですか?」 |
Otomo |
(あれっ? プロヴィにはそう書いてあったのになぁ・・・と思いつつ)「あ、いえ、失礼しました。当然には成立しません。」 |
主査 |
「しないですよねぇ。じゃ、どうなります?」 |
Otomo |
「AがCに対して合意解除を対抗しえない結果、CはBC間の転貸借の存続を主張できると思います。」 |
主査 |
「その場合、Cは、どういう根拠で、土地にいることができるんですか?」 |
Otomo |
「根拠ですか? えー、当事者間の合意のみによって、第三者の権利を消滅させるのは妥当でないので・・・。」 |
主査 |
「いや、そういうことじゃなくて、私は、Cの占有の法的根拠を聞いてるんですよ。難しい話じゃないですよ。」 |
Otomo |
「法的根拠は・・・賃借権・・・だと思いますが・・・。」 |
主査 |
「賃借権ね。」(と言って、何かメモする) |
Otomo |
「・・・?」 |
主査 |
「で、この場合、AはCに対して、具体的にいくら賃料を請求できるわけですか? たとえば、AB間の賃料が10万円、BC間の賃料が20万円だとして。」 |
Otomo |
「えーと・・・。20万円でしょうか・・・。」 |
主査 |
「20万? そうすると、Aは、今まで10万円しかもらえなかったのに、これからは20万円もらえて、えらいおいしい話になりますねぇ(苦笑)。」 |
Otomo |
「はぁ・・・(汗)。しかし、本問では、AB間が既に解除されている以上、BがCに対して賃料請求することはないので、Cは当初契約どおりの20万円をAに支払うべきではないかと・・・。」 |
主査 |
「そうですか。では、AB間の賃貸借契約が、期間満了によって終了した場合のCの地位はどうなりますか?」 |
Otomo |
「はい。その場合には、CはAに対して建物を明渡さなければならないと思います。」 |
主査 |
「どうして?」 |
Otomo |
「はい。この場合は、Cの賃借権も消滅しますので・・・。」 |
主査 |
「じゃ、AB間の契約の期間満了によって、BC間の契約も当然に消滅するわけですか?」 |
Otomo |
「あ、いえ、Bに対する関係では、AがCに明渡請求をすることによってはじめてBの債務が履行不能となり、BC間の契約が消滅するのだと思います。他方、Aに対する関係では、期間満了とともに、賃借権を主張できなくなるのかと・・・。」 |
主査 |
「なるほど。それでは、AB間の賃貸借契約が、Bの賃料不払いを理由として債務不履行解除された場合はどうですか?」 |
Otomo |
「はい。その場合も、やはり、Bに対する関係では、AがCに明渡請求をすることによってはじめてBの債務が履行不能となり、BC間の契約が消滅するのだと思います。他方、Aに対する関係では、解除とともに、賃借権を主張できなくなると思います。」 |
主査 |
「なるほど。ところで、Aは、債務不履行解除をするにあたって、Bには当然催告をしますよね。じゃあ、Cに対して催告する必要はありますか?」 |
Otomo |
「はい。Cにも催告する必要があると思います。」 |
主査 |
「どうして?」 |
Otomo |
「えー、賃貸人Aとしては、賃料が支払われさえすれば一応満足するわけで、転貸人にも支払いの機会を与えるべきだからです。」 |
主査 |
「なるほど。判例はどう言ってますか?」 |
Otomo |
「判例は、Cへの催告を不要だと言っています。」 |
主査 |
「はい。それじゃ、また少し事例を変えますけどね。Bが、Aの承諾を得ずに、建物をCに転貸していたとします。この場合、AはAB間の契約を解除できますか?」 |
Otomo |
「はい、Aは、解除できる場合もあると思います。」 |
主査 |
「できる場合とできない場合を、どう区別しますか?」 |
Otomo |
「はい。無断転貸が、AB間の信頼関係の破壊と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除できませんが、それ以外の場合には解除できます。」 |
主査 |
「ふーん。じゃ、Bがいまだに建物を引き渡していない場合でも、解除できるんですか?」 |
Otomo |
「あっ、いえ、その場合には解除できません。」 |
主査 |
「なるほど。では、この場合、AはCにも催告することが必要ですか?」 |
Otomo |
「いえ、この場合は、不要だと思います。」 |
主査 |
「この場合は不要、と・・・。じゃあ、信頼関係の破壊と認めるに足りない特段の事情があって、Aが解除できない場合、AC間の法律関係はどうなりますか?」 |
Otomo |
「はい。その場合は、承諾がある場合と同様に扱われます。」 |
主査 |
「具体的には?」 |
Otomo |
「具体的には、CがAに対して、賃料支払義務や用法を遵守して使用する義務を負うと思います。」 |
主査 |
「はい。えーと、(民訴の主査に対して)何か?・・・・では、民法は以上です。」 |
Otomo |
「ありがとうございました。」 |
<感想> いわゆる「突っ込み」は、ほとんど受けなかったです。ただ、具体的な賃料の請求額については、AC間では解除の効果を主張できない以上、通常の転貸借と同様に10万円の範囲で請求を認めた方がよかったのかもしれません・・・。主査はそれほど強く撤回を迫るという感じでもなかったので、20万円で押し切ってしまいましたが・・・。 |
|