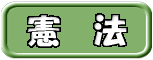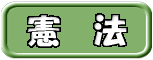<1頁目>
一 A市の図書館運営規則の合憲性
1 A市規則は、A市市民の知る権利を侵害し、違憲ではないか
が問題となる。
2 そもそも、知る権利は憲法上明文ないが、21条1項で保障
されていると解される。
なぜなら、マスメディアの巨大化した現代社会においては、
情報の送り手と受け手が分離・固定化し、情報の送り手の立場
に立たざるを得なくなった国民の立場から表現の自由を再構築
する必要があるからである。
3(1)もっとも、憲法上保障されるとしても絶対無制約ではな
く、他の人権との矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理た
る「公共の福祉」(13条)による内在的制約に服する。
では、どの程度の制約ならかかる制約として許されるか、
違憲審査基準が問題となる。
思うに、知る権利は、個人の人格形成発展に資する重要な
権利である。
さらに、図書館はすべての市民が様々な書物や雑誌を読む
ことができる公共施設であるから、このような権利の制約に
は厳格な基準で判断すべきである。
<2頁目>
そこで、①制約の目的が正当で、②制約手段がその目的達
成のために最小限度である場合に限って合憲であると解す
る。
(2) これを本問についてみると、まず、A市規則の目的は、少
年法61条の立法目的を達成すること、すなわち、少年の社会
復帰・図ることにあり、①制約の目的は正当といえる。
もっとも、かかる目的達成のためには閲覧禁止にまでする
必要はなく、少年法61条に違反すると判断した部分のみ抹消
すれば足りる。よって、②制約手段はその目的達成のために
最小限度であるとはいえない。
したがって、A市規則は知る権利に対する内在的制約とし
て許される範囲を超えており、A市市民の知る権利を侵害し
違憲である。
二 図書館長Cの閲覧禁止処分の合憲性
図書館長CがBに対してなした閲覧禁止処分は、前述のように
違憲のA市規則に基づくものである。
したがって、Cの閲覧禁止処分はBの知る権利を侵害し違憲で
ある。
以 上 |