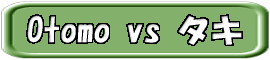
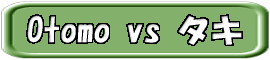
Otomo |
「合格者対談、記念すべき第1回目のお客様は、ネット受験界一の有名人、伊藤塾出身で一発合格者のタキさんをお招きしました。どうもこんばんは。」 |
タキさん |
「こんばんは。」 |
Otomo |
「一応、『Otomo vs タキ』という看板を掲げてみましたが、実際には、聞き手K.Otomo、語り手タキという感じになるかな、と(笑)。」 |
タキさん |
「なにするんすか?」 |
Otomo |
「そうねぇ。HPを見てる方の層も色々だと思うから、とりあえず入門期の勉強、択一の勉強、論文の勉強に大きく分けて話すといいと思うんです。」 |
タキさん |
「ふむ。」 |
Otomo |
「まず入門期ですけど、タキさんは塾だし基礎マスですよね。どんな勉強してました? 勉強時間とか。」 |
タキさん |
「1コマあたり3時間ですね。で、週6時間。講義をあわせて12時間の勉強になります。」 |
Otomo |
「それは、本を読み返す感じで?」 |
タキさん |
「本を読み返すのが1時間、択一20問解いて1時間、論証暗記と全体構造の把握で1時間でした。」 |
Otomo |
「入門の時から択一過去問を解くことの是非については、どう思います? 今ふりかえってみて。」 |
タキさん |
「必要だと思いますよ。」 |
Otomo |
「でも、知らない知識がバンバン出るよ。」 |
タキさん |
「そんなに無かったですよ。正答率は7割超えてましたし。」 |
Otomo |
「基礎マスは結構細かいとこまでやるのかな? たしか、国家の三要素とかいうのがテキストに載ってた気がする。」 |
タキさん |
「ええ。っていうか、それは常識として知ってましたけど。」 |
Otomo |
「入門プロヴィはばっさり切ってるからねー・・・。でも、1時間で20問って、択一合格レヴェルのスピードでしょ。それ、タキくんだからできたのかも。」 |
タキさん |
「うーん。でも、択一って、センター試験とほとんど同じだと思いますよ。解き方とか。」 |
Otomo |
「けど、2割しか受からないってとこが大きく違う(笑)。」 |
タキさん |
「あー、確かに。だからこそ、入門時期で、しっかり択一やっとくべきだと思うんですよね。」 |
Otomo |
「なるほど。自分が入門の時は、少しだけ過去問見たけど、ずいぶんと難しく感じたので、解くのやめてしまいました。・・・講義の復習をやった上で、余力があればやろうと思ってたんだけど、結局余力がなくて。」 |
タキさん |
「やっぱり、教わってる講座の復習になるかってのも重要なポイントでしょう。あまりに講座とやってることがかけ離れると、本来すべき復習がおろそかになってしまいますから。」 |
Otomo |
「そうそう。そっちが本分だからね。塾では、この過去問をやりなさい、っていう具体的な指示が講義の中であったのかな?」 |
タキさん |
「いや、全部やってました。辰巳の過去問詳解を最初から、講座にあわせて。」 |
Otomo |
「えー、全部ですか・・・。ということは、入門が終わった時点で、既に過去問を1周していたと。」 |
タキさん |
「そうですね。択一時期は、憲法刑法は1回やっただけでした。」 |
Otomo |
「・・・(汗)。 普通の頭脳の持ち主には、どの程度の過去問をやることを勧めますか?」 |
タキさん |
「できる限りです。優先順位があるわけで、まず自分の講座の復習。これがちゃんとできて余裕があれば、できる限り解くべきじゃないでしょうか。」 |
Otomo |
「なるほど。」 |
タキさん |
「それぐらい択一は大事だと思います。」 |
Otomo |
「あと、よくある質問として、1つの科目をやってるときに、それ以前の科目を忘れていくんだけどどうしましょう、っていうのがあるんだけど、そのへんはどうでしょう?」 |
タキさん |
「うーん、それは気にしなかったです。」 |
Otomo |
「たまに前の科目を復習するとか、そういうのは不要でしょうかね?」 |
タキさん |
「難しいですね。予備校のカリキュラム上、今の復習をやってると、時間的に難しいと思います。」 |
Otomo |
「じゃ、論文の講義が始まるまではもう見ない、と。」 |
タキさん |
「次の論文の講義の前にひと回しして、予習の形で復習するというふうにはしてました。」 |
Otomo |
「自分は、入門ダイジェストっていう、テープ2本くらいで一科目をまとめたテープをたまに聞いたりしてましたけどね。あれ、塾にもありましたっけ?」 |
タキさん |
「ないですよ。」 |
Otomo |
「そっか。あと、入門期の答練はどうでしょう? 受け方とか。」 |
タキさん |
「必要なんじゃないでしょうか。」 |
Otomo |
「必要ですね。」 |
タキさん |
「僕はまず、形式面を固めてました。ナンバリングの振り方とか、字下げとか、三段論法とか。」 |
Otomo |
「三段論法は、早いうちから体で覚えとくべきですよね。」 |
タキさん |
「一回一回課題をもうけて、ひとついけたら次の、っていう感じで。優答読み込みもやってました。」 |
Otomo |
「そっか。C答とはそもそもシステムが違うんですよね。」 |
タキさん |
「違いますね。いきなり過去問です。問題指定もなしに。」 |
Otomo |
「うわー、無理でしょ、それ。」 |
タキさん |
「簡単な過去問ですよ。あ、でも、民法は難しかったです。21点とか(笑)。」 |
Otomo |
「ま、けど、入門のときに点数気にしても、あんまり意味ないですよね。」 |
タキさん |
「いやぁ点数なんて、最後まで気にしなくて良いんじゃないでしょうか。」 |
Otomo |
「むしろコメント部分?」 |
タキさん |
「どこができてどこができなかったか、なぜできなかったか、の分析と、次の課題設定が大事なんだと思います。」 |
Otomo |
「なるほど。優答の読み込みというのは?」 |
タキさん |
「入門期に、答案のイメージを固めておくの、大事だと思いますよ。2年目は、いかにそれに自分を近づけていくかですから。」 |
Otomo |
「どこに着目するのか、入門生にもわかりやすく説明してあげてください。」 |
タキさん |
「まず、答案の構成要素。問題提起・論証・規範・あてはめですね。」 |
Otomo |
「うん。その型をたたきこむと。」 |
タキさん |
「あと、問題提起にパターンはないか、論証にパターンはないか、優秀だと評価されているのはどこが優秀か、とかですね。」 |
Otomo |
「あ、これブロックだ、というんじゃダメなんですね(苦笑)」 |
タキさん |
「ダメですねぇ。応用きかないでしょう。」 |
Otomo |
「C答だと、予習は解答例の暗記につきるということになってしまうんですが、やっぱ覚えるときに、そういう点を意識してるかどうかで、効果が違うんでしょうね。」 |
タキさん |
「暗記も大事だと思いますけどね。ひとつひとつの勉強を、ゴール見据えて勉強しないとだめでしょう。自分が最終的にどうなりたくて今の勉強をやってるのか、ってことですね。」 |
Otomo |
「五月雨式の勉強じゃダメだと(笑)。」 |
タキさん |
「永遠に受験生やることになります(笑)。」 |
<次回につづく>