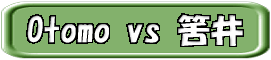
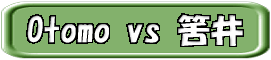
Otomo |
「それじゃ、論文いきましょうか。」 |
筈井さん |
「そうですね。」 |
Otomo |
「まず、勉強時間とかはどのくらいでした?」 |
筈井さん |
「僕、自習室で勉強してたんで、原則9時に行くようにはしてました。」 |
Otomo |
「それで、何時まで?」 |
筈井さん |
「終わりは、夜の8時か9時ですね。まぁ、日によって、多少前後することはありましたけど。」 |
Otomo |
「そうすると、昼食を除いて約11時間だよね。自分も自習室で9時〜9時だったので、同じくらいかな。・・・といっても、波はありますよね。集中してる時間帯もあれば、集中力欠いてる時間帯もあるし、お昼を食べた後は眠いし(笑)。そのへん加味すると、やっぱ10時間くらいかな。」 |
筈井さん |
「ですねー。」 |
Otomo |
「その中で、答練の予習とかをするわけかな。」 |
筈井さん |
「いや、僕は答練の予習はしませんでした。」 |
Otomo |
「予習しないの?!」 |
筈井さん |
「しなかったですね。」 |
Otomo |
「復習の方に重点を置いてた、ということ?」 |
筈井さん |
「そうですね。復習の段階で答案構成を作って、それをストックしていきました。あ、いや、答案構成と言うと誤解を招くかな。かなり模範答案に近いものです。『答案構成以上・答案未満』という感じのものを作ってました。」 |
Otomo |
「とすると、その中には、理由づけとか具体的な論証も入ってるんですか?」 |
筈井さん |
「完全に入ってますね。それを作る過程で、論証を覚えていきました。」 |
Otomo |
「それ、かなり丁寧な部類に入りますね。自分とえらい違い・・・。自分は、答案構成は一切作らないタイプなんですよ。レジュメについてる模範答案をコピーして、気になった所だけをペンでマークして、ストックしてました。論証はプロヴィ読むときに覚えてましたし。まぁ、自分はいわゆる『予習型』なので。」 |
筈井さん |
「僕は『復習型』ですね。」 |
Otomo |
「返却された答案は、どうしてました? 『予習型』の自分は、点数だけ見てポイでしたが(笑)。」 |
筈井さん |
「うーん。僕も、答案が帰ってくる頃には、とっくに復習は終わってますからねぇ。」 |
Otomo |
「ローラーだっけ? それなら1週間返却でしょう?」 |
筈井さん |
「ええ。でも、復習は答練を受けたその日のうちに必ず終わらせますから。」 |
Otomo |
「なるほど。で、答練の予習はしないということは、例えばプロヴィ読んだりとかは、どこでやることになるの?」 |
筈井さん |
「プロヴィは、自分で問題を解いて、さっき言った答案(構成)を作る過程で読みました。僕の場合、まずいくつかの答練問題を集めて、それをあらかじめ体系別に並べておいたんです。で、例えば刑法で『不能犯』の問題をひととおり解いたら、不能犯の部分のプロヴィを読む。それを毎日続けるという感じの勉強をしてました。」 |
Otomo |
「答練の出題範囲とは離れて、完全に自分のペースで勉強してるわけね。答練は、自分の勉強の中でただの通過点にすぎないと。」 |
筈井さん |
「はい。ただ、問題で出たところについてプロヴィを読む、という感じだと、穴が出来るんじゃないかという不安はありましたね。通読してないから。」 |
Otomo |
「まぁ、けど、穴を気にして手を広げ出したら、キリがないしね。」 |
筈井さん |
「僕も、あまり手を広げすぎないように気をつけてました。ほら、最近みんな、答練問題を鬼のように集めるじゃないですか。でも、あれをいっぺんにやろうとしても、知識が拡散しちゃって駄目だと思うんですよね。ある程度、核になる問題をやってから、それに付け足すという形で増やしていくことが必要でしょう。」 |
Otomo |
「そうそう。自分も、前の年の直前答練をあらかじめ集めて体系別に並べておいて、それを秋の時期からちょっとずつ解いていってました。直前期にドッとコピーしたやつを見るのって、自分には不可能でしたし。」 |
筈井さん |
「僕の場合、たとえば4つの予備校の直前答練を集めたとするでしょ。で、二週間でそれに目を通すとして、ただいっぺんに見るだけじゃ拡散しちゃうんですよ。だから、あれを体系別に並べた上で、まず一週目は2つの予備校を最初から最後までやる。で、二週目に残り2つの予備校のを最初から最後まで見る。その方が、体系的理解みたいなのも身につくと思うんですよね。」 |
Otomo |
「うん。直前答練の話が出たけど、ぶっちゃけた話、どこの予備校の答練が良かったとかある?」 |
筈井さん |
「僕はLECだと思います。」 |
Otomo |
「自分もLECやと思うんよ。いや、ほんと、えこひいき無しで。」 |
筈井さん |
「解答例が読みやすいですよね。ま、うちら、LECの基幹講座出身だから、LECの答案を読みやすいと感じるだけかもしれないですけど。」 |
Otomo |
「辰巳の答案は、言い回しがわかりにくかったり、構成がいまひとつだったり、あまり復習する側のことを考えてくれてない気がしましたね。」 |
筈井さん |
「最近、優秀答案を使う勉強って流行ってるじゃないですか。あれは、辰巳の模範答案の出来が悪いからこそ意味のある勉強法であって、模範答案の出来が良ければ優秀答案は必要ないと思いますね。」 |
Otomo |
「ただ、LECは、全体的にちょっと問題が易しすぎるかなっていうのは思ってました。難易度的には、伊藤塾くらいのがいいんだけどな、自分は。」 |
筈井さん |
「概してオーソドックスですよね、LECの問題は。そういう意味で、僕は、論文に自信がない人には『論文の森』とかも勧めたりしますが。意表を突く出題という点では、辰巳とかもそれなりに意味がありました。」 |
Otomo |
「それなのに、プロヴィ問題集だけは、ずばぬけて出来が悪いのが不思議(笑)。作り直せばいいのに・・・。まぁ、いいや。問題集に関して言えば、論文過去問もあると思うのですが。」 |
筈井さん |
「僕、あんまりやらなかったんですよ。ただ、もし落ちてたら、次は論文過去問を徹底的にやろうとは思ってました。」 |
Otomo |
「ただ、困ったことに、コレっていう良い過去問集が無いんよねぇ。どれも、解答例が玉石混交だし。」 |
筈井さん |
「そうなんですよね。結局、一番いいのは、複数の過去問集を買っておいて比較対照することですかね。余裕があれば、ですけど。まぁ、わからないものをわからないと割り切れる人ならいいんでしょうけどね。」 |
Otomo |
「あぁ、それも聞こうと思ってたんだ。勉強してて、わからないことが出てきた時って、どの程度突きつめて行くべきでしょうね? 例えば、自分の場合だと、刑事訴訟法の『罪数と訴因/一罪一訴因の原則』のところがよくわからなくって、いつもあそこで詰まっちゃうんですよ。で、それを調べだして、気がついたら丸一日経ってたりとか。」 |
筈井さん |
「うーん。僕の中でのひとつの基準は、『とりあえず自分の中で何らかの説明ができれば、それでいい』というのがありました。それが具体的にどの程度かは、参考答案とかから判断することになるでしょうけど。」 |
Otomo |
「最低限書けるようにだけはしておいて、あとは割り切って、もう次に言ってしまうという感じかな。」 |
筈井さん |
「そうですね。書ければいいという感じですね。いわゆる『深い理解』みたいなのにはこだわりませんでした。・・・もちろんこれが最善の手段とまでは言えないんでしょうけど。」 |
Otomo |
「ベストではないけれども、他の勉強との兼ね合いを考えれば、その辺りがセカンドベストだと。」 |
筈井さん |
「まさにそうですね。今、セカンドベストって出てきたんですけど、実際この試験って、次善の策、次善の策を着実に採っていくことが大事だと思いますね。」 |
Otomo |
「なるほど。完璧主義は敵だ、と。」 |
筈井さん |
「これは、テキストとか答練とかにも言えるんですよ。どれがベストかっていうのを考えてたらキリないです。むしろ、どれがベターかという視点で考えていかないと、本質からはずれていくような気がしますね。そういう意味で、セカンドベストっていうのは大事だと思います。」 |
Otomo |
「まぁ、一種の妥協でもあるんでしょうけどね。・・・あと、そうだなぁ、判例はどうしてました?」 |
筈井さん |
「百選を見てました。僕ね、憲法が苦手だったんですよ。それで、百選を読むようになりましたね。」 |
Otomo |
「あ、そうだったんだ。」 |
筈井さん |
「ただ、百選を読んだから憲法が得意になったかというと、そうじゃないような気がしますね。我ながらクールな分析ですが(笑)。」 |
Otomo |
「なんじゃそりゃ(笑)。それは、やった方がよかったのか、やらない方がよかったのか・・・。」 |
筈井さん |
「うーん、人によりますね。少なくとも、問題検討が先でしょう。」 |
Otomo |
「憲法とかだと、たいがいの予備校の問題は判例ベースで作られてますから、判例の勉強も兼ねられますよね。」 |
筈井さん |
「僕ね、ある日、憲法で『ハッ』としたんですよ。ほら、過去問で、小学校の近辺にわいせつ広告をしたら駄目とかいう話あったでしょう。」 |
Otomo |
「はいはい。」 |
筈井さん |
「ああいうのも、判例とか見てて、もしそのようなヤバイ広告を野放しにしてたらどうなるのかと。そらまずいよなと。でも、ヤバイっていっても程度があるよなと。それで、明白かつ現在というのを要求するんだな、みたいな。」 |
Otomo |
「審査基準にも、それなりに理由があると。」 |
筈井さん |
「野放しにしたら大変なことになる。でも、かといって、あらゆる場所で禁止しても駄目でしょ。そういうふうに、憲法の問題というのは、両極端の場面を考えてみることで、基準が見えてくるし、あてはめもやりやすくなると思いますね。」 |
Otomo |
「よく、憲法の問題で『常識』が要求されるっていうのも、そのへんなのかな。それは、あてはめの話じゃない? 規範の部分はあらかじめ用意してるわけだし。」 |
筈井さん |
「いや、用意の仕方が問題なんですよ。規範とあてはめは、あくまでセットとして考える必要があると思います。ほら、よく、『判例の規範を覚えなきゃいけない』とか言う人がいるでしょ。でも、それ覚えてたとしても、結局あてはめられなければ意味が無いじゃないですか。」 |
Otomo |
「うーん? そこを現場で考えるんじゃないの?」 |
筈井さん |
「ほら、たとえば、民事訴訟法で、大阪空港訴訟の判例がありますよね。あれって、規範だけ覚えてても仕方ないでしょう。」 |
Otomo |
「あー、なるほどなるほど。あれなんかはまさに、規範とあてはめをセットで用意してるものね。」 |
筈井さん |
「刑事訴訟法の有形力の行使だとか任意同行だとかいう判例もそうです。規範とあてはめをセットとして考えておかないと、意味がないんですよ。」 |
Otomo |
「それは、論文の勉強をする際のこつというか、意識みたいなものとして大事ですね。うーん、なるほど。その他に、添削とかやってて、気になる点とかあります?」 |
筈井さん |
「ありますね。まず、問題文の丸写しじゃない問題提起をしてほしいです。」 |
Otomo |
「オウム返しって印象良くないの?」 |
筈井さん |
「いや、オウム返しそれ自体は悪くないんですよ。ただ、オウム返し+評価を加えた問題提起にしてほしいなと。例えば、問題文の事案を引っ張った上で、『かかる意思に反する取り調べが許されるか』みたいな感じで、この『意思に反する』という自分なりの評価をここで加えるわけです。」 |
Otomo |
「事実に評価を加えるっていうのは、あてはめでよく言われるよね。『シェパードは大型犬の法則(*)』っていう格言を聞いたことありますけど。 *シェパードは大型犬の法則 あれを、問題提起のところでもやった方がいいと。」 |
筈井さん |
「ええ。そういう意味で、問題提起やあてはめの薄い答案が多いですね。単に分量が多いだけじゃ、厚い問題提起とは言えないです。」 |
Otomo |
「ありますあります。分量は多いんだけど、一体どの部分がどのように問題になっているのか、絞りきれてない問題提起ってよく見ますね。」 |
筈井さん |
「なぜその部分が問題になるのか、というところを書いてなかったりね。」 |
Otomo |
「印象って、結構大事なんですよね。まぁ、悪く言えば、単なる採点者側の予断なんだけど(笑)。」 |
筈井さん |
「あと、気になる点としては、案外みんな基本論点の論証ができてないですね。」 |
Otomo |
「一応書いてはいるんだけど、肝心なところが抜けてるとかね。」 |
筈井さん |
「あれは、『暗記はよくない』とか言い過ぎることによる弊害ですね。やっぱり、暗記は必要だと思いますよ。」 |
Otomo |
「論証とかは、かなりかっちりと覚えてたほうだった?」 |
筈井さん |
「覚える・・・というのとは少し違った気がします。理解して書けるようにしておくことと、覚えることはイコールじゃないでしょ。例えば、学校へ行く電車の駅順を書けと言われたら、書けるじゃないですか。ああいう風に、自分の中で常識にしてしまっているから、それを書くこともできるっていう感じです。」 |
Otomo |
「覚える、というより、常識にする、っていう方が適切な表現だよね。あと、論文の問題を実際に解くときの解き方みたいなのは・・・。」 |
筈井さん |
「よく答練の解説とか聞いてると、『問題文のこの部分から、このような問題意識が出てきて、それでこの論点が導かれて・・・』とか言ってますけど、あれって実際には違いますよね。」 |
Otomo |
「違うよね。どちらかというと、論点主義的にパッとまず論点を思い浮かべる。それで、次に、本問でホントにそれを使っていいのかを考えてみる。・・・みたいな感じでした。自分は。」 |
筈井さん |
「うん。直感ですよね、実際には。ああいうのを言葉で説明しようとすると、かえって嘘になっちゃう気がします。」 |
Otomo |
「単なる後づけの説明になっちゃいますもんね、結局。」 |
筈井さん |
「そういう意味では、論文を書くのは一種の職人芸かなと。理屈じゃなくて、慣れなんですよ。とにかく慣れること。だから、いわゆる答案作成法みたいなのが、どの程度有効なのかは怪しいですね。」 |
Otomo |
「というと?」 |
筈井さん |
「例えば、問題文をよく読みましょうだとか、あてはめをしっかりしましょうだとか、そういうのは事前に日ごろからやっておかないと、いざ答案を書く段階では絶対にできないわけです。」 |
Otomo |
「言えてる。普段出来ないことが、本番で出来るわけないものね。」 |
筈井さん |
「だから、いわゆる答案作成のアドバイスは、日ごろの復習の指針みたいなものとして捉えるべきだと思いますね。」 |
Otomo |
「なるほど。そういう日ごろの鍛錬みたいなのを極端にまで推し進めると、自分の『一日一通』とかになるのかもしれませんが(笑)。」 |
筈井さん |
「本番では、普段以上の力を出すことはできないんですから、本番で特別なことをしようとは思わない方がいいでしょう。ちなみに、僕が唯一、本番で普段と違うことをしたのは、『基本的なことだけを書こう!』でしたね。わからないときほど、シンプルに書こうと。」 |
Otomo |
「自分も、答案を書くときのモットーは、『迷ったら書かない』でしたね。書くべきかどうか迷うような事項は、たいてい余事記載の可能性が高いんですよ。それで、誰でも迷わず書くような基本的事項を押さえてれば、まず沈まないって思うようにしてました。伊藤真の論文都都逸って、知ってる?」 |
筈井さん |
「なんですか、それ?(笑)」 |
Otomo |
「論文直前期に、伊藤塾の無料ガイダンスでもらったんです。 (以下、引用) ぜ−全体のバランスこそ合格の決め手 よくできてるでしょう。若干、強引なのもありますけど(笑)。自分は、特に、『苦しいときはコンパクト』『びっくりしたときは、みんなも同じ』っていうのを、すごく意識するようにしてましたね。」 |
筈井さん |
「なるほど(笑)。こういうのも、論文直前期に言われて急に出来るようになるものじゃないんですよね。結局は、日ごろからこういう意識で勉強しておかないとだめだよと、そういう風に受け取るべきだと思います。」 |
Otomo |
「あとね、現場でどの程度答案構成をするのか、というのも人によってずいぶん違うみたいですが。自分は30分くらいかかるんですよ。構成に。・・・それに比べて、筈井くんって、全然書かないんだねぇ。これ、問題文の余白に、一とか二ってナンバリングしてるだけやん(笑)。」 |
筈井さん |
「(笑) いや、構成はじっくりやるべきだと思います。ただ、僕は、書きながら考えることができるタイプだっただけで・・・。」 |
Otomo |
「なんのために答案構成をするのか、って大事だと思うのね。自分の場合は、もっぱらバランスのため。これだけと言ってもいい。答案構成のあちこちに、『5行で』とか、『半ページ以内で』とか、分量の目安を入れていくんです。で、その分量を絶対に守る。そうすれば、時間不足に陥ることはまず生じないし、また論述にもメリハリがつけられるんです。」 |
筈井さん |
「あぁ、それはいいですね。それはやった方がいいと思います。」 |
Otomo |
「自分は、二回目の受験の時に、余計なこと書きすぎて失敗してますからね。内容と同じくらい、いや内容以上にバランスが大事だと思ってました。バランスがまずありきで、その分量から逆算して、書くべき内容を絞り込むという感じですね。」 |
筈井さん |
「今おっしゃったけど、その『失敗して気づく』ってのも大事ですよね。敗因分析というか、自分の弱点を積極的に見つけていくことは必要だと思います。」 |
Otomo |
「そうそう、何がダメなのかっていう分析ね。漠然と『点が上がらない』『会社法が苦手』って思ってるだけじゃ、前に進まないですもんね。」 |
筈井さん |
「僕は、1回目の受験は、憲法で既に不合格を確信したんですよ(苦笑)。あの、規則制定権うんぬんの問題。」 |
Otomo |
「へー、そうなんだ。あの問題は、割と簡単だっていう人が多いけど。論点ずばりだし。」 |
筈井さん |
「あれ、似たような問題は目を通してたんですよ。それなのに、書けなかった。そこで、基本の重要性というか、やっぱり知ってるだけじゃだめで、きちんと覚えてなきゃ書けないんだと、気づいたわけです。」 |
Otomo |
「失敗は成功のもとだね。」 |
筈井さん |
「基本を書けるってのは大事ですね。っていうか、僕の答案、はっきり言って『吐き出し答案』ですよ。」 |
Otomo |
「自分も自分も。『吐き出し』以外の何者でもない(笑)。」 |
筈井さん |
「『吐き出し』自体が悪いんじゃないんですよ。要は、『吐き出し方』でしょ。どこで何をどのように吐き出すべきか、っていう問題で。」 |
Otomo |
「そうそう。それでこそ、使える知識と言えるんよね。」 |
筈井さん |
「で、それは結局、論点の適用範囲・射程範囲の問題にいきつくんだと思います。」 |
Otomo |
「そういうのは、プロヴィ読むだけじゃ身につかないですよね。」 |
筈井さん |
「問題にあたらなきゃだめですね。無数の事例にあたってみて、こちらではある論点が出る、こちらでは出ない。じゃあその違いはなぜ生じるんだ?と、そういう勉強で身につくんだと思います。」 |
Otomo |
「それは自分もやってましたね。自分は余事記載が多いタイプでしたから、問題解くたびに『なぜ本問であの論点は出てこないんだろ?』とか考えること多かったです。類似問題を解くのって大事ですよね。」 |
筈井さん |
「大事ですね。かなり解きました。」 |
Otomo |
「論点が同じでも、違った角度から見れることで、理解が深まるというか。論点の適用範囲・射程範囲って、そうやって緻密になっていくんですよね。」 |
筈井さん |
「そうですね。このあたりも、さっき(入門編)で言った、『インプットとアウトプットは相対的なものである』という話に通じる気がしますね。そういう射程範囲の問題も含めてはじめて『知識』と呼ぶべきなんだと思います。射程範囲をわかってない知識は、単なる『情報』にすぎません。」 |
Otomo |
「いわゆる思考力とか深い理解っていうのも、結局はそういう射程範囲を押さえることに他ならないのかな。」 |
筈井さん |
「そうですね。たまに、思考力を鍛えるために基本書を読めとかいう人がいますけど、あれはおかしいですね。少なくとも、今話したような意味での思考力は、基本書では絶対身につかない。問題、特に類似問題を多く検討することによってのみ身につくと思います。」 |
Otomo |
「全く同意ですね。・・・あと、勉強法について自分が強調したいのは、夏の勉強です。最終合格する前年の夏に、さぼらずきっちり勉強したことによって、かなり力がついた気がするんです。」 |
筈井さん |
「あー、僕もです。論文を受けて、『あれやっとけばよかった』みたいな感覚が残ってる間に始めました。」 |
Otomo |
「秋以降は、やれ商訴だ、年末あたりからは択一と論文の両立だ、みたいな感じで追いまくられるでしょ。そうすると、せいぜい昨年の力を落とさないように維持する程度で精一杯なんですよ。」 |
筈井さん |
「そうですね。」 |
Otomo |
「とすると、昨年プラスアルファの実力をつけられる時期というのは、夏しかないかなと。自分の場合、夏に、全科目の苦手部分を徹底的につぶしたんです。」 |
筈井さん |
「僕も、合格する前の年の夏がターニングポイントだった気がしますね。僕は、あそこで早稲田とかファイナルとか集めた答練をまわしたんです。ものすごいスピードで。あのときにかなり力がついたと思いますね。」 |
Otomo |
「・・・って、もうすでに年明けてるのに、今さら夏の勉強が大事って言ってもアドヴァイスにならないですね(苦笑)。もちろん、論文直前期の必死の頑張りによって力が伸びた部分も大きいですけど。」 |
筈井さん |
「あと、僕は論文対策として、口述過去問もやってましたね。」 |
Otomo |
「それは、ヤマをはるみたいな?」 |
筈井さん |
「いや、知識の整理・確認ですね。これも、さっき言った、同じものを色々な視点から見るっていうことのひとつだと思います。」 |
Otomo |
「自分は見なかったですね。そこまで手を広げたくなかったので・・・。」 |
筈井さん |
「まぁ、あまりお勧めはしないですね、僕も(苦笑)。」 |
Otomo |
「そうですか(苦笑)。じゃ、まぁ、かなり有益な話もたくさん出たところで、論文はこのへんにしときましょうか。」 |
<次回につづく>