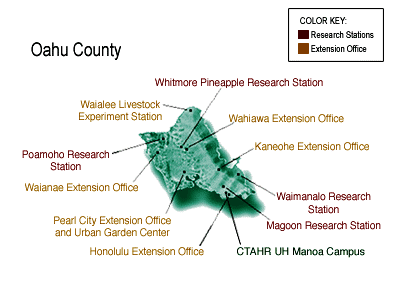 オアフ島全体の地方自治体としては、上記のように
オアフ島全体の地方自治体としては、上記のように5回ハワイ紀行第
甲斐素直
ハワイの地方自治
[はじめに]
第
2回の、ザ・バスに関わる話を述べた際に、ザ・バスのことをホノルル市営バスというのは間違いだ、なぜなら、そもそもホノルル市というものが存在していないからだという趣旨のことを書きました。そして、ホノルル市郡という奇妙な訳語を、その代わりに示しました。おそらく、読者の皆さんも、いったいこの州の地方自治はどうなっているのかという興味をお持ちになったことと思います。それに関する話を、今回は紹介することにしたいと思います。
一 地方自治に対するスタンス
アメリカ合衆国憲法は、地方自治に関する規定を持っていません。当たり前のことです。私の知る限り、地方自治を憲法レベルで保障したのは、現行日本国憲法等、第2次大戦後に制定された憲法がその元祖だからです。だから、成文法として世界最古の憲法であるアメリカ憲法が、地方自治の概念を知っている訳がないのです。
本来、地方自治は、近代市民社会という観点から見ると、敵対的な性格を有しています。近代市民社会は、封建体制との戦いの中で生まれてきたものであり、封建体制の最大の特徴が地方自治にあったからです。すなわち、各地方に中央のコントロールの利かない独立政権が割拠し、円滑な物資や情報の伝達を妨げるというところに問題があり、それを打破することが市民革命の原動力となったのです。その結果、例えば近代市民社会の原点の一つと言うべきフランスでは、今でも県知事が大統領任命であるなど、中央集権的色彩が強い制度となっています。
EUが地方自治の拡充を求めたので、昔に比べると遙かに地方自治が認められてはいますが…。第
2次世界大戦で、全体主義の猛威にさらされて、人類は始めて、地方自治が全体主義から人々を守る上で有意義なものだと痛感しました。強力な中央集権体制を採っている場合には、全体主義者が、中央政府を乗っ取ってしまえば、それで終わりになります。ところが、地方自治が憲法レベルで保障されている場合には、全体主義者は、単に中央政府を乗っ取るだけでは駄目で、一つ一つの地方自治体を辛抱強く乗っ取っていくか、あるいは憲法改正をして地方自治を否定しないと、国全体を支配することができないからです。第
2次世界大戦で、そのことが明らかになったので、大戦後の憲法であれば、地方自治の保障規定が置かれるのが普通となっています。その元祖が日本やドイツの憲法ということになります。だから、その仲間の一つであるハワイ憲法にも、地方自治の保障規定が当然に置かれています。第8章がそれです。ハワイ州憲法の地方自治体に関する規定は、かなり長文なので、直接の紹介を避けますが、地方自治体のことを、政治的下部機構(
political subdivision)と呼んでいます。法的支配関係がないということを明らかにしている前半は判るとして、何故わざわざ下部機構と呼ぶのか、というのは少し不思議でした。地方自治を発展させるためには、むしろ中央政府との対等性を強く押し出す必要があるからです。この点について、ハワイ大学ロースクールの憲法の教授であるヴァン・ダイク先生に伺ったところ、次のように教えてくれました。
「ハワイ州は、強力な中央集権政府である。わずか
わが国学説は、地方自治の拡充をいかに図るか、という点に腐心して、説を組み立てようとする傾向があります。それに対し、アメリカの学説は、強力すぎる各州政府が存在している状況下で、各州からいかに権限を剥ぎ取って、連邦政府を強化するという点に腐心する傾向があります。しかし、そうした傾向が、州政府と地方公共団体との関係にも存在していようとは、正直予想していませんでした。
二 地方自治憲章
ハワイ憲法が、地方自治に対して与えている保障は、学説上、地方自治憲章(
Home rule charter)といわれる類型に属します。日本では、自治体憲章と訳したりします。地方自治憲章という言葉は聞き慣れない方も多いかと思うので、簡単に概要を説明します。日本だと、地方自治法という統一的な法律があって、各自治体は、地方自治法に定められている類型のどれに属するか(市なのか、町なのか、村なのか)によって、自動的に自治体の権限が決まります。それに対して、地方自治憲章では、州が制定した法律で定められた上限枠の中で、自治体側が自らの自治権の内容を選び、それを自ら憲章(
Charter)という形で起草します。その、自治体が内容を定めた憲章を、州議会が、州法という形で議決します。法段階説的に言って、州法は自治体議会が制定する条例よりも上位の法規範です。したがって、地方自治憲章は、自治体議会単独では改正することができないという意味において、自治体にとっての憲法となる訳です。実を言うと、我が国現行憲法が制定される際、そのベースとなったマッカーサー草案では、かなり明白に地方自治憲章の導入を予定していました。地方自治憲章を、アメリカで最初に制定したのはミズーリ州(
1875年)でしたが、その後、この型の憲章を求める運動が全米的に拡大したのです。その意味で、我が国現行憲法制定当時におけるアメリカ地方自治の最先端の形式でした。そこで、日本国憲法に、アメリカの最前のものを持ち込もうと意図して作られたマッカーサー草案は、当然これを採用していた訳です。現在では、全米で7割以上の州が、これを採用していると言われます。しかし、当時の日本政府には、地方自治憲章に関する基本的な知識がなく、したがってさっぱり意味がわからないために、その規定に激しく抵抗しました。その結果、地方自治に関する憲法規定は、マッカーサー草案から、かなり変容されて政府原案になりました。それが、衆議院段階で更に大きく変容されて、現行憲法の条文になっています。現行憲法中で、わずかに元のマッカーサー草案に近い文言が残っているのが、第
95条です。これは、いわゆる地方自治特別法というものを規定しています。現行憲法制定後すぐの頃には、何が地方自治特別法かということに関しては、実務は非常に緩やかで、広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、首都建設法というように、一つの地方公共団体にだけ関係する法律はすべてこれだと考えられていました。しかし、その後、考えが変わり、今では、例えば「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する特別措置法」というような、まさに特定の地方公共団体に関する特別扱いの法律までもが、それには当たらないとされています。
この規定に関しては、依然として地方自治憲章を認めたものと読むのが正しいという少数説があり、私もそれを支持しています。
とにかく、そういう訳で、ハワイには、我が国の地方自治法に対応するものはなく、枠立法と、それを受け手の個別の地方自治体ごとの授権法の形式をとる地方自治憲章が存在しているだけと言うことになります。
三 ハワイの地方公共団体
さて、憲法の文言だけからでは判らないのが、いったいどんな自治体があるのか、ということです。日本なら都道府県及び市町村という2段階の地方自治があるわけです。それに対して、ハワイには、郡(
County)という、ただ1種類の地方公共団体しか存在していません。常識的には、その下に市町村がありそうなものですが、無いのです。これには歴史的な背景があるようです。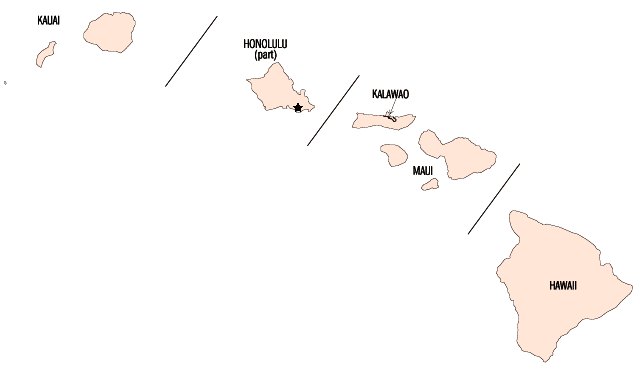
カメハメハ大王が、ハワイ諸島の統一に成功した段階では、強力な中央集権を推進し、地方自治を認めませんでした。それを認めては、せっかくの統一が崩壊する危険があったからに違いありません。王国が存続している間、地方問題は、基本的には国王の枢密院、内務大臣及び国王がそれぞれの島ごとに任命した総督によって処理されていました。
アメリカが、
1898年にハワイを併合したことは前述の通りです。1900年に正式にハワイ地方政府(state government)が設立されましたが、この段階では、完全な中央集権政府が設けられたのです。しかし、1905年に、ハワイ地方議会は、ハワイに近代的な政府を作るための法律を制定しました。その法律によって、カウアイ(Kauai)郡、 オアフ(Oahu)郡、 マウイ(Maui)郡、 ハワイ(Hawaii)郡及びカラワオ(Kalawao)郡という5つの郡(county)が創設されました。このうち、最後のカラワオ郡というのは、ハンセン病の集落だけを行政対象とした特異な性格の郡です。モロカイ島のカラウパパ(
Kalaupapa)半島に、地方政府の厚生省の決定で設置されたといいます。このカラウパパ半島というのは、モロカイ島の地図を見ると一目で見つかります。東西にほぼ直線的にのびたモロカイ島北岸の中央部に三角形に突出した半島です。モロカイ郡が設けられた当時は完全な陸の孤島で、ハンセン病患者は絶対に脱出不可能であることから、この地が選ばれたと言います(カラウパパ半島の地図参照)。我が国のハンセン病と同じで、ハワイでも現在はハンセン病は絶滅しました。しかし、元ハンセン病患者の多くはその後もこの地に残ることを選んだ結果、この地に今も
147人が住んでいます(2000年度のアメリカ国勢調査による)。この郡には、現在も郡政府はなく、州厚生省によって住民の中から選ばれたシェリフ(sheriff)が行政を担当しています。だから、郡という名称はありますが、ここは地方自治体に数えることはできません。ついでに紹介すれば、
2000年の国勢調査によれば、147人の住人のうち、18歳未満は3人だけです。18歳〜24歳が2人、25歳〜44歳が27 人、45歳〜64歳が68人、そして65歳以上が47人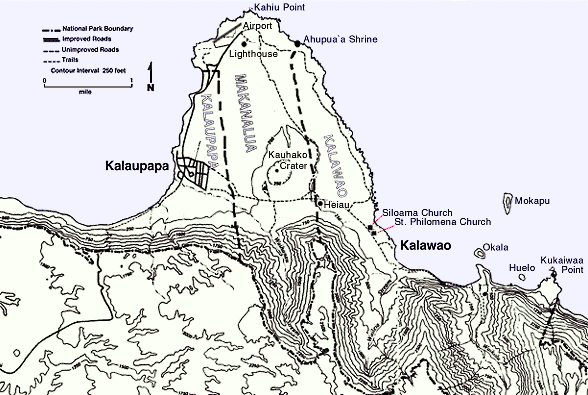 で、住民の平均年齢は59歳という大変な高齢集落となっています。高齢者のほとんどは、配偶者や子も持たず、独りで住んでいます。147人の人口に対し、住居数が115ということが、それを端的に示しています。やがては消滅していく運命の郡なのでしょう。
で、住民の平均年齢は59歳という大変な高齢集落となっています。高齢者のほとんどは、配偶者や子も持たず、独りで住んでいます。147人の人口に対し、住居数が115ということが、それを端的に示しています。やがては消滅していく運命の郡なのでしょう。
カラウパパ半島は、現在はカラウパパ自然・歴史公園(
Kalaupapa National Historical Park)に指定され、一般観光客の立ち入りが厳しく制限されているそうです。もっとも、今でも、ロバだけが通れるような細い道だけが、この郡につながっているに過ぎませんから、入りたいと思ってもおいそれとは入れるところではないようです。これを除く
4つの郡が今日においては、地方自治体として機能してます。これら4郡では、創設当初は、住民から選出された管理委員会(Boards of Supervisors)によって支配されました。ただし、地方政府は、他の地方であれば、郡政府の権限に属するものの多くを保有し続けましたから、各郡の地方公共団体としての権限は、決して大きなものではなかったといいます。また、郡の下に、市町村というレベルの地方自治体は存在していません。それは今日の憲法の下においても、基本的に変わりません。なお、我が国地方教育委員会制度は、アメリカの影響で導入されたものです。しかし、ハワイの教育委員会制度は、我が国のものとは、そして、したがってアメリカのものとも違ったものです。すなわち、ハワイには、州全体で、たった一つの教育委員会しかないのです。それが全島の教育制度を支配しています(ハワイ州憲法第
10章第2節参照)。四 ホノルル市郡
それでは、現実の地方自治はどのように行われているかを、首都であるホノルル市郡を例に、簡単に紹介してみたいと思います。
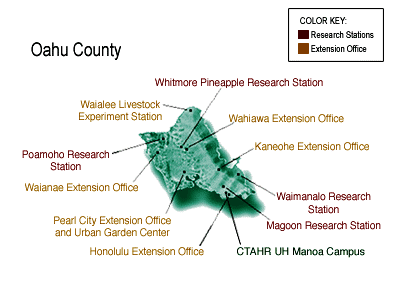 オアフ島全体の地方自治体としては、上記のように
オアフ島全体の地方自治体としては、上記のように
ホノルル市郡議会が地方自治憲章を起草し、承認されたのは、ハワイがアメリカ
50番目の州に昇格した1959年のことです。この憲章は、ホノルル市郡に、長=議会型(Mayor=Council)の地方自治を与えました。市長が行政を、議会が立法を担当するという、日本の普通の地方公共団体と同じ型の制度です。この制度は、1959年の全米市長協議会において、アメリカでもっとも近代的な首都政府の制度であると言及されたと言います。話は少し脱線しますが、ドイツでも、いろいろな地方政府の型があったのですが、今日では、日本と同じような型に統一されつつあります。日本の地方自治制度は、その意味では、始めから良くできている制度であったと言えるでしょう。数次の地方自治憲章の改正を経て、現在のホノルル市郡は、地方自治体として考えられるすべての権限に及ぶようになっています。具体的にあげれば、民間防衛(
civil defense),緊急医療(emergency medical),消防(fire),公園その他の保養施設(parks and recreation),警察(police), 公衆衛生(sanitation),道路(streets),水道(water)等がその権限です。これは、全米でも最大規模の権限を持つ州都であり,その年間予算規模は10億ドルに達しています(2003年度の場合10,053,617ドル)。政治学者は、ホノルル市郡長を、全米でももっとも権限の大きい自治体の長の一つに数えているそうです。市郡長は、任期が
4年で、非政党型選挙で選出されます。アメリカでは、地方レベルでも、政党型選挙、すなわち二大政党がそれぞれ予備選挙を行って、その結果選出された者が本選挙を戦うという型が多いので、非政党型選挙と言うのは、それ自体大きな特徴といえます。議会は
9人の議員から構成され、各議員は、オアフ島に9ある行政区(District)からそれぞれ1名が、やはり非政党型選挙により、4年の任期で選出されます。オアフ島の総人口が、2004年の人口調査で899,593人あったことを考えれば、驚くほど少ない議員数といえます。ちなみに、我が国の場合、約90万人の人口を持つ千葉市が56人、約100万人の人口を持つ北九州市の場合64人となっています。この行政区は、非公式に市(
City)とか町(Town)と呼ばれる区域によって構成されています。一例として、現在の第1行政区に属する市町村を紹介すると、Ewa、 Ewa Beach、Honouliuli、West Loch、 Kapolei、 Kalaeloa、 Honokai Hale and Nanakai Gardens、 Ko'Olina、 Nanakuli、 Wai'anae、 Makaha、 Keaau、それにMakuaと呼ばれる集落で構成されています。あるいは、皆さんにもおなじみのワイキキやダイアモンドヘッドは、第4行政区に属しています。この行政区は、このように選挙権行使の基礎になるものですから、その境界は固定的なものではなく、10年ごとに行われるアメリカの国勢調査の結果を反映して見直されます。今、市町村は非公式のものだと述べましたが、それは、ハワイの地方自治制度は郡という単層で構成されており、我が国の都道府県とか市町村に相当する複層構造を保っていないということを意味します。これまでに説明した歴史に明らかなとおり、市町村レベルが地方自治の主体として活動したことが無く、自然、それが地方自治憲章を作りたいという意識を示すことが無く、その結果、地方自治体にもならなかったという理解をすることもできると思います。しかし、おそらく、強力な中央集権政府を求める意識が、地方自治レベルにもあらわれて、郡の権限を分散することを嫌ったと見るべきなのかもしれません。
我々は、慣用的に、ハワイの州都はホノルル市であるというようにいいます。あるいは公的文書にもそう書いてあることが多いでしょう。しかし、ここまでに説明したことから明らかなとおり、ハワイには全く市制が存在しないのですから、それは誤りだと言うことになります。確かに、上述のように、行政区の構成要素として、非公式には市や町という表現が使われており、それは古くから一体性ある集落のことを意味している訳です。しかし、それはあくまでも名称だけであり、それに対応する地方自治体は存在しないのだと言うことは、明確に認識しておく価値のあることと思います。
また、地方検事は、アメリカの場合、きわめて重要な政治的ファクターですが、ホノルル市郡地方検事の場合、長及び議会のいずれからも完全に独立しており、長や議会の諮問に答える義務はなく、市郡長の支配下にある公設弁護士事務所にも、何の権限もありません。やはり非政党的選挙により
4年の任期で選出されます。ホノルル市郡の人種構成は、
2000年度の国勢調査によれば、白人21.28%、黒人ないしアフリカ系アメリカ人2.35%、アメリカ原住民(いわゆるインディアンに加え、アラスカエスキモーとアリュート人が含まれます。)0.25%、アジア人46.04%、ハワイ原住民8.87%、その他の太平洋系人種1.28%、混血19.93%、ヒスパニックその他のラテンアメリカ系6.70%となっているそうです。この数字に明らかなとおり、ホノルル住民は、ハワイ全体よりもアジア系住民が多く、半数近くに達します。これは当然全米でも一番高い数字です。五 他の郡
他の三つの郡は、名称の変更を経験しなかったという点を除くと、基本的にはホノルル市郡と同じような歴史を辿り、地方自治の形態としても、同じく長=議会型の統治形態を採用しています。ただ、自治体憲章を制定したのはいずれも
1968年と、ホノルル市郡よりもかなり遅れており、人口の少なさ、財政力の低さなどから、内容的にはホノルルよりかなり劣ると言うことです。概略を紹介すれば、次の通りです。
(一) カウアイ郡
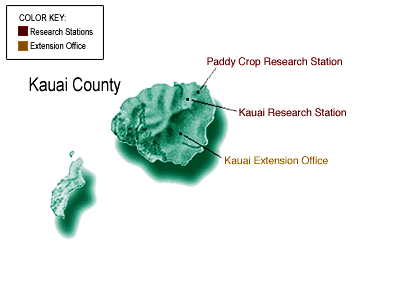
一番北にあるのがカウアイ郡で、カウアイ島とニイハウ島をその領域としています(カウアイ郡地図参照)。
2000年の国勢調査によれば、総人口は58,463人ということですから、オアフ島に比べると、桁外れに人口が少ないことが判ります。郡長(Mayor)は、4年の任期で選出されます。議会は7人の議員から構成され、2年の任期となっています。2003年度の歳入は106.772ドルと、ホノルルに比べてちょうど一桁小さな数字になっています。人種構成を紹介すれば、白人
29.51%、黒人等0.30%、アメリカ原住民0.36%、アジア人35.99%、ポリネシア人9.12%、その他の太平洋系0.86%、混血23.84%、ヒスパニック系8.22%となっています。(二) マウイ郡
中央部にあるのがマウイ郡で、マウイ島に加え、モロカイ島、ラナイ島、それにカホオラウ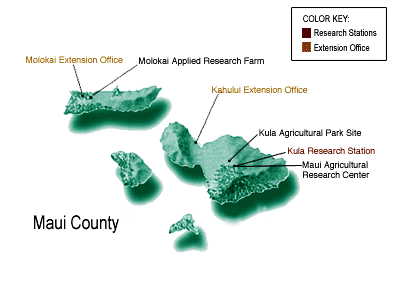 ェ島の計
ェ島の計
政治形態は、他の例に漏れず、長=議会方式です。郡長は非政党型選挙で、
4年の任期で選ばれますが、2選までに制限されています。議会は9人の議員から構成されています。議員になるためにはマウイ郡に住居を有する必要がありますが、投票するためには住居は要求されないという、面白い制度がとられています。任期は2年ですが、5選までに制限されています。2003年度歳入規模は216,960ドルとホノルル市郡の2割程度です。人口は、
2000年度の国勢調査では128,094人ですが、2003年の人口推計では135,605人とされ、ハワイ州でももっとも人口増加の著しい郡です。人種構成は、
2000年時点で示すと、白人33.90%、黒人0.40%、アメリカ原住民0.37%、アジア人31.01%、ポリネシア人10.72%、その他太平洋系1.36%、混血22.24%、そしてヒスパニック系7.85%となっています。人口の実に30.90%が25歳〜44歳という婚姻・出産年齢にあり、それを受けて 25.50%が18歳未満となっていて、これがこの郡の人口の急増の大きな原因となっています。なお、その他の年齢層を示せば、18歳〜24歳7.70%、45歳〜64歳24.40%、65歳以上11.40%で平均年齢は37歳という若い島です。(三)
ハワイ郡ハワイ州では、州名との混同を避けるため、一般にハワイ島はビッグアイランドと呼ばれます(地図参照)。言うまでもなく、ハワイ州で最大の島であるからです。日本でも、群島の中で一番大きな島は、例えば伊豆大島、奄美大島といった調子で、大島と呼ばれますよね。だから、ビッグアイランドという名称そのものは極めて自然です。
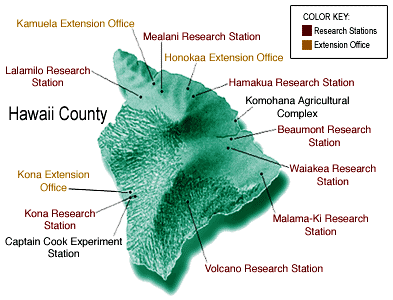 なぜ、この島の名前が、州名と同じかというと、
なぜ、この島の名前が、州名と同じかというと、
郡の政治形態は長=議会方式で、郡長は非政党型選挙により
4年の任期で選出されます。議会は9人の議員から構成され、非政党型選挙により2年の任期で選出されます。2003年度の歳入規模を示せば、208,801ドルとなって、マウイ郡より若干少ないというところです。2000年度の国勢調査では、人口は148,677人です。例によって人種構成を示せば、白人31.55%、黒人等0.47%、アメリカ原住民0.45%、アジア人26.70%、太平洋島人11.25%、その他1.14%、混血28.44%、ヒスパニック系9.49%となっていて、4郡の中ではアジア人比率が最も低く、ポリネシア人の比率が最も高くなっています。とは言っても単なる程度の差に過ぎませんが・・。