 しかし、そこは製造法にかけては第
しかし、そこは製造法にかけては第アーサー・C・クラーク著、ハヤカワ文庫刊
860円今日では、この作者の名前は、地球人類の外的要因による進化を描いた『幼年期の終り』(
1953年)や、海底に開拓地を見いだした人類の未来を感動的に描いた『海底牧場』(1957年)などで、あるいはスタンリー・キューブリック監督と共同制作で大ヒットした『2001年宇宙の旅』の原作者として、広く知られているであろう。その谷間におちて、本書はあまり知られていないかもしれない。しかし、本書こそは、私がこの作者と出会った最初の作品であった。1961年というと、ほとんど半世紀前のことである。ケネディ大統領が、人間を月に送り込むためのアポロ計画をスタートさせたのが、この年である。その、まさに宇宙時代の幕開けという年に発表されたのが本書である。作者の前書きに本書は「その時点までの私にとって、おそらくもっとも成功した長編であり、さっそくリーダーズ・ダイジェスト社という買い手がつき、要約版として出版された」とある。
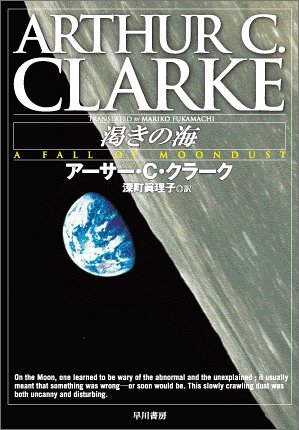
日本語版のリーダーズ・ダイジェストとアメリカ版のそれとの間にどの程度のタイムラグがあって掲載されるのか、私は知らない。しかし、ほとんど間をおかなかったのではないかと思う。当時の日本は、まだ今のように洪水的な出版文化が存在していなかったから、毎月確実におもしろい物語を送ってくるダイジェストは貴重であった。中学生の私は、その届くのを待ち兼ねて毎号読みふけっていたが、本書の要約版については、特に鮮明な記憶があるからだ。
確かに、本書は、人類の未来を見据えた作品を得意とする作者としては、ちょっと異質な作品といえるかもしれない。ここに描かれているのは、ちょっとした資産さえあれば、月に観光旅行に行けるようになった近未来に、月の観光船が巻き込まれた事故を描いたものであるに過ぎないからだ。私と同じゼネレーションの方ならどなたもご同意頂けると思うが、本書を最初に読んだ頃は、その近未来とは
21世紀、すなわち今現在のことと信じて疑わなかった。一体人類は何を手間取っているのだろう。しかし、それでも本書は魅惑的な作品である。通信衛星のアイデアを人類で最初に考え出した作者ならではの、科学的な細部まで矛盾のない舞台設定の中での事故とその救出劇は、何度読んでも迫力のあるものである。
そもそも渇きの海というアイデアそのものが素晴らしい。私が子供の頃、科学者は、月面が細かな塵に覆われていると信じていた。月の海があまりに平らなのは、塵で埋まっているためと考えられていたのである。幸いにもアポロが塵の中に沈むことはなかったが、塵の存在そのものはアポロによっ間違いなく証明された。その塵が、月のある海の一画で、予想以上の広大な面積を埋め尽くしているのが発見され、観光担当者によって渇きの海と名付けられたというのが、本書の基本設定である。海があれば、そこを走る船が造られるのは、観光産業の存在する限り、常に真実である。
本書は、その観光船が、月震にあって、その塵の海で沈没したことから巻き起こる事件を迫真のタッチで描いている。真空中の塵が、固体とも流体ともいえない不思議な性質を示すことから、救出は様々な困難に遭遇することになる。半世紀前の作品とは思えないおもしろさである。
機本伸司著、角川春樹事務所刊、
1700円 この作者が、第1作『神様のパズル』で第3回小松左京賞を受賞して颯爽と登場したのが2002年である。そして、本書が第3作である。今時珍しいほどの遅筆の作家といえる。その分、少なくともSF的な内容は、どれも非常に充実している。第
1作の場合には、宇宙の製造法を問題にしていた。2003年に刊行された第2作『メシアの処方箋』は、その表題どおり救世主の製造法を問題にしていた。宇宙といい、救世主といい、常識的には絶対に作れそうもないものを、現代技術よりほんの少し上というレベルの技術で、何とか作れるのだということを、リアルに説明するところに、この作者の作品の最大の特徴がある。実をいうと、この第
2作は、書いてある内容そのものは非常に面白いのだが、未解決なところが多く、私はシリーズ作品の第1作なのではないかと予想していた。しかし、予想に反して2年間の沈黙の後に発表された本書は、救世主とは何の関係もない話だった。今度も製造法を問題にしているのだが、作ろうとしたのは恒星間宇宙船である。少なくとも、普通なら絶対に作れない宇宙や救世主と違って、まさに現在の技術でも作ろうと思えば作れるものがメインのテーマというのは、ちょっと拍子抜けしたものである。 しかし、そこは製造法にかけては第
しかし、そこは製造法にかけては第
そこで、作者は「終末」という、
SFならではの、まことに豪快な動機付けを行う。といっても、太陽が超新星爆発を起こすとか、ブラックホールに飲み込まれるとかいう凄まじい話ではない。単に、太陽の活動があと100年ばかり、ほんのちょっとだけ、ただし人類が地球上で生き延びるのは非常に難しくなる程度に活発になるのである。ごく限られたエリート達は、もしかすると、地中深くに地下都市を建設するなどして、その問題の100年間を生き延びられるかもしれない。しかし、一般大衆は、おとなしく終末の時を待つほかはない、という状況を作り出す。そこで、インターネットに「ダメで元々、スペーストラベル、略してダメトラ」という阪神ファンなら激怒しそうなホームページを作り、一般大衆から寄付金を募って、ただの人材派遣会社が恒星間宇宙船を造りに掛かるという、まことに人を食った設定である。恒星間旅行ということを真剣に考えると、技術以前の段階でどういう問題が発生してくるのか、ということを、作者特有のリアルさで説明する、まことに楽しい話となっている。
難を言えば、そのリアリティを追求しすぎたために、夢がなくなってしまった点だろうか。思うに、人類という種を存続させるだけの遺伝子の多様性を確保するには、最低限でも
1万人程度のDNAが必要であろう。それが当初計画の段階でも1000人、最終計画では100人、そして飛び立った時はさらに縮小してしまう所が悲しい。