FORTUNE ARTERIAL SHORT STORY
「突撃せよ、我らが修智館探検隊!」
この作品の著作権利は白金さんにあります
他で紹介する時はその旨を出してください、*こことか(爆ぉぉ)
〜起〜
 「承」へ。
「承」へ。
 「転結」へ。
「転結」へ。
草木も眠る丑三つ時といえる時間帯、日が昇っていた頃にはあれほど喧騒の渦にあった学院が静まりがえり、全ての音がまるで壁や窓ガラスによって吸着したように周囲には何一つとして……否、微かにだが足音が二つほど響いてきた。
「なあ、噂は本当なのか? ここに幽霊が出るって話?」
「ホントホント。だって俺のダチがここで白い女の幽霊を見たってさ」
軽口を交し合いながら、余裕綽々の足取りで進む二人の男子たち。
外出用の半袖服を纏っているが、会話から察するにこの学院の生徒達だった。
「にしても不気味だよな、夜の学校ってこんなに静まり返っているなんてさ」
そのうちの一人が始めて見るだろう、通っている学院のもう一つの顔を窺いながら、傍らの親友に囁く。
見やれば空は暗澹とした曇り空により、一欠片の星の明かりも覗けず、頼りになるのは手元にある懐中電灯のみ。後は市販で売られている使い捨てカメラくらいだ。
理由は至極当然、一週間ほど前から学院内にて噂されている幽霊の容姿を、捉えては写真に写すことである。
「そっか? 別にオレはどうってことないぜ。大体、こういうのは噂程度の煙程度で、実際はなにかと見間違いに決まってる」
客観的な思考をもって幽霊を貶し、淀みも無く突き歩いていく。
それから教室、廊下、家庭科室等など順序良く回っていき、全ての順路を確認し終えた頃には二人の顔に落胆と失望の色が濃く覗けていた。慣れない運動の疲労感もあってか、あぐらをかいて床に尻を付く。
「なーんだ、結局噂は偽物だったのか」
隠そうともしない舌打ちをし、男子生徒が忌々しく吐き捨てた。
「やっぱり現実は現実、か。結局無駄骨に済んだかも」
同意見とばかりに友人も追従の言葉を重ねる。
そんな時だった。懐中電灯の明かりが前触れも無く、消灯したのが。
近くにいる友人との身体の輪郭でさえ朧げにも映らないほど、一瞬にして世界が漆黒の闇に閉ざされ、二人は己の肉体と精神が溶け込むような錯覚を感じてしまう。
「なんだよこれ、電池が切れたのか」
「そんなわけない。これは今日買ってきたばかりの新品だぜ、たった数時間で切れるわけないだろう」
「じゃあ懐中電灯が不良品じゃないのか?」
動揺し始める心境を落ち着かせよと必死に操作し始める最中、
『……いっ………ぼうよ…』
二人の耳朶に、こんな静けさが横たわった空間の中でしか、聞き取れないほどの小さな声音が入ってきた。肌に直に氷塊を押し付けられるようなそれに全身の総毛が波立ち、無数の鳥肌が湧き出す。
「「!?」」
聞き間違いかと両者とも顔を見合わせてみて、真実だと把握する。
やがて小さな足音がこつこつと、だが徐々に接近するように反響が高くなっていく。
しかも音の発生源はありえない方向から……すなわち、自分たちが先ほど通ってきた方向からであり、背後から誰かが忍び寄るなどという可能性が無い以上、明らかにそれは第三者のものであり、未知の『何か』でもあった。
「「…………」」
好奇心か恐怖心か、両者は喉の唾液が伝うのさえもどかしい中、何かがもうすぐ近くにまで来ていた。脳裏に唐突と家にいる家族へと無言の遺言書を綴り始めていく。それほど緊迫感が体内を駆け巡っていた。
足音が止まる……『何か』が二人の気配を察したように、一瞬動きを停止する。
再び足を進む音が再開する……ほんの僅かに空の暗雲が途切れ、満月の光によって影が曲がり角から差込む。
人の形をした影絵が廊下の曲がり角で急に止まる……何があったのか判別ができず、男子生徒たちは舌が麻痺するほどの緊張感の中、魅入られるように硬直し続けた。
「…………」
現状を何とか打破しないとと、直感した友人が何事か言いかけ、全身の筋肉を硬化してある一点を直視する。
「な、なんだよその顔……ハ?」
裏返る声色を返しながらも、男子生徒は何事かに気が付いた。
隣にいる友人が身を大きく震わせながら、自分の肩越しを指差すのを。
……背後に誰かがいる、と所作で悟った少年は静かに、静かに振り返る。
皮脂から脂汗が流れる感覚が捉える中、やがて彼はソレを見た。
『一緒に、遊ぼうよ?』
窓ガラスに映りながら儚い笑みを浮かべて、二人の男子生徒に手を差し伸べるこちらには存在しない少女の容姿が。
「という怪談話があるのはもちろん、知っているな?」
歴史と伝統が色濃く反映している生徒会の中で、五人の生徒会員が緊急の対策会議を執り行っていた。とはいえ、あまりにも現実離れした内容なので、困惑と懐疑的な空気が漂い続けていた。
「すいませんがそれと今回の議題と、どういう関係があるんです?」
挙手しつつ孝平が嫌な予感を馳せながら、質問する。
同時にどうもがき、足掻いても、仕事をさせられると知りつつも。
「詰まる所だ、三人には早急にそれの調査を頼みたい。無論、第一優先として」
ん? と生徒会長である伊織は眉を潜めて至極当然に答えた。
あまりの予想通りの反応に、孝平は額に手をやって沈黙する。
「ゆ、幽霊、の調査をですか?」
怯えるように白の小柄で華奢な体が、目に見えるほど大仰に振るわせた。
怪談話などに関して耐性の低い彼女からすれば、今回の件は武器も持たせずに戦場へと行け、と脅迫されているようなものだから。
「ちょっと待ってください伊織先輩。そういうのは見回りの人がするべき仕事でしょう。そもそもどうしてそんな話がこっちに回ってくるんです」
理不尽な伊織の要求に孝平は反論するものの、横から静かな声が割り入む。
この議題を提案した一人でもあり、白の実兄である征一郎だ。
「それだが実は最初に幽霊と遭遇したのはその人で、今は驚きのあまりにぎっくり腰で入院しているらしい」
「そうなんですか」
第一被害者で可哀想になどと、他人事のように祈る孝平。
「じゃあこれは学校側から、正式に依頼されたってことでいいのね」
終始、議題に耳を傾けていた伊織の妹であり、副会長である瑛里華が事の重要度を把握するように、生真面目な顔つきで発言する。きっと真っ直ぐな性分からしてみて、今夜中にでも探索を開始しようと思案しているかもしれない。もちろん、道連れの同伴として自分も含まれているだろう。
「もちろんだ。なるべく早くに事態の収拾を収めたいと言っている。それから費用は惜しまないそうだ。事が事だからな」
「それにしても幽霊だなんて……」
伊織に向けて非現実だと紡ごうとした口を止め、僅かに瑛里華へと目を遣る。
数ヶ月前、ある出来事によって架空の存在であったはずのヴァンパイアを知ったのだから、幽霊だろうが天使も実在すると思っていたから。
「……どうして私の方を見るのかしら、支倉君?」
だが目敏く察したらしく、瑛里華は視線を尖らせて詰問してきだす。
「いや、何でもない。気のせいじゃないのか」
心臓に冷や汗を掻きつつ、孝平は冷静な風采を装って否定する。
まあ、いいけどと追求を断ち切る瑛里華に、安堵しつつ疑問を口にした。
「ところで先輩方も一緒に来ないんですか」
「行きたい所だけだが、俺たちも俺たちなりにいろいろと忙しいんだ。それにこれは君たち三人じゃないと務まらなくてね」
「…………」
微妙に言葉のうちに奇怪な突起に躓いた感触に小首を傾げ、孝平は微細な変動を見逃すまいと、注意深く伊織と征一郎を交互に観察してみる。だが目に見えるほどの情報は引き出せないと観念し、断念する。
「分かった兄さん。この話、引き受けるわ。そもそも生徒の身の安全を守るのは私達の役目だもの」
至極当然とばかりに瑛里華。柔らかさを伴った砂金のような髪が肩から零れる。
何気ない彼女の所作に、なぜか無意識的に目を逸らしてしまう孝平。遅れてどうしてそんなことしたのか、首を傾げた。
そんな彼の苦悶をよそに、瑛里華は隣に佇む白に声をかけていた。
「ところで白ちゃんはどうする? 兄さんはああ言っているけれど、お留守番した方がいいんじゃないかしら」
「私なら大丈夫です。でもお役に立てるかどうか不安で」
「大丈夫、私がきちんと付いているわ。それにしても白ちゃんは生徒会としての自覚を持って安心したわ。……どこかの誰かさんはまだだけど」
「悪かったな、自覚がまだ薄くて」
露骨な瑛里華の悪態にむっと顰める孝平。彼女にはそれを言われたくなかった。
「あの支倉先輩、瑛里華先輩、喧嘩は止めてください」
不安げな表情で見上げてくる白。
「大丈夫よ、白ちゃん。これは何時ものことだから」
「そうそう、白ちゃんは別に気にしなくてもいいから」
互いに白を安堵させようとしつつも、視界の隅では互いをけん制し合う二人。
「まったく夫婦喧嘩も止めておけよ、二人とも」
そんな彼らにどんな感想を抱いたのか、伊織が爆弾を放り投げた。
「兄さん! なに馬鹿なことを言っているの!?」
「伊織先輩、誰と誰が夫婦ですか!?」
絶妙なタイミングで伊織に向き直って反論する孝平と瑛里華。
この瞬間ばかりは、共通の敵の殲滅が最優先とばかりに共闘していた。
「俺は別に誰のことも言ってないが?」
言って、意地汚い笑みを口元で浮かべる伊織。大人気なさ過ぎる。
んぐっ、と息を詰めつつ瑛里華は唇を真横に引き締めた。が、スカートの横で白くなるまで硬く握り締められている拳は、ぷるぷると痙攣し続けている。よほどからかわれるのが癪に障るのだろう。
孝平とて同意見だった、常日頃から詰め寄ってくる彼女と夫婦などという枠に当て嵌めようとする伊織の脳内思考がまったくと言っていいほど、理解不能なのだから。
「話はそれだけなら、もう出て行ってもいいのよね」
言うが早く、瑛里華は憮然とした面持ちのまま、踵を返して部屋を辞し始めた。
「待ってください瑛里華先輩、私も一緒に行きます。兄様、伊織先輩、失礼します」
断りを入れつつ、慌てて瑛里華の後を追い始める白。
何気なく見やりながら、孝平は伊織へ向き直った。
「伊織先輩、征一郎先輩、少し……いえ、何でもないです」
単刀直入に疑問を口にするべきか躊躇った後、孝平は頭を振って断念する。
これがなにか仕組まれたものならば、実際に掛かった方が全部理解できるのではないかと、算段を立てていた。
「伊織、お前もなかなか悪い奴だな」
「そういうお前もだろう征、分かっていて黙っているくせに」
「確かにそうだな。もっとも、孝平は感づいているようだが」
「やっぱり俺の目には狂いはなかったか。だとしたら案外うまく行くかもしれないな」
「そうかもしれない。では伊織、私は別の件の調査に行ってくる」
「ああ、よろしく頼んだ」
差し迫っては機材の調達ね、と断言した瑛里華が孝平と白を街の中へと連れ添って案内したのは路地裏の中の、更に路地裏にひっそりと人知れずに佇む場所だった。
「……なんだここ?」
「廃墟、じゃないですよね?」
十人中十二人が廃墟のようだと即答してしまいそうなそれは、それ自体がレンガ造りの壁のような意匠を施されており、何かの植物の蔓が伝っていてまるで中世の魔女が住んでいる様な佇まい。しかも嵌めこまれている窓ガラスが幾つか割られている形跡すらある。本当にここが目的地……いや、それ以前に居住区なのだろうか?
「にしても、妙に寒いよなここ」
寒気を覚えて孝平は両手で露出している腕を摩り始めた。
夕方とはいえ夏の残暑がここまで蔓延っていないのか、妙に冷涼感を伴った空間が支配しており、夢か現の区別が判別しずらくなる。
「ほら二人とも、ぼーと立っていないで入りましょう」
年代びて古惚けた木製の扉のノブを回し、一足先に踏み込む瑛里華。
孝平と白は目を合わせてみて、頷きあうと異空間へと侵入する。
「うわっ、なんだこれ」
「これは、凄いですね」
二者二様の感嘆を含めたため息を溢した先、多種多彩な品揃えに瞠目する。
雑然として緻密、無関係にして共通、あらゆる古今東西の物品が鎮座していた。
大辞典ほどの大きな本もある、身の丈ほどの白い鏡もある、翡翠色のペンダントもある、どこかの民族が使用しそうな顔のペイントが描かれた盾がある、だがどこか孝平はこの世ならざる『ナニカ』が秘匿されていると直感していた。
ヴァンパイアである瑛里華と多少なりとも空気を共にしているために、孝平は多少の違和感を分かるようになっている。
「こんなに沢山……何時作られたものなんでしょうか」
珍しく好奇心に目を満たせ魅入りつつも、白は骨董品を眺めていく。
意外な事にオンボロじみた外装と打って変わって、中は綺麗に清掃されているようで、埃一つも見当たらず照明が一つ一つ丁寧に照らし出している。
「一体これは何に使うんだろうな」
用途が知れない以上、手に触れるのが躊躇いつつ、孝平は“自分の体が映らない白い鏡”を一歩引いた位置で観察する。
「あ、それに触ったら駄目よ。なんでも自分の死相が分かるみたいだから」
「んなっ」
瑛里華の忠告に、心臓が一際大きく伸縮し、孝平は跳び退る。
「どうしてそんな危険なのが鎮座しているんだ。というよりも、ここは本当にレンタル屋なのか?」
「そんなこと私に言わないでよ、それと後者だけどここほど品揃えが豊富な場所なんて、日本にもそうはないんだから」
「……あまり追求しない方がいいよな、身のために」
「ええ、そうした方がいいわ。命がいくあっても足りないかもしれないし」
そこはかとなく物騒な発言を醸し出し、孝平は背筋が凍える。
「白ちゃんもあまり手に触れないようにね。一応、危険物も混じっているから」
瑛里華は自分の忠告に分かりましたと返事を出す白を見、カウンターに無作法に置かれたベルの柄を優雅な手つきで取り、ちりんと清涼感溢れる音を鳴らせた。
「なあ瑛里華、ここの店主ってどんな人なんだ?」
「そんなの聞かなくても、実際に会ってみれば分かると思うわよ」
「そうじゃなくて、その……そっち関係なのか?」
「さあ、それはどうかしら」
勝気な笑みを浮かべ、瑛里華の思わせぶりに困惑する孝平。
そうこうしている内に、奥の部屋から一人の男性が顔を覗かせてきた。
自分たちよりも若干年上らしい男性は、季節では夏になっているにも関わらず、全身に漆黒の服で着飾っていた。主人らしき彼は瑛里華を見て目を細める。
「いらっしゃい、瑛里華お壌ちゃん。久しぶりだね」
思いの他、柔和な声色で問う主人に瑛里華もまた、お久しぶりですと返す。
「私服じゃないということは、生徒会の仕事ということだね」
「ええ、実は監視カメラを三十個ほど貸して欲しいんです。照明の目安は0.01〜0.1ほどなのでデイライトカメラでカラーの高感度の無線式を、レンズはそうですね……f=6か8の標準をお願いします。記憶媒体はHDで」
「…………」
超古代文明じみた言葉の羅列に、孝平は一文たりとも理解できずいた。
そこから少し離れた場所にいる白もまた、頭にクエッションマークを浮かべている。
「やっぱり幽霊騒動が目的かい?」
「お耳が早いですね。もうそこまで知ってましたか」
「この道は速さと新鮮が命だからね、それから注文の分は明日、学校に持っていくように知らせておくよ」
「ありがとうございます。それでお値段ですけど……」
金銭の交渉を内密に話し合う瑛里華と店主、長くなるかと思いきや、一言二言交し合っただけで全て纏まったらしく、領収書を書き始めた。
「では後はお願いします。出来うれば早めに」
「はい、確かにお受けいたしました。ところでそこの二人は始めてみる顔だね。ひょっとして生徒会員かい?」
視線で自分と白のことだと思った孝平は慌てて会釈する。
「はい、二人とも生徒会員でこの人が支倉孝平君で、あそこにいる女の子が東儀白ちゃんといいます」
「初めまして支倉孝平です」
「……東儀白です」
自己紹介と挨拶をし、二人は再び頭を垂れた。
「東儀ということは、征一坊の親戚かい」
「兄さまをご存知ですか?」
兄の名前を上げられ、即座に反応する白。
「たまにここに来ては、いろいろとね。最近は見かけないけれど、元気にしているのかい」
「あ、はい、兄さまは病気もせず、健康そのものです」
そうかと店長は満足げに微笑み、そうそうと瑛里華に話を持ちかける。
「あ、そうそう瑛里華の嬢ちゃん。例の物が今日入荷してきたけど、どうする?」
びくっと大きく硬直する瑛里華の体。ぷるぷると振動し、煩悶すること数秒、
「マタ、コンドニシマス」
苦渋の中の更に苦渋の決断なんですと彼女から発せられ、常の燦然とした風采が嘘のように消えているのが感じ取れて、孝平はただ事ではないと思案して止めた。誰も命の灯火を自ら掻き消す必要など無い。
「それじゃあ、注文の品をお願いします。ではこれで失礼します」
二人に話の内容を問われるのが恐ろしいのか、瑛里華はぎこちない態度を悟られまいと、無理やりに笑みを浮かべた。
黙々と、ただ黙々と道の真ん中を突貫するように、瑛里華が帰路に就こうと進んでいくのを孝平と白は不審の念に駆られつつ、彼女の耳には届かない音量で会話する。
(支倉先輩、瑛里華先輩どうしたんでしょうか。さきほどの店から出てから黙っていますけど)
(本人に直接言わない方が身のためだよ。ああ見えて結構、気にしているタイプだから)
(何か心当たりでもあるのですか?)
(あるというか、きっと当たりだけど……)
「二人とも、さっきから後ろで囁き合っているのかしら?」
自分の後ろで内緒話を耳聡く聞いた瑛里華が、目を険しく問い詰めてくる。
彼女が肩越しから輝く逆光のために細部まで覗けないが、相当怒っているように見受けられる。現に全身からは周囲の空間が揺らめくような陽炎が迸り、双眸は見たもの全ての心を鷲掴みにして、粉々に引き裂くような真紅に染め上がり、目尻が釣りあがってきだして……そこで吸血鬼化しかけているのを知った孝平。
彼女自身でも自覚してないのだろうが、吸血鬼のルールに抵触しかかっているのに気づき、気を逸らすための何かが無いかと周囲を窺う。
と、視界の端に現状を打破するためのキーアイテムを孝平は発見する。
「少し、待ってくれ二人とも。すぐに帰ってくるから」
「ちょっと支倉君、どこに行くのよ!?」
「先輩?」
突飛な行動に面食らう二人を差し置いて、孝平はある物品を買い物していく。
現にさっきので吸血鬼化の進行を防いだものの、彼は瑛里華の悩みの根本な部分を少しでも解消すべく、好きそうなのを選んだ。
「ほら、これでも食べてくれ」
数分後、孝平がそう言って二人に差し出したのは、コーンに乗せられた真っ赤なアイスクリームだった。意図が測れず、華美な眉を潜める瑛里華。
「ちょっと待ちなさいよ。生徒の模範たる私達に、買い食いをさせるつもりなの?」
詰め寄る瑛里華。無論、事前に反論の準備をしていた孝平は尋ね返す。
「確か瑛里華、うちの学校の校訓は、自由・自立・自尊だよな」
「ええ、それがどうかしたの」
「だとしたら俺たち生徒会とて、自分を厳しく律して、他人に迷惑をかけない行動を取れば大体のことは許されるはずじゃないのか。現に買い食いしても別に迷惑かけているわけじゃないし。むしろ逆に感謝されないといけないし」
路地整然とした物言いに、瑛里華は口ごもる事数秒、
「……あなた、別の意味でだんだん兄さんに似てきてない?」
孝平にとってもっとも辛辣な言葉の弓の豪雨が心臓厭わず、全身を貫いた。
年がら年中、唯我独尊と呼称される彼と同格だと貶されて両足の力が抜け、よろけそうになるのを踏み止まりつつ、気上げに振舞おうとする。
「勝手に言ってろ。まさか驕られたものを捨てるなんて、言わないよな」
「当たり前でしょ、タダより高いも何て無いし、それに捨てるのはもったいないもの」
至極当然のように答え、やや躊躇った後にアイスを口にする瑛里華。
優雅に食するその仕草は様になっていて、一種の絵画だと思わせた。
「でもいいんですか先輩? こう驕ってもらっては悪い気がします」
静々と遠慮を含めて、白はアイスと自分とを交互に見やる。
「別にいいんだ白ちゃん。それにこれは何時もお世話になっている俺のお返しだって思ってくれればいいから」
「そうですが……」
素直な気持ちで返してもなお、思案していた白だが意を決意して「いただきます」とアイスを口にする。瑛里華とは違い、小さな口で少しずつ崩しながら食べていく光景はまるでウサギの雪丸みたいな小動物を彷彿させて、可愛らしいと思えた。
「へぇ、これなかなか美味しいわね。白ちゃんはどう?」
「はい、ちょっと酸っぱいですけど、美味しいです」
可憐な笑みを浮かべつつ、白は瑛里華に率直な感想を述べた。
なんだかこうしてみると、仲睦まじい姉妹とか親友とか上級生と下級生に見えて、自然と孝平の頬が笑みの形に緩んでいく。
「ちょっと支倉君、人の顔を見て笑っている暇があるならアイスを食べなさいよ。溶けかかっているじゃない」
「あ、しまった」
失念したと孝平もすぐにアイスを口にする。途端に舌を滑らかに通っていく酸っぱさと甘さ、確かに美味しい。今度、陽菜たちにでも買って帰ろうか。
「……それにしても、こうして歩くなんて珍しいよな」
ぽつりと呟いた昔の自分を穿り返すような迂闊に、慌てて口を噤む孝平。
別の話題へと逸らそうとして、彼女たちに対して不誠実のような後ろめたさを感じた自分の胸の奥に、懐かしさにも似た哀愁が再び芽生えつつあるのに、動揺しつつあった。
微細ながらも変化している彼の心情を知らずか、二人はそのままの意味で捉えて、会話を続ける。
「別に私達が歩くなんて事態、そんなに珍しくないじゃない。ねえ白ちゃん?」
「はい。私も最近ですが、瑛里華先輩と一緒に街に遊びに行ったりもしてますし」
さしたる苦労もせず、話題が逸れているのを見過ごすか謀りかね、放置する。
(まあいきなり俺の昔話を語った所で、困惑させるだけだしいいか)
心中でどこか本意ではない、言い訳めきをつつ孝平はなぜか、談笑に弾みを始めた瑛里華と白の背に謝罪した。
(ごめん瑛里華、白ちゃん)
ふいにぽたりと、溶けたアイスが孝平の手の縁に垂れた。
「改めて実感するけれど結構、不気味だな。夜の学校というのも」
「そうかしら、私は別にそれほど気にしないけど。そもそも生徒会の仕事でこんな時間にまですることあるでしょう」
「お陰で何時も俺が被害を被っているけれど。ところで、もう少し仕事の量を減らせないのか? 人数を増やすとか」
「無理。その権限は、兄さんと征一郎さんしかないもの。私には出来ないわ」
「やっぱりそうなるのか」
数日後の夜、双眸の先に聳える毎日のように登校している学院の秘められた一面に、孝平と瑛里華は互いに感想を述べながら、改めて光景を垣間見る。
生憎と夜空はほの暗い雲によって、本来空に浮かぶはずの星々の光が遮られ、懐中電灯が無ければ自分の足元に何かあるか分からない有様だった。
「まるで陸の上の深海にいる気分だな、例えるなら」
「なにそれ、支倉君もしかして詩人?」
「悪かったな、詩人で」
辛辣な瑛里華の言葉に、孝平は気を害して鼻を鳴らす。
夜更けともあって、周囲には自分たち以外の人影は見当たらず、どこからか時折吹きすさぶ生暖かな風が肌を摩り、なんとなく自分たちがこれから生物の体内へと侵入するような不気味な錯覚を植えつけされられた。
「白ちゃん、俺の声がきちんとそっちに届いてる?」
耳元に填めたパーツから伸びたコードの途中にある、とあるボタンを押して、彼女を呼び出す。
『はい、こちらの調子は大丈夫です。それにカメラも正常に稼動していますので、いつ入っても大丈夫ですよ』
インカムから接続されたイヤホンから、白の声が鮮明に耳朶に届く。
現在彼女は、監視カメラからの映像を受信するためのパソコンをモニターするために寮の一室で待機しており、何事か発生した際には即座に伊織を初め、先生にも連絡する手はずになっていた。
ちなみに監視カメラの設置を初め、受信側のパソコンの各種設定をしたのは孝平であり、全ての箇所を取り付けるのにかなりの時間を労していた。もっとも後で瑛里華や白による豪華すぎる夕飯をありつけたので、文句は言えない。
『ところで支倉先輩、一つ尋ねてもいいですか?』
「何となく言いたいことが分かるけれど、いいよ」
心当たりのありすぎる白の質問に、孝平は悄然の気持ちで返す。
『リュックサックの中に入っているのは、一体なんなんでしょう』
玄関先の手前に設置された監視カメラの一台の中で、白がモニター越しに孝平が背負っている荷物の中身を見つつ、不審げな声色で言う。
「かなでさんが『幽霊退治をするなら、これが一番!』とか言って渡してくれたものなんだ」
『……またですか』
以前、白が買い物に出掛けた際、奇妙というか奇抜な出で立ちで尾行(ストーキング?)をしたのを思い出したのか、珍しく彼女は気の抜けた返事をした。
「ところで中身は何なのかしら、さっきから妙に嫌な臭いが漂ってくるけれど」
鼻腔に突き刺さる刺激臭に嫌気が差して堪らないのか、先ほどから瑛里華は孝平の近くにまで寄ってきていない。
「ニンニクだよ。まったく、かなでさんも間違った知識で押し付けるなって」
心中でこの場にいない、かなでを罵りつつリュックを玄関脇へと追いやる。
『瑛里華先輩って、ニンニクが嫌いなんですか?』
「ええ、ちょっとあの変な臭いや味がどうしてもね」
『そうだったのですか』
あこがれの先輩のとある一面を覗いて、感嘆をあげる白。
しかし微妙に話が逸れだすのを孝平は感じて、本題へと修正を入れる。
「それにしても監視カメラを使用してもなお、俺たちまでもが探索したいといけないなんて、少しばかり不公平じゃないか? 噂の幽霊は」
「仕方ないでしょ。人から聞いた話やインターネットから推測される気象や時間を初めとした条件を考察してみても、当てはまるパターンが無いもの」
「でも、確か大勢で探索したりしたら、絶対に出てこないんだろう?」
顎に曲げた指をやり、不可解だとばかりに眉を潜める孝平。
「それが妙に気になるのよね。まるで幽霊自身に意思と思考があるみたいで」
同意見とばかりに瑛里華も腕組みをして、ターゲットでありながらも常識の一線を化している幽霊について黙考し始める。
聞き込みや過去の文献などで情報収集してみても、学院にはそのような噂話は皆無であり、また幽霊の根源を探ってみても『恋人の振られた女子学生が飛び降り自殺したが、今だに恋人が忘れられずに彷徨っている』や『学院に入学する直前に、急な病で亡くなったために、未練を残してしまった』などと一貫性のない話ばかりで、手掛かりになるようなものは無かった。
だが、女の幽霊が学校内を歩き回っているというのは事実であり、確かな目撃証言がある以上、こうして直に探索しなければならなかった。幸いな事は、幽霊が敷地外に出没しない点だろうか。下手すれば学院の隅から隅まで足を運ぶ真似をしてしまい、翌日には筋肉痛と寝不足で休日一個が丸つぶれになりそうだから。
「白ちゃんはどう思ってる? 例の幽霊について」
少しでも回答に至る材料を足そうと、白へと話のバトンを渡す瑛里華。
イヤホンの先で黙考の気配を覗かせた後、彼女は憂いを込めて告げる。
『……可哀想だと思います』
「可哀想? なんでそう思うの」
どこか琴線に触れる感覚に戸惑いつつ、瑛里華が先を促がす。
『その亡くなる方が以前、どんな人生を過ごしていたとか、どんな想いを抱いてのか知ろうとも思わないまま、面白おかしく貶されているなんて可哀想だと思いましたので』
沸々と積もっていくような感情を覗かせつつ、白は驚愕の一言を発した。
『だから私、そんな風に話を作り変える人たちを許せないです』
「「…………」」
言葉を喪失するとは、この場面か。会話の穂を繋ぐことすらできない。
人前では滅多に自分の意見を語らない彼女が、静かに語気を荒くして、嫌悪感丸出しの感情をむき出しにしていることが。
それに孝平は冷静に彼女の心情をゆっくり染み渡らせ、理解感得してみる。
「じゃあ、幽霊に会ってみたら聞いてみようか」
『え?』
自然と思い立った提案が孝平の口から零れ、白に同意を求める。
「そんなに気になるんだったら、実際に俺たちが出会ってみて、話してみて、どんな人なのか聞いてみたほうが、その噂を晴らせるかもしれないから。それじゃあ駄目か?」
数瞬の沈黙の幕を周囲に展開させ、やがて白は小さな息を吐く。
『……そうですね、支倉先輩の言うとおりかもしれません』
孝平の提案を受け入れ、それから、
『ありがとうございます、先輩』
感謝の念を抱きつつ、白はよろしくお願いしますと付け足した。
どんな感情を抱いたのか、傍らの瑛里華は柔らかな笑みを孝平へ注ぐ。
「そろそろ時間だから行きましょうか、支倉君。もちろん来るわよね、さっきの宣言が嘘じゃなければ」
含みのある笑みを浮かべながら、綺麗な指を揃えて瑛里華は校舎へと向ける。
何を考えていると、孝平は憮然としつつ当たり前のように言う。
「来るじゃない、付いてこいって。少なくても正面くらいは守ってやるから」
「…………」
予想外の台詞だったのか、瑛里華の体が謹直の姿勢で固まった。
「どうした瑛里華。もしかして動揺しているとか」
「べ、別に動揺なんかしてないわ」
毅然とした風貌を保とうとするものの、どこか揺らめいたものが瞳の奥で過ぎった気がした。無論、孝平の身勝手な思い込みでしか無いが。
〜承〜

〜起へ。

〜転結へ。
片手に持った懐中電灯から照らし出される廊下を、淀みも恐れも無い歩調でこつんこつんと小気味良い足音を鳴らせ、夜の校舎を散策する孝平と瑛里華。
付かず離れずの距離を置きながら、注意深く周囲を観察し、目を光らせる。
「分かってはいるけれど、すぐに幽霊が出現なんてしないんだな」
「当たり前でしょ、簡単に見つけたらこんな事にはならないわ」
「それもそうだな」
首肯しつつ、孝平は隣で真剣に探索する瑛里華を盗み見る。
容姿端整、成績優秀、完全無欠という単語が彼女のために存在しているように感じられ、今宵の闇の中でさえも掻き消すことが不可能なほど、輝きに満ち足りていた。それにお風呂上りなのだろう、一挙一動から零れだすいい匂いが孝平の鼻腔をくすぐる。
いくら生徒会の仕事であり、インカムの先には白が待機しているとはいえ、彼とて年頃の男の子。今日に限っては心音の針がいつもより、大きく揺れていた。
「ちょっと支倉君、真面目に仕事をしなさい」
孝平の視線に気づき、不遜を咎めるように瑛里華が叱咤する。
「あ、いや、いつもよりも綺麗だなって思って……まるで夜天の妖精みたいだって」
饒舌に語る途中で、自分がいつもなく羞恥な言動をしているのに気づく。
慌てて言葉を飲み込むが、もう遅い。ほぼ全て瑛里華の耳に届いている。
変な愛称で呼ばれ、呆けられるものかと過去の経験からして覚悟したが、
「あ、ありがとう。一応、褒め言葉として受け取っておくわ」
意外と満更ではないらしく、瑛里華は滅多に見せない恥じらいの顔を見せた。
期せずに気まずげな空気が二人の間に靄のように立ち込め、間を開けまいとしようとつつも、ふとした仕草で互いが互いに牽制などをし続けていた。
「「なあ(ねえ)……どうぞ」」
ようやく口を開いた瞬間、息があったように重なる声にまた硬直する二人。
(どうしたもんだか)
女性関係どころか、人間関係にさえあまり深く関わらない孝平は、空しいと知りつつも答えを探ろうと視線を宙に彷徨わせる。
出来うれば今すぐ寮へと直行し、かなでが作成したリーサルウエポンを垣間見、今晩の記憶ごと消去させたい気分でもある。というか、させて欲しい。
『支倉先輩、瑛里華先輩、反応がありました!』
そんな矢先だった。白が目標補足を高らかにしたのが。
いよいよ今回における、生徒会の仕事の本当の開始を告げるように。
一瞬で二人の思考は切り替わり、状況を冷静に分析し始める。
「それで場所はどこ!?」
『新敷地の一階、音楽室付近に白い服の女の人が歩いています』
「分かったわ。引き続き観察をお願い!」
間髪入れずに瑛里華は指示を出し、顔をきりりと引き締める。
「行くわよ支倉君、準備はいいかしら」
「ああ、いつでも大丈夫だ。それよりも二手に分かれて挟み撃ちにしたほうがいいんじゃないか。そっちの方が見失わなくて済む」
「そうね、その案で行きましょう」
先ほどの気まずい空気を一蹴した二人は頷き合った後、一目散に別れてつつも目的地へと駆ける。
全力で廊下を走り、階段を飛ばしに飛ばして駆け下り、突き当りの通路を曲がって、渡り廊下を伝い、問題の階へとたどり着く。荒くなる息を整えつつ、インカムで廊下の向こう側に佇む瑛里華へと連絡を入れる。
「瑛里華、そっちには幽霊はいなかったか?」
『いいえ、こちらには誰もいないわ。白ちゃんそっちはどう?』
『目標は……その階から移動した形跡はありませんけど、見失いました』
各モニターを観察していた白が、居た堪れない声色で謝罪する。
夜になっても穏やかにならない温度と湿度に、沸々と額に浮かぶ汗を拭いながら孝平は現実離れした状況に憮然として呟く。
「見失ったって、まさか本当に煙のように消えたのか、嘘だろう」
『でも、この階から上に行っていない以上、部屋の中に隠れてそうね』
「じゃあ、一つ一つ調べつくすしかないか」
『それしかないわ』
仕方ないと孝平は身近にある部屋の取っ手に触れ、ゆっくりと横へと逸らしていく。
途端に開放された重苦しい空気が、毛筋を逆撫でながら床を伝っていった。
思わず息を呑むが、意を決して顔を室内へと突き出し、視線で物色する。
以前、紅瀬に超激辛オムレツを試食した家庭科室の中は、至って平穏そのものであり侵入者が存在する形跡は表には見受けられなかった。
「……いないか」
無意味な安堵をしかけて、かぶりを振って気を引きしめる。
幽霊ならば壁抜けも出来そうな気がするが、怪談話に釣られてやってきた一般生徒が潜んでいる可能性がある以上、中を探索しなければならず、静かに足を踏み入れる。念のためにドアを閉めておく。
「っ!?」
ふいに戸外に物音がした気がして、懐中電灯をそちらへと向ける。
が、結局の所、それは単なる風が窓ガラスを揺らしただけであった。
「はぁ、さっさと調べて瑛里華と合流しよう」
歩くたびに、磨り減りそうな気概を何とか保ちつつ隈なく散策し、異常が無いと判断を下して外へ出ようと……出ようとするのだが、出られなくなっていた。
「って、開かない!?」
遅れて湧いてきた実感と緊張感に苛まれつつ、あらゆる方向へ力を入れる。
だが扉が一枚の壁になったように、引いても押しても反応が起きなかった。
『支倉先輩、瑛里華先輩、聞こえますか?』
『ちょっと待って白ちゃん、こっちは今それどころじゃないのよ』
突然の白の呼び出しに対して、何時もの矜持が嘘のように、瑛里華の声には動揺が色濃く混じっていた。
ひょっとしたらと予想し、孝平はインカムで理由を問いただす。
「瑛里華、一体どうしたんだ?」
『どうしたもなにも、外に出られないのよ。さっきまで開いていたはずのドアが急に閉まって、閉じ込められたの』
「そっちもか?」
『そっちもってことは、支倉君の方もなの?』
「ああ、こっちも完全に閉じ込められた。鍵もかけてないのにな」
視線を見下ろす先、ロックする部分を確認して事実を伝える。
そこでふと孝平は白の用事を聞き漏らしていたのに気づき、話を振る。
「ところで白ちゃん、話っていうのは何?」
『実は敷地の一階に二人組みの誰かが、入ってきています』
『こんな時にまた誰かが探索に来たのね。あれほど学校側から通達させたのに』
自身への好奇心を満たすためだけにやって来た彼らに、呆れや憤然が込めつつ瑛里華がため息を溢すのが聞こえ、次いであれほど頑固に閉まっていたのが嘘のように、取っ手が自然と引けるようになっていた。
「「良かった、出られた…………え?」」
脱出できると直感し、外へ出て重なる安堵の声の方向へ振り向き、ありえない光景に茫然すること五秒ほど、
「「どうして瑛里華(支倉君)がここに?」」
面食らいつつ、互いの顔を指差す二人。慌てて現在地を確認する。
「ここって……まさか教室煉? そんなどうして」
自分の位置を把握した瑛里華が、動揺を露に周囲を見渡す。
それは孝平とて同意見だった。背後を振り返り調理場だったはずの部屋が、昨日の日付が書かれた黒板や、椅子や机が整然と並べられる教室に移動していたのだから。
「ねえ、あれって……何?」
徐に瑛里華が渡り廊下の先を指差す。
「……球、だよな」
見やる先、ぽよんと跳ねる小さな球が……いや、巨大な球体が接近してきている。廊下の天井と床をばんばんとバウンドしながら真っ直ぐに。しかも大きな口を開かせては獰猛な牙を見せつつ。
「まずい、顔を引っ込めないと……おわっ!」
教室内へと身を潜らせようとした途端、背後から押されるように廊下へと突き飛ばされた。振り返る矢先、独りでにドアが閉まりロックされる音が無情に響く。
「これって……もしかしてピンチかしら」
誰とも無く瑛里華が呟き、現実に戻ってきたらしく、身を起こす。
「支倉君、逃げるわよ!」
体制を整えるように立ち上がり、踵を返しながら瑛里華が孝平を呼ぶ。
頷き返して彼もまた遁走するために、足に力を入れて彼女の後を追う。
「支倉先輩、瑛里華先輩、聞こえますか!?」
無意味だと知りつつもマイク越しに向かって、切羽詰った声音で問いかける白。
先ほどからいかなる理由か、あれほど正常に稼動し続けていた監視カメラからの映像が消え、全てのモニターには無味乾燥なノイズが走っていた。現実では考えられない状態である。
「やはりここは兄様や伊織先輩に連絡を入れるべきですね」
そう思い立ち、ポケットから携帯電話を取り出し、兄の携帯電話へと連絡を入れようとする。だが、繋ぐ事ができなかった。
「どうして繋がらないんですか」
困惑気味に白はよく見てみると、携帯の表示に通話圏外の表示が浮かんでいたのを知り、ますます困惑の渦にはまり込む。だがそれも数瞬の内だった。
「……こうなったら、私が行かないといけませんね」
二人の先輩の身の危険を察し、白は立ち上がる。
未だ内心には夜の校舎という恐怖心が燻ぶってはいるが、それよりも二人の先輩の身の安全と、幽霊と直に会って本当の事を知りたいという気持ちが上回っていた。
「待っていてください先輩方。今、行きますから」
小さな身体に活を入れて、白は立ち上がり、
――彼女の背後から白い手が背後から迫り、触れた。
一名様、ごあんなーい。
「な、なあ、廊下って元々、こんなに、長かったか」
「長いわけないでしょう。もう、どうしてこんな事になったのよ」
「むしろ……こちらが、聞きたい」
「だったら支倉君があれを止めてきたらどうなの」
「無理、無駄、無謀だっ……て」
全力前回で足を動かしながら、先の見えない終わりに嘆く孝平と瑛里華。
走れば一分で終着するはずの廊下が永久ループの回廊にでもなったかのように、階の端へとたどり着けないためである。何分ほど駆け抜けているか、携帯時計を見れば一目瞭然なのだが、そこまで二人は気が回ってなどいなかった。
「それに、しても、まだなのか」
体力、気力、精神ともに限界に果てかけた孝平が息も絶え絶えに尋ねる。
「しっかりしなさい支倉君、ここで立ち止まったら私達、あれにぺしゃんこにされるわよ」
至極当然の瑛里華の叱咤に、明日から体力を付けようと孝平は実感した。
いや、むしろ彼女の体力の一割を今、ここで供給されたい。
「支倉君、ほらあそこを見なさい」
瑛里華の声に顔を上げる。廊下の突き当たりが見え始め、階段に至る場所があった。
あそこに非難すれば、少なくとも球体と正面衝突は免れるだろう。
「もう少しだから、頑張りなさい」
無言で孝平は頷き、最後の力を振り絞って必死に両足を前に動かす。
「きゃ!」
そうしてたどり着いた矢先、一足先に瑛里華が突き当たりを曲がった直後、校舎に侵入した本人らしき一行が何か悲鳴を荒上げつつ、突き飛ばした挙句に去っていくのを垣間見た。
「瑛里華、大丈夫か!?」
「別にだいじょ……痛っ!」
気丈げに返そうとして顔を顰める瑛里華。右足を労わるように指を遣る。
綺麗な眉を苦痛に捻じ曲げ、額には脂汗が浮かばせ、何かを堪えるように彼女は唸っていた。
「もしかして、瑛里華見せてみろ」
怪訝に思いつつ、一つの可能性を予想して孝平は、瑛里華の足首を診察する。
「……やっぱり」
最悪な状況に孝平は頭を抱えるしかなかった。
恐らく先ほどの衝突で、瑛里華の足首が捩れたのだろう。
「捻挫かしらね、これは」
冷静に状況を分析しつつ、瑛里華は他人事のように呟く。
一応はそれほど腫れてはいないが、肌に伝わる熱は高くなり始め、一刻も早く病院へと向かうべきなのは明らかだった。とはいえ外部と連絡が取れない今では、保健室にでも行き、応急処置を施すしかない。
「それよりも支倉君、今は逃げないと。このままだと私達、押しつぶされるわよ」
「……いや、もう大丈夫みたいだ」
「どうしてそう言い切れる……あれ?」
孝平の言葉に瑛里華が釣られて見遣ると、いつの間にか球体が消滅しているのを知り、目が丸くなった。
「それにしても無敵の副生徒会長も、意外と抜けているんだな」
保健室に向かい、捻挫をした瑛里華の足首に貼り付けた湿布の上から、ぎこちない手つきでテーピングしつつ、意外な側面を目の当たりにした孝平は、込み上げてくる笑いを隠せずにいた。
遅れて笑いものにされた瑛里華からの反撃が来ると、咄嗟に身構えてみたがなぜか当の本人は意味深に孝平を凝視し続けている。
「支倉君って、最近よく笑うようになってきたわね」
「そうか? 別にいつものことだと思うけれど」
「絶対にそうよ。それに以前のあなたって、笑っていても会話を円滑にするための上辺だけみたいで、中身は空っぽみたいだったもの」
指摘されてみて、今までの自分の身の在り方を振り返ってみる。
この学院に転校する前と、して以降の自身の変化を。
「……確かにそうかもしれない。以前は積極的に誰とも関わろうとしなかったし」
「どういうこと?」
重大な何かを吐露しようと察した瑛里華の双眸が、次の言葉を待とうと辛抱強く待ち続ける。もちろん、ここで話を止めるほど孝平は人が出来ていない。
保健室の硬いベッドに腰を下ろして、彼はかつての記憶を語りだす。
「昔から両親の仕事柄、一箇所に留まることがなくてさ、数ヶ月に一回転校なんてことも珍しくなかった。まあ、当時の俺は子供だったから拒否権が無かったから仕方が無かったけど」
一瞬目を瞑って転校した先を思い返しても、名前もろくに覚えておらず、顔の輪郭やどのような声色さえ不鮮明なクラスメイトの姿ばかり。そもそも、そんな人間が現実に存在したかさえも、覚束なかった。
最初の頃は親しい友人と別れて悲しかった、涙を流した時だってある。
だけれど、何時頃だったのだろうか? それが当然の通過儀礼であるのに。面だけは人当たりの良さそうな笑顔の仮面を被り、その奥にある本心を悟られまいとし始めたのは。
「いろんな所に言った。中にはこの街みたいな場所だったりとか、交通の便が激しい場所だったりとか」
時には鬱蒼と多い茂る木々や自然に囲まれた田舎に転校したこともあった。時には鉄筋コンクリートが乱立する無機質な不夜城の都心に転校したことがあった。だが、孝平の眼に映る景色には色彩といったものが無く、全てが全て白黒のように単調な景色でしかなかった。
ある意味、それは幼い頃の孝平自身がとった、ある種の防衛本能。
これから先、無数にある悲しみから逃れるために、いろんな意味で諦観した結果である。苦しみや悲しみから目を背ける事により、幼いがゆえの繊細な心を絶望の色に染めることにより、己の存在を保つために。
「でもこうして皆と一緒に暮らしているって実感するなんて場所は、まったく無かった。それどころかこうして誰かと親しく話すなんて、しようと思わなかった。無意味だと感じていたから」
だからこそ支倉孝平は、今に至るまでそれをし続けていた。そもそも、相手を知るという事はすなわち、自分自身の胸の内を教えるものなのだから。
「…………」
沈黙の幕を纏う瑛里華に、孝平はでもと頭を振るう。
「でも、こうして本当に暮らしてみたいって思ったのは、ここが初めてだと思う。例えこの先、親父たちが戻って来いって言っても、嫌だって反論したいくらいにさ」
「どうして今、そんな大切なことを私の前で告白したの」
孝平の話にどんな感想を抱いたのか、瑛里華が真意を探る声色で尋ねる。
「なんでだろう。この街に来てから、いろんな経験を見て、受けて、積んで、なんて言うかとても暖かい輪の内に自分がいるみたいか感じたしたからかな」
「やっぱり支倉君、詩人というかポエマーなのね」
「……そうかも」
苦笑し、孝平は瑛里華が何か呟いたように聞こえた。
「なにか言った?」
掠れた問いみたいのに孝平はもう一度、確認の意を取る。
「じゃあ、今は楽しい?」
紡ぎだされたのは、現状の気持ちだった。
「ああ、今はすごく楽しいよ」
それに孝平は今の気持ちを包み隠さず告白した。
「とはいえ、今日の見回りはこれで終了するしかないか」
瑛里華の足首を覗きつつ、孝平は調査の断念を決断する。
どちらかといえば、判断を下すのは瑛里華だが、彼女また同意見なのだろう。表情に苦渋の悔しさを見せつつ、孝平の考えに賛同した。
「ごめんなさい支倉君。私がしっかりしてなかったせいで、こんなことに」
歯噛みしつつ、瑛里華はしゅんとうな垂れて珍しく謝罪する。
「別にいいよ。それに瑛里華のせいじゃない」
フォローしつつも、今夜の瑛里華の一面を垣間見、孝平はいじわるに笑う。
「それにしても今日はやけに殊勝だよな。いつもそれならいいのに」
「……馬鹿。誰のせいよ」
言って、瑛里華は孝平の額にデコピンを喰らわせた。思わず仰け反る。
だが、彼は察していた。それが照れ笑いの裏返しということに。
ひりひりする感触を味わいつつ、ベッドに横たわろうとして、
『悪戯、悪戯、遊戯、楽しいかなー?』
壁の向こう側からやけに耳に響く、奇怪な歌詞と出鱈目なハミングの歌声が聞こえてきた。思わず横の瑛里華と顔を合わせる。合わせてから息が身近に感じられる位置なのに気づき、反射的に距離を取った。
「この変な歌声は、かなでさんかしら」
視線を僅かにそらしつつ、ごほんと咳ばらいして瑛里華。
暗闇の中でもしっかりと高揚した頬の色が覗ける。
「いや、それは絶対にない」
極めて平静に努めつつ、孝平はその意見を否定した。
「どうしてそんなことが分かるの」
「こんな時のために、対かなでさん用の最終兵器を寮に残してきたから」
「最終、兵器?」
「それよりも息を潜めよう。今はそれが先決だろう」
小声で潜めながら問う孝平に、しぶしぶ瑛里華は自分の行動を倣う。
現在かなでは『こーへーが行くなら、わたしも付いていく♪』と豪語していたのだが、ただでさえ調査が危険極まりないのに、彼女が同行しては豪雨のち雹、そしてタイフーンの極悪三兄弟が襲来するような状態に危惧していた孝平は、かなでにとある約束を交わしていた。途端に断固死守するような猛烈な気概を今でも覚えている。
だからこそ確実に今晩、かなでは寮の一室から出られないだろう。
同時に詰まる所、この接近してくる足音は第三者でしかあり得ない。
思考を巡らせるのを中断したのと平行に、ぴたりと二人がいる保健室の前で音が区切られた。緊迫感が体中に駆け巡る。いよいよ対峙する時が来たと直感した。
(まったく、こんな時に最悪だ)
胸の内で悪態をつき、状況の危うさに頭を抱える。
逃げようにも瑛里華が捻挫しているために退路が無く、救援を呼ぶにしてもインカムからは何の反応すら返ってこない。唯一の頼り綱である白への連絡できず、絶体絶命だ。
(なら、せめて瑛里華だけでも守らないと)
もしもの事態があってはいけないと、孝平は瑛里華をかばうように躍り出た。
「っ!?」
背後で瑛里華が動揺で瞬きするのを知らず、孝平は腰を少し落としつつ何時でも攻撃できるような姿勢を取った。恐怖で金縛りになりそうなのを、歯を食いしばって押し留める。
かつんと取っ手が手に触れる……心臓の脈が一瞬停止する。
静かにドアが横に移動する……掴み掛かろうとし、足が痙攣で動けないのを知る。
体が心に反応できない中、完全に開放された先にいたのは……、
「支倉先輩、瑛里華先輩、探しましたよ」
「白、ちゃん?」
肩で息をして、安堵の表情を浮かべる白だった。
あまりの急転すぎる状況に把握できずに煩悶する二人。
そんな彼らを知らずと、白は入室しては孝平の足ごしに瑛里華の足首を注目する。
「瑛里華先輩、大丈夫ですか? 痛そうに見えますが」
「ええ、支倉君が看護してくれたから、大事には至らなかったわ」
良かったと白は胸を下ろし、今度は孝平に深々と謝罪した。
「支倉先輩、いろいろすいませんでした。仕事を放棄したみたいに」
「いや別にいいよ。白ちゃんだって俺たちの身を案じて、ここに来てくれたんだし」
むしろ助かったと言葉を紡ごうとして、入り口付近に誰かが佇んでいたのを見た。
「君は……?」
「こんばんは。それから始めまして?」
はにかんだ笑みを浮かべつつ、肩の位置で切りそろえられた艶やかな黒い髪を揺らしつつ挨拶する少女は、至ってどこにでもいる女子高生だった……背後の光景が透き通るように見える意外は。
〜転結〜
 〜起へ。
〜起へ。
 〜承へ。
〜承へ。
「ということは、今回の幽霊騒動は全部が全部……」
全ての顛末を聞き終えた瑛里華が自称、幽霊と名乗る少女を見上げた。
闇夜に溶け込むではなく、闇夜と同一のような彼女は苦笑しつつ肯定する。
「まあ、白さんから聞いた話だとそうみたいかも」
言って身を翻すと、眩い光が全身の奥から発光していく。
目の前の景色を黒で塗りつぶすように鮮明な、だが不思議と瞼を焦がすような強烈さではなく、寧ろ春の日差しのような柔らかさを持っていた。
「うわっ……」
光が掻き消えると、傍らにいる白が感嘆を漏らす。
そのはず、彼女は制服姿から純白のワンピース柄へと変化を遂げていた。
これには孝平とて、目を張るものがあった。深窓の淑女のように儚く、それでいてどこか陰のあるような危うい存在のように見受けられた。思わず見惚れてしまう。
「どう? 似合うかな白さん」
「凄くお似合いです、茜さん」
「えへへっ、やっぱそうかな?」
再びくるりと回り、遠心力でふんわりとスカートが捲りあがる。
「ところで茜。ちなみに聞くけど、どこからどこまで見ていた?」
なるべく足元を覗かないように注意しつつ、孝平は言う。
タメ口なのは本人から、そうしてほしいという意を飲んだためである。
「ええと、全部かな。二人が廊下を行ったり来たりして悲鳴をあげたり、ここに来る時におんぶしたりとか」
「私というものが……なんていう失態なの」
意気消沈と、うな垂れては頭を上げる気配を見せない瑛里華。
ただでさえ羞恥ものを、彼女が全て垣間見ていたのだから無理も無い。
「怪我さえしなければ、この後もいろいろなプログラムを組んでいたんだけど。……例えば、真っ赤なパラが舞い散る中で瑛里華さんが羽の付いた可愛らしいぬいぐるみを着飾って、踊ったり……」
ぴくりと一際大きく、瑛里華の肩が強張った。
なぜか孝平はそれに、全身の神経が凍りづく激痛が走った。
「んー、カエルのぬいぐるみの方が良かったかな?」
「あなたも兄さんと同類なのね?」
絶対零度並みの超低温の双眸が、茜へと満遍なく注がれる。
周囲の人間ごと瞬間冷凍させそうな威力を孕んだそれを茜は、ふぅとため息で一蹴し、
「それより私に聞きたいことがあるから、危険を承知でここまで来たんでしょう?」
前置きは無用と、本題へと切り出した。嫌なほどの切り返しようである。
むっ、と瑛里華は眉を潜め、卑怯者めと小声で呟いた。
「ええ、今夜ここに来たのは悪戯の真相と、あなたの正体よ。聞かせてもらえるかしら」
「別にいいよ。それに今夜で終らせるつもりだったし、それに生徒会の人がわざわざ足を運んでもらえたんだら、告白しないと割に合わないだろうし、怪我させてまで何も言わないほど私は厚顔無恥じゃないからね」
思いの他、律儀な言葉で返して茜は遠くを見やる目で口を開く。
「私がこんな風にしたのは今、噂されている話が全てデマカセだと伝えたかったから」
「デマカセ?」
オウム返しに訪ねた白に茜は向き直っては頷き、
「私が死んだ理由が恋人の振られた女子学生が飛び降り自殺したが、今だに恋人が忘れられずに彷徨っているとか、学院に入学する直前に、急な病で亡くなったために、未練を残してしまったっていうのを嫌というほど聞いたから。だからそれは違うって、連日連夜と誰かに伝えたかったのに、全員が驚いて逃げるんだもの」
要するに噂が違うと言いたくて、誰かに伝えようとしたが、逆にそれが恐怖を連鎖させる悪循環に陥ってしまったという事だろうと、孝平は思った。
「とは言っても、驚かせているうちに快感を覚えてきちゃって、今じゃあこうして全身全霊にかけて、驚かせているけれど」
いろんな意味で本末転倒では? などと内心で介入したくなる孝平。
が、口にするよりも虚実の話の方が重要だと察し、噤んでおく。
「……いろいろと文句を言いたいけれど、それよりもあなたが無くなった理由を教えてくれる?」
「私が死んだ理由、それは……」
演出のためなのか、真実を口内に貯めに貯めていく茜。
「「「死んだ理由は?」」」
身を乗り出し、事の真偽を聞こうと耳を傾ける。
息をするのも、もどかしく張り詰める中、
「オモチを喉に詰まらせたことによる、窒息死だから」
奇想天外な説明に、全員が全員ずっこけた。
どのくらいなら、瑛里華は金色の髪から飛び出たクセ毛一本が、くるりと丸まり、
孝平は思い切り、前頭部から激しい騒音と共に床に突っ込み、
白は目と口を丸くして、ハニワのように硬直していた。
「なぜにオモチなんだ?」
僅かな沈黙の後、痛たたたっと額を摩りながら、立ち上がる孝平。
あははと、愛想笑いを浮かべつつ茜は視線を一同に向けず、語り始めた。
「それがね、私は無類のオモチ愛好者でよく昼食のおやつに食べるほどなんだけど、ある日オモチを食べていたら、喉に引っかかったみたいで、気が付いていたら幽霊になっていたってワケ。いやー、本当にあれは苦しかったわ」
「な、なんていうオチなんだ……」
愕然とした面持ちで、孝平はこめかみに指をやりながら呆れ返る。
あまりにも馬鹿馬鹿しくて、ツッコム気概すら湧き上がらないほどに。
「それにしても……」
不意に真剣みを帯びた表情で白をまじまじと注視する茜。
不穏な気配を察して、白がびくりと身を硬直させる。その隙に、
「とりゃ!」
重力を無視した跳躍力で白の華奢な背後へと圧し掛かると、白いうなじに頬をなすり寄せる。
「きゃっ! や、止めてください茜さん!」
可愛らしい悲鳴をあげなげる白。次第に涙目になりかけていく。
貞操の危機(?)を察知した瑛里華がすかさず、止めに入る。
「ちょっと何をしているの茜さん! 白ちゃんから離れなさい!」
痛む足を押してまで背中から剥がそうと手を伸ばすが、虚無の宙を振り払ってしまう。眉を潜める瑛里華だが、すぐに相手が幽霊であることを失念して、くっと唸った。
「白タン、白タン、白タン〜♪ やっぱり白タンは可愛いな〜。来たからには驚かそうと連れ込もうとしたけれど、可愛さのあまりに二人の元に無条件で連れてっちゃうほど可愛いな〜♪」
融解しそうなほど光悦な表情と言葉遣いで、茜は白の体と密着し続けている。
「お願いですから、白タンって言わないでください〜」
珍しく困り果てる白が、脱力してぺたりと尻餅を付く。
「だからいい加減にしなさい、この破廉恥幽霊!」
沸点が超越して、出来もしないのに瑛里華はなおも掴み掛かり続けた。
「さて、お次は身体検査でも行きましょうか〜〜〜♪」
それを意にしないように茜は嬉々とした表情と声色で獰猛なアナコンダのごとく腕をしならせ、今度はブラウスのボタンを外したり、半そでから侵入しだしては、ありとあらゆる部位を触れ始めた。
しかも窓の外へと視線を急速旋廻していた中では、胸をもみ始めているのが垣間見えた。鼻血や鼻がたれ垂れ下がらなかったのは、孝平は幸運だった。
「たたたたっ、助けて〜〜〜〜! 兄様、神様〜〜〜〜っ!」
顔を朱に染め、あられの無い悲鳴をあげながら、手足をばたつかせる白。
だが暴れれば、暴れるほど拘束力が深まるらしく、更に密着を強める結果になる。
「ほほう、70のA、51、72ときましたか。白ちゃん、やっぱりあなた人気が出るわよ、特にそっち系の人たちには」
「そっちって、どっちのことですか〜〜〜っ!」
忌み奇怪なやり取りを傍観しつつ、孝平は間違っても絶対に茜を伊織とかなでと顔合わせしてはいけないと、深く心に刻み付けた。頑張れ支倉孝平、学院の平和は君の双肩にかかっている。
「はぁ…………」
さて、どうしたものかと彼は肺から重いため息を溢す。
「支倉君! よそを見てないであなたも手伝いなさい!」
それを見咎めた瑛里華の劈くような叱咤。尻を叩かれるようにようやく、孝平は重い腰を上げた。
「じゃあ今夜はこれで終わりね。皆、お疲れ様。明日は日曜日だし、ゆっくり眠って疲れを取っておいてね」
いつの間にか暗雲が晴れ、満点の星空の光で照らし出す寮の入り口前で、一同に解散と感謝と労わりの意を唱え、瑛里華は全身の筋肉を解すように背筋を伸ばす。
彼女でも緊張などで疲れていたのだろう、ふぁと可愛らしい声が漏れていた。
「あ、あの、先輩、ちょっといいでしょうか」
呼ばれて目線を下げると白が、憔悴げに孝平の足元を虚ろな双眸で固定していた。仕方が無いと孝平は内心で冥福を祈る。
なんでも茜曰く、白には幽霊媒質といって幽霊と直接触れ合える能力があるらしく、それを悪用されたのだから。まあ、最後には電力を充電したらしい茜が撤退してくれたお陰で、最後の一線は乗り越えなかったが。
「モニターの電源だろう? きちんと俺が消しておくから白ちゃんはそのまま帰ってもいいから」
「ありがとうございます、では……」
そよ風が吹けば、地平線へと飛びそうに頼りなさ過ぎる足取りで、家路につく白。
沈黙を保つべきか、労わりをかければ良いか煩悶している内に、彼女は寮の明かりが消灯されつつも、開かれている玄関へと消えていった。
「…………」
ふと視線を感じると、瑛里華が困惑げに自分を注視していた。
「どうした瑛里華、他に伝え忘れた事でもあるのか」
「ううん、ちょっと支倉君に聞きたいことがあって……いい?」
「ん?」
瑛里華が言い淀むのに小首を傾げつつ、孝平は構わないと軽く返事する。
「どうしてあの時、私を助けたり庇ってくれようとしたの」
尋ねられて一瞬、何の事と尋ね返そうとして、とある節に思い当たる。
捻挫をした瑛里華を背負って保健室に運んだのと、幽霊から彼女を守ろうと前に立ち塞がった件についてだろう。だからこそ彼は飾り気の無い言葉を告げる。
「どうしてって当たり前だろう、女の子だから守るのは」
至極当然で、自然と取った行動に不可思議な目で見遣る中、更に瑛里華は何かに急き立てられるように言葉を重ねていく。
「だって、私はバンパイア……吸血鬼なのよ、人間じゃないのよ。だから守ってもらう必要なんて」
「人間だよ、お前は。他の誰が、例えお前自身が人間じゃないと言っても、俺は人間だと言い続ける。いや、続けてみせる」
「…………」
さすがに瑛里華もこれには絶句して、謹直な姿勢で硬直した。
夜の学校からここに至るまで違和感を全身から発露すれば、嫌でも看破できた。
どういう訳か、彼女は妙に自分との一線を引こうと躍起になっている気がした。種族としての掟かもしれないし、本人の固執かもしれない。もしくは両方か。
だが学院生活では、少なくてもこうして面を合わせている時くらいは、『人間』としての『千堂瑛里華』として接していたい。そう感じられた。
それにそう、この憂慮を初めとした悲観的な顔は、彼女に似つかわしくない。
現に今も瑛里華を見ていると胸の奥がもどかしくて、辛くて、胸を締め付けられる。彼女の僅かな挙措に不安に抱きつつも、一歩踏み込めない自分に苛立ちすらこみ上げてくる。
なんとなく、孝平自身が瑛里華に対して抱いている感情の欠片をかけ集めようとして、
「……支倉君で良かったかも」
ふいに双眸の中に何か揺れる物を覗かせつつ、瑛里華がぽつりと囁く。
「え?」
「私が吸血鬼だって……知ってしまったのが支倉君で良かったって、言っているの」
顔を上げて白状した彼女は、相応しい勝気な笑みを浮かべていた。
途端に孝平の胸の内の蟠りがすっと、消え去るのが分かる。
(ん?)
なのになぜか、針の先で突付かれた様に痛みを感じる自分がいて、困惑する孝平がいた。だが、特に理由も無くそれを掻き消してしまう。
「それにしても驚いたわ。まさかあんな所を目撃されるなんて、思わなかったもの」
「それはこちらの台詞。まさか吸血鬼が現実に存在するなんて、思わなかったし」
互いに似た言葉を重ねあい、視線を組み合わせて、ぷっと笑い出す。
「もう、支倉君と話をしていたら、いろんな悩みが馬鹿らしくなってきたわね」
口調では孝平を罵りながらも、満面の笑顔がそれを否定している。
「さて、もう例の件で遅くなったし、早く寝た方がいいぞ」
もはや昨日の出来事になった事件を思い返しつつ、就寝を進言する孝平。
瑛里華もまた頷き、玄関のドアを開ける直前、振り返る。
「それもそうね孝平。週明けの生徒会、一緒に頑張りましょう」
「ああ、用事が無ければ」
「用事があっても、来なさい。副生徒会長からの命令よ」
「了解、了解」
「了解は一回でよろしい。じゃあね孝平、おやすみなさい」
「ああ、お休み瑛里華」
ふっと笑みを返す瑛里華の後姿を垣間見て、遅かれ孝平はある点に気づく。
「…………あいつ、俺のこと孝平って言ったか?」
「で、誰なの。いつまで人の背中を眺めているのは」
全ての景色が寝静まった学院の廊下の中、茜が振り返らずに誰何の声を放つ。
「まったく、気づいているだろうに」
意外なほど、即座に反応が起こり、廊下の曲がり角から二人連れの男子の姿が闇の中から浮かび上がった。音信不通となっていた、妙に上機嫌な伊織と妙に不機嫌な征一郎である。
彼らを眺めつつ、茜は自慢げに腕組みをして豪胆する。
「当たり前でしょう、幽霊となって早数年。それなりのことは可能になったしね」
「それでどうだった、三人は? 目に張るものがあったか」
だが聞く耳を持たない様子で、伊織は先ほど家路についた三人を訊ねる。
「ええ、合格。なかなか面白そうな人材でこの先楽しみ」
話を逸らされたのに嫌な顔を見せず、茜は珍しく笑みを浮かべた。
次いで、白と抱き合った感触を思い出したように、両手を組んでは身をよじり始める。心なしか今の心情を描くように、音も無く宙を浮き始めた。
「特に白ちゃんは可愛かったな〜。ああもう、あの子が妹ならもっと、もっと、おもいっっっきり、抱きしめてあげたいわ! ああ、あの感触、あの悲鳴、あの恥しい顔、そそっちゃう♪」
「…………」
「わわわっ、ちょっと待った! さすがにあなたに射られると消滅しちゃうじゃない!!」
徐に背負っていた和弓を構え、矢を弦に引っ掛けては射る体制を整える征一郎に、茜が慌てて周囲に溶け込むように消え去る。だが、彼の鷹の目のごとき鋭き眼光は、未だ消えていない。
「こら征、話が逸れているだろう」
「済まん、伊織。昔からこいつとはそりが合わなくてな」
「分からないでもないが、彼女は白が気に入っているから、あの世に連れ込もうな度という変な事はしない。そうだろう茜?」
「当たり前でしょう。あんな虫けらどもと違って、あの子は本心から私の事を知ろうと思い、そして私のために怒った。もちろん、瑛里華と孝平も含めてね」
再び二人の前に顕現すると途端に先ほどの白の身体に融合しそうなほど、べったり甘えていた茜の表情がなりを潜める……否、完全に消滅していた。同調するように周囲の空気が只ならぬ妖気に晒されたのか、悲鳴をあげる様に空間が軋み、窓ガラスがこみ上げてくる憤怒を示すように小刻みに振動していく。
「未だに人間嫌いなのは、相変わらずか」
「はっ。死んでもなお、人を貶し続けるようなゴキブリ連中をどうして好きにならないといけないのよ」
伊織の言葉に、この世に現存する人間など路傍の石ころですらない蔑視と口調で、茜はき捨てる。
次いで、苛立ちを隠しきれずに茜は、髪の毛をがしがしと掻き毟る。だが、
「とは言っても一応契約をしたのだから、ちゃんと守護者としての役目はしておくから安心して。これでもあの子達が来てからは結構、楽しんでいるし」
先ほどの嫌悪感丸出しの感情は失せ、元の様子に戻った茜はくすっと笑う。
「後、これ以上、怪談話はこれっきりにしてくれ、PTAとかもいろいろうるさくなってきたしな」
「分かってる、分かってるって。あの子達にも言ったように、今夜で最後だから安心して」
ぷーと膨れっ面で、伊織の案を茜は許諾しつつ、「あっ」と思い出す顔を浮かべる。
言うべきか、言わざるべきか問答し、やがて彼女は忠告をし始めた。
「それからそう、幽霊のしきたりとかで詳細までは語れないけれど」
言葉の裏に秘められた深刻さに、二人の表情が引き締まる。
「この先、あの子達にはいろいろと難題が待っているみたいだから、守ってあげて。お願い、伊織、征一郎」
憂いを込められた嘆願に、数年前の先輩である女性を前にして、二人は力強く頷いた。
……などという件があってから、早くも二週間も経過していた。
あれからすぐに学院内で噂されている件についてはは事実無根であり、幽霊など実在しないと新聞部が発行する新聞にて瑛里華が公式発表した結果、今ではもはや過去の話として忘れ去られようとしていた。
もっとも、その後も何度か夜の校舎へと足を赴いた者がいた小耳に挟んだが、惨憺たる結果を目の当たりにしているだろうという生徒会一同の見解により、注意勧告など一切していない。
だが、ここに今から孝平が真実を確認しようとしていた。
「こんな所に、通路があるなんて知らなかった」
あの夜、帰り際に“彼女”から耳元で新校舎が増築された際に、出来てしまった抜け穴のような部分の出入り口を知らされた孝平は、現在では実験室となっている一室の天井からあるブツを見て欲しいと、その通りにしていた。
「にしても、けほけほ」
中に充満していた煙を思わず吸い込み、咳する孝平。
広さはおよそ一メートルほどで、手と膝を立てて歩かないといけないほど狭さによる閉塞感と、暗闇で身の上から圧迫するような感覚を植えつけさせられる。
「よっこらしょっと」
慣れない手取り、足取りで這い始める孝平。しきりに通路の天井に頭をぶつける。
「くおっ、もう少し拡張できなかったのか、ここは」
意味も無く、当時の業者の悪態をつく孝平。
頭部に無数のタンコブが形成しそうになる直後、通路の途中で何かを発見した。
「もしかして、これか……」
数年間手付かずで放置された結果、茶色に色あせた封筒を手にする。
孝平は手にしていた懐中電灯を床に置き、封を切った。
「さてさて、どんな話なんだか……」
ただ読んで、とだけしか知らない孝平は胡坐をかき、心構えもなく率直に遺書を読み漁り、もう一度気を取り直して、ゆっくり朗読し始めた。
――私は好きでこの世に生をうけたわけじゃない。
――自分から頼んで生まれてきたわけじゃない。
――あれが勝手に人を生ませただけなのに。
――誰がこんな色の無い世界へと追いやったのだろうか。
――意味も無く蔑み、死ねなどと罵倒するこんな世界に。
――下らない、この世など全て下らない。
――私には何も無い、成し遂げる理想や生きる理由さえも無い。
――何もかも空っぽなのに、あれらは良い子などと喜んでいる。
――あれらの娘が目の前で、どんな気持ちを抱いているか知らずに。
――可哀想な人たち。
――私は憎む。この世に存在する全ての物を。
――父も母も姉や弟も、クラスメイトも、見知らぬ誰かも何もかも。
――そう思う心と一緒に、全てが消し去ればいいのに。
――こんな牢獄だけの世界から、何もかも消し去ればいいのに。
――ねえ。私は、なに?
「…………」
遺言書にしては誰宛ではなく、詩にしてはあまりにも暗鬱すぎる手紙。
自分を呪い、両親を呪い、世界を呪い、最後まで絶望のまま絶命した彼女。
その無念が今もなお継続しているのだろう。でなければ、現在まで思念が残留できないはずがない。とはいえ紙の劣化状態からして、相当の年月が経過していたので、今となっては何事が起きたかは定かではないし、調査しようが無い。
だが、半比例するように胸が締め付けられるほどの共鳴感を覚えるのだろうか。
孝平は思案し、やがて一つの答えを導く。
「彼女は、俺と同じだったのか」
ぽつりと孝平は呟き、遅く実感が胸の奥から湧き上がってきた。
……そう。彼女は、茜はかつての自分と少しだけ似ていることに。
本心を隠し、自分の心すら理解できず、ただ今だけを過ごしていた点が。
『孝平さん、少し宜しいでしょうか?』
『ん、どうかしたのか茜。というか、言葉遣いがおかしいぞ』
『それは置いておいて、実は………に隠している手紙を読んで欲しいの』
『別にいいが、どうしてそんな物を』
『見たら分かります。後、孝平さん。わたしと同じような道を歩かないで』
『?』
あの時の慈愛に満ちた茜の儚い笑みの裏に隠された苦悩を、今の今まで知らなかった孝平は、
「馬鹿野郎」
自然と唇から罵倒の念が零れた。自分自身でもなく、茜でもなく、泣き続けていた女の子を見て見ぬ振りをしていた人たちに対して。押し留められない憤りがこみ上げてくる。
下手をすれば第二の茜に自分がなっていたかもしれないが、周囲には瑛里華や伊織といった、理解しようと本心のまま接しようとしてくれた人たちがいた。だからこそ今の孝平がいる。恵まれ過ぎると誇張しても過言では無い。
しかし、当時の彼女にはそんな人が存在しなかった。何も無かったのだ。
そこでふと、もし茜がクラスメイトになっていたらと、考えてみる。
――ひょっとしたら似たもの同士、嫌悪しあっていたかもしれない。
――似たもの同士、気があって友達になれたかもしれない。
――もしくは、恋人同士になっていたのかもしれない。
――はたまた生徒会の一員となって、一緒に働いていたかもしれない。
多種多様の空想がひっきりなしに脳内から浮かび上がってきて、
…………古惚けた手紙の上に、一点の雫が落ちた。

ぺーじとっぷへ
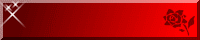
SSぺーじ入り口へ。

さやかFCへ。

とっぷぺーじへ。



