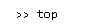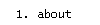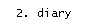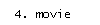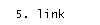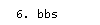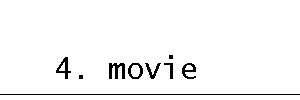 |
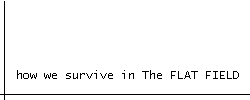 |
||
|
||||
|
||||
 |

「ひかりのまち」
どうにもこうにも、映画館であんなに泣いてしまったのは本当に久しぶりのことだ。
切なくて美しい世界に住む、他人からみたらショボイ、でも自分にとっては 抜き差しならないもやもやを抱えてしまった人々ばかり登場する。
伝言ダイヤルにいそしむナディア、ナディアの姉はシングルマザーで自由な恋愛を楽しむデビー、 夫との距離を感じている臨月の妹モリー。そしてこの三姉妹の両親は セックスレスになって久しいし、デビーの元夫ダンは息子のジャックを愛しているけれど 軽くていかにもなダメ男。そしてジャックは両親に愛されていることは知っていても いつもどこかに寂しい表情を見せる。
この映画にはドラマティックな場面はなにもない。ごく普通の人々のごく普通の 生活(不幸ってわけじゃないけど、べつに満たされてるってわけじゃない)の中の 4日間が切り取られているだけ。
私の中の足りないモノは一体何なのだろう。側にいてくれる人?かまってくれるパパとママ? 夫との距離?夫婦の絆?
足りないモノを必死に埋めようとしても全然埋まらないし、却って穴を広げちゃったり、 広げられちゃったり。
それでも彼らは生きていくし、街のひかりは彼らを温かく包み込む。責めもせず、癒しもせず。
この映画をみて思ったことは、人って結局最後まで独りだということ。生まれついた 時から孤独は背負わされていると言うこと。そこから逃げることはできないし、 というか逃げるなんてお門違いだし、どうにか気合入れて生きていくしかないん だな、というのを改めて気付かされた、というか。
ひかりの中にいる人皆がショボイもやもやを持っていて、なにか足りない気がしていて、 切なくて、孤独を感じていて、それでもどうにか生きていくんだよっていうメッセージは ありふれたものかもしれないけれど、私の中に強く強く響いてしまって、どうしようも なくなってしまったんです。
登場人物が立った地点と私の立っている地点が見事に重なってしまったというか、 こんな身近な場所に映画がきてしまったというか、そういう体験が初めてといって いいくらいなので、なんだかとまどってしまったんだろうなあ。
ほんのちょっとの希望が託されたラストシーン。この後に皆を待っていること。
それは足りないモノを埋められる日、だろうか。それともまた同じような 日々なのだろうか。