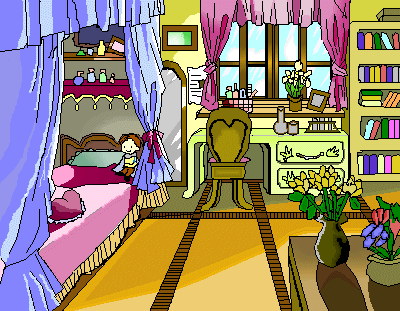
こんにちは!
ぼく、ピコっていいます。生まれて間もない黒妖精です。
ぼくたち妖精族は、人間の仕事のお手伝いをして暮らしを立てています。今日、ぼくは生まれて初めて長老様に呼ばれ、ザールブルグという町に、人間のお手伝いをしに行くように言われました。
初めてのお仕事です。わくわくします。自然に足が軽やかになります。
ぼくには大きな夢があります。大勢の人間のお仕事を手伝って、たくさん修行をして、いつか憧れの虹妖精になることです。
今日は、その第一歩。ぼくにとって、記念すべき日です。
「よ〜し、やるぞ! ・・・あっ!」
勢いあまって、川に落ちちゃいました。
「ここが、ぼくの働く場所・・・」
すごく大きな建物です。『あかでみい』っていうらしいです。ぼくの雇い主は、ここで錬金術の勉強をしている学生だそうです。
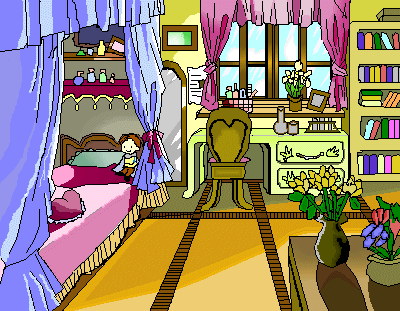 |
| <Illustration by あきこ様> |
お部屋に行ってみました。高そうなものがたくさん置いてありますが、きちんと片付いています。雇い主の姿は見えません。
「留守なのかなあ」
秋の午後の日差しが、大きな窓から差し込んで、絨毯の上に日だまりを作っています。ふかふかした絨毯の上に座りこんで、ひなたぼっこを始めると、ついうとうとしてしまいました。
「ちょっと! 何やってるのよ、あなた!」
いきなり、とんがった声が頭の上から降ってきて、心臓が止りそうになりました。見上げると、ピンクのマントを着て錬金術師の格好をしたおねえさんが、緑色の大きな目でにらんでいます。
「あ、あの、はじめまして・・・ぼく、妖精の・・・」
「わかってるわよ、あたしが雇ったんだから。でもね、ひなたぼっこさせておくためにお金を払っているわけではなくてよ。さあ、すぐに採取に出かけなさい。行く先はヘウレンの森よ」
「ええっ・・・」
「何よ。なにか文句でもあるの?」
「・・・いえ、行ってきます」
あわてて材料入れのかごをつかむと、転がるように出口に向かいます。追い打ちをかけるように、おねえさんの声が追いかけてきます。
「いいこと、あたしが欲しいのは風乗り鳥の羽なんですからね。竹とか、ヤドクタケとか、つまらない材料ばかり取って来てはだめよ。わかっているわね!」
息が切れるまで走って、町の外の草むらでようやく一息つきました。しばらくぼんやりしていると、なぜか涙がこみ上げてきました。
(ちがう・・・何かちがう・・・)
森を出る時に思い描いていたのは、きちんと仕事をして、雇い主に喜ばれる自分の姿でした。それなのに、現実は・・・
(いきなりあんな言い方されるなんて・・・ぼく、何か悪いことしたのかな?)
「森へ、森へ帰りたい・・・」
でも、妖精族には掟があります。お金をもらっている以上、雇い主がいいと言わない限り、妖精の森へ帰ることはできないのです。
ぼくはとぼとぼと、ヘウレンの森に向かいました。
「どうしよう・・・」
ヘウレンの森は、恐いところです。コウモリがぼくの頭すれすれに飛んで来たり、ヘビの抜け殻だと思って拾おうとすると中身が入っていたり。吸血鬼が出るっていう噂もあります。
早く仕事を済ませて町へ帰りたい。でも、ここへ来て10日も経つのに、まだ帰れません。なぜって、肝心のものが見つからないんです。風乗り鳥の羽が・・・。
出てくる時の、雇い主のおねえさんの言葉が、耳にこびりついて離れません。
(いいこと、あたしが欲しいのは風乗り鳥の羽なんですからね・・・)
よく考えると、ぼくは風乗り鳥の羽なんて、見たことがないんです。どんな色と形をしているのか、森のどこを探せば見つかるのかもわかりません。ちゃんと聞いてから出てくれば良かったと思っても、もう後の祭りです。
「どうしよう・・・」
だんだん日が西に傾き、冷たい風が吹いてきます。今夜も暗い森で一人ぼっちで野宿するのかと思うと、心細くて涙が出てきました。
その時、すぐそばの草むらがザワザワと動き、黒い影がぬっと現れました。
「ひゃあ!」
腰が抜け、かごをひっくり返してしまいました。せっかく集めた材料が、地面に散らばります。逃げようとしても足が言うことを聞いてくれません。
(怪物だ! もうだめだあ)
「あら、妖精さんじゃない。こんにちは」
「へ!?」
「あ、脅かしちゃった? ごめんね」
怪物だと思ったのは、人間でした。風変わりな帽子に、オレンジ色のマント。錬金術師のいでたちをしたおねえさんです。でも、ぼくの雇い主とは違って、ひとなつっこそうな目で微笑みかけています。
ぼくの顔を見たおねえさんが、ふと眉をひそめました。
「どうしたの? 泣いてるの?」
「じ、実は、頼まれたものがあるんですけど、どうしても見つからないんです・・・」
ぼくの話を聞くと、おねえさんはちょっと首をかしげて、(どうしようかな)と考えこんだように見えました。でも、すぐににっこり笑って、
「いいわ。わたしのを分けてあげる。風乗り鳥の羽でしょ。今日はついていて、10個も手に入ったのよ。4つもあればいい?」
「え・・・そんなに?」
「困った時はお互い様よ。それじゃ、頑張ってね」
「どうもありがとう・・・」
また涙が止らなくなりました。でも、さっきとは違う涙でした。
森で出会ったおねえさんのおかげで、ぼくはなんとか最初の仕事をこなすことができました。
帰ると休む間もなく、険しいヴィラント山や遠い東の台地に行かされました。川に落ちたり、怪物に追いかけられたりしているうちに、ぼくは黒妖精から茶妖精、赤妖精へと成長しました。でも、一人前と言われる緑妖精になるまでには、まだまだ長い修行が必要ですし、目標の虹妖精になれるのは、気が遠くなるくらい先のことです。
仕事にはなんとか慣れましたが、やっぱり雇い主のおねえさんは苦手です。決して悪い人ではありません。でも、ものの言い方がきついのと、人使い、じゃない妖精使いが荒いのです。最初に出会った時のショックが残っているのか、あの高飛車な言い方で命令されると、頭がしびれたようになって、ちゃんとした返事ができなくなってしまうのです。
そんなある日・・・
ぼくは、材料がいっぱいになった重いかごを背負って、エルフィン洞窟から部屋に戻ってきました。
「ただいま」
ふと作業台の方を見ると、見たことのない後ろ姿が目に入りました。
(新しい妖精を雇ったのかな?)
初めはそう思いましたが、どうもぼくたちの仲間とは違うようです。背は、妖精族よりも頭ひとつ分大きくて、がっちりした体つきをしています。からだ全体が白っぽく、服を着ていないように見えます。そして、ぼくとは比べ物にならない素早い動きで、乳鉢やろ過器を使ってなにやら調合しています。
「あら、帰ってたの」
いつのまにか、後ろに雇い主のおねえさんが立っていて、また息が止りそうになりました。おねえさんは、作業台の方を見ながら、得意そうに続けます。
「どう、あたしの調合したホムンクルスは? やっぱりヘルミーナ先生のいった通りだわ。鈍くさい妖精なんかより、100倍は役に立つわね。それに、お金もかからないし」
そして、おねえさんはぼくをじっと見下ろしました。
「だ・か・ら、あなたはもう用なしなの。帰っていいわよ」
「え?」
「聞こえなかったの? あなたは要らなくなったのよ。さあ、調合の邪魔よ。早く森に帰りなさい」
何がどうなったかもよくわからないまま、外に押し出されたぼくの後ろで、ドアがバタンと閉まりました。
(が、頑張ったのに・・・)
崖から突き落とされたような気持で、ぼくは妖精の森に帰っていきました。
森へ帰ったぼくは、何をする気も起きず、毎日をむだに過ごしていました。たくさんの人の役に立って、いつか虹妖精になるという夢も、すっかりしぼんでしまっていたのです。
(どうせぼくなんか・・・鈍くさいだめな妖精なんだ)
草むらの隅で丸まって、いつも涙を流していました。
今日も泣き疲れて、シャリオ山羊をつないである柵の上にちょこんと座り、草を食んでいる山羊をぼんやりと眺めていました。
すると、後ろの方から長老様の声が近づいてきました。別の足音も聞こえます。
「・・・あいにくとな、今は青妖精も緑妖精も出払っておっての。こんなのしか残っておらんのじゃよ」
「いえ、誰でもいいです。急な仕事が入ってしまって、とにかく調合を手伝ってもらえれば・・・」
(何の話をしているんだろう・・・ま、どうせぼくには関係ないや)
「こりゃ、ピコ! 何をぼんやりしておる! 仕事じゃぞ、いつまでもうじうじといじけておるでない! 早く町へ行く支度をするのじゃ!」
長老様の怒鳴り声も、遠い世界のもののように聞こえます。
(うるさいなあ。仕事なんか、ぼくにはできないよ・・・)
首を振って、断ろうと振り向くと、
「あら、あなた、いつかヘウレンの森で・・・。元気だった?」
長老様と一緒にいたのは、ぼくの初めてのお仕事の時、ヘウレンの森で風乗り鳥の羽を分けてくれたおねえさんだったのです。それにしても、人間は、ぼくたち妖精の区別がつかないはずなのに、ぼくのことを覚えていてくれたなんて・・・。
「お願いよ。2週間でロウを80も作らなければならなくなって、いくらでもお手伝いがほしいの」
なにか、ぼくの胸の中に暖かいものが湧いてきたような気がしました。
「ぼ、ぼくでもいいんですか」
「もちろんよ。さあ、早く行きましょう」
おねえさん(エリーさんといいます)の工房についたぼくは、他の6人の妖精と一緒に一生懸命はたらき、なんとか80個のロウを作ることができました。喜んだエリーさんは、教会からもらってきたチーズケーキをぼくたちにも分けてくれました。
ぼくはそのままエリーさんの工房ではたらくことになりました。ぼくが調合していると、時々エリーさんが心配そうに見守っていることがあります。思わず緊張して、手がすべってアイテムを割ってしまうことがありますが、エリーさんは苦笑いしながら許してくれます。
1年が過ぎました。
すこしずついろいろな調合を覚え、ぼくは黄妖精まで成長しました。一人前と言われる緑妖精まで、あと一歩です。
ある朝。
「うんしょ、うんしょ」
ぼくは魔法の草をすりつぶして、緑の中和剤を作っていました。
その時、工房の隅で、青妖精のプニプニがエリーさんに話しかけている声が聞こえてきました。
「ねえ、おねえさん」
「ん? なあに」
「今日の夜ね、ぼくの友達がここに遊びに来たいって言うんだ。呼んでもいいかなあ」
「え、いいわよ。今はちょうど急ぎの仕事も入ってないし」
「ホント! やったあ! じゃ、さっそく呼んでくるね」
エリーさんは、飛び出していくプニプニを、にこにこして見送っています。
そして、夕方。
工房に、小さなノックの音が聞こえました。
「は〜い、開いてま〜す」
エリーさんが明るく応えます。ドアが開き、ぼくの仲間たちが入ってきました。
「こんにちはー」
「こんにちはー」
「こんにちはー」
「こんにちはー」
「こんにちはー」
「こんにちはー」
「こんにちはー」
・・・・・・
ドアの脇で出迎えるエリーさんの顔が、だんだん引きつって来ました。結局プニプニは、黒妖精から紺妖精まで、合わせて20人もの妖精を呼んできたのです。
1時間もしないうちに、大騒ぎが始まりました。踊る妖精、歌う妖精、転がる妖精、じゃれる妖精、飛びはねる妖精・・・本棚から参考書が落ち、調合途中の材料が入った乳鉢がひっくり返り、たちまち工房は、3ヶ月も掃除していないようなありさまになってしまいました。
ぼくがピーポーと二人でソファのクッションでどこまで飛び上がれるか競っていた時、ふと部屋の隅で突っ立っているエリーさんに気付きました。目がうつろです。半べそのような表情を浮かべています。
と、エリーさんはマントをひるがえすと工房から出て行ってしまいました。
ぼくたち妖精族のパーティは、いったん始まると、一昼夜は続きます。大勢で、食べて、しゃべって、歌って、踊って、何もかも忘れて時を過ごすのです。
(エリーさん、そのことを知らなかったのかな・・・)
ぼくはエリーさんが気の毒になりました。
(でもまあ、明日になれば終わるんだし、いいかな。ごめんね、おねえさん)
そっと心の中でつぶやき、騒ぎに仲間入りしました。
しばらくすると、ドアが開いて、二人の妖精が入ってきました。
「おまたせ〜」
「持ってきたよ」
パテットとピッケの兄弟です。食べ物や飲み物ではちきれそうなかごを引きずっています。
「さあ、シャリオミルクに、チーズに、カステラ、ヨーグルリンク・・・それから、これも持ってきたよ」
「やったあ!」
歓声が上がります。
(え、それって・・・)
ぼくはびっくりすると同時に、ちょっと不安になりました。
パテットがかごの底から取り出したのは、シャリオ酒のびんだったのです。
シャリオ酒は、人間には知られていない、妖精のお酒です。シャリオミルクにお酒の木の樹液を入れて発酵させ、1年ほど寝かせます。そして、最後にぷにぷに玉をひとかけらだけ入れるのです。
こうして作ったシャリオ酒を飲むと、妖精はわれを忘れて騒ぎ続けます。妖精のパーティを盛り上げるには絶好ですが、ひとつだけ困ったことがあるのです。これを一口でも飲むと、2週間は酔いが覚めません。
ということは、工房での妖精パーティは、普通なら1晩で終わるはずが、2週間も続くことになるのです。その間、工房で寝ることもできなければ、調合することもできません。
(それじゃ、おねえさんが困っちゃうよ)
そう思って、ぼくはパテットを止めようとしました。でも、その前に、びんは手から手へ回され、みんなが口をつけてしまいました。
騒ぎはますます大きくなっています。
(どうしよう・・・。とにかく、エリーさんに知らせなきゃ)
ぼくはこっそり工房を抜け出しました。
「おねえさん、どこに行ったんだろう・・・」
ザールブルグの石畳の道を、ぼくはパタパタと走り続けました。夜が更けて、明りがついている家もまばらです。
中央広場に出て立ち止まり、あたりを見回します。正面には王様が住んでいるお城があります。右には教会が、左の方には町の人が「妖精の木」と呼んでいる大木があります。
ふと、妖精の木がぼくを呼んだような気がしました。
近づいていくと、太い木の幹にもたれかかるように座っている人影が見えました。首から下をマントで被って、静かな寝息を立てています。なんだか、起こすのが気の毒みたいです。
(でも、起こして話を聞いてもらわなきゃ)
ぼくはごつごつした妖精の木の幹をよじ登って、エリーさんの耳元で叫びました。
「おねえさん、起きて!」
「うぁ・・・?」
エリーさんがうっすらと目を開けました。
「あら、妖精さん・・・。ええとね・・・あなたは、ヘーベル湖に、採取に・・・」
寝ぼけています。
「おねえさん、しっかりしてください。たいへんなんです!」
「だいじょうぶ・・・。バッチリ・・・すぐにできるから・・・」
まだ寝ぼけています。
仕方がありません。ぼくは、工房から持ち出してきたガッシュの木炭のかけらをつぶして、エリーさんの顔にふりかけました。
「・・・ん? やだ、なに、この臭い!」
エリーさんが飛び起きました。はずみで、ぼくは地面に転げ落ちてしまいました。
「ピコじゃない。何やってるの?」
草の上に丸く転がったぼくを、エリーさんが不思議そうにのぞきこんでいます。ぼくはあわてて起き上がると、シャリオ酒のことを説明しました。
「ええっ、2週間も!? そんなあ」
エリーさんの顔が青ざめています。
「ごめんなさい。止めようとしたんですけど・・・」
「ううん、あなたは悪くないよ。それより、何かないの? 酔いを覚ます方法。そうだ、酔い止めの薬があるじゃない。あれを飲ませれば・・・」
「だめですよ。人間の薬は、妖精には効かないんです」
「そっか・・・。じゃあ、つねるとか、ひっぱたくとか・・・わたしの父さんが酔っ払った時に、よく母さんが父さんのおしりをつねって起こしてたけれど」
「それもだめです。痛ければ、その時だけわれに返るけど、痛くなくなれば、すぐに元に・・・あっ!」
頭の中で、ひらめくものがありました。もしかしたら・・・
「おねえさん!」
エリーさんに、ぼくの考えを話しました。
「ええっ? でも、そんなことして大丈夫? ・・・それに、本当に作れるの? そんなの今まで聞いたことないよ」
「でも、やらなきゃならないんです」
ぼくの心に、不思議な自信がわいてきていました。エリーさんがうなずきます。
「そうか・・・そうだね」
「じゃ、ぼく、必要なものを取ってきます」
「気を付けてね」
1時間後。
材料と道具をつめこんだかごを背負って、妖精の木のところに戻ると、エリーさんは火をおこして待っていてくれました。ぼくを見て、目を丸くします。
「どうしたの、その格好」
「え? ああ、これですか。パーティでは普通ですよ」
帽子は半分ひきちぎられ、黄色い服はミルクやパイのかけらやジャムのしみでまだらになっています。工房の中を、戸棚までたどりついて戻るだけで、こんなになってしまったのです。
「すごいのね、妖精さんのパーティって」
エリーさんが変な感心をしています。
「そんなことより、始めましょう」
ぼくはかごから材料と道具を出して、地面に並べはじめました。
シャリオミルク、ハチの巣、竹、お酒のもと、山羊の角、各種の中和剤・・・。乳鉢に、遠心分離器、トンカチにやっとこ・・・。
月明かりの下、調合作業が始まりました。
どのくらいの時間がたったのか・・・
「あ、できた、できた、できましたよ」
「やったね!」
びんの中には、乳色をした液体が詰まっています。顔を近づけると、ぷんとお酒の香りがします。
「あとは、これを飲ませるだけね」
「はい」
「行きましょう」
エリーさんは、ぼくを肩に乗せて工房の外まで連れていってくれました。
「じゃ、わたしはここで待ってるから」
エリーさんと別れ、びんを抱えて工房のドアを開けます。
「みんな、新しいシャリオ酒を持ってきたよ!」
妖精の頭がいっせいにこっちを向き、歓声がわきおこります。
「さあ、飲んで飲んで」
ぼくは念には念を入れて、ひとりずつ確かめながら飲ませていきました。間違えて自分が飲んでしまわないようにしながら・・・。
しばらく様子をみました。相変わらず、踊ったり歌ったりの大騒ぎが続いています。
(うまくいかなかったのかな・・・)
急に不安になってきました。
と、その時・・・。
「あいたたた・・・」
プニプニが、おなかを押えてうずくまりました。それを合図にしたかのように、
「痛っ!」
「痛いよう」
「いててて」
「助けて」
と、次々に悲鳴が上がりはじめました。みんな、おなかを押えています。シャリオ酒の酔いは、すっかり覚めているようです。
ぼくは手を叩いて、みんなに言いました。
「さあ、パーティはそろそろ終わりですよ。外に出れば、おねえさんがお薬をくれますからね」
「え」
「お薬」
「そうだ」
「ぼくたち」
「もう帰らなきゃ」
みんな、おなかの痛みに顔をしかめながら、よろよろと出口に向かいます。ドアの外では、特効薬の小びんを持ったエリーさんが、ひとり一さじずつ、薬を飲ませてあげています。もちろん、この特効薬も妖精に効くように特別のブレンドで作られています。
あっという間に、工房はからっぽになりました。ごみの山だけがあちこちに残っています。
外に出ると、エリーさんがひとりで舗道に腰を下ろしていました。東の空が赤く染まっています。もう夜明けは近いようです。
ぼくに気付いて、疲れた顔に微笑みが浮かびます。
「ホントに効いたわね、あの薬。でも、どうやって考えついたの? お酒に妖精パンを混ぜるなんて」
「小さい頃、妖精パンを食べておなかをこわして、すごく痛い思いをしたことがあるんです。全然痛みが止らなくて・・・。だから、あれくらい痛ければ、酔いを覚ませるかなって」
「ふふ・・・すごいわ、ピコって。いつか、虹妖精になりたいって言ってたじゃない。きっとなれるよ」
「え、そんな・・・」
「だって、これってピコのオリジナル調合だもの。名前をつけて売り出したらどう?」
「・・・」
その時、朝の最初の光が射してきました。
その光を浴びて、ぼくの服が一瞬、虹色に輝いて見えたのは気のせいだったのでしょうか。
<おわり>
<付録>
| −<妖精の酔い止め薬・レシピ>− | ||
| シャリオミルク | 3.0 | |
| お酒のもと | 3.0 | |
| 妖精パン | 1.0 | |
| 遠心分離器・乳鉢を使用 | ||
<○にのあとがき>
ぼくが、初めて書いた「エリアト」小説です。
磯貝さんの「Alchemistの玉子」に投稿して、何人かの人に「面白い」「ピコがかわいい!」と言ってもらったおかげで、これまでずっと書き続けているわけです。
また、他の小説の中で、本筋とあまり関係なく出てくる「ピコをいびるアイゼル」のお約束シーンも、ここから始まりました。
アイゼルファンの皆様、テラフラムなど投げないでくださいね。
作中の「アイゼルの部屋」のイラストは、あきこさんからいただいたものを、ご本人の許可を得て使わせていただきました。
ところで、ぼくは「エリアト」「マリアト」のキャラクターの中で、いちばんピコに似ていると言われています。
別に、いつもこき使われているわけではないんですけど。