庡梫彅尦偼壓婰
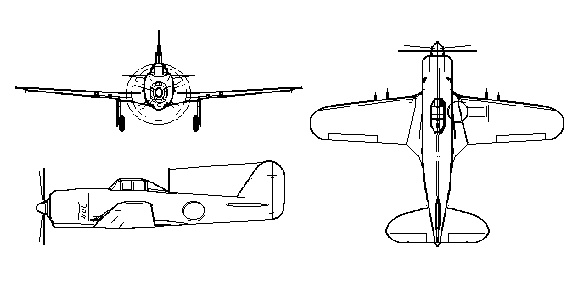
慡暆丂11.99倣丄慡挿丂9.35倣丄 憤廳検丂3800噑丂嵟崅懍搙丂596km/h
丂敪摦婡丂拞搰乽梍21宆乿1990攏椡丂晲憰丂婡廵12.7mm亊係丂忔堳丂1柤
丂丂 悈忋愴摤婡乽嫮晽乿傪嵞愝寁仺乽巼揹乿偙傟傪慡柺揑偵尒捈偟仺乽巼揹夵乿
偲夞傝摴傪偟偨偑奀孯偺婜懸傪偵側偭偰搊応丄悾屗撪奀忋嬻偱僌儔儅儞婡
偵戝懪寕傪梌偊堦桇楇愴偵戙傢傞怴宆婡偺弌尰偲嫲傟傜傟偨偑丄偡偱偵
抶偟偺姶偑丒丒丒尰懚偡傞婡懱偼巐崙埳梊儕僋偵1婡丄枖挷嵏梡偵
暷崙偵帩偪嫀傜傟偨1婡偑僆僴僀僆嬻孯攷暔娰強桳偲側偭偰偄傞
庡梫彅尦偼壓婰
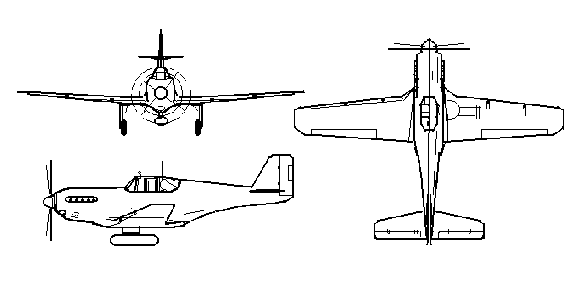
慡暆丂11.30倣丄慡挿丂9.80倣丄 憤廳検丂3780噑
丂 嵟崅懍搙丂708km/h丂晲憰丂婡廵12.7mm亊係丂忔堳丂1柤
僄儞僕儞丂僷僢僇乕僪儅乕儕儞1350/1590攏椡
丂丂 戞擇師悽奅戝愴偵偍偄偰嬻椡愝寁偺憌棳梼偺嵦梡偵傛傝憖廲惈丒慁夞擻椡
懍搙悜晛E峲懕嫍棧偺壗傟偵傕桪傟僶儔儞僗偺偲傟偨僗僢僉儕偟偨婡懱偼
傑偝偟偔嵟桪廏愴摤婡偲偄偆愴摤婡偺柤婡偱偁偭偨
摿偵峲懕椡偼棸墿搰偐傜偺擔杮杮搚嬻廝偵敪婗偝傟傞帠偲側偭偨
弶旘峴偼奐愴1擭慜偱偁偭偨丒丒丒
庡梫彅尦偼壓婰
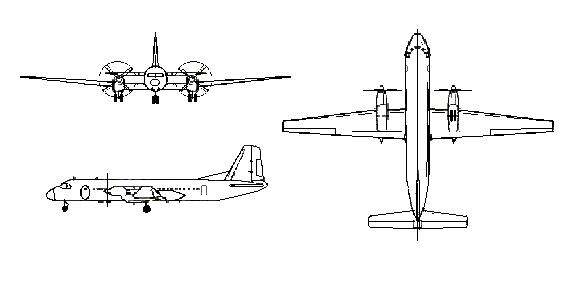
慡暆丂32.00倣丄慡挿丂26.30倣丄慡崅丂8.98m丄 弰峲懍搙丂450km/h
丂 嵗惾悢丂60乣64惾丄嵟戝棧棨廳検丂25.000kg丄峲懕嫍棧丂1200km丄
丂丂 妸憱嫍棧丂乮棧乯1400m乮拝乯1110m丄丂僄儞僕儞丂儘乕儖僗儘僀僗丒僟乕僩MK543-1Q10K
怴悽婭戞堦抏偼弮崙嶻椃媞婡YS-11
枹偩偵桞堦弮崙嶻婥丄搶嫗僆儕儞僺僢僋偺崰搊応偱尰嵼傕拞丒嬤嫍棧
棧搰楬慄偱妶桇偟偰偄傞丄奐敪偑杮摉偵弌棃傞偐摉弶敿怣敿媈偩偭偨
恖乆偵奐敪僠乕儉偼柾宆傪撪憰偐傜壗傑偱尰暔戝偱嶌傝岞奐偟OK傪彑偪庢偭偨
YS-11偺YS偲偼僾儘僕僃僋僩柤乽桝憲婡惢憿丒丒丒乿偺摢暥帤偐傜偲偐
庡梫彅尦偼壓婰
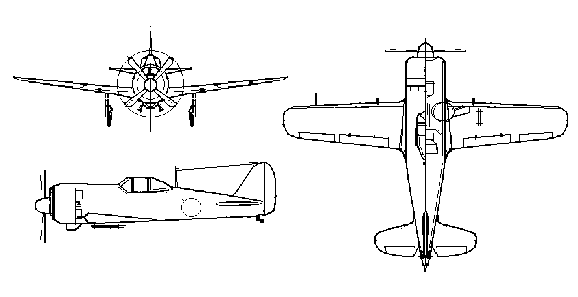
慡暆丂11.30倣丄慡挿丂9.74倣丄憤廳検丂3750噑丄 嵟戝懍搙丂624km/h/6500m
丂 僄儞僕儞丂嬻椻惎宆18婥摏僴-45乽梍乿丂2000攏椡丂忔堳丂侾柤
丂丂 晲憰丂婡娭朇丂20mm亊2丂12.7mm亊2
楇愴丒敼偵師偖憤惗嶻婡俁係俋俋婡丄1944擭巐幃愴摤婡乽幘晽乿偲柦柤偝傟
検嶻懱惂偵擖偭偨偑愴嬊偺埆壔偲偲傕偵廩暘側帒嵽丄曗媼偑偱偒偢
偙偺婡偺擻椡傪敪婗偟偨偲偼巚偊偢廳愴摤婡壔抶傟偑偙偙偵傕丒丒丒
愴屻暷孯偺僥僗僩偱懍搙丄忋徃椡丄塣摦惈丄壩椡丄杊壩杊抏摍
偄偢傟偵傕暥嬪偺偮偗條偺柍偄擔杮偺嵟桪廏愴摤婡偲夵傔偰妋擣偝傟偨
偪側傒偵偙偺婡偺憡庤偼暷孯偺嵟崅寙嶌婡偱僲乕僗傾儊儕僇儞 P-51
乽儅僗僞儞僌乿偱偁偭偨
庡梫彅尦偼壓婰
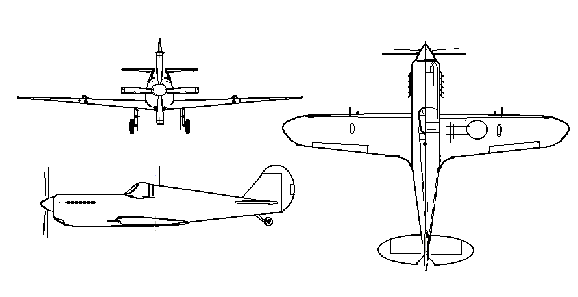
慡暆丂11.16倣丄慡挿丂9.37倣丄憤廳検丂3526噑丄 嵟戝懍搙丂670km/h
丂 僄儞僕儞丂R.R儅乕儕儞63丂1710攏椡丂忔堳丂侾柤
丂丂 晲憰丂婡娭朇丂20mm亊2丂7.7mm亊係
傑偝偵2師戝愴偺柤婡丄僀僊儕僗杮搚杊嬻愴偱塸崙偵彑棙傪傕偨傜偟偨
偙偺婡偺愝寁幰偼R.J.儈僢僠僃儖偱偁偭偨偑丄愝寁屻庒偔偟偰巰嫀偟偨
屻宲幰偵傛傝夵椙偑懕偗傜傟忢偵戞堦慄偱妶桇偟偨丄
悽奅拞偺愴摤婡偺愝寁幰偑偙偺婡傪昗揑偲偟偰奐敪偵偁偨偭偨偲偐
尨宆偺弶旘峴偼1936擭俁寧偱偁傝丄擔杮偱偼97幃愴摤婡抋惗偺崰偱偁傞
偟偐偟昤夋偑儊僢僒乕僔儏儈僢僩偲帡偨傛偆偵側偭偨丒丒丒(-_-);
庡梫彅尦偼壓婰
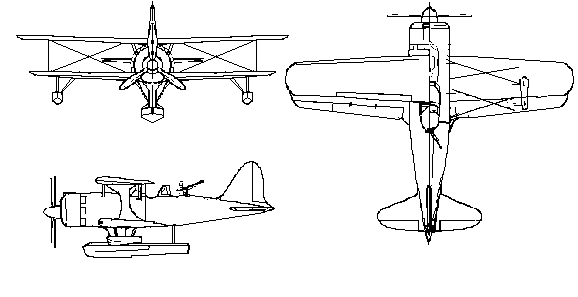
慡暆丂11.00倣丄慡挿丂9.50倣丄憤廳検丂2550噑丄 嵟戝懍搙丂396km/h
丂 僄儞僕儞丂乽抂惎13宆乿丂800攏椡丂忔堳丂2柤
丂丂 晲憰丂婡廵乮屌掕乯丂7.7mm亊2丄婡廵乮慁夞乯丂7.7mm亊侾丂敋抏60噑亊2
擔杮奀孯嵟弶偱嵟屻偺慡嬥懏惢暋梩婡丄婡懱偐傜僼儘乕僩傊偺儔僀儞摍
嬻婥椡妛揑偵姰惉偝傟暋梩婡偺嵟崅摓払揰傪嬌傔偨丄愴娡傗弰梞娡摍偵
搵嵹偟掋嶡旘峴傗娡戉忋嬻偺寎寕梡偩偭偨偑丄娡戉愴偑夁嫀偺愴棯偲側傝
旘峴応偺柍偄懢暯梞偺搰乆偑妶桇偺晳戜偲側偭偨
巕嫙偺崰丄壗屘偐偙偺婡偺僾儔儌傪壗婡傕嶌偭偰忺偭偰偨婰壇偑丒丒丒
摉帪偼侾侽噋偖傜偄偺僾儔儌偩偭偨偑丄惁偔惛岻偵弌棃偰偄偨偲巚偆
壗屘偐夰偐偟偄傕偺偵夛偊偨婥偑偡傞丒丒丒丒(^_^;)
庡梫彅尦偼壓婰
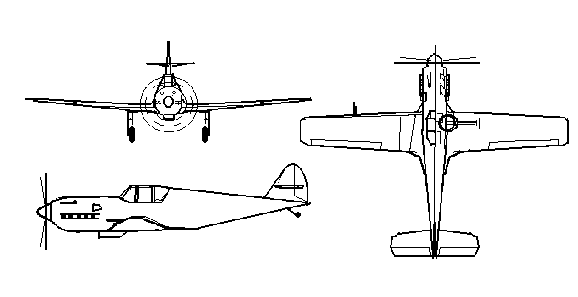
慡暆丂9.92倣丄慡挿丂9.02倣丄憤廳検丂3362噑丄 嵟戝懍搙丂670km/h
丂 僄儞僕儞丂僟僀儉儔乕儀儞僣DB605DCM丂1800攏椡丂忔堳丂1柤
丂丂 晲憰丂婡廵丂13.0mm亊2丄婡娭朇丂30mm亊侾
擇師戝愴拞偺庡椡愴摤婡偺拞偱堦斣屆偄楌巎傪帩偭偰偄傞
晲憰丄峲懕嫍棧摍偵嬯尵傕偁傞偑B宆丄E宆丄F/G宆丄K宆偲夵椙偑廳偹傜傟
忢偵庡椡愴摤婡偺嵗偵偁傝懕偗丄30,000傪挻偡検嶻婡偲側偭偰偄傞
幵偺儚乕僎儞偲嫟偵暔嶌傝偵懳偡傞僪僀僣偺愝寁仌媄弍傪巚傢偣傞
梋択偱偡偑丄巹偑嵟弶偵嶌偭偨儔僕僐儞偑偙偺僗働乕儖儌僨儖偱偁偭偨
柾宆壆偺恖偑弶傔偰偺恖偵偼掅梼偼柍棟偲尵傢傟偨偺偵丒丒丒丒
寢壥偼埬偺掕丄弶僼儔僀僩偱掇僔儍儞丂埲屻偼曗廋偟偰忺傝偵側偭偰偄傞
庡梫彅尦偼壓婰
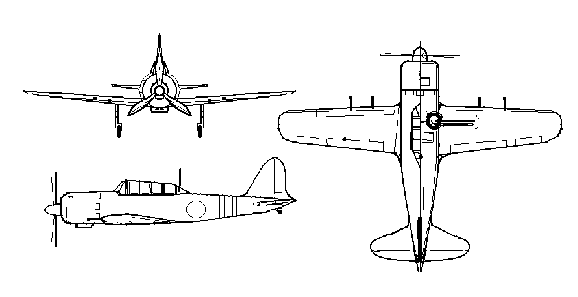
慡暆丂11.00m丄慡挿丂9.12倣丄憤廳検丂2733噑丄 嵟戝懍搙丂565km/h
丂 僄儞僕儞丂乽塰俀侾宆乿丂1100攏椡丂忔堳丂1柤
丂丂 晲憰丂婡廵丂7.7mm亊2丄婡娭朇丂20mm亊2丄敋抏丂60噑亊2
楇愴乮僛儘僼傽僀僞乕乯奆偝傫屼懚抦偺擔杮奀孯晄媭偺柤婡
偙偺婡偵偮偄偰巹偑尵偆傛傝奆偝傫偺曽偑徻偟偄偺偱偼丒丒丒
寉検壔偺捛媦偵傛傝崅懍惈丒奿摤惈偵桪傟丄嫮椡側晲憰壩婍傪憰旛
惗嶻婡悢丂10,425婡偼擔杮偺嵟懡惗嶻婡悢偱偁傞
庡梫彅尦偼壓婰
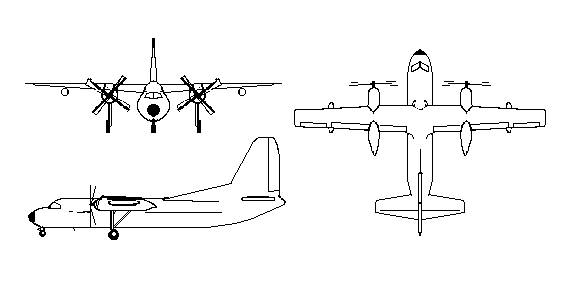
慡暆丂29.01m丄慡挿丂23.52倣丄慡崅丂8.38m丂嵗惾悢丂40乣44
丂 嵟戝棧棨廳検丂17860噑丂弰峲懍搙丂490km/倛丄峲懕嫍棧丂2410km丄
丂丂 僄儞僕儞丂儘乕儖僗儘僀僗丒僟乕僩俆俀俉
僼僅僢僇乕幮惢偺僞乕儃丂僾儘僢僾婡
庡梼偑媞幒偺憢傛傝忋晹偵桳傞偨傔偒傢傔偰挱傔偺椙偄椃媞婡
棧拝棨妸憱嫍棧偑侾侽俆侽m乣侾侾侾侽m偱偁傝儘乕僇儖慄偺
庡椡偲偟偰妶桇偟偨丄悅捈旜梼偵慡擔嬻偺僔儞儃儖儅乕僋偑
偙偺婡偵側偤偐傄偭偨偟偩偭偨傛偆側婰壇偑丒丒丒丒丒丒丒
偨偩僞乕儃僾儘僢僾偺偣偄偐僄儞僕儞壒偑崅偐偭偨傒偨偄
庡梫彅尦偼壓婰
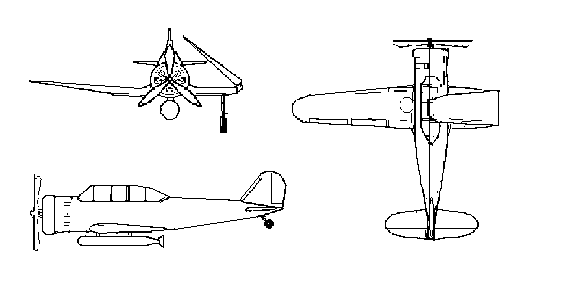
慡暆丂15.52m丄慡挿丂10.30倣丄忔堳丂3柤丂憤廳検丂3700噑
嵟戝懍搙丂350km/倛丂晲憰丂7.7mm婡廵1丄敋抏800噑亊1枖偼60噑亊6
丂丂 僄儞僕儞丂拞搰嬻椻俋婥摏乽岝-13宆丂770hp
娡峌偼崅懍惈擻傪椙偔偡傞堊庡梼柺愊傪偓傝偓傝傑偱棊偲偟偰偁傝
庡梼抐柺偼巺愳塸晇偺愝寁傪嵦梡丄枖弶偺堷偒崬傒媟傗庡梼偼愜忯幃傪
乮娡撪偵廂梕帪偵僄儗儀乕僞乕偑巊梡偝傟偰偄傞堊乯嵦梡偟偨
嵟弶偼僄儞僕儞奐敪偑娫偵崌傢偢摢晹偑偡傫偖傝偟偰偰偍偐偟偐偭偨偑
乽塰乿偵姺嵹偝傟偰偐傜偼乮2崋娡峌埲屻乯偼摑堦偝傟偨婡懱偲側偭偨
堷偒崬傒媟傗愜傝忯傒偼桘埑幃傪嵦偭偨偑壗偣嵟弶偺帠偱埆愴嬯摤偟偨
偙偺奐敪偱偼妛峑傪弌偰3乣5擭偺庒偄媄弍幰払偺怴媄弍傊偺挍愴偲
傾僀僨傾偑帋傒傜傟屻偵幚傪寢傫偩乮嫵孭丟擔乆挍愴丄掹傔傞側乯
庡梫彅尦偼壓婰
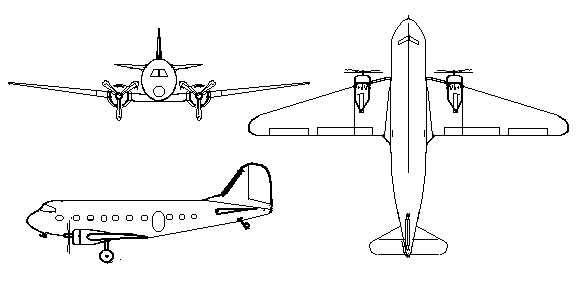
慡暆丂28.96m丄慡挿丂19.65倣丄慡崅丂5.16倣
丂 憤廳検乮俥倳倢倢乯11880噑丄弰峲懍搙丂220km/倛丂峲懕嫍棧丂1740km
僄儞僕儞丂倫仌倵倰-1830-92丄悇椡丂1200hp亊2丄嵟崅崅搙丂7600m
戞擇師悽奅戝愴拞偵孯梡婡偲偟偰搊応丄屻偵椃媞婡偲偟偰妶桇
惗嶻婡悢偼1枩埲忋偱丄崱偱傕梞夋摍偱尒傞偙偲偑偁傞
DC-3偺C偼桝憲婡乮壿暔婡乯偺Carrige偺C
妸憱楬偼1000儊乕僩儖傕偁傟偽棧棨偱偒丄椃媞婡偺応崌忔堳偼30恖
庡梫彅尦偼壓婰
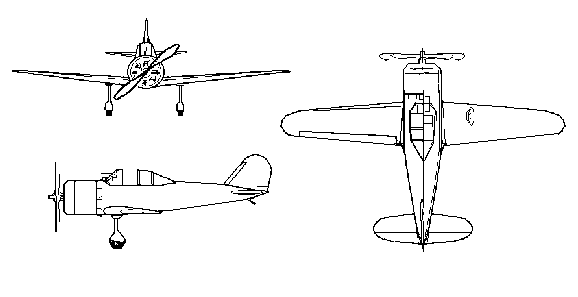
慡暆丂11.30m丄慡挿丂7.53倣丄忔堳丂侾柤丂憤廳検丂1130噑
嵟戝懍搙丂460km/倛丂峲懕嫍棧丂627km丂嵟崅崅搙丂12250m
晲憰丂7.7mm婡廵2乮屌掕乯丂丂僄儞僕儞丂嬻椻俋婥摏拞搱僴乕侾壋丂650hp
97幃乮拞搰僉-27乯偼揙掙偟偨寉検壔偲摨帪偵摉帪偺僴僀僥僋傪摦堳偟
嫼埿揑側奿摤擻椡傪帩偮愴摤婡偲偟偰悽奅巎忋摿昅偝傟傞寉愴摤婡偲偟偰搊応
媟偼惍旛偝傟偰側偄旘峴応傪峫椂偟堷偒崬傒傛傝傕屌掕媟偲偝傟偨
梋傝偵傕奿摤惈偑椙偐偭偨堊丄屻乆偺廳愴摤婡壔乽敼乿偺揥奐偑抶傟偨
尨場偵側偭偨偲傕堗傢傟傞丅嫵孭丒乭桪惃傪曐偮偵偼媄弍奐敪傪懹傞側乭偐
暯惉8擭9寧10擔攷懡榩偱敪尒偝傟偨尰懚偡傞桞堦偺婡懱偼
廋暅偝傟暉壀偺懢搧愻暯榓婰擮岞墍偵曐懚偝傟偰偄傞
俽倫倝倰倝倲丂倧倖丂俽倲倢倧倳倝倱
庡梫彅尦偼壓婰
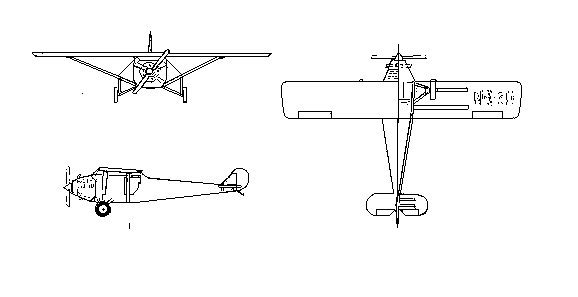
慡暆丂1係.0m丄慡挿丂8倣丄慡崅丂3倣
丂 憤廳検乮俥倳倢倢乯2330噑丂乮俤値倫乯975倠倗丄敪摦婡丂儔僀僩慁晽俰亅俆們丂俀俀俁倐倫
儊乕僇乕丂俼倷倎値峲嬻俠倧乮僒儞棉矁G僑乯
俼倷倎値丂俶倄俹"俽倫倝倰倝倲丂倧倖丂俽倲倢倧倳倝倱乭
1927擭5寧21擔扨撈戝惣梞墶抐旘峴傪惉偟悑偘偨丄僠儍乕儖僘俙丒儕儞僪僶乕僋偺垽婡
俶倄俹偼僯儏僂儓乕僋丒僷儕偺摢暥帤丂僨僓僀儞偼僪僫儖僪儂乕儖偺庤偵傛傞
偙偺旘峴偺惉岟偼旘峴婡偑悽娫偵擣傔傜傟傞偒偭偐偗偲側偭偨
乭梼傛偁傟偑僷儕偺摂偩乭偼偙偺旘峴傪塮夋壔偟偨傕偺
擱椏僞儞僋傪慜曽偵抲偄偨堊丄幚嵺偼慜曽偑尒偊偢
愽朷嬀偐僒僀僪偺憢偱偟偐奜偑傒偊側偐偭偨
捠徧乽愒僩儞儃乿
庡梫彅尦偼壓婰
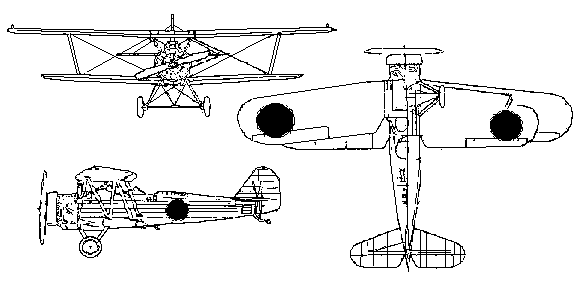
慡暆丂11.0m丄慡挿丂8.05倣丄慡崅丂3.20倣丄庡梼柺愊丂27.70噓丄
帺廳丂1000噑丂搵嵹検丂500倠倗丄敪摦婡丂嬻椻惎宆9婥摏300乣340攏椡丄
幚梡忋徃尷搙丂5700倣丄峲懕嫍棧丂1020倠倣丄忔堳丂2柤
惢嶌強丂墶恵夑岺彵憿暫晹丄愳惣惢嶌強偺嫟摨奐敪
嬨嶰幃偼奀孯峲嬻戉偺楙廗婡偱丄棨孯峲嬻戉偱嵦梡偝傟偨婡庬偼嬨屲幃
暋梩偺楙廗婡偱婡懱偺怓偐傜捠徧乽愒偲傫傏乿屇偽傟偰偄偨,摿挜偲偟偰
僆儗儞僕怓偺婡懱偱憖嶌惈丄埨掕惈偵桪傟偰偄偨丅徍榓俋擭偐傜侾侾擭娫梋傝偺娫偵
俆俇侽侽婡嬤偔憿傜傟偨丄偙偺悢偼楙廗婡偲偟偰偼悽奅嵟懡偱偁傝懠偵椶傪傒側偐偭偨
埨掕惈偵娭偟偰偼憖廲瀰傪偼側偡偲帺慠偲埨掕旘峴偵夞暅偟偨偲傕尵傢傟傞