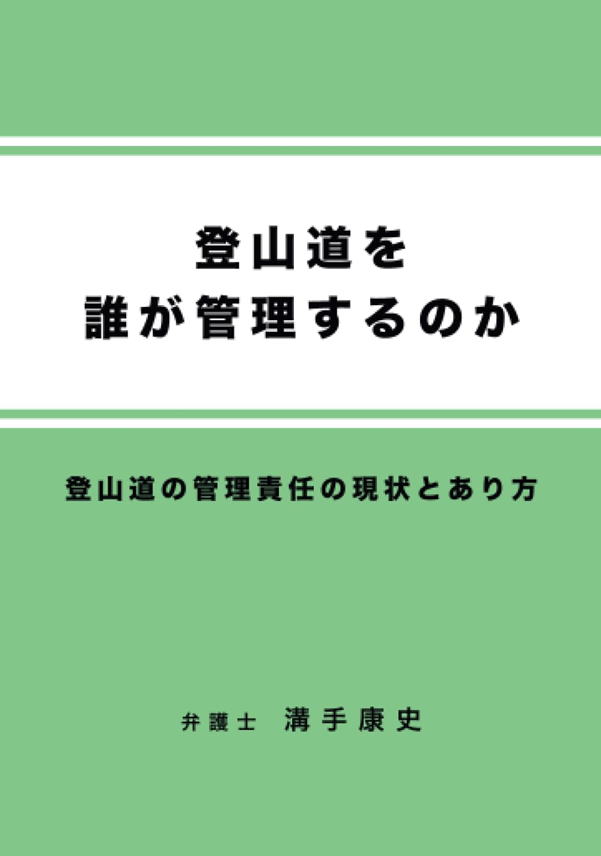2024年
溝手康史
2025年1月
国立公園の管理上の問題、講演、予定
鹿児島
2024年12月3日
「登山指導者の責任」、講演、群馬県、オンライン
高校登山部の指導者が対象
2024年12月1日
阿寺の岩場の閉鎖
埼玉県にある阿寺の岩場が年内閉鎖になるようだ。
閉鎖の理由は、事故が起きた場合の責任問題を恐れることにあるようだ。
・自己責任の原則
登山は自己責任が原則であり、クライミングも同じだ。しかし、日本ではこれが十分理解されていない。
クライミングで法的責任が生じるのは、人工壁や整備された岩場でのロープ確保などの失敗の場合である。高山でのクライミングでは法的責任が生じにくい。
岩場の管理者は、岩場の支点等の安全性を保証していいれば、支点の崩壊等について責任が生じる場合がある。それ以外は、「通常有るべき安全性」は、支点の安全性を含まない。
本来、岩場の支点は利用者の自己責任で使用すべきだが、自治体やルートを整備した団体が岩場の支点が安全であるかのような宣伝をすれば、管理責任が問題にりやすい。したがって、自治体や山岳団体は、ルートの視点の安全性について騙るべきではない。クライミングルートは個人がボランティアで整備すべきであって、山岳団体などが組織的に整備すべきではない。組織的に整備すると、安全性を保証するかのような誤解が生じやすいからである。
「通常有するべき安全性」は、支点の安全性を含まないので、岩場の土地所有者に事故の責任が生じることはない。しかし、この点が、日本ではあまり理解されていない。
日本の裁判所は、危険を伴うアウトドア活動を理解できないこと、工作物責任を広く認める傾向があることから、岩場の所有者が責任問題に不安を感じやすい。
裁判で、自己責の原則が明確になることが必要だろう(判例なし)。
・岩場お使用許可の問題
岩場の使用許可は、契約書で内容を明確にする事が必要だ。それをすれば、簡単に岩場の閉鎖ができない。
欧米ではそれが当たり前だ。アメリカでは私有の山にトレイルを開設する場合には、必ず、契約書を交わす。欧米では、「事故が起きれば閉鎖」ということはありえない。
使用貸借では、使用期間、契約解除事由などを明確にしておくことが必要。
日本では、多くの岩場で「土地所有者の許可を得た」と言う人が多いが、契約書がなく、許可が有効かどうか疑わしい場合も少なくない。公図、登記簿、戸籍謄本などで相続関係などを調査し、土地所有者全員の印鑑証明と印鑑がなければ、法的に有効だという証明ができない。
・冒険を嫌い、「危険なことをしてはいけない」という日本の文化と世論の非難文化が、クライミングの発展を妨げている。人工壁でのクライミングも十分危険なのだが、それが国民に理解されていないので、人工壁でのクライミングを非難する傾向はないようだ。
2024年11月8日
日本の生産性が低い原因
無駄な管理の多さが1つの原因(原因のすべてではない)
登山を例にあげれば、
日本では、
・高校に山岳部があり、顧問の教師が同行する。
・役所が登山届を管理する
・登山届提出を義務付ける条例
・役所が山岳事故の防止に躍起になる
等
欧米では、登山は登山者の自己責任であり、これらの管理がない。
ヨーロッパでは学校の部活動がない。生徒のスポーツは親が管理し学校が管理しない。日本では教師が自動の登校指導をするが、欧米ではそれは親の責任。
アメリカでは高校のクラブはあるが、外部指導者に委託し学校が管理しない。日本の外部指導者制度は学校の管理下に置くので、教師、学校の負担が重い。
教師は教育の専門家であり、スポーツ指導者ではないというのが欧米の考え方。日本では素人が部活動の顧問をするので、無駄が多く、事故が起きやすい。
欧米の役所は登山届を扱わない。登山者が自分で登山届を管理するのが自己責任(家族や友人に預ける)。
欧米では、山岳事故の防止に関与しない。それは登山者の自己責任。役所が事故防止に努力しても、登山者の自覚がなければ、事故は減らない。そのため、日本方式では無駄が多い。
欧米では、役所は事故が起きた後の救助活動に関与するだけである。
日本では行政が多くの管理をするので、管理に労力、税金がかかる。
「生産性がよい」というと、日本人は、「がんばる」イメージを持つが、欧米では、そもそも日本人が考える管理をしないので、労力、税金がかからない。欧米人は日本人ほどがんばらない。それが社会的効率につながる。
韓国は禁止によって山岳事故を防止する。欧米では、そのような禁止をしない。
2024年11月8日
トランプ政権と日本の安全保障
日本は、今後もアメリカの庇護下で安全保障を維持する。
トランプは、」当然、日本の軍事費増加を要求するだろう。そして日本はそれを受け入れるだろう。
しかし、アメリカ優先のトランプ政権は、日本国内が戦場になった場合に日本を最後まで防衛するかというとそうではない。アメリカは自国の防衛に必要な限度で日本を守るが、
アメリカの利益にならなければ日本を見捨てる。日本の防衛に金がかかり過ぎれば、トランプは簡単に安保条約を破棄するだろう。
日本が憲法の文言通りに軍隊を保有しない場合、「中国やロシアが攻めてきたらどうするのか」という議論がなされる。そして、米軍に守ってもらうか日本が自前で軍隊を持つ必要があるという主張がなされる。
しかし、ウクライナ戦争に見られるように、日本国内が戦場になれば、日本に戦禍が生じる。アメリカが日本の防衛するかどうかは、金次第だ。
では、日本が自前で中国やロシアに対抗できるだけの軍備を持つか。
日本が軍隊を持たず、安保条約もなければ、日本が占領される可能性がゼロではない。しかし、戦争をしなければ戦禍は生じない。軍隊を持っても戦争をすれば、戦禍が生じる。戦禍を回避するためには戦争をしないことが必要だ。
たとえ、他国に占領されても、服従しない国民を他国が支配することは容易ではない。非暴力の不服従というガンジー主義ほど占領国にとってやっかいなものはない。これに根を上げてイギリスはインドから撤退した。
第二次世界大戦デンマークはほとんど戦わずドイツに占領された。第二次世界大戦でのデンマーク人の死者数は数百人である。
しかし、その後、デンマーク人はナチスに非協力を貫き、デンマークを統治するナチス責任者はデンマーク人に協力せざるをえなかった。デンマークン人に協力しなければ、ドイツは占領地の統治ができなかったのだ。
ソ連軍、アメリカ軍がアフガンから撤退したのは、占領地を統治できなかったからだ。
アメリカがイラクから撤退したのも同じ。
支配地の国民が非協力を貫けば、広大な領土を統治できない。
日本の満州支配は、満州人の協力者がいたから可能だった。そうでなければ、広大な満州を日本の役人だけで統治すれば、金がかかって仕方がない。満州の工場で満州人が働かず日本人だけが働いたのでは工場を維持できない。
戦後のアメリカの日本統治は、日本人の協力者がいたから、できた。
ウクライナがロシアと戦わなければすぐに占領されるが、第二次世界大戦中のデンマークのような姿勢を貫けば、ウクライナを占領するロシア人はデンマーク人に協力せざるをえなくなる。この場合には戦禍は生じない。ウクライナは軍隊を持っていたために戦い、戦禍が生じた。
軍隊を持たない国は、非暴力のガンジー主義をとることになる。それが戦争と戦禍を回避する最善の道だ。
2024年11月7日
トランプ政権の誕生
今後、アメリカは、自国中心主義になる。
戦後日本は政治、経済、軍事的にアメリカに依存してきた。
しかし、アメリカが自国中心になると、日本はアメリカべったりの対応を維持できなくなる。アメリカの言う通りにすれば、日本に不利益になる。
アメリカと対等の立場でモノを言うためには、アメリカへの依存を脱却する必要がある。
アメリカに日本を守ってもらうという方針では、アメリカは当てにできない。アメリカは、自国のためにならなければ、簡単に日本を見捨てるだろう。
アメリカが国連などで反対した場合に、日本がそれにくっついて行動すれば、日本が国際的に孤立恐れがある。日本は自分できちんと判断して行動する必要がある。
アメリカの自国中心主義は、日本が自立するための機会でもある。
2024年11月4日
「登山道を誰が管理するのか」 (デザインエッグ発行)2刷発行
第2版となっているが、本の内容に変更はなく、第2刷である。
誤字、脱字の訂正等を行った。
2024年10月18日
「人はみな同じ」ではない
日本では、「人はみな同じ」という言葉が受けやすい。人間の価値に差はないという意味では、これは正しい。
しかし、「誰でもがんばれば同じことができる」という意味では、間違いである。
登山では、登山者の体力、経験、知識、判断力の違いを無視すれば、事故が起きる。まったく同じ登山をしても、登山者の個人差、能力差が生死を分ける。
最近、登山道での転倒、転落、疲労などによる救助要請が多い。これは、その登山コースに照らして未熟な登山者が大挙して登るからである。富士山はその典型だ。富士山では初心者や未熟者でも登りやすいように、至れり尽くせりの登山環境を整備した結果、大量の初心者、未熟者が押し寄せ、事故が多発する。
教育の場では、「誰でもがんばればできる」という考え方が、悲劇を生みやすい。人間に能力差があり、誰でも同じことができるわけではない。
運動オンチは、どんなに努力しても、100メートルを10秒で走るのは無理だ。
音楽オンチは、どんなに努力しても、音楽家になれない。
凡才はがんばっても天才になれない。
努力が天才を生むのは、ある程度の才能のある者の場合である。
プロ野球の世界では、努力の有無が成功をもたらすが、プロ野球選手のレベルは、もともと凡才のレベルではない。プロ野球の世界は、もともと才能のある者の集団である。運動オンチは、どんなに努力しても、プロの選手にはなれない。
運動オンチや音楽オンチでも、音楽家やプロ選手ではなく、別の分野をめざすことで個性を発揮できる。能力差は、向き不向きということだ。
日本の学校では、誰もが一流校をめざしてがんばる傾向が、多くの悲劇と無駄をもたらしている。
「誰でもがんばればできる」扱いは、結果的に社会の生産性を悪くする。自分に向いていないことに無駄な時間をかけるからである。これは、徒労だ
日本には、「誰でもがんばればできる」という横並び文化がある。集団の中で絶えず他人を意識しながら生活する人が多い。
心理学では、人並以下を受け入れない傾向が指摘されている。
学校では、誰もが同じことをし、それができるかできないかが評価基準になりやすい。それができなければ、落ちこぼれ、である。
登山では、一般ルートをコースタイムで歩かなければ、「人並以下」になり、無意識のうちにがんばる登山者が多い。
一般ルートは「誰でも登ることができる」という錯覚が多くの事故をもたらしている。
一般ルートを「誰でも登ることができる」ように整備することが、事故をもたらす。
自然物である人間は個性があり、ひとりひとり異なるので、もともと全員が同じことができるはずがない。
能力がなければ、がんばってもできないのは当たり前である。しかし、できなくても、それで人間の価値に差が生じるわけではない。
できない=無価値という考え方に問題がある。
日本では、「できない」ことが無価値を意味する傾向があり、それで誰もができるようにがんばろうとする。
その場合の「できるかどうか」は、市場価値を持つかどうかが評価基準になりやすい。市場経済の価値観に汚染されている
学校で勉強ができることは価値を持つが、登山ができることは価値を持たない。登山は市場価値をもたらしにくいからだ。しかし、クライミングがオリンピック種目になると、俄然、クライミングが価値のあるものとして社会の注目を浴びた。日本の社会は、金次第、と言うと言い過ぎだが、日本は経済優先の傾向が強い。
人間の能力が金になるかどうかではなく、人間の自然性を科学的に考える哲学が重要である。
2024年10月16日
「登山道を誰が管理するのか」 (デザインエッグ発行)2刷
この本は5月に出版したが、誤字、脱字を訂正したものを第2刷とし、11月4日に発行する。内容は1刷とまったく同じ。
第2刷のつもりで修正したが、出版社の扱いは、「第2版」になっている。しかし、内容は1刷(1版)とまったく同じだ。
アマゾンでは、現在、1刷は扱わず、2刷(2版)の予約しか受け付けていない。
11月4日までは1刷を販売してもよさそうなものだが、アマゾンはそれをしない。オンデマンデ方式の制約か。
オンデマンデ方式は注文を受けてから印刷する方式。
2刷の発行は11月4日以降になるが、1刷は私の手元にあるので、直接注文があれば販売可能だ。
2024年10月14日
京都北山・廃村八丁
京都周辺を旅行したついでに、廃村八丁を訪れた。
佐々里峠から品谷山を経て、品谷峠から八丁にスモモ谷を下降したが、谷は荒れていた。尾根を下った方がよほど楽だっただろう。
八丁から刑部谷を登ったが、道はほとんど崩壊し、倒木が多い。川をへつり、倒木を乗り越え、靴を濡らさないように何度も飛び石伝いに川を渡ったので、やたらと時間がかかった。沢歩きのつもりで最初から水の中を歩けば楽だろう。
刑部滝を越えると、一転して非常に歩きやすくなり、拍子抜けした。
佐々里峠から品谷山までは登山道が整備されているが、佐々里峠には品谷山登山口を示す標識はない。ダンノ峠への分岐点にも標識はない。刑部谷には赤いテープが若干ある。それ以外は標識があっても、字が消えているものが多い。
コースが荒れているせいか、他の登山者に出会わなかった。
スモモ谷や刑部谷を初心者向きに整備するのは、かなり大変だ。かりに整備しても、今後、大雨や大雪で簡単に崩壊するだろう。もともとそのような地形だからだ。
廃村八丁に人が居住し、山仕事がある間は、金と労力をかけて毎年、通路を整備していたのだろう。経済的な必要性があれば、それが可能だが、登山のためにそれをするのは、無駄だ。
スモモ谷や刑部谷を自然のまま放置すれば、いずれ熟練者向きのコースになる。刑部谷は沢歩きのコースにすればよい。荒れたスモモ谷の登降は時間ばかり食い、つまらないので、踏み跡程度の尾根を歩けばよい。
そのように危険表示すればよい。
スモモ谷や刑部谷を初心者のハイキングコースにするのは、もともと地形的に無理がある。
欧米では、ハイキングは地形の険しくない場所が対象であり(鎖、はしご、ロープは不要)、険しい地形は登山やクライミングの対象にし、工作物で整備しない。自然を工作物で整備しても、雨や雪の自然回復力が強いので、簡単に崩壊する。
中途半端に登山道を整備すれば、初心者が入り、事故が増えるだろう。
自然の法則に逆らって整備すれば、やたらと金と労力がかかる。富士山の登山道も、自然に逆って初心者向きの道を維持するので、金と労力がかかる。それでも事故は増える一方だ。
 廃村八丁
廃村八丁
廃村八丁という言葉は、哀愁やロマンをそそり、古くからハイキングコースになっている。
しかし、1941年に廃村になったものの、それまでの定住者はわずか5家族であり、行政上の村ではない。したがって、人がいなくなっても廃村ではない。5家族が転居したということだ。
こんな辺鄙な場所に5家族が住んでいたことに驚かされるが、かつて、自動車が普及するまでは、日本の多くの居住地区が辺鄙な場所だった。戦後になって車道ができ、それらが辺鄙な場所でなくなったのだ。
廃村八丁に戦後に人が居住していれば、トンネルなどを掘って車道を設置しただろう。しかし、人が居住していなければ、それをしない。
日本中に定住者がいなくなった地区は無数にあるが、定住者がいなくなっただけでは、廃村とは呼ばない。廃村八丁はハイキング用に意図的に作り出されたイメージである。
低山では、山の中に、かつての住居跡を見ることがある。山の中に石垣や柿の木、壊れた食器、金属くずなどが残っている。
現在は、定住者がいなくなっても、道路を利用して車で元の住民が定期的に元の住居、田畑、山、墓地などを行き来する。
それでも、定住者がいなくなった辺鄙な地区には哀愁がある。
そんな地区は日本中に無数にある。それらを廃村とは呼ばない。「住人のいなくなった地区」と呼ぶ。
今後、日本中で、定住者がいなくなった地区が増えるだろう。
2024年10月12日
自己責任とは何か
憲法上、人間は生まれながらにして自由であり、これは自己責任と一体である。その例外として、過失責任や安全配慮義務などがある。
登山は危険性のある自然の中で行う活動であり、自然が持つ危険性をコントロールできる範囲で楽しむ。危険性をコントロールするのは登山者である。
登山道の利用も自己責任である。
自己責任の原則は、国民が自律的にものごを考え、判断できることが前提である。
これは万国j共通の考え方である。このような欧米の考え方が、世界のスタンダードになり、日本もそれを取り入れた。
これに基づいて、欧米では、登山の危険防止は登山者の責任であり、行政は登山の事故防止にほとんど関与しない。
行政が登山道を整備するのは、登山の実現や環境保護のためであって、事故防止のためではない。登山道に事故防止のための工作物を設置しない。登山道にできるだけ人工物を設置しないのが、自然保護の考え方である。欧米では、登山道に鎖やハシゴはない。登山道にロープを設置することがあるが、これは登山の実現のたに必要最小限とされる。
欧米では役所は登山届を扱わない。登山は自己責任だからである。
登山届は家族や知人に提出し、登山届の管理は行政の仕事ではない。
自然公園では、レンジャーがトレイルをパトロールするが、これは環境保護のためである。自然公園の管理規則に違反する者をレンジャーが現行犯逮捕する。
行政は危険表示をするが、事故防止のためにそれほど税金を使うことがない。
救助活動は事故防止とは別の問題であり、欧米では、たいてい公的な山岳救助救助体制が整っている。欧米では、行政は、山岳事故の防止にほとんど関与しないが、山岳救助救助には熱心である。
これに対し、日本では、行政が登山の事故防止に努力する。事故防止のために、登山道を整備し、登山道に、鎖、ハシゴ、策、階段、ロープ、落石防護ネットなどを設置する
事故防止のために登山道の入口で行政関係者が注意を呼びかけ、事故防止おために登山道をパトロールする。
行政が登山届の提出を呼びかけ、役所が登山届を管理する。登山届を義務付ける条例を制定する自治体もある。
日本では、「行政が登山者の安全を守る」というパターナリズムが強い。そこでは、自己責任の考え方はない。日本で行政が事故防止のために多くの設備を設置し、多額の税金を支出することは、登山の自己責任と矛盾する。
国家が登山者ゃの安全を守る考え方は、登山者がが自律的にものごを考え、判断できないことが前提になっている。
山岳事故が起きれば、世論が登山者を激しく非難し、ここで自己責任という言葉が使用される。
日本では、事故後の公的な救助体制が不十分であるが、その根拠として、自己責任といういう言葉が使用される。
欧米では、山岳事故が世論から非難されることはない。なぜなら、登山が自己責任に基づく活動だからである。
日本では、実態としては、登山は自己責任に基づく自由な行動ではなく、「国家によって許された活動」であり、山岳事故は、国家に対する背信行為として世論が非難する傾向がある。その際に自己責任という言葉が使用され、その場合の「責任」は「非難を受ける」という意味である。
英語でも、非難を意味するblameという言葉があるが、これが責任という日本語に翻訳される。
しかし、自己責任という場合の責任は、respnsibilityであり、そこには非難の意味はない。
責任という日本語は、古い時代に中国から入ってきた言葉であり、それが、明治以降、blame、respnsibility、liabilityの訳語に当てられた。日本古来の責任とrespnsibilityは、かなり意味が異なる。
責任という日本語はあいまいな言葉である。多くの日本語がそうであるように、責任という言葉もあいまいであり、さまざまな意味で情緒的、恣意的に使われる。
respnsibilityに非難の意味はないが、日本語の責任には非難の意味が強い。そのため、自己責任という日本語に非難の意味が生じるのだが、法的な自己責任の原則では非難の意味はない。自分で自分を非難することはナンセンスである。自己責任の原則は国家から干渉されな自由の原則の考え方に基づく。
明治になって、自己責任の原則が欧米かtら日本に移入されたが、この言葉は日本的に変容し、日本の文化に合うように日本独自の進化を遂げたと言えよう。
国家や役所に対する依存心が、国民が自律的にものごを考え、判断することを敬遠させた。
2024年10月9日
量が質を変える
自動車などの人工物は量が増えても質は変わらない。
しかし、社会的なものは量が増えれば質が変わる。
大学や大学生は量が増えれば質が変わる。戦前は旧制帝大しか大学がなかった時代と、現在では大学の質が違う。旧制中学、高校と現在の高校では質が異なる。
教師も数が増えて、さざまな人格の教師が増えた。
日本は大学の数が多いので、大学の教師の質もさまざまだ。数が増えると、それはやむを得ない。
弁護士も、数が増えて弁護士が多様になった。さまざまな弁護士がおり、弁護士の人格や能力はさまざま。弁護士の不祥事が多いのは、さまざな人間が弁護士になるようになったからである。法科大学院や司法試験で学生の人格が淘汰されるわけではない。
登山道が整備されて誰でも登山をするようになると、事故が増える。富士山では、観光客や初心者がたくさん登るので、事故が増える。
明治の頃、穂高や槍ヶ岳は誰でも登れる山ではなかったので、登山者が限られ、事故が少なかった。しかし今では初心者も登ので、事故が多い。
大衆化するだけでは、量が増えて、弊害が生じる。
量を増やす場合には適切な管理が必要である。しかし、日本ではそれがなく、管理することなく量が増えることを放任するので、弊害が生じる。
大学を、一定の要件さえ満たせばすべて認可する方式で数を増やせば、大学と学生の質が落ちる。大学の数を増やした状態で無償化をしようとすると、莫大な税金がかかる。北欧では、大学の数をむやみに増やすことをせず、数がす少ないから無償化できたのである。
ミルフォードトラックで快適な登山を実現できるのは、登山者数を1日60人程度に制限しているからである。
富士山では、登山者数を制限すれば、環境保護とサービス向上ができる。
2024年10月9日
窮屈な日本の社会
カナダのバンクーバーに住んでいる光浦靖子氏が、テレビで、「日本人の能力と、絶対ズルしないでしょ、職場でも。それなのにこんなに長い時間働いて疲れてるけど、向こうの人や他の国の移民の人は凄いいい加減な感じの人も多いんですよ、日本人と比べたらね。だけどもっとショートな時間で働いて生きていけるわけで、ニコニコしてるでしょ。だからシステムがおかしいよねっていうことになって」と述べた。
同感だ。
私が外国に滞在した期間は通算しても6か月くらいしかないが、外国に関する本はたくさん読んだ。
欧米は、合理性といい加減さがあり、アジア、アフリカは不合理さといい加減さが同居している。
日本は、不合理なことを情緒的、几帳面に追求するので、生き苦しい社会になりやすい。欧米では電車が2,3分遅れても問題にならないが、日本では世論から非難され、組織内で責任者探しが始まる。日本では、責任者叩きと責任者探しが、恐い。
北欧では、教師は、子供が熱を出せば簡単に仕事を休むので(自治体が教師の代替要員を準備している)、日本人から見れば、北欧の教師は「やる気がない」ように見える。
他方、日本の教師は、子供が熱を出しても、仕事を休むことができない。熱のある子供を預かってくれる施設も日本ではほとんどない。配偶者ももちろん仕事を休めない。子供が熱を出せば半狂乱になり、夫婦喧嘩が始まる。日本人はとにかくよく悩む。頻繁に子供が熱を出せば、教師は休職するか、退職する。
日本には、「ミスに対し厳しい」文化があり、これがささいなミスでも責任を負う扱いをもたらす。ここでいう責任は法的責任ではなく、「組織や世論から非難される」という責任である。
文化は簡単には変わらないが、意識的に制度を変えることで文化も変わる。日本では、意識的に制度を作ることがっ少なく、日本では、「野放し」、「成り行き任せ」が多い。
2024年10月7日
無駄の多い日本の社会
・車中泊用の車が売り出されているが、日本では、車中泊が禁止されることが多い。サービスエリア、道の駅、公園の駐車場、道路傍のパーキング、スキー場の多くが車中泊禁止だ。仮眠は認めるようだが、仮眠と車中泊の違いがよくわからない。金のかかるオートキャンプ場を利用するのであれば、車中泊用の車は必要ない。日本では車中泊用の車が売れない。
・マウンテンバイクで走行できる山道がほとんどない。山道を自転車で走ると、ハイカーから迷惑行為として叩かれる。山道となっている林道は、多くが車両通行禁止だ。自転車も車両に入る。その結果、舗装された道路を走るほかないが、それならマウンテンバイクではない自転車の方がよい。日本ではマウンテンバイクが売れない。
・山梨県で登山道を有料化し、税金を使って登山規制を行ったが、弾丸登山は減っても事故が増えている。何のための登山規制かわからない。弾丸登山が減れば、山小屋は喜ぶ。
・登山道を工作物で整備すればするjほど、初心者登山者が増えて事故が増える。富士山がその典型だ。
・富士山では税金を使って落石防護ネットを設置する一方で、登山者の渋滞を放置するので、落石が起きると登山者に当たる確率が高い。
・道迷い遭難が起きる度に、道迷いしやすい箇所に標識を設置するが、それ以外の場所で登山者が道迷いするので、切りがない。標識を設置しても、それを見落とす登山者やよく見ない登山者がいる。
・登山者を増やそうとして、自治体が税金で避難小屋と呼ばれる宿泊小屋を設置するが、遭難者が増えてかえって救助のための税金支出が増える。遭難者を世論で叩くことで、遭難者を減らそうとしても、うまくいかない。
・自治体が利用者を増やそうとして登山道を観光用の歩道にすべく整備をすることが多いが、事故の管理責任を問われることがあり、かえって損害賠償金の支払いで税金支出が増えて、思惑がはずれることがけっこうある。その後は、多額の税金で整備した歩道を閉鎖する。
・利用者が想定を下回って、投入した税金を回収できない空港、港湾、農道、観光用林道、ほ場整備した農地が何と多いことか。
・法科大学院を作って弁護士を増やしたが、弁護士の仕事が増えていないので、経済的に困窮する弁護士が増えている。大学は法科大学院制度で儲けようと思たが、法科大学院の人気がなく学生が集まらない。国は法科大学院をつぶしていく政策に転換し、法科大学院の約半分がつぶれた。法科大学院制度の失敗で多額の税金が無駄になっている。
・大学歯学部、教育大学院大学、大学院、博士課程、各種国家資格なども作り過ぎて、その弊害が生じている。
・日本では無駄なハコモノへ(さまざまな制度や国家資格も含む)の税金支出が多い。これは、業界団体から政治献金を受ける政治家の影響力が大きいからだ。自分の選挙区にハコモノを持ってくる政治家が有権者の支持を得るという利権構造がある。
・役所は、重大なミスとささいなミスを区別することなく、「あらゆるミスがあってはならない」と考えて、ミスを防止するために多大な労力をかけるので、人件費などの税金がいくらでもかかる。欧米の役所に較べれば、日本の役所はささいなミスが少ないが、重大なミスは結構ある。1円の計算間違いを是正するために、多額の残業代を支払う役所は笑い話の対象だ。従来は、これをサービス残業で行っていたが、最近は、それが、難しくなっている。
2024年10月
「山岳事故の法的責任」(新版)の発行(デザインエッグ)
アマゾン、楽天などで購入可能
山岳事故の責任に関して、2015年に本書の旧版を発行したが(ブイツーソリューション)、在庫がなくなったので、この度、内容を書き改めて新版を発行することにした。
旧版では、判例(裁判例)を簡単に紹介したが、新版では、判例について登山者の参考になるように解説を詳しいものにした。これは、登山者から、裁判事例の内容について質問を受けることが多いからである。
また、白馬岳ガイド登山の刑事事件、アコンカグアガイド登山事故、那須雪崩事故、救助活動に関する積丹岳事故、富士山事故などの判例を追加した。
10年前は、その後に那須雪崩事故などが起きるとは思っていなかった。
山岳事故の裁判は、1~2年に1件くらいの割合で起きている。
近年、弁護士の数が大幅に増え、国民の間に、「何かあると裁判を起こされるのではないか」という不安が生じている。
しかし、日本は裁判を起こしにくい制度の国であり、弁護士が増ても裁判は増えていない。むしろ、近年、裁判件数は減っている。
山岳事故は増えているが、山岳事故の裁判が大幅に増えることはない。
それでも、山岳事故の裁判はマスコミが大きく取り上げるので、たとえ1件の裁判でも登山者に大きな不安を与える。アメリカは訴訟社会であり、山岳事故も多いが、山岳事故の裁判は稀だ。
日本は、欧米に較べて裁判件数が少ないのに、山岳事故の裁判は欧米よりも多い。
何故か。その背景についても、この本の中で触れている。

2024年9月
日本山岳スポーツクライミング協会(JMSCA)のガバナンス委員
JMSCAのガバナンス委員会の委員に就任した。これで、JMCSAの委員は、夏山リーダー資格委員会委員の2つになった。JMSCAの顧問弁護士でもある。
現在、ガバナンス委員会では、理事選考委員の選任規定などの規則等の見直しについて議論している。
2024年9月27日
日本の登山道で事故が多い理由
整備された登山道で、転倒、転落、滑落、道迷いなどが多い。一定の経験があれば、起きないはずの事故が多発している。富士山での転倒、転落、滑落、道迷いがその典型だ。
穂高の一般登山道での事故も同じだ。事故が起きた箇所は危険個所とされるが、経験者には危険ではない。未熟者に危険だということだ。
欧米では、山歩き中の道迷いは多いが、転倒、転落、滑落事故が少ない。それは、欧米のトレイルは山頂に向かうことなく、危険個所が少ないからだ。
日本の登山道は、ほとんどすべて山頂に至る。山頂付近は、岩稜、岩壁が多いが、そこに鎖、はしご、ロープを設置し、誰でも山頂に登れるようにする。鎖、はしご、ロープの管理者は不明であり、メンテナンスされるとは限らない。
欧米では、鎖、はしごの設置をしない。ロープやワイヤーを設置することがあるが、多くない。ロープやワイヤーは管理者がメンテナンスする。欧米では、岩山の山頂付近はクライミングルートになっており、登山道の対象ではない。
日本の登山道は、急峻な尾根や斜面を登ることが多いが、これは山頂に登ためである。欧米では、トレイルは山頂に向かわないので、急峻な尾根や斜面を避けて、歩きやすい箇所にトレイルを設置する。
日本の登山道のイメージは欧米にはないので、登山道ではなくトレイル、ハイキング道と呼ぶ方がふさわしい。
誰でも山頂に登れるように、岩場や崖、急峻な箇所にロープやワイヤーを設置し、それを「一般ルート」と呼び、多くの初心者、未熟者が登るので転倒、転落、滑落、凍死事故が多い。
欧米のトレイルは危険個所がないので、初心者、未熟者の転倒、転落、滑落、凍死事故が少ない。山頂付近は、クライミングの対象であり、初心者、未熟者が登ることはない。
欧米では、山麓の山歩きと山頂付近のクライミングを区別する。日本では、山麓も山頂付近もすべて登山であり、本来歩いて登るのが無理な場所も、誰でも歩いて登れるように人工物で整備するので、事故が多い。人工物の設置は自然破壊。
単純化すれば、
日本では、誰でも山頂に登りたいので、誰でも山頂に歩いて登れるように鎖とはしごを設置するが、欧米ではそれをしない。欧米では、山頂付近の岩場や崖、急峻な箇所は、それに見合った能力のある者が登ることが自然だと扱う。
誰でも山頂に登れるように自然を加工する考え方は、誰でも大学に入れるように大学の数を増やす考え方と同じである。
山頂付近に鎖とはしごを設置すれば、登山がやさしくなり誰でも山頂に登ことができる。大学の数を増やせば、大学入学がやさしくなり、誰でも大学に入れるようになる。
登山や大学のレベルを下げることは国民の自己満足であり、ある種のポピュリズムである。
日本では、一部の者しか山頂に登ることができないのは「差別」であり、全員を同じ扱いにする考え方が強い。
「がんばれば誰でもできる」という考え方が日本では強いが 現実には、人間の能力差と経済的格差がそれを妨げる。
経済的格差を解消すれば、「がんばれば誰でもできる」と考える人が多いが、登山では、経済的格差に関係なく登山者の能力が事故に直結する。
街中でも、経済的格差を解消しても、人間の能力差があるので社会的格差が生じる。
大学の数を増やし、経済的格差を解消すれば、誰でも大学に入れるようになるが、競争社会では、大学間の格差と学生の能力差が社会的格差をもたらす。
誰でも大学に入りたい→大学の数を増やす→金をかけて大学を出ただけでは意味がない。
登山では、人間の能力差が「誰でもできる」ことを妨げる。岩場や崖、急峻な箇所では、初心者、未熟者はがんばるだけでは事故を防ぐことができない。
登山者の能力に応じた登山をすることが、事故を回避するうえで必要だ。
登山道の危険性別に形態を区別し、登山道の危険性に対処できる登山者が登れば、登山道に起因する事故はほとんど起きない。
街中では、経済的格差の解消と同時に、人間の資質や個性に応じた教育や処遇が必要である。競争社会では必ず社会的格差が生じるが、一定レベルの陳儀保障や生活保障があれば、格差は深刻な問題をもたらさない。資質や個性は、能力、創造力、忍耐力、意欲、性格、気質、体力、体格、障害の有無、疾患の有無、性別などを含む。
2024年9月22日
アフォリズム
・ドイツの天才偽物画家ベルトラッキは専門家でも見抜けない贋作を描く天才画家だ。日本の美術館も騙された。その贋作もかなり価値があるのではないか。美術館は、天才画家の描いた贋作として展示すればよろしい。また、贋作ではなく、オリジナルの画を描いても価値があるはずだ。オリジナルの画よりも贋作の方が高く売れたということか。それで、彼は億万長者になった。
騙された人は彼に損害賠償請求できるが、裁判で、ベルトラッキは、「贋作でも十分高額だ」という抗弁が成り立つだろう。
・広島カープは大失速によってセリーグを混戦にし、面白くしており、十分その役割を果たしている。
・弁護士の過剰が問題になっているが、若い弁護士は公務員や企業に採用試験を受けて就職すればよい。しかし、これをすると、法学部卒の会社員、公務員との競争になり、法律の知識で法学士が負けるので、法学部の人気がますます低下する。また、司法試験に受からない法科大学院卒者も会社員、公務員になり、それも法学士、弁護士資格保有者との競争になる。
・日本は、欧米と違って、法律ではなく世論で動く社会なのに、欧米のマネをして法律で動く先進国の仲間入りをしようとして無理をするから、こうなる。日本は、社会の実態に基づいて、非法治国家として堂々と動けばよい。日本を訪れる外国人に、「日本は法律ではなく、世論で動く社会である」ことを説明しなければ混乱が生じる。混乱とは、「日本は法律で決まってないことをうるさく言うおかしな国だ。なぜ非難されるのか理解できない」ということから生じる。
・アメリカでは法科大学院はあるが、大学法学部がない。ヨーロッパでは大学法学部があるが、法科大学院がない。日本と韓国には、大学法学部と法科大学院の両方がある。
それらは大学が学生から金を稼ぎ、国が税金を大学にばらまくためにある。
・昔から、年貢と税金は、取れるところから取るのが原則だ。生きぬように殺さぬように。破産しても未納税金は消えない。しかし、重税で往く人がいる。
・誰でも他人よりも劣っていることを嫌う。誰でも平均以下であることを嫌う。それで登山道の一般ルートは誰でも登ることができると思いたがる。しかし、一般ルートで誰でも事故を起こさないわけではない。平均以下の登山者は、一般ルートで事故を起こしやすい。
・一般ルート、バリエーションルートという言葉はやめた方がよい。バリエーションルートという言葉を使うと、バリエーションルートに憧れる登山者が出てくる。バリエーションルートを死語にすれば、それを小説のタイトルで使うこともなくなる。
・一般ルートやコースタイムという言葉をやめれば、「一般ルート」を「コースタイム」通りに歩かなければならないと考える登山者がいなくなり、疲労で動けなくなる登山者が減るだろう。
・整備された登山道での転倒、転落、疲労、体調不良、道迷い事故が多い。これは、登山道を整備した結果である。登山道を整備すると初心者登山者が増え、登山道での転倒、転落、疲労、体調不良、道迷い事故が増える。富士山がその例だ。
・「〇〇でなければならない」と考える日本人が多い。これは学校教育の成果だ。管理する側は管理しやすいが、社会が発展しない。
・「〇〇でなければならない」とい考え方が、うつ病やひきこもりを増やす。
・日本は厳しい管理社会だが、管理者の都合で管理しやすいことや管理者に「得なこと」だけ管理し、面倒なことは管理しない。学校では、課題や規律、道徳、作法などを厳しく管理するが、いじめや落ちこぼれは放任する。国民は、お上に管理されることで安心感を得る。
・ヨーロッパは、国民の自由や自律を前提とする管理社会。アメリカは、国民の自由や自律を前提とする自由放任社会。
・日本人は、役に立たないマニュアル作りが好きだ。役人は、マニュアルがあると安心する。災害対策マニュアルは、災害が起きない限り役に立つ。平時のマニュアルは安心材料。災害時にマニュアルが役に立たないことが多い。想定通りの災害がないからだ。災害ではたいてい想定外のことが起きる。マニュアルを作ると、人々はそれで安心し、災害時の臨機応変の判断力が低下する。
・司法の世界の要件事実教育は、マニュアル教育の延長上にある。要件事実に基づいて裁判官は判決を書きやすくなるが、それで判決の内容が適正なものになるわけではない。
・最近は、すぐに、「どうすればよいのか」と尋ねる人が増えている。パソコンの操作は、「どうすればよいのか」が当てはまるが、自然や人間はそうではない。
「どうすれば事故を防ぐことができるか」というハウツーものを書いた本や講習会の人気が高い。しかし、判断力は短時間に覚えることができるものではない。
最近、やたらとマニュアルを求める弁護士が増えている。
・野生動物は得か損かで行動する。人間もその本能がある。快楽や金を得ることは「得なこと」に属する。
日本の役所は得か損かで行動する。役所にとって得なことは、国民にとって損なことが多い。
ボランティア活動は、自分にとって得ではないことを行う活動であり、野生動物の本性に反する。それは人間性と呼ばれる。
役所が野生の本性ではなく人間性に基づいて動くかどうか、それは政治家を選ぶ国民次第だ。
弁護士も、得か損かで動く傾向があるが、そうではない弁護士もいる。そういう弁護士は儲からない。
・弁護士の仕事はつまらない。しかし、人間の社会は弁護士を必要とし、弁護士の仕事は社会的に重要だ。裁判官の仕事はもっとつまらない。しかし、人間の社会は裁判官を必要とし、裁判官の仕事は社会的に不可欠だ。
2024年9月21日
富士山では夜間登山禁止か・・・・世界では夜間登山は当たり前
富士山の山梨県側では、山小屋宿泊者を除き、午後4時以降の入山が禁止される。
しかし、世界のスタンダードでは、夜間登山は当たり前である。
欧米では、夜間から歩き始めるトレッカーがいる。昼間は暑いので夜間しか歩かない登山者。
キリマンジャロでは、午後11時頃から歩き始め、稜線で朝日を迎える。そこではご来光を拝む仏教の思想はないが、朝日に輝くキリマンジャロを見ることができる。
富士山でも、ご来光を見るために深夜、山小屋を出発する。
世界では、夜間登山は珍しくない。
富士山5合目を夜出発すれば、朝、ご来光を見るのにちょうどよい。
富士山の登山道は整備されているので、経験のある登山者は、夜でも歩くことが可能だ。富士山はそういう経験者向きの山だ。
富士山で生じている問題の多くは、未熟な登山者の放任状態がもたらしている。
世界の常識からすれば、富士山の登山者数は1日数百人が限界ではないか。そうすれば、未熟な登山者が減り、事故が減る。
2024年9月20日
山歩きのリーダーにロープ技術が必要、ハイキングリーダーにクライミングの訓練が必要
日本では、山歩き(縦走)とクライミングを別物と考える登山者が多い。
「自分はロープを使うような危険な登山をしない」と言う登山者が多い。ほとんどの登山者は歩く登山をし、クライミングを危険なものと考え、敬遠する。
しかし、そういう登山者も岩稜登山をする。手を使ってよじ登ることがclimbingであり、岩稜の縦走登山はこれに当たる。岩稜ではclimbing技術が必要だ。登山は、mountain
climbingであり、もともとclimbingである。
日本では、本来、クライミングの対象となる険しい山でも、稜線に鎖とはしごを設置して、クライミング技術がなくても誰でも登ることができるように整備した。
山頂まで鎖やはしごを設置するのは、日本特有の方法である。ヨーロッパにあるフエッラータは、岩壁にはしごとワイヤーを設置した有料の商業施設であり、これは登山ではないと考えられている。
その結果、日本では山岳ガイドの仕事が少なく、山歩き中の事故が多い。欧米の山歩きでは、転倒、転落、滑落事故は少ない。道迷いは、世界中の山で起きるが。
マッターホルンなどでも、山頂まで鎖とはしごを設置すれば山岳ガイドの仕事がほとんどなくなり、山小屋を濫設すれば事故が多発するだろう。
「誰もできる」ようにする考え方は、日本では一般的であり、横並びで集団行動をする日本人の行動様式に合っているのだろう。誰でも大学に入れるようにすることなど。
しかし、誰もが大学に入れるようになれば、学士の資格が無意味になり、大学生間で格差が生じる。
「誰もが富士山に登りたい」という願望を実現するために富士山を整備したが、その結果は事故の多発だ。富士山の高度、気象は、相応の訓練をしなければ「誰でも登れる山」ではないので、事故が起きる。
登山でも、鎖とはしごを設置しても、能力の劣る者が事故を起こしやすい。その象徴が妙義山の縦走路だ。ここは、「鎖とはしごで整備したから事故が多発する」典型例だ。
「人は皆同じ。誰でもできる」扱いをしても、人間の能力差をなくすることはできない。
「人は皆同じ。誰でもできる」扱いは、人々に表面的な安心感を与えて現実逃避の気休めでしかない。
「人はみな同じ。がんばれば誰でもできる」は、格差社会で人々に安心感を与えるが、同時に、悲劇ももたらしやすい。
格差解消ではなく、社会的格差と人間の格差がもたらす弊害を解消する政策が必要なのだ。
UIAA(世界山岳連盟)では、ハイキングリーダーに簡単なロープ技術を必要としている。普段クライミングをしない人でも、リーダーはロープ技術が必要だということだ。これが世界のスタンダードだ。
山歩きとクライミングは別物ではない。険しい山の縦走でも、クライミングの訓練をしているかどうかで時間や事故率の違いが顕著だ。
縦走登山でも、道迷いや救助活動ではロープ技術が必要だ。リーダーにはロープ技術が必要。
山歩きからクライミング技術を排除する考え方は、山歩きの対象を制限する。登山道のない山や未知の山を歩くには、クライミング技術が必要になることが多い。
整備された登山道でも、雨などで崩壊すれば、クライミング技術が必要になる。登山道でも、増水した川の渡渉ではロープ技術が必要だ。
本来、登山は、山歩きとクライミングが一体になった活動である。それを、危険個所に鎖とはしごを設置することで、クライミング技術がなくても登れるように工作したのだが、それに限界がある。縦走でもクライミング的要素がある。登山を山歩きとクライミングに二分することに、もともと無理がある。
ハイキングリーダーが、クライミング技術やロープ技術を学ぶには、山岳などへの加入、講習会などがある。独学は危険だ。
岩場では、経験が重要だが、講習会では経験を学べない。経験ある仲間との岩稜登山ややさしいクライミングが重要。3級程度のクライミング訓練が、槍ヶ岳ー西穂高間などでの縦走登山の安全度を高くする。
2024年9月19日
なぜ、登山で無理をするのか
自分の能力にあった登山をすることが必要である。
万全の装備、登山届、登山協力金などを払い、弾丸登山をすることなく山小屋に宿泊しても、富士山で事故を起こす人が多い。
富士山で事故を起こす人は、たいてい自分の能力を超える登山をしている。下山中に疲労から転倒するのがその典型だろう。
登山道での転倒、転落、疲労、道迷いのほとんどが自分の能力を超える登山をしている。
自分の能力を超える登山の背景
・登山では、がんばるのが当たり前になっている。
登山=がんばる、のイメージは、どこから生まれたのだろうか。欧米では、山歩き=楽しむ、のイメージなのだが。
もともと、がんばるに相当する外国語はないと言われている。
日本人は、がんばることが好きだ。
学校登山では、生徒にがんばらせようとする。登山=遊びでは、学校ではダメなのだ。
登山は遊び、レジャーであり、がんばるのではなく、楽しむことが必要だ。そうすれば事故が減る。
・横並び意識
日本では、「人間に能力差がある」と言うとたいてい嫌われる。
「人は皆同じ」、「がんばれば誰でもできる」が好まれる。」
一般ルートは、誰でも登ることができる→自分も登ことができるはずだ、と考えやすい。しかし、一般ルートで多くの事故が起きており、誰でも事故を起こさないわけではない。
誰でも、他人以下と見られたくない。人並以上でありたいと考える人が多い。一般ルートを登ことができなければ、人並以下とみなされることになるので、それを誰でも受け入れたくない。
「登山者に能力差がある」と言うと、「能力がないというのか」、「差別だ」、「バカにされた」などと言う人がいる。
しかし、生物に個体差、個性、能力差があるのは当たり前。能力差は個性、と言うとわかりやすい。
・日本の登山道は、誰でも山頂まで登れるように整備されている。しかし、誰でも事故を起こさないわけではない。
逆説的なことだが、「誰でも登れるように整備する」ことが、多くの事故をもたらしている。
整備のあり方が事故につながっている。事故の多い箇所は、登りにくくし、事故を起こすような人が登れないようにすることが必要だ。
「誰でも富士山に登りたい」という国民の需要に答えるべく、富士山の登山道を整備した結果、事故が多発している。富士山を初心者が山頂まで登りにくくすれば、事故が減る。
巨岩がゴロゴロし、手を使うようなコースは、初心者が敬遠するだろう。他方で、初心者用には、山頂ではなく、富士山を一周するハイキングコースにするなど。
明治以降、誰でも山頂まで登れるように整備することが、多くの事故をもたらし、登山の魅力を失わせた。
これは、戦後の日本で、誰でも大学に入れるように大学の数を増やしたことが、大学と学生の質を低下させ、国民に多額の教育費を使わせ、大学卒の資格をほとんど無意味にしたことに似ている。全員が大学に入れば、競争社会では学士の資格は無意味になる。
北欧などでは大学も数が少なく(それで学費の無償化ができた)、進学塾や塾通いもなく、国民が教育費に無駄な金を使うことがない。ヨーロッパでは高校卒業が難しく、高卒の資格が価値を持っている(高校とは別の専門学校が多い)。高卒で3か国語をマスターしている。日本では、誰でも高校に入り、誰でも卒業できるようにしたので、高卒の肩書は競争の上で価値を持たない。
2024年9月17日
投入堂での事故
鳥取県の国宝投入堂で事故が起きた。ここでは過去に何人も人が亡くなっている。
事故が多いのは、ここが観光名所になっており、多くの観光客が訪れるからである。
ここは、入場料をとり、歩道が整備されているが、危険である。歩道の危険性のレベルは経験者向きの登山道レベル。登山経験者レベルでは、まず、事故は起きない。
登山道としては少し危険なレベルだが、観光用としては非常に危険だ
石鎚山の鎖場や由布岳の鎖場よりもやさしいが、ここを多くの観光客が歩けば事故が起きやすい。一般の観光客は行かない方がよい。かりに、小さな子供を連れて行くのであれば、危険個所でロープで確保した方がよい。
現状は入場料をとって観光用に提供しているが、これまで何件も死亡事故が起きていること、観光用の歩道ではないことを表示し、未熟な登山者を抑えることが必要。
観光用に提供して利用者を増やそうとすれば、事故も多い。
 投入堂の登山道・・・・若干、危険
投入堂の登山道・・・・若干、危険
2024年9月17日
街路樹は危険か
街路樹の倒壊や枝が落下する事故が 起きている。そのため、街路樹をすべて切り倒す自治体もある。
最近は、街路樹を嫌う自治体が増えている。維持管理に金がかかり、事故の原因になるからだ。
街路樹は社会的生産に寄与しない。
街路樹が倒壊することがあることは間違いないが、それが人身事故をもたらす確率は大きくない。街路樹の倒壊事故が起きると、それが稀な事故なので、マスコミが大きく報道するので目立つが、事故率は高くない。
むしろ、街中の看板、電柱、道路標識などの工作物の倒壊、落下事故、ビルからの落下物事故の方が多い。これらは時々起きるので、珍しいことではなく、マスコミが報道しない。台風が来れば、必ず日本中で多くの看板や屋根瓦が飛ぶ。
ビルからの落下物事故は、死亡事故が起きた時しか報道されないが、けっこう多い。そのため、私は、ビルの下を歩くときは、上からの落下物に注意しながら歩く。街路樹が倒壊するよりも、こちらの方が恐い。
ビルからの落下物j事故があるからと言って、ビルを取り壊す人はいない。
問題は、街路樹の倒壊事故の事故率である。
この確率が低ければ、それほど問題にする必要はない。
街路樹の維持管理に金がかかるが、街路樹は、街の景観、美観、住みよい街作りなど、居住環境に大きく貢献する。居住者の幸福度に貢献する。これは、金につながらないが、重要な価値である。それがあるから、欧米では街路樹を大切に維持している。
腐食した街路樹を切り倒すのは当然だが、健全な街路樹もすべて切るのは、ナンセンスだ。
そのナンセンスさは、富士山を見ようとする観光客を排除するために税金で目隠壁を設置する某自治体の愚かさに匹敵する。
日本の役所は、発想が幼稚で文化度が低い。
2024年9月8日
日和田山でのクライミング禁止
日和田山では、かなり前からクライミング禁止になっているが、以前からiクライミングが行われてきた。
しかし、少し前に、また、クライミング中の死亡事故が起きた。
今後、日和田山でのクライミングが可能かどうか不透明だ。
日和田山の登山口に田部井淳子氏の記念碑がある。それは、「日和田山からエベレストまで」というタイトルになっている。
記念碑に、田部井氏が日和田山に何度も通い訓練をしたと記載されている。
田部井氏は日和田山の岩場に通ってクライミング技術を磨いた。田部井氏は、日和田山のハイキングコース歩いて訓練をしたわけではない。エベレストはハイキングの延長ではなく、登攀の延長にある。
もし、日和田山の岩場がクライミング禁止になれば、将来の田部井淳子は生まれない。
日和田山の岩場は、スケールが小さい。広島の天応烏帽子岩山の10分の1くらいのスケールだ。
こんな小さな岩場が多くのアルピニストのトレーニング場所として全国で有名になったことに驚かされる。
場所が東京に近いこと、アプローチの便利さ、岩登りを始めた人から中級者まで楽しめることが、日和田山を有名にしたのだろう。
ホールドの多い岩なので、小さな岩場だが多くのルートがとれる。難易度の高いルート設定も可能だ。
日和田山は、東京から電車で日帰りできる点がよい。
しかし、岩場を使用禁止にし、同時に、田部井氏を日和田山の宣伝材料にするのは、矛盾である。日和田山の象徴である岩場を使用禁止にすれば、日和田山は全国に無数にある平凡なハイキングの山になる。
関係者が日和田山の岩場に誇りを持っているのか、いないのか、よくわからない。たぶん、岩場はいらないと思っているのだろうが、それでも、田部井淳子氏やエベレストを地域振興に利用したいのだ。
穂高や槍ヶ岳で死亡事故が起きても、登山禁止にしない。
しかし、低山の岩場は死亡事故が起きるから簡単に使用禁止になる。、
「危険だから使用禁止にする」のだが、富士山でも死亡事故が何件も起きても、富士山は登山禁止にならない。
根底に、クライミングは経済的効果につながりにくいという点があるようだ。経済優先の考え方。
日和田山の岩場をもっと有効に活用すれば、日和田山と高麗の知名度をもっと高めることも可能だろう。
 日和田山登山口の田部井淳子氏の記念碑
日和田山登山口の田部井淳子氏の記念碑
 日和田山の岩場にあるクライミング禁止の看板
日和田山の岩場にあるクライミング禁止の看板
2024年9月7日
安全登山のための登山道を考える・・・・・シンポジウム
主催:日本山岳サーチ&レスキュー研究機構 等
13:00~17:00
東京
私は、「登山道の管理責任と登山道の形態」 というテーマで話をした。
参会者は、オンラインを含めて105人。
2024年8月
八ヶ岳での道迷い遭難
ネット記事・・・「道に迷って行動不能に…八ヶ岳連峰ニュウから下山中に遭難 東京・清瀬市の64 歳女性を救助」
私は、8月の初めに、稲子湯-本沢温泉ー夏沢峠ー天狗岳ーニュウ(2353m)ー稲子湯を歩いた(テント泊)。
ネット記事では、2200m付近で遭難したということであり、だいたいその場所がわかる。少し迷いやすい箇所があったが、よく整備された登山道だ。ある程度の登山経験があれば道迷いしないだろう。
テープの数を増やせば、初心者、未熟者用の登山道になるが、日本のすべての登山道を初心者用にテープだらけにすれば、テープは自然界のゴミであり、環境破壊になる。
その先の石楠花尾根は登山道が崩壊して迂回箇所が何か所もあり、谷から尾根に登ったり下ったりする。その表示が石楠花尾根の分岐点にあれば、私は下山路に白樺尾根を選択しただろう。これは林道につながる下山路だ。
一気に谷に下れば最短距離の登山道になるが、それをしないのは、石楠花の時期に花を観賞できるようにしたのだろう。しかし、登路が崩壊したせいもあるが、石楠花尾根は快適ではない。
ネット記事の遭難場所は、石楠花尾根に入る手前で前である。
救助要請時刻が午前10時30分なので、遭難者は、おそらく白駒池からニュウに登ったと思われる。
問題は、白駒池ーニュウー稲子湯がハイキングコースとして表示されている点にある。白駒池ーニュウは、歩いたことはないが、恐らく歩きやすいと思われる。しかし、ニュウー稲子湯は悪路だ。ニュウ付近には、白駒池から登ったと思われる登山者が多かったが、稲子湯に下山する登山者はいなかった。石楠花尾根を登る重荷を背負った女性の2人パーティーに出会ったが、熟練者と思われた。「こんな急登のコースを夏に登る物好きもいるのだ」と思ったが、相手も、「こんなコースを荷物を背負って下る人もいるのか」と思ったかもしれない。
ニュウー稲子湯をハイキングコースと表示すると、勘違いしやすい。私もハイキングコースだと勘違いしていたが、悪路だった。
八ヶ岳はいくつも登山道があり、どれを選択してよいか迷いやすい。稲子湯の表示につられて石楠花尾根を選択したが、稲子湯までは林道経由の別の登山道もあった。どのコースが歩きやすいかの表示が分岐点にあればよいが、それがない。林道経由のコースは歩きやすいが、八ヶ岳では林道経由のコースは表示しないことが多い。林道関係者への遠慮があるのだろうか。あるいは、稲子湯温泉にとって、このコースが客を呼び込むために都合がよいのだろうか。
遭難者にはこのコースはレベルが高すぎた。
自分のレベルに見合った登山道を選択することが必要だが、日本ではそれがしにくい。
登山道の難易度を統括する管理者がいないまま、ボランティアでなり行き任せで整備しているのが現状だ。
富士山の登山道は至れり尽くせりの過剰な整備がなされているが、それでも大量の初心者が押し寄せれば、事故が増えるのは当然だ。登山を許可制にして、登山者数を制限すること、アプローチや登山をもっと不便にして初心者が登りにくくすることが必要だ。
 ニュウ(2353m)
ニュウ(2353m)
2024年8月12日
富士山での世界のスタンダードと日本のやり方の対立
富士山で、行政関係者が、「夜間歩かないでください」、「富士山は、夜間、散歩するところではありません」、「それがルールです」などと言い、外国人登山者が、「そういう法律がありますか?」と質問したそうだ。そういうネット記事があった。
ネット記事は、法律だけがルールではない、という趣旨のことを書き、外国人登山者を非難していた。この種の記事に多くの日本人が、「外国人はけしからん」と共感する。
しかし、世界のスタンダードに照らせば、外国人登山者の方が正論である。
拘束力がなければ、ルールとは言えない。拘束力のないルールに基づくスポーツでは、まともな競技などできない。ルール違反があってもルールに強制力がなければ、何でもアリの乱闘競技になるだろう。
行政指導やお願い、常識などは、ルールではない。「そういう法律がありますか?」という質問は、欧米では、当然の素朴な質問である。それに対し、イエスかノーで答えず、「法律だけがルールではない」と答える日本人は世界で孤立する。
法律は、イエスかノーか、黒か白かの世界である。日本は、それらをあいまいにして、お上の指導と世論の圧力で動く国である。日本も法の支配を憲法上の基本原理にしているが、日本では、「法律だけがルールではない」という日本人が多い。これでは、先進国の仲間入りができない。
富士山では、ご来光を見るために、夜間、山小屋を出て山頂まで歩くので、夜間登山が当たり前である。ご来光を見るための登山を認めれば、夜間登山を認めることになる。
弾丸登山の禁止は法律や条例がないので、「お願い」である。それを「ルールである」として強制するのは詐欺的なであり、無理である。これはフェアではなく、先進国では恥ずかしい。
富士山でトレランの大会もあり、トレランが禁止されていない。しかし、弾丸登山の禁止を唱え、それに強制力がなないのに、強制力があるかのように「禁止」という言葉を使用することは欺瞞的だ。
日本がグローバル化すれば、世界のスタンダードに従う必要がある。世界のスタンダードが正しいかどうかは問題ではない。歴史の流れに「正しいかどうか」はない。欧米の価値観がたまたまが世界のスタンダードになっただけであり、そこには正しいかどうかは関係ない。日本の憲法や民法、刑法なども、欧米の価値観を取り入れて作っている。しかるに、その運用を日本独自のやり方でやっても世界から孤立する。
日本が鎖国するのであれば別だが、欧米を真似て憲法や民法、刑法などを制定し、欧米の価値観を取り入れたのだから、それらの運用も世界のスタンダードに従う必要がある。
富士山で必要な規制は法令で定める必要があり、違反すれば現行犯逮捕するような法律・条例に基づく管理規則が必要である(アメリカの自然公園では、管理規則に違反すれば現行犯逮捕される)。それをしないのであれば、憲法上の自由が原則である。法的な規制がなければ自由ということだ。それが世界のスタンダード。
日本では、学校で憲法を教えない(試験のために暗記させるだけで憲法の価値観を教えない)。
それをしない限り、今後いつまでも、日本人が外国人登山者に愚痴を言って非難するだけで、何も進歩しないだろう。
行政指導やお願い、常識などを、日本的なルールと称して強制しようとしてもうまくいくはずがなく、多額の税金を浪費するのが日本の実態であり、それが日本の生産性を悪くする。
日本では、ものごとを不合理に情緒的にがんばって実現しようとして失敗し、税金を浪費することが、あまりにも多い。
2024年8月
日本最高所の野天風呂(八ヶ岳、本沢温泉、標高2150m)
 稲子湯から歩いて4時間、テント泊
稲子湯から歩いて4時間、テント泊
2024年8月5日
ストックの先端にゴムを装着すべきか
日本では、登山道を荒らさないためにストックの先にゴムを装着するのが常識化している。
しかし、これは日本特有の現象だ。
キリマンジャロでは、現地タンザニアガイドから、「ストックにゴムをつけると危険だから外せ」と言われた。ストックにゴムをつけると、下山時にスリップしやすい。これは、その通りだ。
ミルフォードトラックでは、欧米人のハイカーは誰もストックの先にゴムをつけていなかった。
ストックにゴムをつけると下山時にストックでスリップを防止する機能を発揮しにくくなる、。
世界では、環境保護のために登山者数を制限するので、ストックが登山道を荒らすことは問題にならない。登山者が多ければ、登山靴でも登山道が荒れるだろう。
ストックの先端にゴムを装着することは、自然環境の保護とは関係がない。ストックの先端にゴムを装着することは、登山道という人工物を保護するのであって、自然を保護するものではない。登山道は人工物であり、登山道自体が自然環境を破壊する。したがって、登山道の整備は、自然環境を破壊する程度を最小限にとどめることが要請される。しかし、日本では、登山道に、はしご、鎖、ロープ、柵など、大量の工作物が設置される。
自然保護の観点から言えば、登山道は自然へぼダメージの少ない形態とし、投入する工作物をできるだけ少なくする必要がある。
登山者が多ければ制限する必要がある。
環境保護→登山者数を制限する。
事故防止→ストックの先にゴムを装着しない。
という考え方が必要だ。
ストックの先端にゴムを装着することは、登山道を保護するためであり、人工物を保護するものだ。
日本では、事故の防止よりも登山道の保護の方が優先される。
私は、スリップしやすい下山路では、ストックのゴムを外すことにしている。登りでは、スリップする危険がないので、ストックにゴムを装着することが多い。
ツアーガイドが、ツアー客にストックのゴムを外すように指示をし、その結果、ツアー客がスリップして事故が起きると、ツアーガイドが損害賠償責任を負う可能性がある。
ツアーガイドは、スリップしやすい個所では、タンザニアのガイドのように、ツアー客にストックのゴムを外すように指示をすることが望ましい(これは法的な注意義務ではない)。
2024年7月29日
K2での遭難
K2西壁に挑戦した平出、中島ペアが遭難した。
無酸素、アルパインスタイル、未踏ルートであり、リスクが極めて高かった。
K2のノーマルルートは、エベレストのノーマルルートより難しいが、K2西壁はそれよりもさらに難しい。
ある登山家は、「危険な登山に挑戦していると、いつかは死ぬ」と言った。
オリンピックでは、どんなに力があっても、ほんのちょっとした油断で負けることがある。ヒマラヤでは、どんなに力があっても、ほんのちょっとした油断が死に直結する。
平出氏45歳、中島氏39歳。
植村直己(享年43歳)、長谷川恒男(享年44歳)、谷口けい(享年43歳)、高見和成(享年51歳)、星野道夫(享年43歳)
名越實氏は、50歳の時の年賀状に、「ワシはとうとう50年生きたぞ」と書いていたが、65歳で冬の北アルプスで遭難死した。
昔、私が所属していた山岳会の赤松氏が亡くなったのは20代だった。
みな、遭難死である。
なぜ、そうまでして危険なことに挑戦するのか。
そうしないではいられない衝動があるからだ。登山家の性というべきか。
2024年7月17日
富士山山・・・駆け込み登山
富士山の山梨県側で、16時のゲート閉鎖前に入山する登山者が問題になっている。
しかし、条例で16時まで入山を認めたのだから、問題はない。
14時に入山しても、体力のない登山者は危険だ。15時55分に入山しても、体力があれば、それほど問題ではない。
山小屋に宿泊しない登山者も、法令で宿泊を義務づけていないので、問題はない。
赤ん坊を背負った登山者は危険だが、禁止していない。
三浦雄一郎のような高齢者登山は禁止されていない。
行政が、登山者の行動の細部に介入すると禁止だらけになる。
行政が、登山の安全性を確保しようとすると、こうなる。
富士山は、初心者が入山しやすい体制に問題がある。
世界では、環境保護のために許可制がスタンダードになっている。これは、事故防止が目的ではない。
欧米では、登山は自己責任なので、行政は事故防止にあまり介入しない。それが本来の自己責任。事故防止のために役所が多額の税金を使っても、あまり役に立たない。事故防止は登山者自身にまかせるほかない。
役所がどんなに事故防止に努力しても、初心者が多く登れば事故が増える。
事故防止のために16時以降の登山を禁止するというのは、子供の発想だ。なぜなら、16時以前のの入山者が事故を起こすので。
16時にゲートを閉めるのは、職員が17時に帰宅するからでしょ。
事故防止にならないのであれば、最初からゲートを設置しない方がよい。ゲートに多額の税金がかかっている。無駄なことは最初からしないというのが、欧米型の合理的な考え方だ。
日本では、自己責任を強調しながら、行政が事故防止のためにやたらと介入する。それらにすべて税金がかかり、役所の仕事が増える。日本では、自己責任は、行動の基準ではなく、世論が非難するための道具だ。
2024年7月11日
富士山山開き・・・・事故が多発
富士山では、山開きしたとたんに事故が多発している。
マスコミは、山開き前の登山は危険だと報道するが、山開き後の方が事故が多い。
山梨県側は1日の登山者を4000人に制限するが、事故は減らないだろう。初心者が1日に4000人も登れば、事故が多発するのは当然だ。山小屋に宿泊しない登山者がいなくなっても、それは事故の件数とは関係がない。事故を起こすのは、ほとんどが山小屋宿泊者だからだ。
静岡県側で入山規制をしないのは、国有地に登山道があるからだと報道されている。国の同意がなければ、山梨県のような入山制限ができない。
国は、山梨県方式に同意しないのだろう。その理由は、おそらく、山梨県のやり方が法律的に稚拙な方法であり、法的トラブルに対処できないからだろう。山梨県の方法は、入山料ではなく、登山道の利用料であり、これは、日本でも、世界でも前例がない。登山道を有料にしないのは、登山道はもともと危険なものであり、安全化できないからである。安全化できないものを製造物と同じように有料化できないからである。
人工的施設の有料化は施設管理責任が伴う。山梨県の登山道を遊歩道にするほかなくなる。遊歩道では、歩道の管理責任が生じやすい。
これに対し、世界で採用されている入山料は、自然エリアへの入域料であり、人工的な施設の利用料ではないので、施設管理責任が生じない。公有地であれば、入域料を徴収できる。
熟練者の弾丸登山は事故にならない。初心者の弾丸登山が危険なのだ。初心者は、山小屋泊りでも危険である。つまり、弾丸登山かどうかではなく、初心者かどうかが重要なのだ。
弾丸登山者の数が公表されていないが、おそらく少ないはずだ。弾丸登山者で事故を起こした者の割合も公表されていない。
短パンの外国人登山者の映像を流して、無謀な登山者のイメージをを伝えるが、遭難者のほんどは短パンではない。つまり、軽装登山だから遭難しやすいという関係がない。初心者は万全の装備でも遭難しやすい。
メディアは軽装の登山者が遭難しやすいというイメージを報道するが、現実は、装備に関係なく、初心者が遭難している。
富士山での事故のほとんどは初心者の事故である。
富士山は初心者向きの山ではない。また、観光客には無理だ。
事故防止のためには、初心者や観光登山者が登りにくくする工夫が必要だ。
それには、
・許可制
・マイカー規制
・5合目駐車場の規制、5合目駐車場の廃止など
・登山道を初心者が登りにくいものにする。
富士山は初心者が登りやすく整備していることが、事故を多発させている。
登山道を整備すれば事故が増える・・・・これは明治以降の北アルプスで実証されている。
入山料を1万円にしたとしも初心者は登るだろう。
カナダのある国立公園では、入園するには、1万円の入園料と1時間のレクチャー受講を義務づけていた。これは入園者が少ないからできるのだが、公園内に山小屋、橋、標識、整備された道はない。
2024年7月8日
安芸高田市長選と東京都知事選‥‥ネットの仮想空間と実体のギャップ
4年前、安芸高田市民は、当時「無名だった」石丸氏を圧倒的な支持で当選させ、
「石丸劇場」が生まれた。これは、ネットの世界で繰り広げられる政治が多くのネット民を喜ばせる劇場である。
石丸氏は安芸高田市の税金を使って、ネット配信をして自己の政治的知名度を上げ、4年後、
「石丸劇場」の舞台を東京に移した。
石丸氏の関心は、安芸高田市民の方ではなく、自己の政治的野心を実現するための対象としての全国のネット民の方に向いていた。安芸高田市民は、常に、蚊帳の外だった。「石丸氏に利用された」という感情を持つ安芸高田市民が多いのではないか。
今回の東京都知事選では、石丸氏はもはや無名ではなく、ネットとメディアで知名度が高かった。
が、石丸氏は大差で小池氏に敗れ、安芸高田市では、石丸氏の後継候補者が落選した。
今回、安芸高田市で、石丸氏の後継候補者の獲得票数は、当選者の約3分の2だった。東京都知事選でも、石丸氏の獲得票数は小池氏の約3分の2である。安芸高田市と東京都で状況が似ている。
都会のネット民やマスコミ関係者(たいてい都会に住んでいる)は、「安芸高田市のような保守的な田舎者と一緒にされてたまるか」というプライドがあるようだ。
そのような人たちは安芸高田市で石丸氏の後継者の候補者が落選しても、「それだから田舎はダメなのだ」と考え、東京では、石丸氏が落選しても大健闘したと評価する。マスコミは、「石丸氏が東京都知事選で2位の票を獲得するも、安芸高田市長選では石丸氏の後継候補者が落選した」と報じた。
しかし、安芸高田市の石丸氏の後継者の候補者は、組織的な支援がない中でよく健闘したというべきだ。石丸氏の後継候補者を支持したのは、保守系改革派の浮動票である。
東京でも安芸高田市でも、どちらもほぼ同じ政治状況にある。いずれも、保守本流が政権を維持した。
石丸氏は保守系改革派とみるべきだろう。安芸高田市で落選した石丸氏の後継者の候補者も保守系改革派の人である。政策内容や手法は維新に近い。議論の仕方は橋本氏に似ている。
保守的な市民が保守系の首長を選ぶ構図は、安芸高田市でも東京都でも同じである。
石丸氏が安芸高田市の市長になっても政界は問題視しなかったが、東京都知事選で2位の票を得たことで、政界に激震が走った。これは、田舎の野球の弱い高校で活躍していた選手が、野球の強豪校にレギュラーになり、全国大会では負けたが活躍し、注目されるようなものだ。安芸高田市の市長程度では、政界でバカにされやすいが、東京都知事選は、そうではない。
たとえ僅差で落選したとしても、支持者にとって落選の結果は同じだが、大差で負けた石丸氏は2位の得票数を獲得したことで、政治的成果を得た。今後、維新の影の支援を受けて選挙に出る体制を固め、選挙で「成功した」と言えよう。
石丸支持者は、既存政権、既存政党、与党政権に対する批判票であり、全国のどこでも批判票が増えている。
いつの時代でも政治や社会に対する不満がある。
かつては、そのような不満は、水戸黄門や大岡越前のような英雄像に救済を期待した。
1970年代には、大学紛争や左翼勢力が大きな影響をもたらした。
今の時代は、テレビやネットで半沢直樹的な痛快な批判者に人気が集まる。私は、関心がないので、半沢直樹のドラマを見ていないのだが(朝ドラも見ない)、「痛快」、「カッコイイ」という程度で、ネットでの人気が一気に高まる。
小泉氏の郵政改革や、一時期の維新ブームなどは、「既存勢力をつぶす」というスローガンで人気を博した。小泉氏は、小泉劇場が冷めやすいことを知っていたので、すぐに引退した。
中坊氏は「平成の鬼平」と呼ばれて人気を博したが、その手法はパワハラ的な強引さが目立ち、失脚した。
維新も攻撃的な議論のスタイルで一時期人気を博したが、その勢いは、今は、ない。
石丸氏もそのような手法に似た面がある。
石丸氏は、ネットなどで言葉での政治演出が巧みだが、現実政治はうまくない。言葉と実践は違う。実践では、政治的な能力や経験が必要だ。
石丸氏は自分への批判や意見を許さない傾向がある。ネットは一方通行なので、好むのだろう。
泉元明石市長は、マスコミから叩かれても、実践を通して明石市民を自分の味方にした。暴言発言後の辞職・・・・再当選がそれを示している。
しかし、石丸氏は、実践を通して安芸高田市民を自分の味方にできなかった。最初の当選は、対立する有力候補者のいない状況下での無風選挙だった。次の選挙が事実上の市民による審判の機会だったが、石丸氏はそれを避けて任期満了前に辞職した。もし、市民の審判を受けていれば、落選する可能性が高かった。
その点で、石丸氏は政治家として市民の審判を受けて当選した実績がない。
石丸氏は、そのような選挙実績がないまま、ネットで支持を得て、メディアに頻繁に登場する。実体とメディアの演出の間に大きなギャップがある。
石丸氏は相手を攻撃する議論は得意だが、生産的な議論ができない。
民主主義は、互いに意見を出して議論をし、よりよい方向を模索する過程でなければならない。
一方的なl攻撃的な議論・・・・これはポピュリストの特徴であり、石丸氏はネット社会のポピュリストだ。
登山の世界でも、「栗城劇場」でネットを通して言葉が一人歩きをした。メディアでの派手な演出が栗城氏の登山に多くの支持と資金を集めた。
しかし、実際の登山と言葉による演出は異なる。
「栗城劇場」では、現実の登山がうまくいかなかった。ネットは、圧倒的な支持から非難に変わった。ネットに、「騙された、金を返せ」などの書き込みがなさた。
東京都知事選でも、選挙に負けた石丸氏が満足そうなコメントを出したが、石丸氏は、次の選挙のための知名度を上げる戦略だったのかもしれない。
しかし、支持者の中には、本気で、「当選する」と思って支持した人が多いのではないか。落選して笑みうを浮かべる候補者に、支持者が不信感を持つのは当然だ。
選挙後の、石丸氏の高圧的な姿勢に、ネットやメディアで反感を感じた人がいる。ネットの風向きは簡単に変わる。
栗城氏が無酸素単独でエベレストに登れないと、「詐欺だ」、「金を返せ」と言ったネット民。メディアも、栗城氏を登山に無知な視聴者を騙すペテン師などと非難した。それと同じことが、石丸氏にも起こりうる。
石丸氏がネットで叩かれても、「あのやり方では、そうなるだろうな」というのが感想だ。
「栗城劇場」は、栗城氏が遭難死した後も、栗城氏の関連本の出版などで続いている。
4年前以降、全国で盛り上がった「石丸劇場」は、安芸高田市では石丸氏の後継者が落選し、東京では石丸氏の落選という結果になった。
「石丸劇場」は、かつての維新ブームや「橋本劇場」に似ているが、それらは、今は、もう、ない。
当初、市民から期待を持って迎えられた「石丸劇場」は、4年間の市政で市民を落胆させた。
劇場は熱しやすく、冷めやすい。
ネット空間は虚構の世界であり、簡単に成果をもたらすが、虚構空間は簡単に崩壊しやすい。
石丸氏は、今後、政治家としての実体が伴うかどうかが問われる。
2024年7月6日
山岳遭難の法律問題・講演
三重県山岳遭難対策協議会
山岳事故の法的責任問題、登山道の管理の問題を扱った。
参加者数は、オンラインを含めて、約250人で関心の高さが感じられた。
その後の懇親会、翌日の伊勢山上(328m)での登山を含め、三重県の関係者にお世話になりました。
その後、伊勢神宮を見て、伊勢ー奈良県ー大阪ー山陽道経由で帰宅した。

 伊勢山上のハイキングコース!(安心してください。迂回コースがあります)
伊勢山上のハイキングコース!(安心してください。迂回コースがあります)
2024年7月4日
ヒマラヤでの遭難
長野県山岳協会副会長で高校山岳部で長年指導してきた大西浩さん(松本市)が、パキスタンのカラコルム山脈に位置するスパンティーク(7027メートル)を登頂後の下山中に亡くなったことが3日、分かった。
大西浩氏はよく知っている人だ。
2024年6月28日
栗城劇場・・・・デスゾーン
私は栗城氏に関心がなかった。
しかし、「デスゾーン」という本の中古本が非常に安かったので、資料として買って読んでみた。
メディアについて考えさせられた。
栗城氏が、無酸素、単独でエベレストをめざすと言うことは、個人の自由である。どのような登山をすべきか決まったものはなく、どのようなスタイルでもよい。栗城氏のいう単独登山は、登山隊を組織し、スタッフ、ポーターを使用するが、登山行動は1人で行うスタイルであり、テントなどをポーターが荷揚げしたようだ。アルパインスタイルではない。
このような登山スタイルは故人の自由だが、それを単独登山というと誤解をまねきやすい。
これをメディアが、「無酸素、単独登山」と呼んで派手な演出をしたことが問題だった。
メディアはその影響力の大きさから、社会的責任があるからだ。1登山家がエベレストの無酸素単独登山を言っても誰も相手にしないが、メディアが取り上げると社会的な影響が大きい。
また、メディアが栗城氏をヒーロー扱いしたことも問題だ。栗城氏は、多くの8000m峰に登頂しており、力のあるヒマラヤ登山家だったが、ヒーロー扱いをするほどのものではない。また、「無酸素、単独登山」の可能性が低かったので、メディアはその点を報道する必要があった。
メディアが派手に演出した結果、登山に失敗すると、多くのネット民から、「騙された」、「金を返せ」、「ニセモノ登山家」などの非難がなされた。メディアの演出が詐欺まがいだった。
メディアは事実を正確に報道するのが、その倫理だが、視聴率を稼ぐために過剰な演出をすることが多い。栗城劇場はそのようなメディアの過剰な演出が生み出した。
「デスゾーン」には、栗城氏の登山家としての能力の客観的な評価がない。これがなければ、栗城氏がニセモノかどうかの評価ができない。栗城氏の登山家としての能力の客観的な評価なしに、栗城氏についてさまざまな証言や問題点を記述しても、すべて「砂上の楼閣」でしかない。
また、「デスゾーン」は、個人と故人のプライバシーを扱っており、名誉棄損、プライバシー侵害の可能性がある問題本だ。
この本は、メディアの商業主義の延長上で書かれている。賢明な登山者は、商業メディアとネット民から距離を置く必要がある。
2024年6月16日
ヒマラヤでの遭難
ネット記事から・・・・・パキスタンで登山中に行方が分からなくなった日本人2人のうち1人の遺体が収容されました。パキスタン北部にある標高およそ7000メートルのスパンティーク峰を登っていた平岡竜石さんと田口篤志さんは、12日に行方が分からなくなっていました。地元当局は15日の捜索で、標高6000メートル付近の地点で「平岡さんの遺体を発見し収容した」と発表しました。一方、田口さんの安否はまだ分かっておらず、捜索活動が続いています。・・・・・・
国際山岳ガイドの平岡竜石氏は、私の事務所に来たことがあり、よく知っている。日本有数の高所登山の山岳ガイドだった。
また、1人、知人が亡くなった。残念だ。
2024年6月15日
広島県北労連・労働法律相談センター事務所開所式
広島県、三次市
出席し、挨拶した。
この相談センターは、20年くらい前からあり、開設当初から協力している。
2024年6月14日
ボランティア活動の功罪
額が低すぎるとして猟友会が熊の駆除活動を拒否した。
町は、狩猟免許保有者にボランティアで無報酬で熊駆除を依頼した。恐らく、ボランティアには町外の人もいるだろう。
一時的にはボランティアで熊の駆除ができるかもしれない。
しかし、ボランティア活動は、するかしないかが自由なので、都合が悪ければ出動しないことが可能だ。今後、継続的にボランティアで熊の駆除ができるかどうかわからない。ボランティアは熊以外の動物の駆除はしないだろう。
ボランティア活動でも、銃の事故の損害賠償責任や刑事責任が生じる。拙著「ボランティア活動の責任」参照
ボランティア活動者が死傷しても、公的な補償はない。
動物の駆除をボランティア活動に依存しても、継続的な駆除は、難しいだろう。
一般に社会的な活動をすべてボランティアでまかなえば、経費がかからないので、都合がよい。
医療、教育、建設、土木、福祉などすべてボランティアでまかなえば都合がよい。しかし、ボランティア活動は、するかしないかが自由なので、継続性がない。
そこで、これらの分野は職業として遂行するシステムになったのだ。また、専門家=職業化という経過が多い。医師や弁護士の仕事が無料のボランティアの国はない。
災害時などはこれらのボランティア活動があるが、それは一時的なものだ。一時的、緊急的なことがボランティア活動の対象になりやすい。
動物の駆除を継続的に行うには、職業的な業務として遂行するほかないだろう。
動物の駆除が経済的採算がとれれば商業化する。鹿を捕獲し、鹿肉販売の採算が取れれば、商業化できるが、現状はそうなっていない。野生の魚類や海産物はその捕獲、販売が漁業として商業化している。
自治体は、金がかかるので動物駆除に消極的だ。福祉、介護、教育、環境保護、スポーツ、司法などは、経済効果を見込めないので、自治体は消極的だ。
現状では、動物の駆除は自治体の義務的な業務ではない。
国民の安全を守る点で、熊の駆除は警察の業務だが、市街地での発砲が禁止されているので、警察官は街中で発砲できない。自衛隊の射撃隊に任せる方法もあるが、それには法整備が必要だ。
問題は、国が熊対策に本気になっていないことだ。現在は、自治体任せ、ボランティア任せだ。
法律で動物駆除を自治体の業務として位置づけ、国が自治体に補助金を支出する体制が必要ではないか。
2024年5月31日
那須雪崩事故判決
5月31日、2017年に起きた那須雪崩事故の刑事裁判で、宇都宮地裁は教師3人に禁錮2年の実刑判決を出した。
判決の構造
被告人3名について、安全区域限定義務違反、安全確保措置設定義務違反、計画内容周知義務違反・・・・・共同過失
被告人3名中2名について、即時退避指示義務違反、適時情報共有措置義務違反・・・・・・個別過失
コメント
・ほとんどの事故に関係者のミスや落度はあるが、ミス・落度=過失ではない。
過失がある場合でも、それに民事責任を科すか、刑事責任も科すかは、ある種の法的な価値判断である。どの範囲を刑罰の対象とするかは検察官が判断する。近年、起訴された山岳事故はすべて有罪になっている。
・予見可能性を緩やかに考えれば、ほとんどの事故で予見可能性が認められる。
結果を予見できたから責任を負うというよりも、結果を予見すべきだったかどうかが問われる。結果を予見すべきだったとすれば、予見可能だったとされ、注意義務が科される。
斜度30度以上の斜面に30センチ以上の新雪があったこと、訓練場所があいまいだったことなどから、雪崩事故の予見可能性が認められた。
・事故に対する3人の関与の程度は異なるが、裁判官は、3人の刑に差を設けることをしにくかったのだろう。この点を高裁がどのように判断するかが問題だ。
・雪崩を予見可能だったが、注意を怠って予見しなかったというのが、法律家の考え方だが、それはタテマエの理屈である。実態は、雪崩を予見できなかったから事故が起きたのである。もし、雪崩を予見していれば、講習を中止するはずだからだ。教師は、雪崩を予見できなかったが、雪崩を予見すべきだったので、事故に対し責任を負うのである。
・雪崩を予見できなかったのは、注意を怠ったからではなく、雪崩を予見する能力不足が原因である。3人の教師のうち、2人の教師は登山家と呼べるほどの経験はなかった。注意不足を指摘するだけでは雪崩事故を防ぐことはできない。雪崩対策には相応の能力が必要である。それがなければ、雪崩の可能性のある場所で講習をしてはならない。
・従来、学校関係の山岳事故で実刑になったことがなく、初めての実刑判決である。交通事故では、初犯でも2人が死亡すれば実刑になることが多い。それに較べれば、8人死亡の事故で禁錮2年は軽い。交通事故などに較べて山岳事故の量刑が軽いのは、自然的要因が関係するからだろう。
・近年、裁判所において、過失事故の厳罰化の傾向と、山岳事故の厳罰化の傾向があるが、それにそった判決である。安全であることに対する世論の高まりが背景にある。
・事故に直接関与した者だけでなく、事故現場にいない管理者の刑事責任を課した点が注目される。
自動車事故や原発事故でも、事故現場にいない安全管理者の刑事責任を問う傾向がある。従業員が自動車事故を起こした場合に、事故現場にいない会社社長や課長を安全管理者として起訴するケースが増えている。
「不作為」が刑罰の対象となり、明らかに過失責任を問う範囲が拡大している。検察官の起訴の範囲が拡大している。従来は起訴しなかった者を、近年、起訴するようになっている。起訴されると有罪になることが多い。
・事故現場にいない安全管理者が刑事責任を問われる傾向は、「管理者がもっと注意をする」のではなく、「誰も管理者や責任者にならない」傾向をもたらしやすい。
これは、例えば、
実行委員長不在の実行委員会がイベントを実施する
PTAなどで、会長や副会長、会長代行を置かない。
管理者不在の登山道
などがその例である。
会長、副会長、事務局長不在の協議会で、20人くらいの委員が共同作業を行えば、20名全員が起訴されにくい・・・・それが刑事責任回避の手法になりやすい。現実に、佐賀県で官民共同のサマーキャンプで、結果的に役員全員が無罪になったケースがある。これは集団的無責任の組織事故である。
・今後、ツアー登山や山岳団体の講習会などでの事故に関して、起訴されるだけでなく、被害者の数が多ければ、実刑判決になる可能性がある。
・危険を伴う活動は、学校、ツアー登山、講習会以外の形態で行う必要がある。高校生の場合は、学校以外の場所で親の管理下で行うべきである。
・今後、学校の部活動で危険を伴う活動はできない。雪山登山は高校ではできない。夏山でも事故の危険性がゼロではない。柔道やラグビーでも事故が起きると教師が刑事責任を問われる可能性がある。
・部活動は教師のボランティア的な業務であり、教師の義務ではない。ボランティア的活動に刑罰を科すと、活動従事者が減る。今後、学校の登山部の活動範囲の縮小や廃部が増えるだろう。
・教師の登校指導も、現在、教師のボランティア的な業務として行われているが、登校中に事故が起きると、教師が刑事責任が問われる可能性がある。欧米では、児童、生徒の登校は、学校ではなく、親の管理下で行っている。日本でも、児童、生徒の登校は親の責任において行う必要がある。
・国は、学校の部活動の指導を外部委託することを推進しているが、学校の顧問教師が安全管理することは変わらないので、外部指導者を採用しても法的な扱いは変わらない。外部指導者は顧問教師の補助者の扱いになる。外部指導者のミス=顧問教師の過失=学校の民事責任。教師個人は刑事責任。
・被告人は控訴すると思われる。
・欧米では、このような判決はない。欧米では高校山岳部がない。日本のような高校の部活動のある国は欧米にはない。アメリカのハイスクールの部活動は、学校外の専門家に委ねているが、高校山岳部はないだろう。ヨーロッパでは学校の部活動がない。生徒のスポーツは、学校の管理下ではなく、保護者の管理下で行われる。欧米では、教師は部活動に関与せず、教育に専念する。
日本でも、教師は部活動に関与せず、教育に専念した方が教育の発展に資するのではないか。
日本では、部活動=教育と考えているが、運動部の活動はスポーツであって、勉強とは異なる。
日本は、学校と会社中心社会。危険を伴う活動は、学校の管理を離れて学校外のクラブや保護者の管理下で行う必要がある。また、会社中心社会が仕事中心社会をもたらしている。男性の場合は、飲食、レジャー、冠婚葬祭、交友関係が会社中心であり、「元〇〇社員」の肩書が死ぬまで続く。「元院長」、「元裁判官」、「元〇〇大学教授」なども同じ。
2024年5月27日
「登山道を誰が管理するのか」 (デザインエッグ発行)
(目次)
はじめに
登山道が遭難に関係する
登山道の整備のあり方
登山道の管理
今後の課題と展望
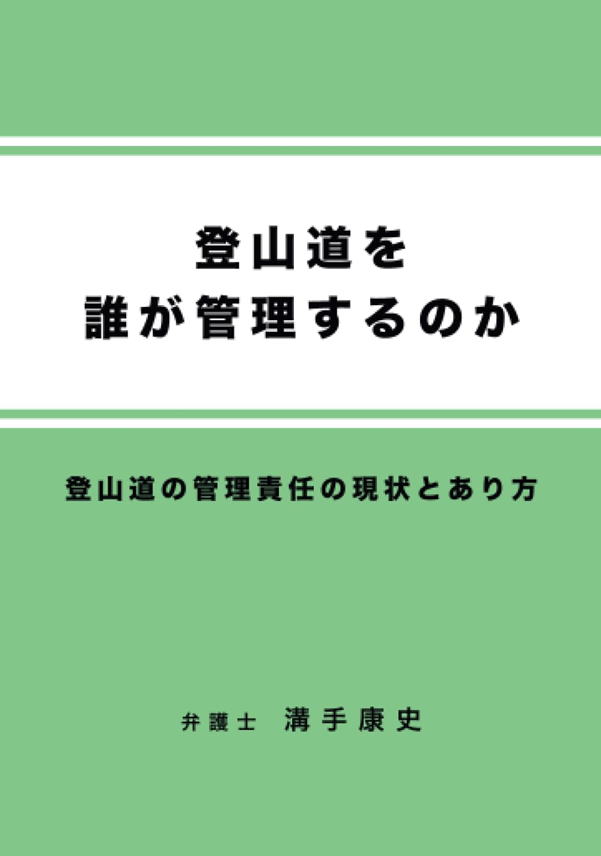
2024年5月25日
登山道に関する法整備の動き
令和5年 環境省による登山道整備の実態調査・・・・私もヒアリングを受けた。
登山道法研究会などの活動やマスコミの関心が高まる。
令和6年 衆議院・超党派「山の日」議員連盟が法制化に向けて、勉強会を実施・・・・私もヒアリングを受けた。
議員立法がなされることは間違いないが、その内容は未定
登山道整備や山岳地域振興を義務付ける漠然とした法律になるのではないか。法律で具体的なことを義務づけるには、関係法令との調整が大変だ。
イギリスのCountryside and Rights of Way Act 2000は1冊の本になるくらいの分量がある。これは具体的権利、義務、手続、罰則、土地所有権の制限、他の法令との調整規定が多いからだ。
2024年5月15日
衆議院・超党派「山の日」議員連盟総会でのヒアリング
東京
超党派「山の日」議員連盟
会長 衛藤征士郎衆議院議員
事務局長 務台俊介衆議院議員
議題:「登山道の管理不足と利用者の要求水準の変化について」
(ヒアリング)
北海道大学大学院農学研究院 教 授 愛 甲 哲 也
みぞて法律事務所 弁護士 溝 手 康 史
一般社団法人 北杜山守隊 代表理事 花 谷 泰 広
YAMANASHI MTB 山守人 代 表 弭間亮
総務省
林野庁
環境省
私は、登山道に関する法制度の現状と登山道の管理責任について話をした。
関係者の考え方はさまざまだろう。
環境省は環境保護を考え、自治体は地域振興(経済振興)を考え、山岳団体は、経済振興ではなく、登山振興を考える。山小屋や警察などは、事故防止を重視するだろう。
私は、登山に限らず自然へのアクセスの保障や環境保護は国民の幸福追求を実現し、個人の自立と自律を支え、民主主義社会の基礎を形成すること、また、それは人間の生存にとって必要だと考えている。
2024年5月12日
富士山登山通行料
富士山の山梨県側登山道では、7月1日から通行料2000円が必要になる。
また、入山者が1日に4000人に制限されるが、山小屋宿泊者は制限されないようだ。つまり、4000人の制限は、環境保護のためではなく、山小屋に宿泊しない登山者を規制するものだ。トレランや熟練者の日帰り登山、訓練などが規制される。
規制の趣旨があいまいだ。事故防止のためであれば、山小屋宿泊者の事故者も多いので、これが問題になる。富士山では初心者登山者が多いことが、事故の最大の原因だ。山小屋の数が多すぎるのだ。山小屋の数が少なければ、初心者登山者が減り、事故も減る。
弾丸登山の制限は、事故防止ではなく(山小屋宿泊者の事故者も多い)、単に、山小屋が儲からないから制限するということのようだ。
世界の潮流は、事故防止ではなく、環境保護のための登山規制である。
登山者が多すぎることが環境破壊の原因である。弾丸登山者の数は知れており、弾丸登山が環境破壊の原因ではない。
山小屋宿泊者が無制限では、環境保護にならない。
環境保護のために登山を許可制にするのが世界の潮流だが、日本は世界の潮流から孤立している。
2024年5月2日
犬伏山(791m)・・・・・手入されない登山道の典型
広島県安芸高田市にある犬伏山に登った。
これは、ヤマップで見て、笹で登山道が見えにくい山とされていたので、調査のために登った。
登山道は、全体の3分の2が笹で覆われて見えなくなっていた。3分の1は笹に隠れているが、何とか登山道の痕跡を見分けられる。他は、登山道の痕跡が見えない。
看板は倒れて笹の下にあるか、成長した笹に隠されている。
登山道のうち1割くらいは、笹がなく、すっきりとした快適な登山道の箇所がある。笹を刈れば快適な登山道なのかもしれない。
登山道が笹に埋没しているので、地図、コンパス、GPSで確認しながら進む。ところどころに、赤いリボンがあるので、これも参考にする。リボンの数が少ないので、あくまで補助的なものでしかない。
林道は、倒木があり、車は通行できない。その先に駐車場の看板がある。
ネット情報は、令和2年~4年頃の情報でり、現在は笹がさらに成長している。腰~頭くらいの高さの笹の中を泳ぎながら進む。
笹に埋没し、展望はない。山頂も展望ゼロ。
問題は、林道入口や駐車場に、登山道の看板がある点だ。この看板を見れば、登山道があると思って初心者が入り込む可能性がある。初心者は道迷いする確率が高い。
これは登山道の看板に「騙される」のあり、日本ではよくあることだ。これに陥ると遭難する。
犬伏山が藪山として有名になるのはかまわないが、その場合は、「登山道は笹のために見えません。道迷いの危険が高いので、初心者は登らないでください」という危険表示が必要である。初心者に登らせないための管理が必要だ。
笹漕ぎとルートファインディングを楽しみたい人以外は、登らない方がよいだろう。
 登山道は直進しているが、笹の下にあり、登山道が見えない。こういう箇所が続く。
登山道は直進しているが、笹の下にあり、登山道が見えない。こういう箇所が続く。
2024年4月4日
落雷事故
4月3日に、宮崎県でサッカー中の落雷事故が起きた。
雷鳴や雷雲などの落雷の予兆がある場合には、管理者に損害賠償責任が生じるというのが判例だ。
今回は、その予兆がなかったが、落雷が予見できたかどうかが争点になる。落雷注意報は出ていたようだ。
予見できたかという議論は、禅問答に近い。
数年後に民事裁判になるだろう。なぜ数年後かといえば、日本では、すぐに裁判することはしないからだ。アメリカでは、事故の数週間後に裁判を起こすことがあるが、日本では、事故の検証や第三者委員会などが先行する。消滅時効が迫って訴訟提起する。山では、夏はたいてい落雷注意報が出ており、たいてい午後は積乱雲がある。それだけで落雷の予見可能性があるかどうか。山ではほとんどの場合に、落雷の予見可能性が認められ、限りになく無過失責任に近づくだろう。
学校事故でも、裁判所の考え方は、実態としては無過失責任に近づいている。防ぎようのない事故でも、過失があったとみなされる。これは、学校は安全でなければならないという社会的価値観を裁判所が重視するからであり、ある種の価値判断だ。日本はそういう社会であり、裁判所は逆らえない。
学校では無過失の補償制度が必要ではないか。労災補償のような制度だが、それでも学校の責任を追及する裁判がなくなることはないだろう。
2024年3月28日
アメリカでの橋梁事故・・・・救助活動打ち切り
3月26日に事故が起き、その夜、警備隊が救助活動を打ち切った。・・・・日本人から見ると、救助活動の打ち切りが早すぎると思うのではなかろうか。
一般に、公的な救助活動は、生存の可能性がなければ打ち切られる。
日本でも同じであり、冬山遭難では、警察、消防の捜索、救助活動は数日で打ち切られる。遭難対策協議会も警察に連動する。あとは、遭難者の家族や友人らが捜索を行うほかない。
救急車は、事故直後であれば搬送するが、死亡を確認した場合は、被害者(遺体)を搬送しない。遺体搬送は家族がマイカーか霊柩車で搬送する。タクシーも遺体搬送を拒否する。病院も遺体を病院者車で搬送してくれない。多くの場合、救助隊員が死亡を確認していないことにして救急車で搬送し、病院で死亡を確認する。
ただし、日本では、警察、消防は政治で動くので、御嶽山の噴火事故、自衛隊関係の海難事故などでは、政治的な判断から1年以上も捜索活動が続けられた。これは特別扱いである。1年後も生存の可能性があったということではない。
山岳事故でのこのような特別扱いは、ほとんどない。雪崩事故の場合は、警察が生存の可能性があることにして、長時間、捜索することがあるが、不公平感は否めない。
冷たい海水に落下すれば、数十分で死亡するので、アメリカの公的救助機関は法律に忠実に生存の可能性がなくなれば、あっさりと捜索を打ち切るようだ。
日本であれば、公的機関が数日間は捜索して「救助」し(救助活動なので、遺体発見とは発表できない)、病院に搬送して死亡を確認するだろう。
2024年3月20日
登山リーダーの責任・・・・オンライン講義
日本山岳スポーツクライミング協会・夏山上級リーダー講習会(関東地区)
実施日 2024年3月20,23,24日
2024年3月18日
北海道新聞の記事
3月12日の北海道新聞の羊蹄山雪崩事故に関する記事に、僕のコメントが掲載されている。
記事では、「事故防止を目的とした冬山の規制は国内外でほとんど例がない」というコメントに
なっているが、僕が述べたのは、法的な規制についてである。
法的規制ではなく、行政指導による規制は日本では多い。富士山の冬山登山の禁止などが、行政指導による冬山登山の禁止の例だ。しかし、冬山登山の法的な規制は、群馬県と富山県の登山条例くらいのものだろう。バクカントリースキーの法的な規制はほとんどないが、法行政指導による規制は多いかもしれない。
法的規制と行政指導を区別することが重要だが、これを混同する人が多い。
2024年3月13日
バックカントリースキーの規制
事故防止のためにバックカントリースキーを規制すべきだという声が一部にある。世界では、エリアを定めて環境保護のために許可制にする場合がある。
アメリカの富士山ことホイットニー山では1日の登山者が100人程度に制限されている。しかし、欧米では、環境保護のために登山を許可制にすることは多いが、事故防止のために規制することはほとんどない。バックカントリースキーの規制はほとんどない。
夏の富士山で事故防止のために登山を規制すべきだろうか。
富士山では環境保護のためび登山を規制する必要がある。
事故防止のために登山を規制できない理由
・規制するのは危険な行為である。包括的にすべて禁止することは過剰な規制であり、憲法に違反する。バックカントリースキーでは危険性の程度が地形や雪の状況、時期次第で変化する。固定的なものではない。降雪直後は危険でも、数日すれば雪が安定して危険でなくなる。2月は危険でも、3月は安全なコースがある。危険かどうかを誰が判定するのか。役所が判定するとすれば、役所に専門家を置かなければならない。事故防止のノウハウは役所にはない。アウトドア活動の素人の公務員では判断できない。
・役所が危険かどうかの判断をすることは危険である。これは、中国が危険な行為を取り締まることをイメージすればわかる。国家にとって不都合な行為を規制することになる。
・事故防止のために登山を規制しても、事故は減らない。富士山がその例だ。富士山では事故が増えている。
・効果のないことをするのは税金の無駄だ。規制をするには、役所の人件費がかかる。公務員のサービス残業で扱えば別だが。
・規制は、違反者に刑罰を課さなければ効果がない。危険な行為を処罰する国家は「危険国家」である。中国、ロシア、北朝鮮、戦前の日本がその例だ。
・日本では、行政指導としての禁止が多いが、これは、法的拘束力がなく無意味だ。アウトドア活動を禁止すると先進国と言えないので、それはできず、拘束力のない「禁止」をする。この禁止は国民には効果を持つが、対外的には、「日本は法的には国民のアウトドア活動を制限していません」と弁解できる代物であり、悪質である。日本の政治にはこのようなゴマカシ、いい加減さが多い。
・行政指導は欧米では稀であり、欧米人は行政指導としての禁止を理解できない。行政指導は、それに違反しても違法ではない。欧米人は、「できるのか、できないのかどちらなのか」と考える。行政指導は、法的には「できる」が世論から「禁止」だとして叩かれることを意味する。
・山岳スキーがオリンピック種目になったが、バックカントリースキー人口が増えれば、山岳スキー競技が強くなる。クライミング人口が増えれば、オリンピックのクライミング種目が強くなるのと同じだ。オリンピックでやたらとメダルをとりたがる日本人は、バックカントリースキーの規制ができないのではないか。
・バックカントリースキー事故で亡くなる人は多くない。年間、20人もいないのではないか。マスコミが大きく報道するので、j事故が多いと感じる人が多い。海難事故で年間700人くらい亡くなっているが、「海水浴を禁止しろ」と言う人は少ない。役所が努力しても海難事故がなくならない。事故防止のノウハウは役所にはない。
事故防止のためにできること
・行政ができることは、アウトドア活動の規制ではなく、警告表示、登山道の管理などである。アメリカやカナダでは、自然公園をフロントカントリーとバックカントリーに分け、前者はトレイル、標識などを整備し、後者は整備ではなく危険表示をする。カナダには、橋や標識が一切ない国立公園があり、危険だが、禁止しない。その代わり入山料100ドルを徴収し、入山者に約1時間の危険性の講義を行う。
・危険が生じれば、役所はトレイルをクローズするが、これは通行禁止ではない。欧米では、日本的な法的拘束力のない「禁止」はない。役所は危険情報を提供する。
・アウトドア団体や研究機関が、講習会、事故防止のノウハウ、研究活動、啓蒙活動を行っている。
2024年2月25日
伊吹山での事故
伊吹山で落石による死亡事故が起きた。
これに関して、伊吹山は、「登山禁止」、「入山禁止」、「伊吹山は登山自粛」などの報道がなされた。
「登山禁止」、「入山禁止」、「登山自粛」、「登山道の通行禁止」、「登山道の閉鎖」は、意味が異なる。
「登山禁止」は、登山はダメだが、観光などは認められる。
「入山禁止」は、観光で進入するのもダメ
「登山自粛」は、あくまでお願い、行政指導であり、拘束力がなく、登山をしても違法ではない。
「登山道の通行禁止」は、登山道以外の場所であれば、登山が可能。冬は登山が可能。
「登山道の閉鎖」は、禁止ではない。
これらを区別しなければ、法治国家とは言えない。
法律的には、おそらく、登山道の通行の自粛、もしくは登山道の閉鎖ではないか。これは、行政指導。
また、雪が積もれば、登山道が埋没するので、閉鎖は無意味になる。
管理する側からすれば、やたらと禁止を使いたがる。禁止すれば、許可された行為だけができる。これは、人は生まれながらにして不自由であり、国民は、国家から、許可された行為だけができるという考え方であり、江戸時代はこのような支配体制だった。明治以降も、似たようなものであり、現在でも、実態はこれに近い。学校や、会社はこの考え方だ。長谷川恒男が、「学校は刑務所のようだった」と述べたのは、このような意味だろう。
2024年2月23日
外国人登山者の遭難
外国人登山者の遭難の報道が多い。
外国人登山者の遭難件数の正確な報道はないが、おそらく増えているのだろう。富士山登山や北海道でのバックカントリースキーで外国人の遭難事例が多いようだ。
このような遭難がある度に、日本的な非難がなされるが、それでは遭難は減らない。
外国人の観光客が急増しているが、外国人の観光客が増えれば登山者も増える。「外国人の観光客を増やしたいが、登山者は増えてほしくない」が自治体のホンネかもしれないが、それは無理である。富士山などでは観光客と登山者を区別できない。ニセコでも、外国人スキーヤーがコース外滑降をするのだ。コース外滑降を禁止しても、バックカントリースキーを法的に禁止できない。
バックカントリースキーを禁止することは登山を禁止することを意味し、登山を禁止すれば日本は先進国の仲間入りができなくなる。中国やロシアですら、登山を禁止していない。北朝鮮であれば、登山を簡単に禁止できる。
登山を禁止すれば、観光を禁止することになる。登山と観光は区別できない。これは、観光登山や、高尾山、富士山、尾瀬、阿蘇山、上高地などのハイカーを考えれば、理解できるだろう。高尾山を歩く人は観光客なのかハイカーなのか。ハイキングは登山の一形態である。
外国人の観光客が増えれば登山者も増える。登山者が増えれば、事故も増える。これは避けられない。
欧米では、山岳事故の救助活動は役所が行っても、、山岳事故の防止は役所の仕事ではなく、もっぱら民間団体が行う国が多いようだ。役所が登山届を受理しない国が多い。欧米では、登山届は家族や山岳会などに出すべきであり、役所に出すことはないようだ。なんで、役所が個人の行動のことまでいちいち心配してやらなければならないのか?余計なお節介だ、という考え方。 日本とは発想が違うのだろう。
2024年2月2日
「登山道の管理や法的責任」講演
福島県、郡山市
環境省ロシアと中国のロシアと中国のロシアと中国
郡山市は遠方なので、2泊3日の旅行になった。
この日の郡山は非常に寒かったが、参加者は約130人。
参加者は、国、市町村、県、観光協会、山小屋などの関係者、山岳ガイドなど。
登山道の管理の問題に対する関心の高さがよくわかる。

2024年1月
キリマンジャロ登山
年末年始、キリマンジャロ(5895m)に登った。
18年前頃から、高校の同級生でキリマンジャロに登る計画があった。
当初、60歳になって行く計画だったが、雇用延長などで実現しなかった。
次に、65歳になれば、ヒマになるのではないかと思われたが、コロナの影響で実現しなかった。
そして、68歳の今、実現した。
外国の高山に登りたいという人は多いが、たいてい願望だけで終わる。願望を実現するには、意欲が必要だ。
11日間の休暇をとることは、要職にあるサラリーマンには難しい。ようやく仕事から解放されると、年齢的に、体力、気力が衰えていることが多い。
しかし、今回、これが実現したのは、意欲が勝ったからだろう。
キリマンジャロは歩いて登ることができる山であり、特別な技術はいらない。日本国内で15キロくらいの荷物を背負って数日間の縦走登山をしている人には、キリマンジャロは難しい山ではない。ダイアモックスを飲めば、高度障害もほとんど出ないだろう。この日は、キリマンジャロの稜線にけっこう雪があったが、通常はキリマンジャロの稜線に雪はない。
 この日の行動時間は、午後11時出発で、約17時間だった。夜中、降雪の中を行動した。
この日の行動時間は、午後11時出発で、約17時間だった。夜中、降雪の中を行動した。


 廃村八丁
廃村八丁