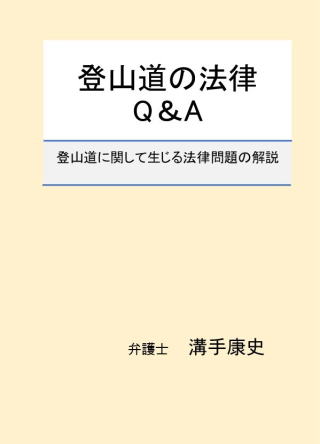2025年 溝手康史
2025年12月18日
本の出版
「緊急時に登山者はどう行動すべきか 登山者の緊急時の倫理、法律、リスク回避 」、デザインエッグ、2026、1309円、2026年1月5日発行
アマゾン、楽天などで注文可能

(目次)
◆登山中の置き去り
富士山での「置き去り」事件 / トムラウシでの「置き去り」事件 / エベレストでの「置き去り」事件 / アコンカグアでの「置き去り」事件 / 「置き去り」の刑事責任 / 「置き去り」の民事責任 / 緊急時の行為の違法性 / 倫理と法的な義務
◆捜索、救助活動
ボランティア活動と職務行為 / 登山仲間の捜索、救助活動 / ある救助活動の思い出 / 山岳遭難対策協議会所属の民間人の捜索、救助活動 / 山小屋従業員の捜索、救助活動 / たまたま遭遇する登山者への援助 / パーティー内での相互援助 / 救助義務
◆その他の緊急時の行為
緊急時の行為は多様 / レジャーとしての山歩きとアルピニズム的な登山
/ 立山での遭難 / 2009年のトムラウシでの遭難
/ 幌尻岳での事故 / 愛別岳での事故 / 大峰山での道迷い遭難1 / 大峰山での道迷い遭難2 / GPS機器と読図 / 裏山で遭難か / 冒険性と緊急時の判断 / 山小屋への侵入行為 / 緊急性を利用する犯罪 / 落石をよけようとして他の登山者に衝突 / 遭難者の緊急行為 / 自然公園法と緊急時の行為
◆緊急時の業務行為
業務とそれ以外の行為の違い / 緊急時の医師の医療行為 / 緊急時の警察官、消防職員 / 警察の救助活動中の事故 / 消防の救助活動中の事故 / 緊急時の山岳ガイドの活動 / 緊急時の教師の活動 / 大朝日岳での熱中症事故 / 西穂高岳での落雷事故 / 官民共同の活動
◆
緊急時の判断と行為
緊急時の判断と行動の選択 / 自己責任と救助行為 / 緊急時の判断と行動のリスク
2025年11月
「凪の人 山野井妙子」(柏澄子、山と渓谷社)
「凪の人 山野井妙子」(柏澄子、山と渓谷社)を読んだ。
この本には、山野井妙子さんの厳しいクライミングと登攀が次々と出てくるので、まず、それらの登山の質、数、内容に圧倒される。しかし、それだけでなく、登山以外の「生活」の部分が非常に印象的だった。
それは、家事や畑仕事をし、山に登るというただそれだけのことだが、そこには、「人間が生きるために必要なことは何か」を考えさせる「生きる哲学」がある。もっとも、彼女は、そんな大げさなことはまったく考えていない。ごく自然に当たり前のように生活し、苛酷な登山を楽しんでいるようだ。
「SNSを見ない、他人と比較をしない、他人からどう見られるか気にしない」ことひとつとっても、今の日本では難しいことだが、彼女にはごく自然なことなのだ。
彼女の自然で単純な生活の根底に、生きる力や生活力がある。それがギャチュン・カンからの壮絶な脱出を始めとする多くの登山に表れているのだろう。
この本は、過去の日記、記録、関係者からの丹念な聞き取りなどにより、正確で中身の濃い内容になっており、楽しく読むことができた。
映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」
映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」を観た。
田部井淳子のエベレスト登頂、その後の登山隊内の対立、親子の確執、東北大震災、病気との闘い、夫婦の絆など盛りだくさんの内容の映画だ。
田部井淳子さんの本は、昔、いくつか読んだことがあるが、内容はあまり覚えていない。
映画の最後にこの作品はフィクションだという字幕が出るが、吉永小百合、佐藤浩市、のんなどの役者が、それぞれ個性的な演技をすれば、実在の人物とは異なる人間像になる。
吉永小百合さんは登山が趣味であり、田部井淳子さんと親しかったことから、田部井淳子役をすることになったのではないか。
映画は「現実」とは異なる別の作品だが、映画のストーリーは概ね、実際にあった出来事に基づいているようだ。
山岳映画として見れば物足りない部分があり、内容を欲張り過ぎた印象があるが、映画の主要なテーマは家族の関係や絆を描いた点にある。その点で多くの人が感銘を受けるだろう。
2025年10月1日
ある名言
以前、女優の綾瀬はるかさんが、あるテレビ番組の中で、「仕事でミスした時は、『まあ、いいか、別に死ぬわけじゃないし』と考えることにしている」と言っていた。
私はこれを聞いて、「名言だ」と思った。たとえ演技でミスをしても、それで人が死ぬわけではない。学校の校則に違反しても、それで人が死ぬわけではない。裁判所は細かい手続きに少しでも反していると大騒ぎをするが、私は、「それで人が死ぬわけじゃないのに、なぜ騒ぐのか」といつも思う。
誰でも、仕事などでミスをし、あるいは、うまくいかないことがあるが、「それで人が死ぬわけじゃない」と考えれば、ずいぶん気が楽になる。しかし、日本では、ミスをした当人が、「それで人が死ぬわけじゃない」と言えば、几帳面な関係者は激怒するかもしれない。
他方、登山、アウトドア活動、医療、輸送業務などの場面では、ミスが人の死につながることがある。そこでは、「人が死ぬわけじゃない」ではなく、「人が死ぬことがある」という危機感が必要だ。
人の生死にかかわる場面かどうかの判断が重要だが、しばしばその判断を間違える。多くの死亡事故が全く想定外の場合に起きる。それでも、裁判などでは、後知恵から、「事故は予見可能だった」とみなされることが多い。
規則、規程、マニュアル、コンピューターなどは、あらゆる事柄を一律に扱い、人の生死にかかわる重要性の判断ができない。臨機応変にこの判断ができるのは人間だけだ。アウトドア活動などで自然と関わることが、この判断力を養ってくれる。
「判断力を養う過程」自体に、自然がもたらすリスクがあるのが登山。登山教室などで「大きな教育効果」を上げようという熱意が事故につながることがある。少しずつステップアップすることが必要だが、自重したつもりでも、無理をしていることがある。後で「あれは、実は、危なかった」ことに気づくことが、多々ある。
国立登山研修所が、警察庁・山岳事故データ分析
国立登山研修所が、警察庁の2021~2023年の山岳事故データや10年前との比較などの分析結果を公表した。これは、登山研修所のウェブサイトに掲載されている。
若年者の道迷いが減少し、高齢者の転倒・転滑落は依然として多いが、都道府県別に見れば、道迷いや転倒・転滑落の割合が大きく異なることなど、貴重な分析がなされている。
また、登山人口は約860万人、年間延べ登山回数は約4300万回と分析されている。
日本の1年間の山岳遭難件数は約3000件であり、山岳事故の事故率はそれほど高くない。この事故率の低さが、登山者に、「山岳事故は滅多に起きない。他の人に事故が滅多に起きないのだから、自分も事故に遭わないだろう」という安心感をもたらすのではないか。この点は、自然災害に対する慢心に似ている。
しかし、わずか数回の登山で事故に遭う人もおり、そういう人にとって事故率は非常に高い。他方で、何十年登山をしても、事故に遭わない人もいる。事故に遭うかどうかは登山者の個人差が大きいが、この点は統計数値に表れにくい。
山歩きをする登山者の多くは、「人間の能力にそれほど違いはない。他の人にできるのだから、自分もがんばればできるはずだ」と考え、無理な登山をしやすい。「登山は誰でもできる」と考え、初めての登山で富士山に登る観光客がいる。ネットには、「簡単に登った」という情報があふれている。
日本語の「がんばる」、「安心」、「他人並み」などの言葉は、登山でもそれ以外の場面でも、弊害をもたらしやすい(「がんばる」や「安心」には、日本特有の意味があると言われている)。
能力があってもなくても、登山者が自分の経験、体力、技術にふさわしい登山をすれば、事故は滅多に起きない。かなり登山経験があって、自分の能力を超える登山をすれば、事故が起きやすい。「慢心」や「過信」もある。
冒険的な登山はもともと事故のリスクがあるが、登山者の大半は、そうではなく、登山道を歩くので、登山者が自分にふさわしい登山道を選択する環境作りが重要だろう。
https://www.jpnsport.go.jp/.../zenzanso/20250731nagano.pdf
緊急銃猟
登山道は「人の日常生活圏」ではなく、「緊急銃猟」の対象ではないということだが、上高地などの歩道は「人の日常生活圏」に入るだろう。
山小屋(旅館業法が適用される)、キャンプ場、観光地、車道、遊歩道、牧場、田畑などは、「人の日常生活圏」に入ると思われる。ただし、観光地化した登山道と遊歩道との区別がつきにくい。登山者で渋滞する登山道と混雑するキャンプ場の違いはあまりない。そのうえ、熊は簡単に移動する。
一般に、法令は、役所の「画一的な管理のしやすさ」を重視して基準を設けることが多い。その観点から「人の日常生活圏」を緊急発砲の区別の基準にしたのだろう。
しかし、本来、発砲駆除の必要性、合理性、人命被害の切迫性、緊急性などで決めるべきではないか。「人の日常生活圏」の要件では、人命への被害が切迫した場面で、自治体職員が発砲指示の判断を迷いやすいのではないか。
刑法上の緊急避難に該当する場合には、銃使用の違法性がないので、登山道付近で人が熊に襲われた場合に、発砲しても違法とは言えない(登山道で駆除しろという意味ではない。ハンターに義務はない)。
法律は、人間が頭で考えて作ったものであり、必ず法律の適用範囲のあいまいさが生じる。国は、最も合理的な制度を作る必要がある。
2025年9月3日
害獣駆除
行政は、害獣駆除で発砲しても、ハンターに責任が生じないという説明で、ハンターに安心感を与えようとしている。
自治体職員が指示した場合でも、通常は、ハンターのミスによって事故が起きる。この場合、ハンターに刑事責任が生じやすい(自治体職員が誤射を指示すれば、自治体職員が刑事責任を負う)。
民間人に害獣駆除の義務はない。責任を負いたくなければ、害獣駆除を引き受けないことだ。
日本では、行政の仕事を補完する「義務的ボランティア活動」が多く、これらは断りにくいが、「責任を負うのが嫌なら、しない」ことが必要だ。
自治体主催の市民ハイキングなどのリーダーをボランティアで引き受ける場合でも、引き受ければ責任を負う自覚が必要だ。
「善意」であれば、責任が生じないということではない。
ただし、多くの人がさまざまなリスクに挑戦した結果、社会が発展してきたのであり、責任を負うことを恐れてはいけない。また、その結果としての「失敗」に対し、社会は寛容であるべきだ。
2025年9月1日
富士山条例
富士山の山梨県側では、「県職員が、富士山の登山者に「入山を禁止できる権限が付与された」、「サンダルや短パンなどの軽装登山者の入山に際し、県職員が登山者に、入山を禁止できる権限が付与された」などと報道されている。
「山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例」には、登山道の利用、管理に支障を及ぼす行為や、時間外登山などの禁止や利用拒否の規定がある。
しかし、この条例に罰則規定はなく、また、この条例は県道である登山道の管理に関する規定であり、登山道以外の場所を歩く登山者にこの条例は適用されない。つまり、「登山道」利用の規制であって、「入山」規制ではない。
条例に罰則がないのは、条例で法律以上の罰則を科すことができるのかどうかの問題や、罰則の対象行為があいまいなことなどが関係している。
このような問題があるので、実際には、指導にとどまっているのだろう。
しかし、記事のように、県職員に「入山禁止の権限」があると勘違いする人が多いだろう。無謀な登山は、当然、すべきでないが、登山の規制を正確に理解することは重要だ。
2025年9月1日
ハンターの誤射事故の責任
ハンターの誤射の責任が議論されているが、ハンターは自治体職員ではく、ボランティアもしくは自営業者なので、誤射に過失があれば、ハンターの損害賠償責任が生じる。ハンターは損害賠償責任保険に加入する必要がある(組織で加入すればよい)。
自治体はハンターの発砲を強制できない。ハンターは自分の意思で発砲するかどうかを決めるが、発砲すればその責任を負う。
緊急駆除の場合に自治体が損害を補償する制度があるが、自治体がすべての損害を補償するわけではない。
ただし、害獣駆除でハンターが公務員の指示によって発砲する場合には、ハンターを自治体の活動の補助者とみなし、国家賠償法に基づいて自治体が損害賠償責任を負い、ハンターは責任を負わない扱いが可能だろう。
誤射事故が起きれば、ハンターが業務上過失致死傷罪に問われる可能性がある。これが原則である。
国は猟友会などに「通常、害獣駆除に従事するハンターに刑事責任は生じない」と説明しているようだが、これは紛らわしい説明だ。害獣駆除にあたるハンターが公務員の指示に忠実に従う場合には、発砲は公務員の判断によるものであり、ハンターではなく誤射を指示した公務員の業務上過失致死傷罪が問題になる。それを除けば、発砲は発砲者の責任であり、それが嫌なら「発砲を拒否する」ことが必要だ。
また、法令に基づいて、行政処分として、狩猟免許や猟銃免許の取り消しがなされることがある。
以上の点は、交通事故の場合の民事責任、刑事責任、行背処分(減点、免許取消処分など)と同じ考え方になる。
過去に、ハンター間の誤射事故やハイカーへの誤射事故がある。
遠くで銃声や猟犬の鳴き声が聞こえる場合には、ハイカーは注意が必要だ。鈴の音はハンターに聞こえないので、私は、藪山では、クマ、イノシシ対策も兼ねて、笛を吹くなどしている。
ハイカーへの誤射は、おそらく、自分の乗った飛行機が墜落する確率よりも低いのではないかと思われ(データはないが)、それほど心配していない。
銃の誤射による事故では、被害者に落度のある場合や不可抗力の場合を除き、「誰かに責任が生じる」ことが多い。法的責任には、社会を納得させる手段の性格がある。責任の発生を心配するよりも、事故が起きない工夫の方が重要だ。
2025年8月26日
簡単に保釈を認めない日本の裁判所
機械メーカー「大川原化工機」の刑事事件で、勾留中に保釈が認められず、被告人が胃がんで亡くなった。
メディアは、警察、検察の責任を問題にしているが、保釈の判断をするのは裁判所であり、裁判所の責任が大きい。この点に触れるメディアは少ない。
裁判所は、被疑者や被告人が無罪を主張すれば、勾留を継続し、保釈を認めないことが多く、それが問題だ。
山岳事故に関して、時々、刑事責任を問われるケースがあるが、関係者が長期間勾留されれば、自営業者は倒産し、まともな病気の検査、治療が受けられず、死ぬことがある。無罪を主張すれば、家族との面会も禁止されることが多い。そんな非人道的なことがあってよいのかと思うが、それが現実だ。裁判官は、自らが勾留されることがないので、勾留を軽く考えやすい。
これまで山岳事故などで起訴されたケースはすべて在宅事件だった。つまり、逮捕、勾留されていないということ。もっとも、2012年に那智の滝を登ったクライマーが軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたケースがあるが、軽犯罪法違反は原則として現行犯逮捕できないので、逮捕は違法であり、すぐに釈放された(その後、不起訴になった)。
日本では、逮捕、勾留が世論へのみせしめ、制裁、政治的パフォーマンスとして行われる傾向がある。世論から叩かれると、再起不能な損害を受けやすく、警察、検察が世論を主導する。
長期間勾留することが当たり前の日本の司法は、先進国では異常だ(トランプは刑事事件で起訴、勾留されたが、即日、保釈された)。
2025年8月23日
熊出没とキャンプ場の閉鎖
薬師峠キャンプ場(太郎平キャンプ場)に熊が出没したため、キャンプ場が閉鎖された。
以前、上高地の小梨平キャンプ場でも、熊が出没したため、閉鎖されたことがある。これは熊による被害を防ぐためだが、キャンプ場管理者が法的な管理責任を問われないためでもある。役所は責任を負うことを恐れる。キャンプ場閉鎖後は、縦走登山者は、適宜、「ビバーク」するほかない。緊急時のビバークや登山は禁止できない。
日本では、熊被害に限らず、少しでも、キャンプ場に危険が生じれば、キャンプ場が閉鎖される可能性がある。
アメリカやカナダでは、キャンプ場に熊が出没することが珍しくない。しかし、それによって、キャンプ場やトレイルが閉鎖されることはほとんどない。その代わりに、熊に関する危険表示、食べ物の保管やゴミ処理に関する自然公園の規則やキャンプ場規則が厳しい。食料は専用の缶に入れること、食料を高い木の枝から吊すこと、缶の携行の義務づけ、ゴミ処理の方法などを規則で細かく規定している。アメリカやカナダでは、キャンパーの自己責任の範囲が広いが、それは熊対策の自己規律が前提である。キャンプ場の管理者が危険表示をすれば、キャンパーが熊に襲われても、管理責任は生じない。
しかし、日本では、熊によってキャンパーが被害を受ければ、キャンプ場の管理責任が生じる可能性がある。これまで、裁判になったケースがないが、キャンプ場で熊被害が起きれば、裁判所は、キャンプ場の管理責任を認める可能性がある。
日本では、危険表示をしていても、それによる免責を裁判所が認めることは稀だ。消費者契約法は、包括的免責条項を無効と規定している。日本の社会は自己責任を嫌うが、そこには自己規律の欠如が当たり前の社会状況がある。裁判所は、このような社会状況に基づいて判断する。
この傾向は、行政が、危険性を伴うアウトドア活動を制限する傾向にも表れている。役所は、パターナリズムに基づいてアウトドア活動を規制する。また、世論も、事故が起きれば、必ず、登山禁止などの意見が出る。
これらの点が、日本でのアウトドア活動の発展の障害になっている。
他方で、近年、労働、福祉、教育などの場面では自己責任論が主張され、山岳事故が「自己責任である」として世論から非難される。
これは、日本で、自己責任の考え方が正しく理解されていないことが関係している。
登山者の自己規律を支援(アメリカのキャンプ場規則などがその例)したうえで、自己責任に基づくアウトドア活動を広く保障する必要がある。
2025年8月11日
競技団体のコンプライアンスについて
広陵高校をめぐる一連の騒動と同様のことは、山岳競技でも起こる可能性がある。
山岳団体に加盟する団体で暴力事件等があった場合、競技を主催する山岳団体の対応が問題になるが、山岳団体は、団体の規定に基づいて加盟団体を処分すれば足りる。
「出場辞退」は、世論の非難、誹謗中傷、同調圧力などに基づく日本的な現象であって、競技団体の処分に「出場辞退」はない。
高野連は、加盟団体の不祥事を公表するかどうかに関する規程を設けており、それに基づいて広陵高校の暴力事件を公表していなかった。この点に、コンプライアンス上の問題はない。
高野連は公益財団法人、JMSCAは公益社団法人であり、財団法人は加盟団体、社団法人は社員(会員)のための民間団体である。この点で行政機関と異なる。これらの団体は、加盟団体や会員に関する個人情報を保護する義務がある。大学や企業も同じだ。
公益性のある大会では、公益性と個人情報保護のバランスに基づいて、どこまで国民に情報を公開するかを判断することになる。日本では、事件を公表すると誹謗中傷の対象になりやすいので、慎重な運用が必要だ。
世論の誹謗中傷や脅迫は、侮辱罪、名誉棄損罪、脅迫罪などの犯罪に該当する可能性がある。誹謗中傷や脅迫行為に対し、厳正な法的措置が必要だ。
学校での暴力やイジメについては、加害者の責任は当然生じるが、現段階では、学校や教師に、管理義務違反、いじめ防止法違反などの責任が認められるだけの証拠はないようだ(現在、第三者委員会で調査中)。競技団体は、「確定された事実」をもとに、規程に基づいて対処すべきであり、世論の誹謗中傷やあやふやな事実に基づいて判断することは、コンプライアンス違反になる。
2025年7月1日
富士山の閉山期間中の入山料
富士山で、山開き前に入山料を払わずに登る登山者が問題になっている。しかし、条例は、山開き中についてのみ規定しているので、それ以外の期間に入山料(山梨県は通行料)を徴収できない。夏季以外の期間については、ガイドラインが規制するが、これは拘束力がない。
現在の非常に複雑でわかりにくい方式で、1年間を通して通行料・入山料を徴収するのは無理だ。これをするには、土地所有者である国と神社などの同意を得る必要があるが、不思議なことに、富士山でのこれまでのさまざまな規制を推進してきた「富士山における適正利用推進協議会」に神社は加入していない。富士山の八合目から上は神社所有だという最高裁判決が確定した後も、長年、神社に登記がなされていない問題もある(現在も未登記だと思われる)。
2025年6月30日
自己責任について
自己責任は、法的には、他人に損害賠償責任などの法的責任が生じないことをいう。日常用語としては、自己責任は、自分の行動に自分で責任を持つという程度の意味だろう。自己責任に非難の意味はない。
しかし、日本では、「自己責任である」という言い方で事故の当事者を非難する人が多い。そこでは、「責任」が「悪い」という情緒的な意味で使用され、「自己責任=自分が悪い」という意味になる。
人間行動は自己責任が原則であり、登山もそれに含まれる。欧米では、自己責任の領域に国や自治体はあまり介入しない。自己責任の領域は個人の自律的行動に支配され、そこでは人間の賢明さが必要になる。賢明でなければ、自律的に行動をしても、ものごとがうまくいかない。誰でも賢明に行動できることが近代市民社会の前提だが、現実の人間はそれほど賢明ではない。富士山などで事故が多いのはそのためであり、戦争も同じだ。
山岳事故の防止は自己責任なので、欧米では、国や自治体は事故防止にあまり介入しない。日本でも、山岳事故の防止は自己責任だが、国や自治体が山岳事故の防止に非常に熱心である。これはパターナリズムであり、自己責任の考え方と矛盾する。しかし、日本では、これを矛盾だと考える人は多くない。
もともと、日本では、個人の自律的行動を重視せず、個人を管理の対象とみなす傾向が強い。そこに非難用語としての自己責任を持ち込んでも、矛盾しないのだろう。
個人の自律的行動が、近代市民社会を成立させ、同時に、近代登山をもたらした。個人が賢明でなければ、賢明な自律的行動が成り立たず、登山も民主政治もうまくいかない。
山岳事故への非難
日本で山岳事故が世論から非難されるのはなぜだろうか。
ネットでは、しばしば、「道楽で事故を起こした」として山岳事故が非難されるが、同じ道楽でも釣りや海水浴中の事故は世論から非難されることは少ない。これは、釣りや海水浴は誰でも行う可能性があるが、登山をする人は限られるという違いが関係しているのではないか。日本の登山人口は数百万人であり、人口全体の中では少数派だ。
山岳事故を非難する人のほとんどは登山をしない人たちであり、これが日本では多数派だ。世論は社会的多数者によって形成される。日本では社会的少数者が多数者から抑圧されることが多い。憲法の人権規定は、社会的少数者の利益侵害を防ぐことに意義があるが、日本ではその点を理解する人は多くない。日本は、憲法よりも行政運用や世論の方が重視されやすい。近年、ネットで形成される情緒的な世論が政治を左右する傾向が、世界中で強まっている。
日本は経済偏重の社会であり、仕事が重視される。社会的生産に寄与しない登山などのレジャーは、仕事以外の「余った時間」(余暇)に行う余計な活動であり、邪魔者扱いされやすい。しかし、富士山や尾瀬のように、レジャーが経済的利益をもたらす場合は重視される。
日本で義務的活動が重視され、自発的な活動を軽視する傾向も、山岳事故への非難と無関係ではないだろう。しかし、主体的に行う登山は、経済的利益と無縁で自発的な活動だからこそ幸福感をもたらしやすい。
2025年6月29日
山梨県の富士山レンジャー
山梨県の富士山レンジャーに関して、ネットでは、山梨・吉田ルートでは、「軽装登山者は通行を拒否」、「レンジャーにより強力な権限」などと報道されている。
富士山レンジャーは、地方公務員法上の「会計年度任用職員」であり、これは、アルバイト、パートなどの非正規雇用職員だ。
富士山レンジャーについて、「山梨県富士山レンジャーに関する規則」が規定するが、それを見る限り、職務のおもな内容は、自然公園法や山梨県自然環境保全条例などに基づく環境保護活動である。
もっとも、この規則に、富士山レンジャーの職務として、「登山の安全に関する啓発」、「その他知事が必要と認める事務」が規定されている。これが、山岳遭難の防止に関する職務ということなのだろう。
しかし、この規則には、「軽装登山者は通行を拒否」、「レンジャーにより強力な権限」に該当するような規定は見当たらない。そもそもこの規則には罰則規定がない。
罰則を伴う権限は、自然公園法や自然環境保全法などにあるが、これは環境保護に関する権限である。自然公園法や自然環境保全法などは、山岳事故の防止に関して何も規定していない。
富士山レンジャーは平成26年にできた制度であり、環境保護のために有益な活動をしてきたと思われる。しかし、山岳事故の防止については、今後も指導や啓発活動しかできないと思われる。
2025年6月18日
フライデーDIGITAL
「タダのりはもうダメ!」山で遭難…救助に来てもらったら、どれくらい費用がかかるのか? 解決策は?
https://friday.kodansha.co.jp/article/428648
これに僕のコメントが載っている。
2025年6月4日
「ミヤネ屋」と富士山ヘリの有料化
以前、富士山での救助活動の有料化について、読売テレビの「ミヤネ屋」の取材があり、取材内容が没になったことをフエイスブックに書いたが、ネット記事を見ると、5月20日に「ミヤネ屋」でこの問題について放送したようだ。
野村修也弁護士のコメントが記事に掲載されているが、これは的を射ているとはいいがたい。
富士山の法的規制が困難な理由は、富士山は、国、神社、県が所有しているので、県だけで入山規制できないことにある。県ができるのは、道路法に基づく登山道の規制だ。県が言う「閉山」は「登山道の閉鎖」であって、富士山全体の「閉山」ではない。
国、神社、県が共同すれば、富士山登山の許可制が可能だ。
ヘリを含めた救助活動の有料化については、「閉山期間中の山岳」を対象に有料化することは法技術的に困難だ。
上記の通り、県が言う「閉山」は法的根拠がない。登山道の閉鎖すれば、登山道と関係のない冬山登山者などの救助活動が有料になるというのは、説明がつかない。
9月の富士山は富士スバルラインを利用する観光客が多いのに、登山道を閉鎖したという理由から救助活動を有料化するのは不合理だ。法的に「閉山」していない富士山で、有料化の範囲を図面化し、それが合理的だと国際的に主張するには、かなりの蛮勇が必要だろう。
スイスは山岳も街中もすべて救急ヘリと救急車が有料だが、日本でも県の防災ヘリについては、法的には街中を含めて有料化できないことはない(警察ヘリと市の防災ヘリの有料化は法改正が必要)。国民の同意があれば、だが。
別のメディアからも取材依頼が来ているが、さて、どうなることか。
2025年6月4日
山梨県の富士山レンジャーの公務員化
「山梨県は、「富士山レンジャー」を任期付きの県職員とすることで、富士登山にふさわしくない軽装者や十分な装備を持っていない場合には、5合目で入山を拒否できる強い権限を与えるなどの新たな規制を説明した」というネット記事があった。
この規制の法的な問題点
・軽装の判断基準の問題。「軽装」を法令で定義することは難しい。気温が高ければ、五合目では軽装でも問題はない。防寒具を所持していればよい。また、好天の日に六合目までしか行かないという観光客は軽装でもよいのではないか。そもそも登山装備を法令で規制することに無理がある。世界では、「軽装登山」を法令で禁止する国はないだろう。
・トレイルランナーは軽装だが、どう扱うのか。登山道を走ってはいけないという法令はない。トレランは弾丸登山。途中までしか登らない人も弾丸登山。
・県職員に権限を与えるということだが、それに従わない者に罰則を科すのでなければ実効性がない。アメリカのレンジャーには逮捕権限がある。県職員が行政指導(法的拘束力がない)をするだけであれば、現在と大差ない。指導員の県職員化は、権限強化よりも「指導員に給料を払う」意味があるのではないか。
・富士山の登山道は県道なので、県が道路法に基づいて規制が可能。また、県有地は県が土地所有権に基づいて規制が可能だが、富士山には国有地と私有地がある。山頂付近は神社所有地(神社が裁判で勝訴し、最高裁で確定)。県だけでは登山道以外の山全体の入山規制(閉山)ができない。山梨県の規制は五合目ゲート以外の場所から進入する者に対処できない。
・富士山の登山者の過剰(年間約20万人)が事故を多発させている(遭難件数は年間約60件)。登山者が減れば遭難も減る。世界では、事故防止ではなく、環境保護のために登山者数を規制する。日本では、入山者数の規制は政治的にタブーとされており、そこに問題がある。
・ボランティアの指導員は法的な注意義務が生じにくいが、公務員の指導員には法的な注意義務が生じる。県職員が間違った指導をした場合の責任の自覚が必要だ(県の法的責任は滅多に生じないが)。権限と責任は一体であり、本来自己責任である登山に行政が介入すればするほど、行政の責任が生じやすくなる。そのため、欧米では、個人の自己責任の領域に行政はあまり介入しない。
・一般論としては、過度のパターナリズムは個人の自律を妨げやすい。
2025年6月2日
入山者数の制限
山と渓谷の2025年6月号に、テント設営のルールとして、キャンプ指定地では、間隔を詰めてテントを設営するように書いてある。日本の人気のあるキャンプ場は混雑するので、これはやむをえないだろう。
しかし、これは山が混雑することに原因があり、入山者数を制限すれば、ゆとりのあるキャンプサイトを設置することが可能だ。
欧米ではスペース的に余裕のあるキャンプサイトが多い。アメリカなどでは、隣のテントから一定の距離を置くことを規則で義務づけている自然公園もある。世界では、人気のある山域では、環境保護のために入山者数を制限し、そのため山が混雑することが少ない。辺境の登山者が少ない山域では、たいてい、どこでもキャンプ可能だ。入山者数を制限すれば、山小屋、登山道、テントサイトが快適になる。下の写真は大雪山のヒサゴ沼のテントサイトだが、登山者が少ないので快適だ。
日本では、アメリカなどの営造物公園と違い、土地所有権を取得しない地域制公園であり、自然公園の規制に限界があると言われる。しかし、北海道や北アルプスの山の多くが公有地にある。日本の国立公園の約70パーセントは公有地である。公有地では、土地所有権に基づいて山小屋、登山道、テントサイトの管理が可能だ。私有地にある山では、土地所有権を無視して入山規制ができないが、公有地では入山規制が可能だ。入山者数が減れば、事故も減る。富士山で事故を減らすために最も有効な方法は、登山者数を減らすことだろう。入山者数の制限にそれほど税金はかからない。
日本では、環境保護のための入山規制をほとんどしない一方で、山岳事故防止のための規制や管理に行政が異常に熱心だ。これは世界的に見ればかなり奇異である。
欧米では、登山は「自己責任」で行うものとされ、事故の防止は登山者に委ね、行政はあまり関与しない。日本では、「自己責任」という言葉は、誰かを非難する場面で使われることが多い。これも世界では奇異だろう。自然の中では、街中のように事故の防止が容易ではないので、欧米では、「効率の悪い税金支出をしない」という考え方もあるのだろう(事故防止は、もっぱら山岳団体やボランティア団体が担う)。
2025年5月29日
外国人の軽装登山
「無謀な登山者 羊蹄山では短パン、半袖シャツ姿の外国人カップルがSOSで「Sorry」夏山シーズンも入念な準備を…山岳ガイドが指摘する“低体温症”への注意」というネット記事がある。
富士山などでも、半そで、短パンスタイルの外国人登山者がいる。欧米では、半そで、短パンはhikingの一般的なスタイルのようだ。彼らは、富士山や羊蹄山をハイキングのつもりで登るのだろう。日本の登山を紹介したロンリープラネットのガイドブックでも、富士山や羊蹄山登山をhikingと表現している。
欧米のハイキングは、通常、山頂をめざさないが、日本の山歩きは山頂をめざし、高度や気象などの自然環境が厳しい。その点を理解しない欧米の観光客が半そで、短パンで山に登るのだと思われる。彼らは、後で「Sorry」と言うくらいだから、「悪気」はないのだろう。
日本人でも、軽装の観光客が富士山などに登っている。2014年の御嶽山の噴火事故では、山小屋に避難したハイカーの多くが、ヘッドランプや雨具を持っていなかったことが報告されている。
日本の山歩きと欧米のハイキングの違いを外国人に理解してもらうことは必要だが、人間は、自分が経験したことがないことを簡単に想像できるほど賢くはない。また、普段登山をしない観光客は、「登山の前に気象条件、地形、ルートなどを調べる必要がある」ことが理解できないのではないか。
登山が大衆化して登山者層が広がれば、事故も増える。
世界では、環境保護のために登山者数を制限し、それが、結果的に遭難件数を減らす効果をもたらしている。
富士山などでは、登山者数を制限することが、遭難を減らすもっとも有効な方法ではないかと思われる。
2025年5月22日
静岡県富士登山条例
富士山の静岡県側では、令和7年5月9日から、入山料を課す静岡県富士登山条例が施行された。
条例の内容は以下のとおり。
・入山料は1人4000円。ただし、富士山の閉山期間中は入山料は課されない。閉山期に、登山口に職員を配置できないからだろう。閉山期に登る外国人観光客が増えるかもしれない。
・条例では、各登山道の基準点(計3か所)から山頂側に立ち入る場合に登山料の支払義務が生じる。登山道上では、「基準点から山頂側に立ち入る」文言の意味が明確だが、登山道以外の場所ではわかりにくい。基準点からトラバースする場合は、入山料の対象ではない。
・原則として山小屋に宿泊することを義務づけている。
・事前講習と入山届を義務づけ、事前に県が入山証を交付する。
・午後2時から午前3時の間は、登山道の通行が「規制」されるが、山小屋宿泊予約者は規制の対象外。この規制は道路法上の規制ではないようだ。
・富士山の登山道は道路法上の県道になっており(山梨県側も同じ)、道路法に基づいて、県道の一部を通行禁止にできる。しかし、道路法は交通の安全の観点から道路の一部の通行を規制するのであり、雪のない9月などに、山小屋が営業していないという理由から公道を通行禁止にすることは道路法の趣旨に反する。登山道の閉鎖(closed)と通行禁止は異なる。
・登山道の通行禁止は入山禁止を意味しない。登山道以外の場所を歩けば、道路法の規制が及ばない。道路以外の山全体を入山禁止にするには、静岡県に土地管理権が必要だが、富士山には国有地や神社の私有地がある。
・アメリカでは、公有地での登山を許可制にして有料化し、入山者数を制限するが、この静岡県では、「基準点から山頂側に立ち入る」行為に入山料を課し、入山者数の制限をしない。
・条例違反に対する罰則はない。条例の入山の定義があいまいなので、罪刑法定主義に照らし、罰則を科すのは無理である。
罰則がなければ、条例を無視する外国人が多いのではないか。新型コロナ流行時のマスクを着用と同じである。
・登山道が道路法上の道路の場合や、山梨県のように登山道の一部を有料化した場合には、道路の管理責任が問題になりやすい。登山は自己責任が原則だが、「道路」、「有料」が利用者に「安全」のイメージを与えやすいからだ(山梨県側登山道での落石事故に関して現在裁判中)。
2025年5月21日
女人禁制
大峰の山上ヶ岳(1719m)は、昔から、宗教上の理由から「女人禁制」とされている。しかし、これについては以前から論争があり、1999年に奈良県の女性教師13人が大々的に山上ヶ岳に登頂し、寺院から抗議を受けた事件もあった。
山上ヶ岳は寺院が所有する山なので、憲法上の平等原則の間接適用の問題になる。法律家としては、裁判になることを期待してしまうのだが、現実にはこの問題が裁判になることはない。
実際には、女性登山者がいても、寺院が女性登山者を実力で阻止することはなく、裁判の対象になる「事件」が起きない。「事件性」がなければ裁判が難しい。
このようなあいまいな状況は日本では多い。剣岳の三の窓での幕営、自然公園内の沢登り中の幕営、キャンプ場のない山域での幕営、雪山での幕営など・・・これらは幕営の必要性と自然公園法の行政運用(指定キャンプ場以外でのキャンプの原則禁止)の狭間で黙認状態にある。そのため「事件」が起きることがなく、裁判にならない。
しかし、外国人にはあいまいな運用が通用しにくい。山上ヶ岳が、信者だけが使用する私的な閉鎖空間であれば憲法上の問題は生じないが、一般登山の対象になれば、私的領域でなくなる。特に観光地としてグローバル化すれば、「女人禁制」が問題になりやすい。宿坊では、原則として宿泊を拒否できないとする旅館業法との関係で紛争が生じる可能性がある。
世界中で利用者の多いロンリープラネット発行の「Hiking IN JAPAN」(2009、この本で言うhikingは登山の意味)には、山上ヶ岳に関して、性差別(sexism)を支持しないと書かれている。「女人禁制」の信仰、文化、伝統は尊重されるが、国民に不利益を与える場面では憲法上の制約を受ける。
2025年5月20日
富士山で防災ヘリを有料化すべきか
「無謀な富士登山に地元市長が激怒…「救助費用は自己負担にすべき」というネット記事があった。これは、富士山で2回救助要請をした外国人登山者に腹を立てた市長の発言だ。
埼玉県では、条例で消防ヘリを有料化しているが、「特定の山頂から半径1~5キロの範囲が有料」という決め方をしている。
埼玉県の条例には、以下の問題がある。
・有料化する範囲が恣意的で、合理性がない。法律や条例には公平性が必要だ。
・一定のエリアでの急病人を有料にすることは、救急ヘリの趣旨に反する。
・県境付近の山では、埼玉県以外の都道府県に救助要請をするだろう。
・県警ヘリは無料なので、遭難者は警察に救助を依頼するだろう。
・有料化で得られる埼玉県の収入は、年間30万円程度であり、少ない。ヘリ有料化は政治的な意味が強い。
・埼玉県でも自然災害はヘリ有料化の除外対象だが、山岳遭難と自然災害の区別はあいまいだ。噴火事故、落石事故、雪崩事故、土砂災害は、統計上、山岳事故に分類される場合と自然災害に分類される場合の両方がある。登山者12人が死亡した1980年の富士山落石事故は自然災害とされた。御嶽山噴火事故は自然災害、火打山噴火事故は山岳事故とされた。どちらに分類するかは、政治的に決まる。
消防機関の活動は一般に無料であり、特定エリアの防災ヘリだけを有料化することは、恣意的で公平ではない。
警察のヘリは、犯罪捜査などさまざまな場面で使用され、警察組織は、消防組織と違って、事実上、全国で統一的な組織になっており、ヘリの運用も全国で同じだ。
どんな社会でも、犯罪がなくならないのと同じく、制度を乱用する者がいる。救急車の利用の乱用事例は多い。制度の乱用に対する制裁は別途検討する必要があるが、「制度の乱用者がいるから、すべての利用を有料にする」考え方は不合理だ。
アメリカでは、ほとんどの州で救急車が有料だが、山岳救助活動は無料だ。
スイスでは、山岳かどうかを問わず救急ヘリが有料だが、国民の多くが加入する保険でヘリの費用が支払われる。
世界の先進国では、特定のエリアの救急ヘリを有料にする国はないと思われる。
富士山で、防災ヘリ、警察ヘリを有料化するのは無理である。
2025年5月16日
読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」でインタビュー(続)
読売テレビから連絡があり、「ミヤネ屋」では、急遽、埼玉・三郷市で起きた小学生ひき逃げ事件を大きく取り上げることになり、富士山救助の有料化問題は延期することになったとの連絡があった。
恐らく、私の意見が番組の企画に水をさしたのだろう。
こういうことはよくあることだ。
2025年5月15日
読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」でインタビュー
今日、読売テレビから、富士山の救助費用の有料化についてzoomでインタビューを受けた。5月16日放送の「情報ライブミヤネ屋」でインタビュー内容を使いたいとのこと。
富士山の閉鎖期間中だけを対象に有料にする法律、条例は公平性、合理性に欠けること、全期間を対象に街中の救急車を含めて制度を乱用する者に制裁金を課すことは可能であること、救助活動の有料化は、国民の多くが保険に加入することが前提になること、本来の自己責任に非難の意味はないことなどについて話をした。
インタビューを受けたのは、夜の8時からだった。テレビ局では深夜まで働くのが当たり前なのだろう。
「情報ライブミヤネ屋」を見たことはほとんどないが、約30分間の取材のうち、使うとしてもおそらく数秒程度だろう。
以前、広島の某テレビ局は1時間取材したが、結局、取材内容をまったく使わなかった。若い記者は取材に熱心だったのだが、おそらく、上司が、私の話した内容が気に入らず、取材内容を「没」にしたのだろう。NHKの某支局の取材では、2時間くらい取材で引き回され、ひどい目に遭ったことがある。
それでも、私は、基本的にメディアの取材を断ることはない。
2025年5月7日
「大雪山国立公園愛別岳滑落事故訴訟について」、国立公園832号、自然公園財団、2025
2025年5月6日
登山道のペンキでの標識について
登山道に木にぺンキで目印がしてあることがある。
木の所有者の許可を得ることなくこのような目印をすれば、器物損壊罪になる。しかし、価値のない雑木にペンキで印をつけても被害額は0円であり、木の所有者から警察に被害届が出ても、通常、不起訴になるだろう。
岩にペンキを塗ることは岩の損壊に当たるが、通常、岩に財産的価値がないので器物損壊罪にならない。以前、富士山で、登山道から外れた場所の岩にペンキで目印をつけた者がおり、メディアが大騒ぎしたことがあるが、器物損壊罪にならない。
自然公園では、標識の設置に環境大臣等の許可がいるが(普通地域を除く)、ペンキを塗ることは、自然公園法の「工作物の新設」とは言えない。
木や岩の所有者が黙認する場合でも、登山道の標識は、できるだけ環境への負担の少ない方法がよい。リボンは簡単に外すことができるので、木にぺンキを塗るよりも、リボンを設置する方が環境への負担が少ない。木にテープやリボンを設置することは木の「損壊」とは言えない。
しかし、北アルプスなどの木のない岩稜では、岩にペンキで目印をすることはやむをえないだろう。ペンキやリボンは登山道の迷いやすい箇所に設置され、間違いようのない箇所には、リボンを設置しない。しかし、残雪期は、登山道が雪に埋没するので、初心者はリボンがないと迷いやすい。
2018年の新潟県の五頭連山での親子遭難では、残雪のために迷いやすかったようだ。大日ヶ岳も、明瞭な登山道があるためか、リボンなどがほとんどない。ネットに、この山は、残雪期は迷いやすいという書き込みがあった。
雪があれば道が消えて迷いやすくなるのは当たり前だが、雪のないハイキングをするつもりで登り、途中から雪が出てきてビックリ、ということがある。そこから引き返せばよいが、体力に自信があるとそのまま登り続けることがある。
標識をどこにどのように設置するかは、登山道の管理者が決めるが、日本では管理者が不在の登山道が多い。
2025年5月5日
組織と個人の関係について
私は、長年、登山をしてきたが、その間、山岳連盟やJMSCA(日本山岳スポーツクライミング協会)の必要性を感じたことはなかった。登山をする場は所属する山岳会であり、山岳連盟やJMSCAがなくても登山が可能だった。登山をするうえで、山岳連盟やJMSCAの支援を受けたことはない。一度だけ、海外登山で山岳連盟隊を名乗ったことがあるが、これは、個人が集まってパーティーを結成した後に、形式上、山岳連盟隊を名乗っただけである。山岳連盟やJMSCAは、頼まれて「その活動を手伝う対象」だった。
私は、長年、弁護士をしてきたが、その間、弁護士会の必要性を感じたことはない。弁護士の活動は、個人の活動と、有志で結成する団体、研究団体、弁護団などで行った。弁護士会がなくても、弁護士としての活動ができた(私は、一時期、約30の団体に所属していた)。弁護士会は、私にとって必要ではなく、頼まれて「その活動を手伝う対象」だった。
登山でも弁護士業でも、社会的な活動をする組織は必要だ。しかし、「あれも、これも必要である」と考えると、組織は際限なく肥大化する。弁護士会には数十の委員会があり、毎日会議をしている。無報酬の活動はいくらでも増やすことができる。組織が肥大化すれば活動資金が増えるが、弁護士会は強制加入団体なので、資金が足りなければ会費を値上して資金を調達している。その結果、現在の弁護士会費は月額5万円以上だ(会費が月額約10万円の地区もある)。しかし、山岳団体は会費値上げが難しく、活動が肥大化すれば財政破綻しやすい。
活動の肥大化は行政でも生じる。「あれも、これも必要である」と考えると、いくら増税しても足りない。北欧の学校では、職員会議や報告書の作成がなく、指導要領の拘束もほとんどない。自分の子供が熱を出せば、教師は仕事を休む(代替教師がいる)。生徒のスポーツは地域で行い、学校は関与しない(責任もない)。教師は教育の専門家として処遇され、教師はもっとも人気のある職業だ。
多くの日本人は、北欧の教師は「手抜き」をしているように感じるだろう。日本では、管理業務の「手抜き」どころか、莫大な税金を使って管理を強化している。学校の管理下での部活動の地域移行を考えるので、教師のブラック労働は変わらない(責任も変わらない)。日本の教師は、自分の子供が熱を出しても仕事を休めないので、大変だ。
日本の社会には組織的管理を重視する傾向があり、これが会議や会務を際限なく増やしている。事故、災害、不祥事などが起きる度に管理業務が増える。その分、個人の幸福度が減る。肥大化した組織の活動を削ぐことは「手抜き」ではなく、効率的な社会と個人の幸福追求のために必要だ。
2025年4月22日
資格と需要
報道によれば、文科省は、今後、私立大学が学部や学科を新設する際の審査基準を厳格化するということだ。日本では、これまで、高校や大学の設置を簡単に認可し、過剰になればつぶしてきた。
「作っては、つぶす」・・・これが日本の基本的な政策だ。
法科大学院を設置し過ぎたため、採算がとれず、法科大学院の半分がつぶれた。「食えない弁護士」が増え、弁護士の横領などが増えている。歯科医も、歯学部を大増設した結果、歯科医が過剰になり、つぶれる歯科医院が少なくない。 大学の博士課程も大増設したが、需要を考えずに増やしたので、博士号取得者の就業が難しい。
需要に応じて大学の数や資格者数を決める必要があるが、日本でそれをしないのは、教育や資格取得が業界の利権の対象になっているからだ。業界から政治家への政治献金がモノを言う。環境保護のため入山規制をしないのは、登山が経済活動の対象だからだ。
山岳ガイドの資格は国家資格ではないが、これも需要に関係なく資格を与えている。アマチュア資格と違って、職業ガイドは、需要に見合った資格者数にしなければ、山岳ガイドが職業として成り立たない。
ヨーロッパでは、需要に応じて大学の数や資格数にコントロールしており、大学への入学、卒業がかなり難しい。山岳ガイドの国家資格取得も難関だ。その結果、大卒の肩書や山岳ガイドの資格に権威がある。
日本では、大学などを「作っては、つぶす」、あるいは、需要を無視した過剰な有資格者数になり、無駄が多い。国民は資格取得のために無駄な学費を消費しても、資格を生かせず、不幸感が強い。国が使う無駄な税金で業界が潤うが、社会的には効率が悪く、生産性が悪い。
2025年4月21日
人との繋がり
しばしば休日に里山を放浪する。道のない場所を歩くので、万一、山の中で動けなくなると、発見、救助が難しい。登山道は山の中の「線」だが、山の中の「面」を捜すことはかなり困難だ。そのため、常に、ココヘリを持参し、歩くエリアを家族に知らせておく。この場合、家族から関係機関への通報が命綱になる。
最近、登山届の提出を義務化する自治体が増えているが、登山仲間や家族が警察などに通報しなければ捜索は始まらない。ここでも登山仲間や家族とのつながりが命綱だ。
街中でも、人との繋がりがなければ、簡単に「遭難」する。最近、孤独死が問題になっているが、人との繋がりがなければ、自宅で病気で動けなっても誰も気づかず、「自宅内遭難」する。誰もが他人との繋がりで生きている。人との繋がりは、経済、精神の両面がある。
登山での人との繋がりの典型が登山パーティーだ。パーティー内の関係次第で、遭難しやすいパーティーもあれば、そうではないパーティーもある。単独登山では、パーティーの危険回避機能がない。しかし、登山では、危険が生じた時に、見知らぬ登山者が援助する場面は多い。山では何が起きるかわからず、誰もが、「いつ自分が他人の援助を必要とするかわからない」ことを理解している。そこには、自分を他人の立場に置き換える想像性がある。
この点は、街中でも同じであり、社会から恩恵を受ければ、社会への恩返しの気持ちが生まれやすい。それがボランティア活動の精神になる。しかし、ここで話がかなり飛躍するのだが、アメリカのトランプや最近の日本の傾向は、それに反することが多いような気がしている。
2025年4月20日
高校の部活動での事故
4月19日、埼玉県の御岳山(1080m)で県立高校の山岳部の活動中に生徒が滑落し、意識不明になっている。一般登山道での事故であり、それほど危険な山とは思えないが、それでも事故が起きる。
この種の事故は何でもない些細なミスから起きる。街中では、歩道で転ぶだけですむようなミスが、自然の中では(登山に限らない)重大な事故につながりやすい。
責任の有無は、事故の詳細がわからないので、今の段階では不明だ。
事故が起きると、そこに固定ロープを設置すべきだという意見が出ることが多いが、少しでも危険な場所にロープを設置すれば、山がロープだらけになり、定期的なメンテナンスが必要になる。
このパーティーは、参加生徒数が20人と多かった。しかし、4、5人のパーティーであれば、この種の事故が起きないというものではない。
通常は、一般登山道ではロープでの確保をしないが、教師は、20m程度のロープを持参した方がよい。UIAAのハイキングリーダー資格では、引率者に簡単なロープ確保の技術を要求している(JMSCA上級夏山リーダー資格はUIAAに準拠している)。
多くの場合、一般登山道では引率教師は生徒に注意喚起をするくらいのことしかできないが、注意喚起をすれば事故が起きないというものではない。文科省は学校の部活動の外部指導者導入を推進しているが、外部指導者が同行してもしなくても、この種の事故は起きる。
生徒は頭部にけがをしたので、今後、高校の部活動でのヘルメット着用が問題になるかもしれない。北アルプスでは、自治体が山歩きでのヘルメット着用を奨励している。ヘルメットを着用するかどうかは、登山者や学校の裁量に委ねるべきで、登山者の装備に行政が介入することは、私的領域への過度の介入と言うべきだろう。
2025年4月19日
ロマンス詐欺
フェイスブックの利用者に対する詐欺があるようだ。
男性には美人の女性、女性にはハンサムな男性からの友達リクエストが来る。外国の整形外科医、実業家などを名乗るケースが多いようだ。SNSで親しくなり、最後は、必ず、金の話が出る。
SNSでは、写真、氏名、経歴の偽装が簡単にできる。フェイスブックに多くの写真(盗用した写真)が掲載されていても、投稿の中身がなければ怪しい。例えば、自称整形外科医なのに医学的な投稿がまったくないなど。
以前、私は、多くの人に、「いくら騙されても、金さえ渡さなければよい」と話していたが、それではダメだということがわかった。最初に少しでも騙されると、それが簡単にエスカレートするのだ。
少しでも怪しい場合には、他人に相談することが必要だが、騙されて金を送金した後に初めて他人に相談する人が多い。不安、動揺、あせり、自分の失敗を人に知られたくない心理、恋愛感情などの人間の心理が他人への相談を妨げる。その手口の巧妙さは感心するほどだ。
国家が国民を騙すこともある。ヒトラーは「わが闘争」という本の中で、「国民は小さな嘘には騙されにくいが、想像を超える大きな嘘には簡単に騙される」という趣旨のことを書いた。国家レベルの詐欺は珍しくない。国民は、まさか国や大統領が国民を騙すとは夢にも思わないのだ。
日本は資格大国であり、役に立たない民間資格や国家資格が多い。資格を乱発することで国民に金を使わせ、もうけることができる。これは一種の資格商法であり、詐欺的だ。
クラウドファンディングも問題がある。キリマンジャロに登ることを「冒険」と称して、その費用をクラウドファンディングで集めたケース(これは冒険ではない)、ヒマラヤ登山の費用をクラウドファンディングで集めたケースなどは、あまりにも安易な金集めだ。昔から、ヒマラヤ登山などで限られた範囲の企業や個人からカンパをもらっていたが、クラウドファンディングは面識のない大衆から金を集めるので、トラブルが生じやすい。故栗城史多氏のクラウドファンディングでも、「騙された」、「金を返せ」などの苦情が生じた。クラウドファンディングを利用した明らかな詐欺事件もある。クラウドファンディングでは、理念、使途、資金管理、会計報告、明朗性が重要だ。
登山とハイキングの違い
ハイキングと登山はどう違うのですかという質問を受けることが多い。
日本語のハイキングという言葉の意味はあいまいだ。裁判所の判決文の中で、川原での子供会の水遊びをハイキングと書いた裁判官がいる。奥多摩や丹沢での山歩きを「ハイキング」と記載するガイドブックがあるが、奥多摩や丹沢の登山道には危険個所があり、転落や道迷い遭難が多い。
一般に、ハイキングは安全で誰でもできるというイメージを与えるが、そのようなコースでも危険個所があることが多い。2018年に新潟県の五頭山で親子が遭難したケースでは、遭難したコースは、地元の観光パンフレットにハイキングコースとして紹介されていた。そのパンフレットを見て、小さな子供連れでも登れると考えた可能性がある。
自治体や観光協会は、利用者を増やそうとして、パンフレットなどに「ハイキングコース」と記載する。しかし、観光は経済効果をもたらすが、登山がもたらすものは、経済効果ではなく事故のリスクである。登山に経済効果を期待することが、環境破壊や自然のオーバーユース、事故の増加などの多くの問題をもたらしている。
ハイキングという言葉の濫用は事故につながりやすい。この点を自治体、観光協会、出版社などは自覚する必要がある。ハイキングの言葉は、事故の危険性の低い山歩きに限って使用すべきだ。尾瀬の木道歩きはハイキングだが、奥多摩や丹沢での山歩きはハイキングではない。上高地では、バスターミナルから横尾までがハイキングの対象だ。1980年に吊り橋事故が起きた大杉谷の歩道について、裁判所は判決文にハイキングコースと書いたが、断崖や鎖場を登ることはハイキングではない。日本の多くの山は山頂付近が急峻であり、これはハイキングの対象ではない。山頂をめざすことなく山麓を歩く場合はハイキングの対象になる。
事故を減らすうえで、ハイキングという言葉の使用範囲を限定することが必要だ。
コンプライアンス
最近、会社、役所、団体などで、やたらとコンプライアンスという言葉が使われる。
コンプライアンス(法令遵守)は、本来、先進国では当たり前のことだが、日本の社会は、法律ではなく、世論と役所の指導(行政指導)で動くことが多い。日本のコロナ対策は、基本的に法律ではなく、世論と役所の行政指導で行われた。日本では法律と無関係のルール遵守だったのだ。
会社、役所、団体などでコンプライアンスが叫ばれるのは、日本の社会が法律で動いていないからだ。
他方で、夫婦、家族、近隣、学校などでは、コンプライアンスを言うと、たいてい嫌われる。「家庭に法律はいらない」、「教育の場に法律を持ち込むことは、教育の失敗だ」と言う人がいる。しかし、もともと、夫婦、家庭、学校は法律に基づいて成り立っている。
登山の世界でも、法律の介入を嫌う人が多い。法律が登山の邪魔をするというイメージがあるからだ。歴史的には、法律がそのような役割を果たしたことは事実だ。今でも、日本では、法律は登山を制限することが多い。
しかし、もともと憲法や法律がなければ登山はできないのであり、江戸時代はそうだった。現在も、登山は法律的にあいまいであり、その結果、世論から叩かれると登山ができなくなることが多い。役所の拘束力のない指導にもさからいにくい。法律で、できることとできないことを明確にすることが必要だ。
もともと、法律が規律する領域は限られる。法律は、個人の自由の領域には介入できないが、日本では個人の「私的領域」があいまいなため、コンプライアンスの重視が管理の強化につながりやすい。
学校、大学、会社、役所などで管理が強化され、役人や管理職が無駄な管理業務に追われ、その分、生産性が悪くなる。これはコンプライアンスの無理解と責任回避傾向に原因がある。
紛争の多くが人間関係から生じるが、法律は人間関係に介入できない。それは個人の「私的領域」だからだ。しかし、最近、人間関係を法律で解決しようとする人が多い。法律の力で夫婦関係が円満になるはずがない。
会社でも、夫婦でも、登山でも、法律が規律する領域と個人の自由の領域の区別が明確であることが、コンプライアンスの前提になる。
落雷事故
奈良市で中学校の部活動中にグラウンドに落雷があり、2人が重体になっている。
1996年に高槻市で高校の部活動としてのサッカーの試合中に起きた落雷事故では、裁判で学校等の損害賠償責任が認められた。最高裁は、雷雲や雷鳴があれば、落雷事故の具体的予見が可能だと述べている。雷雲や雷鳴があったとしても落雷の確率は低く、さらに、特定の場所にいる特定人が被雷する確率は限りなく低い。しかし、それでも、最高裁が落雷事故の予見可能性を認めたのは、最高裁が、「学校の活動は安全でなければならない」という法的な価値判断をしたからだ。
近年、甲子園の野球大会では、試合中に雷雲等があれば、試合を中断している。
今回の事故では、落雷事故の予見可能性の有無はわからない。
実際には、漠然と落雷の危険性を感じることはあっても、現実に落雷事故が起きることを予測することは難しい。それでも学校の活動では、あと知恵の理屈で重い注意義務が課されることが多い。
1967年に西穂高岳付近で高校の学校登山中に生徒ら11人が亡くなった事故が有名だが、これは裁判になっていない。これは55人の集団登山だったので、明らかにまずかった。
夏の高山ではほぼ毎日落雷注意報が出る。高山では落雷のリスクが常にあるので、ある程度のリスクを承認しなければ登山ができない。熱中症のリスクも同じだ。それを学校の保護者が受け入れるかどうか。
JMSCA役員選考委員会
JMSCA(日本山岳スポーツクライミング協会)の役員選考委会があり、東京を往復した。その他に、私は、JMSCAのガバナンス委員会、UIAA委員会などにも属している。
JMSCAでは、若干名の有給職員を除き、ほとんどの関係者が、ボランティア活動、または、若干の費用が支給されるボランティア的活動をしている。JMSCAはオリンピックのクライミング競技を運営しており、日本のオリンピックへの参加や各種のスポーツイベントは、基本的にボランティアが支えている。
私は、国立登山研修所の専門調査委員もしているが、これは日当が支給されるので、ボランティア活動ではない。しかし、報酬額が低いので「ボランティア的」な活動である。国立登山研修所の活動に多くの山岳ガイドが関与しているが、報酬額が低く、「ボランティア的」な仕事になっている。
専門家の活動では、仕事とボランティア活動の区別が重要だ。JMSCAなどでボランティア的活動が多いのは、団体に金がないからである。多くのスポーツ団体に金がないので、関係者のボランティアが支えている。
他方、国や自治体などは、金がないわけではないので、これに関与する専門家に相応の報酬支払が可能、必要だ。しかし、実態は、国や自治体は、専門家のボランティア的な協力を活用し、支出を抑えようとする。その典型が、学校の部活動の顧問であり、教師の残業タダ働きを利用して支出を抑えている。これはボランティア活動の「悪用」に他ならない。これでは教師のなり手が少ないのも当然だ。
弁護士についても、国や自治体は、「ボランティア的な仕事」として報酬を低く抑え、時には、「これはボランティアでやってください」などと、露骨に無報酬での仕事を要求することもある。
学校の登山部の指導を外部指導者に委託しようとしても、報酬が安ければ山岳ガイドは簡単には引き受けられない。生活と責任がかかっているからだ。学校の部活動の指導は学校の業務の一部であってボランティア活動の対象ではない。仕事では、相応の報酬支払が必要だ。
非営利の山岳活動に関わる医師、看護師、山岳ガイド、教師などの専門家は多いが、その中に弁護士は少ない。多くの団体でコンプライアンスが問題になっており、法律家の需要が大きいのだが、弁護士の営利的傾向がそれを妨げる。特に、最近は、弁護士の数が増えて競争が激しいので、弁護士の業界に、「(金のある)顧客獲得につながらないことはしない」傾向が強い。
雑誌「日経トレンディ」2025年5月号
雑誌「日経トレンディ」2025年5月号に、「親切すぎる登山 最新入門」という特集記事がある。その中の山岳捜索・救助費用について、少し前に記者から電話で簡単な取材があり、私の説明も少し引用されている。
この記事は、登山に関するさまざまな情報が記述されているが、「知識なし 体力なし 専用ギアなしでも明日から行けるように!」との見出しや、登山アプリを使えば、「地図いらず、で登れる」などと記載し、気軽に登山ができることを強調している。これは「安易な登山」になりかねない。
記事の後半は、一転して、遭難すると高額な捜索救助費用がかかることを強調し、1日に最大200万円かかると書いてある。しかし、通常はそんなにはかからないだろう(公的救助費用は、埼玉県を除き、無料)。
記事の中に、道迷いや疲労で動けなくなった場合は、山岳保険から支払いがないケースがほとんどだとの記述がある。問題になるのは「救援者費用保障特約」の適用範囲だが、山岳遭難の中で道迷いがもっとも多いので、これを対象外とする保険は山岳保険と呼べないだろう。JMSCAの山岳共済も、山岳保険の支給対象となる遭難は、「生死に関わる危険に遭遇し、自力での帰還が不可能になった状態」とされ、これは道迷い等を含む。
登山道のグレーディング
登山道のグレーディングの指標として、技術度、難易度、体力度などがあげられることが多い。
しかし、体力度は、荷物の重量や1日の歩行時間によって変わるので、客観性がない。荷物の重量や、1日の歩行時間を4時間とするか10時間とするかで体力度が異なる。スイスやニュージーランドなどの登山道の分類では、体力度を表示することはない。体力度の表示は、コースタイムと同じく、日帰り、小屋泊の登山者向けの情報だが、登山道の分類とは別の事柄だ。
アメリカで長年、ロングトレイルを歩いた経験のある勝俣隆氏(トレイルブレイズハイキング研究所専務理事)の説明では、アメリカのトレイルはだいたい7種類あるが、体力度は分類の指標になっていない。同氏らのユーチューブ配信あり。雲ノ平山荘でのトークセッション:「アメリカで体験した0歳のハイキングトレイルと100歳のハイキングトレイル」& Outdoor Ethic(2023)。
また、アメリカやスイスなどでは、危険度が登山道分類の指標になっているが、日本では登山道の危険度の表示をしない傾向がある。難易度と危険度は異なる。「安全性=危険性の程度」であり、事故を防止する観点から、登山道の危険度の表示は重要だ。
登山道などに自己責任の記載のある看板がけっこうあり、山岳事故が起きる度に、ネット上に自己責任の言葉が飛び交う。
しかし、欧米では、自己責任という言葉はあまり使われない。
自己責任は、自由が保障され、自律的に行動することが前提だが、同調圧力が強く、義務的行動を重視する日本では、もともと自己責任の前提が稀薄だ。
日本では、自己責任は、他人の行動を非難する場合に使われることが多い。山岳事故はその典型だ。
また、自己責任は、責任回避の手段や、事故を防止するためにも使われる。「自己責任なので、事故を起こさないように注意してください。事故が起きても管理者は責任を負いません」という意味で使用される。
日本では「責任」という言葉に非難の意味が強く、この意味では、「責任」が嫌われ、「無責任」が安心をもたらしやすい。
しかし、「責任ある行動」という時、そこでいう責任は、注意義務、倫理、道徳などを含み、非難の意味はない。この意味の責任を自覚することは大切なことだ。
日本の社会は、法律ではなく世論で動く傾向が強く、「世論からの非難」に対する不安が強いので、行動が世論に左右されやすい。これは「責任ある行動」にはほど遠い。
日本と欧米のリーダー像の違い
「タテ社会の人間関係」(中根千枝、講談社、1967)の中に、日本の組織ではリーダーの役割は参加者の和を維持する点が指摘されている。他方、欧米では、リーダーシップを発揮するリーダー像だと述べられている。この点は、現在でも変わらないとのこと(「タテ社会と現代日本」、中根千枝、講談社、2019)。
登山で言えば、日本山岳スポーツクライミング協会(JMSCA)が、夏山リーダー資格を国際山岳連盟(UIAA)の資格に準拠させようとした時、日本と欧米のリーダー像の違いが問題になった。
UIAAのリーダー資格では、リーダーがリーダーシップを発揮し、リーダーが参加者の安全を守る。そのためリーダーに簡単なロープ技術を要求する。
しかし、従前の日本の夏山リーダー資格は取りまとめ型のリーダーであり、ロープ技術を含まなかった。そのため、JMSCAは、UIAAに準拠して、新たに上級夏山リーダー資格を作り、簡単なロープ技術が必要な資格にした。
政治、経済の場面でも、日本では、取りまとめ型、調整型のリーダーが多い。
このリーダー像の違いは、興味深い。中根氏は、日本と欧米の社会構造の違いを指摘している。日本では個人間のヨコの関係が希薄なので、リーダーが個人間の人間関係に介入して調整する。雇用主や役所が個人の私的な領域にまで干渉するのも同じか。
法的な注意義務は、法律の要件に基づくので、欧米型のリーダーが法的責任が生じやすいということではない。山岳会などでは原則としてリーダーは参加者の法的な安全確保義務を負わない(ただし、道義的には、リーダーは初心者の安全に配慮すべきだろう)。
二子山でのクライミング事故裁判について
2022年に二子山(1166m、埼玉県)の岩場でボルトが抜けてクライマーが滑落し、骨折する事故が起きた。
2023年9月に、事故の被害者が、地元のクライミング協会(社団法人)と自治体を相手に165万円の損害賠償請求をする裁判を起こした。2024年11月に裁判が結審したとの情報があるが、詳細は不明。裁判が起された時、マスコミの取材を受けてコメントした記憶があるが、その内容は忘れた。
一般論としては、自然の岩場の利用は自己責任が原則であり、欧米ではこのような裁判はないだろう。この裁判の背景に、自治体の関わり方の問題や感情的な問題もあるようだ。
自治体が公の施設として岩場や支点を安全管理していたのかどうかが問題になるが、もともと自然の中でのクライミングは危険なものであり、「町おこし」の対象になるようなものではない。人工壁とは異なる。
請求額も少ないので、裁判所が話し合いによる解決を図る「和解」を勧める可能性もある。
2019年に起きた富士山での落石死亡事故について、2024年に、国、県、神社を被告とする損害賠償請求訴訟が起こされた(現在、訴訟中)。
これは、山梨県が登山道の一部を有料化する前の事故だが、有料化を含めて登山道の安全管理を強化すれば、「安全な登山道」のイメージが生じ、事故が起きると紛争が生じやすくなる。安全化すれば、「事故が起きるのはおかしい」と考えやすい。登山道は、登山道にふさわしい管理、利用者が危険性を了解しやすい管理が必要だ。それが遊歩道との違い。
事故を防ぐために至れり尽くせりのサービスをすると、かえって初心者が増えて事故が増える面がある。
また、渋滞すれば落石事故が起きやすい。富士山や穂高などでのの渋滞をなくするには、入山者数の制限をする必要がある。
2025年4月9日
「大雪山国立公園愛別岳滑落事故訴訟について」
国立公園832号、自然公園財団、2025年4月号
この裁判では、一般の登山道とバリエーションルートとの分岐点に設置された標識の不備などに関して、登山道の管理責任が争われたが、責任が否定された。判例集未搭載。裁判所の考え方がよくわかる判決文。
2025年4月4日
日経トレンディ、2025年5月号、「親切すぎる登山」
「親切すぎる登山」という特集がくまれ、その中で、山岳遭難の捜索、救助費用に関して取材を受けた内容が記載されている。
しかし、電話での取材であり、私が話した内容の一部が引用され、趣旨が十分に記事に反映されているわけではない。
また、山岳保健では、道迷いの捜索、救助費用が出ない場合が多いといの記述があるが、疑問がある。少なくとも、日本山岳スポーツクライミング協会の山岳共済保険では、急激・偶然の事故以外に、「緊急な捜索・救助活動を要する状態」になった場合が支給対象になっており、道迷いにより行動不能となり、警察に救助要請をした場合は支給対象になる。
2025年3月日
フェイスブック
フェイスブックを始めた。
世の中にこういう便利なものがあることを初めて知った。他の人よりも20年くらい遅れているのかも。
2025年3月20日
リーダーの法的責任
日本山岳スポーツクライミング協会、夏山上級リーダー講習会、オンライン
2025年3月7日
日本山岳・スポーツクライミング協会、ガバナンス委員会
日本山岳スポーツクライミング協会(JMSCA)のガバナンス委員会が、21時から開催される。
私はオンラインで参加する。
夜の開催となったのは、その時間帯しか関係者の都合がつかなかったからである。
私は、JMSCAの夏山リーダー講習専門委員、役員選考委員、ガバナンス委員になっている。
日本では、あらゆる団体で会議と報告書が多い。JMSCAも会議が多い。役員の中にはほぼ毎日会議をしている人もいるようだ。
JMSCAは公益社団法人であり、一部の専従職員を除き、役員は無報酬であり、これらはボランティア活動ないしボランティア活動的な活動だ。
ただし、交通費などの実費が支給されるので、有償である。無報酬、有償ということ。
JMSCA主催の講習会の講師には、低額の謝礼が出るので、これは報酬である。
JMSCAに限らず、ほとんどのスポーツ関連団体の役員は、ボランティア活動ないしボランティア活動的な活動をしている。
全国的な組織は、役員に交通費などの経費の支払をするが、地方の組織は経費の支払いはなく、たいてい手弁当である。
このようなボランティア活動で、国体、スポーツイベント、オリンピックなどが実施されている。
これらのボランティア活動は、義務ではないので、「嫌ならしない」が原則だが、国体やオリンピックなどを実施しないわけにいかないので、これらの世話をすることは、義務的ボランティア活動になる。ボランティア活動が義務的になる場合は、社会奉仕活動と呼んだ方がよい。
弁護士会の委員会は、無報酬だが、交通費が出るので、有償、無報酬の活動だ。
これも、義務的な傾向がある。
私は、5つくらいの弁護士会の委員会に所属しているはずだが、時間がないので、何もしていない。
自治体や国が設置する第三者委員会の委員、情報公開審査会委員などの各種委員、自治体での相談、講演などは、弁護士の仕事であって、ボランティア活動ではない。
しかし、自治体や国は、これらを弁護士にボランティアとして依頼する傾向がある。その方が安上がりだからである。.
自治体関係の各種委員仕事の報酬額は1日1万円程度であり、ボランティア的な仕事になっている。
自治体は「金がない」というのが口癖で、無意味な事業を実施して多額の無駄遣いをするので、弁護士の報酬をケチる。
自治体主催の講習会でも、遠方に1泊2日で講師をしても、講習時間が4時間程度あれば、報酬は2万円程度である。これもボランティア的仕事と言ってよい。
国までも、自治体にならって、弁護士に支払う報酬をケチることが多い。
ボランティア活動と仕事の区別がなければ、弁護士の職業が成り立たない。
しばしば、第三者委員会の活動が世論から叩かれ、第三者委員会の委員が多額の報酬を税金からもらっていると思い込む人が多いが、ネットで誹謗中傷するのは、自分ではボランティア活動をすることがない人たちであり、「他人は多額の金を得ている」と思い込みやすい。しかし、世の中には、善意に基づいて金にならない活動をする人は多い。
以前、私は、30くらいの団体の役員や委員をしていたことがある。それらはすべてボランティア活動ないしボランティア活動的活動である。
それらを整理し、かなり減らした。
「〇〇した方がよい」と考えれば、ボランティア的な組織や活動、会議が際限なく増える。
弁護士会は、「〇〇した方がよい」と考えて委員会を増やしたので、日弁連には50くらいの委員会があり、毎日、多くの会議を実施している。
それらは必要性に基づいて行われているが、その経費を捻出するために、弁護士会の会費はどこでも月額5万円以上になっている(各地の弁護士会によって異なる)。日本の弁護士会費は世界一高額だ。それが、弁護士会の多くの活動を経費的に支えているが、同時に、弁護士のボランティア活動の大きな障害になっている。弁護士の仕事をほとんどしない「ボランティア弁護士」にとって、高額な弁護士会費は、弁護士登録することの妨げになる。
義務的ボランティア活動をしていると、それだけで人生の時間が終わりかねない。また、ボランティア活動で過労死しかねない。
それをライフワークと考える人はそれが本望かもしれないが、そうではない人は、ボランティア活動に優先順位をつけること、トリアージが必要だ。
「〇〇した方がよい」ではなく、「何をすべきか」が重要なのだ。そのためには、「〇〇した方がよい」ことであっても、「それをしない」ことが必要になる。
2025年3月3日
「登山道の法律Q&A 登山道に関して生じる法律問題の解説」
デザインエッグ発行
82頁
1210円
2025年3月3日発行
登山道があるのが当たり前だと思っている人が多いが、登山道について知らないことが多い。登山道は誰が設置、管理、整備しているのか。登山道の欠陥のために事故が起きた場合に誰に責任が生じるのか。登山道以外の場所を歩いてもよいのか。犬連れ登山ができるのか。登山道に関する要望は誰に言えばよいのか。本書は、登山道に関して生じるさまざまな疑問について、登山の法律問題に詳しい弁護士が33の質問と回答形式で書いている。
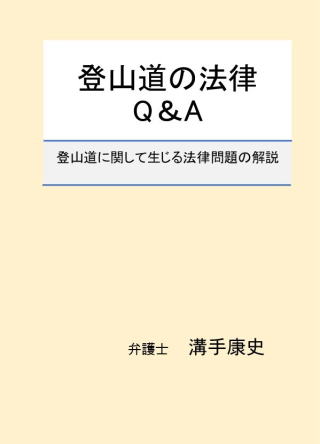
2025年1月
安芸高田市に対する国家賠償請求訴訟
2023年に安芸高田市に対し、国家賠償請求の裁判を起こした。
これは、安芸高田市に戸籍謄本等の請求を行ったところ、交付請求書記載のものと異なる謄本が交付されたことについて、市の窓口担当者の義務違反を理由とする損害賠償請求である。
当時は石丸市長だった。
私は市に「対し、なぜこのような書類の交付になったのかという説明を求めたが、市はまともに回答しなかった。
そのため、やむを得ず、提訴した。
当初、三次簡易裁判所に提訴したが、職権で、広島地裁三次支部に移送され、さらにそこから、広島地裁本庁に移送され合議事件に付された。
裁判所から見れば、3人の裁判官が担当しなければならない大事件だったようだ。
裁判の中で、安芸高田市の戸籍の窓口業務を民間委託し、民間人が戸籍謄本の交付事務を行っていることが判明し、驚いた。
戸籍という住民のプライバシーに関わる業務を民間人が行っていることを、ほとんどの市民は知らない。この是非を議論すべきだ。
2025年1月に、裁判所の勧告に基づいて和解した。和解内容は、市は、今後、適切に事務処理を行うといった趣旨の内容だ。
2025年1月22日
霧島山の自然の保護と利用に関するセミナー・ワークショップ
主催 環境省九州地方環境事務所、霧島錦江湾国立公園管理事務所
場所 えびの市
「登山道の管理と事故の責任」について講演した。