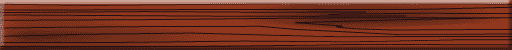
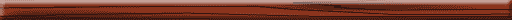



これは、私が田舎でのんびりと暮らしているという話ではない。
私が司法修習生だった時のことであるが、ある女性の司法修習生が、「銀行からカードでお金が降ろせるんですね」と言って驚いていた。これを聞いた私は怪訝に思い、さらに尋ねてみると、その人はそれまで自分で銀行で金を降ろしたことがないということがわかり、唖然とした。「じゃあ、お金が必要な時はどうしているんですか」とその人に聞くと、その人は「だって、お金がいる時はいつもお母様から必要なだけもらっているんですもの」と答えた。ちなみに、司法修習生の間ではその女性のあだ名は「お嬢様」だった。その司法修習生はその後裁判官になった。ついでに書くと、やはり司法研修所に「おぼっちゃま」というあだ名の司法修習生がおり、彼は後に弁護士になり、その後、時々裁判の当事者になっている某新興宗教に入信して教団の一員になった。
私の知っている裁判官で、裁判の時に「銀行でお金を降ろしたことがないので、通帳を見ても何のことかわからない」と言った五〇代の裁判官がいた。預金通帳の見方は説明を聞けばすぐわかることであるが、問題はその裁判官に「生活の臭い」が感じられないということだろう。
このような裁判官に裁かれる人は運が悪いというべきかもしれない。
それでも、ここ、日本の片田舎の三次市近辺では、多くの市民の裁判所についての考え方は「大岡越前」の時代と大差ない。ここでは、国が市民から強制的に徴収するお金のことを、「税金」とは呼ばず「年貢」と呼んでいるので(これは私がそう呼んでいるだけだが)、裁判所が市民の税金で運用されているとは誰も考えていないらしい。田舎の人は自分たちは「市民」ではないと本気で思っている(町民、村民と呼べば納得してもらえる)。
「裁判官のかたち」(現代人文社)という本の中で、私と同期のA裁判官は、裁判官研修時に経験の少ない裁判官が「小説から学ぶ」ことをしきりと勧められていることを述べている。最高裁は裁判官の経験が少ないことや、裁判官が世間の常識からかけ離れることを気にしているらしく、裁判官が小説からいろんな経験を学ぶことを勧めているらしい。最高裁は、小説であれば、裁判官が書斎の中でも「安全」に経験を積めると考えているのかもしれない。
しかし、小説はあくまでフィクションであり現実とは異なる。私は文学少年だった高校生の頃、休みの日など一日に一八時間くらい寝食を惜しんで小説を読んでいたが、全くの世間知らずだった。しかし、当時の私は世の中のことを本で読んで知っていると思っていた。当時は本を読むのに忙しく実人生を生きる暇がなかった(?)。たとえ何万冊も本を読んでいたとしても、実社会の経験がなければ無知と大差ない。人生経験のある人が小説を読めば、あるいは役に立つことがあるかもしれないが、経験のない人が書物で経験を学ぶのは愚の骨頂であり、役に立たない。
ある裁判官は、裁判官は多くの事件を通じて世の中のことを知っていると主張しているが、裁判所の記録や証言で世の中のことがわかったような気になるというその発想そのものが、恐ろしい。
カヌーイストの野田知佑が司法研修所で自分の体験や自然保護について講演をした時、修習生からはあまり質問もなく極めて反応が鈍かったことを、野田知佑がどこかで書いていたのを読んだことがある。それまでの人生の中で自然にあまり触れたことがない人は、世界中を放浪している野田知佑とは住んでいる世界が違い過ぎ、野田知佑が理解不可能な「変人」にしか見えなかったのかもしれない。
最近は自然保護が問題となる裁判も多いが、現在の裁判官が果たして自然の価値を実感できるだけの経験を有し、それだけの生活環境にあるのだろうかという気がする。既に一八〇〇年代に自然保護を唱えたイギリスの有名な詩人のワーズワースや、自然保護の父とされるジョン・ミューアは、自然の中での生活や放浪の中で自然保護の重要性を悟ったのであり、書斎で自然保護を思いついたのではない。
自然の持つ価値は、単に自然を眺めたり田舎で生活するだけで理解できるというものではない。自然の価値を理解できるかどうかは、経験によって得られる知識に基づく感性に左右される。ワーズワースが自然を理解するためには「教養」が必要だと述べたのも同じことだろう。農民がしばしば自然保護に無関心なのは、農村に住んでいても自然の価値を理解できるだけの感性がないからである。
あらゆる人権は人類の長年の経験や権利侵害の実態の中から生まれてきたものであり、それは全て人間の泥臭い生活実態に根ざしている。裁判所はいわゆる新しい人権を容易に認めず人権の内容も狭く解釈する傾向があるが、裁判所が人権の内容を解釈するとき、その背後にある人々の生活実態や権利侵害の実情を裁判官が「実感」できることが前提になる。たとえば、「日照権」、「自然享有権」、「平和的生存権」、「表現の自由」、「被疑者の権利」などの権利の具体的内容を理解するうえで、それまでの裁判官の人生経験や生活に基づく価値観が大きく影響するはずである。現在の多くの裁判官が置かれている生活環境や経歴、経験からすれば、多くの場合(例外はある)、裁判官が人権の持つ価値を「実感」できるだけの生活基盤が乏しいと言わなければならない。
これに加えて、多くの裁判官は、最高裁の容認する範囲でしか「ものを考えられない」という傾向がある。裁判官が自分でものを考えなくなれば、それは役人と同じではないか。
私は登山やクライミングが趣味なのでその例を持ち出すのだが、例えば、ロープを使用してクライミングをする方法は、恐らく何冊もクライミングの本を読んでも理解することは難しい。頭で考えると仕組みを理解するのは難しいが、実際のクライミングを見ればすぐにわかる。実際に自分でクライミングをすればクライミングがもっとよくわかる。要するに、クライミングは「理解する」ものではなく「やる」ものなのだ。クライミング中の判断の仕方や経験則はクライミングの経験を相当積まないとわからない。何事も事実を把握するには経験に勝るものはない。書物や伝聞によっては事実を把握することがどれほど難しいことか。昔の人はいいことを言っている。百聞は一見に如かず。
裁判が専門的分野に関わる場合、鑑定などで専門家の意見を聞くことになるが、その専門家の能力の有無や専門家の意見の優劣の判断は、裁判官の資質や経験、価値観などに左右される。裁判官がそれを自分で判断できない場合には、専門家の肩書や権威を鵜呑みにすることになるのだろうが、だいたい、「肩書」ほど当てにならないものはない。
もっとも、このように言うと、経験しなければ事実や経験則を把握することはできないという経験至上主義になりかねない。世の中の全てのことを経験することは所詮不可能である。
しかし、真実にできるだけ接近し誤りを最小限にとどめるために、人を裁く裁判官は可能な限り多様な経験を有し、多様な階層、経歴の持主であることが要請される。一人の人間の有する経験は時間数でいえば全て年齢に応じて平等であり、一人の人間が一生の間に有する経験はたかが知れている。同質的な裁判官ではなく、一人一人の裁判官の有する経験、経歴が多様であること、そこから多様な価値観が生れ、多様な価値観が競合し合い、その過程でよりすぐれた判断が淘汰されてくる。同じような経歴、同じような経験、同じような境遇のもとに生活してきた裁判官では、価値観の多様性を実現できない。同質的な価値観のもとでは「一人がこけたら皆こけて」しまう。民主主義社会では多様な価値観を競合させることが要請されている。
裁判の事実認定や判決は、数学のように論理的一義的に結論が出るのではなく、裁判官の全人生、経験、価値観、思想が色濃く反映するのであり、裁判所が多様な価値観の持主で構成されることが偏った裁判を防ぐために必要である。また、それにより、裁判に対する市民の信頼も高まる。しかし、まずまずの裕福な家庭に育ち、進学校や一流大学で勉強し、若くして裁判官に任用され、一生裁判官として生活するという現在の傾向のもとでは、裁判官の経験や価値観の多様性を望むことができないだろう。
最高裁は、地域でボランティア活動をしている裁判官を紹介し、「であるから現在の裁判官も世間を知らないということではない」と言いたいのだろうが、地域でボランティア活動をしている裁判官はりっぱであり、私もそのような裁判官に感心し敬意を表したいが、問題はそのような個人的なことではなく(個々に優れた市民感覚を有する裁判官はいる)、あくまでシステムの問題である。
私はどの世界でも「血の入れ替え」が必要だと思っている。「血の入れ替え」により、新たな価値観や経験、考え方などを取り入れることができるが、それがない社会は「安定」はするかもしれないが、種々の点で硬直化し発展が阻害されるように思われる。新しい血は古い血を刺激して活性化させ、「血の入れ替え」による刺激は社会の活力源になる。
裁判官、弁護士、企業の社員、公務員、学者などが相互に転職可能なシステムが必要であり、それにより、できるだけ多様な価値観、経験を共有することが少しでも可能になるのではなかろうか。裁判官が、弁護士はもちろんのこと、企業、公務員、大学教師などからも任用されるようなシステム、逆に、裁判官から弁護士、公務員、民間企業へという転職のシステムがあってもよい。
裁判所だけではなく弁護士の世界も「血の入れ替え」は必要だと思う。現在では弁護士になる社会的階層や経歴がかなり限られているのではないかと思われ、いったん弁護士になれば弁護士の住む世界も意外と狭いものではないかと思う。弁護士と依頼者との関係は、一般社会の人間関係や友人関係とは異質である。弁護士が市民感覚を失わないためには、弁護士の給源が多様であることや弁護士と他の職業との「血の入れ替え」が絶えず必要ではないかと思う。「先生と呼ばれる馬鹿」と言われるように医者や弁護士など、長年「先生、先生」と呼ばれていれば碌なことにはならない。
私も面白みのない法律を扱う仕事以外に転職できるのであれば、転職したいくらいだ。
ヒマラヤのある地方では、今でも、結婚する際、同じ村の者とは結婚できず他の村の者としか結婚できないという風習のある地域がある。これは、小さな同じ村の中だけで結婚を繰り返していると血が濃くなりすぎて弊害が生じるので、「血の入れ替え」が必要なことを長年の生活の知恵として人々が知っているからである。村社会といえども「血の入れ替え」は必要なのだ。
私は広島県の旧賀茂郡内の当時の小学校の全校生徒数が一〇〇人程度の狭い地域で育ったが、かつてはこの地域の住民は同質的な村社会の厳格な掟に縛られていた。村の掟に反すると村八分がまっていた。村八分は意識して行われるものではなく、住民が自然に無意識のうちに行ってしまうものであり、それは同質的な村社会を維持しようという自己保存本能に基づいている。この地域に住む私の母は村の掟の生き証人のような人だが、最近の宅地造成で人口が増えた結果「余所者」が増えて自然に「血の入れ替え」が進み、村の掟を守る住民はもはや地域で少数派になってしまった。「血の入れ替え」により村は開放的になり、村の掟はいつの間にか消滅していくのだろう。「村の掟」を破るには「血の入れ替え」が有効なのだ。
私は大学生の頃 「公害問題研究会」というサークルに入っていた。これを略して「公問研」と言うと「肛門研」と勘違いされたり、公害研究会を「合ハイ研究会」と聞き間違えるけしからん同級生もいたが、後にこのサークルのメンバーで裁判官になった人もいる。私は東大の法学部では授業に余り出席せず、三ケ月教授の民訴ゼミを無断欠席してゼミから追い出され勉強では落ちこぼれたが、他方で、病院を訪問して公害患者の話を聞いたり、夜間中学の生徒(と言っても一〇代、二〇代、上は六〇代くらいの人や中国から帰国した元在留日本人などがいた)と一緒に夜間中学の授業を受けたりソフトボールをしたりして、のんびり楽しく過ごしていた。
社民党の党首になったB弁護士は私と大学で同じクラスであり、彼女も学生時代にサークル活動などをしていたが、当時、そういう人は極めて少数で、ほとんどの学生は勉強と自分の娯楽だけの狭い世界に住み、驚くほど勉強の要領のよい学生が多かった。
私は裁判官になる人が社会の多様な階層を代表していることが必要だと思うが、競争社会の現在では、競争に勝った階層の世帯が子供の進学面でも圧倒的に優位の立場にあるので、裁判官になる人の社会的階層も偏ったものとなっていると思われる(「不平等社会日本」中公新書などを参考)。
この点は、恐らく、その世代や時代が大きく影響していると思われる。戦後間もない時期に生まれた世代には多様な経歴、経験があるのだろうが、高度経済成長以後に生まれた学生の経験は驚くほど偏っているというのが私の印象である。
そして、裁判官になった後の人間関係は同質的な村社会の関係しかないように思われる。
これは裁判所だけではなく、日本の官僚機構も非常に閉鎖的なムラ社会であり(私は一時公務員をしていたことがあるのでよくわかる)、そこでは市民へのサービスよりも組織や権限などを維持する方が優先される。そこでは肝に銘じなければならない格言として、「出る杭は打たれる」、「長いものには巻かれろ」、「前例踏襲」、「みんなで渡れば恐くない」などがある。
いずれにしても、裁判官の任用はできるだけ多様な給源から行ない、同質的閉塞的な「裁判官村」に幅広く「余所者」の血が流入するようにした方がよい。
私は、最高裁や簡裁以外の裁判官も、ポストによっては公務員、学者、会社員など法曹資格者以外の者でもその資質と能力さえあれば裁判官になってよいと思う。そして、裁判所の人事はドイツのような裁判官人事委員会のような開かれた機関が行うべきだと思う(「人間の尊厳と司法権」木佐茂男などを参考)。司法制度改革審議会も、裁判官の人事制度について、「可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すべきである」と述べている。
しかし、言うことは容易いが実現することは簡単ではない。
陪審制、参審制、裁判員などは市民の意見や感覚を裁判に反映させると同時に、市民が裁判の主体になり司法に関心を持つという意味で有用だと思う。市民が裁判所を「お上」と考え裁判は「お上」に任せ放しということでは改革はなかなか進まない。民主主義社会では、市民がどのような裁判を受けるのかを市民自らが決めなければならない。
自然科学以外の分野では、高邁な理論や学説の背後の意外なところで、その理論や学説がその人の人生経験に色濃く規定されている、ということがよくある。そういう意味で人生経験は、その人の価値観や思想を形成するうえで大きな影響を及ぼすと言ってよい。
私は田舎の公立の小学校、中学校に通ったが、そこにはチンピラや不良少年など色んな人間がいた。
私は、「公立の中学校は荒れているので、子供を私立中学校に行かせた方がいいのでは」という妻に対し、「中学校が荒れるのは当たり前である」と言って長女の私立中学校進学に反対し、子供達には「学校の勉強なんか一生懸命やっても仕方ない。学校の勉強以外の本を読んだり、外で遊べ」と常々言っている。おかげで、素直な長男は私の言う通りに全く勉強せず外で遊んでばかりいて、一時、小学校の勉強についていけなくなったことがあり、その時は少し反省した(広島弁護士会会報73号、2002)。

村に暮らす 溝手康史


