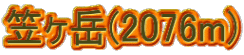
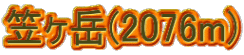

コロナ禍の夏、今年10座目の山として志賀高原のランドマークである「笠ヶ岳」を選んだ。県外の宿泊については何となく監視の目が有り、体力も落ちていることから、往復1時間弱で登れるこの山に決
めた。
北アルプスの百名山、笠ヶ岳(2898m)が有名であるが、粘性の大きな溶岩で形成された鐘状火山である志賀高原の笠ヶ岳も、長野盆地から見ると美しい菅傘の形状で、多くの人々lを魅了している。
[行程]
2020年8月18日(火)
自宅5:30→国立・府中IC→長野東IC→県道66号→12:00笠ヶ岳登山口12:15→12:40山頂13:45→14:05笠ヶ岳登山口→15:10横手山15:55→志賀・草津高原道路→万座有料道路→軽井沢IC→上信
越道→関越道→練馬IC→20:15自宅
 [山行日誌]
[山行日誌]
前回の一切経山と同じく車の走行距離が600キロ近くなるので、前夜は早く寝て早朝出発した。中央道から長野道に入り、信州中野ICで降りる予定であった
が、途中の諏訪湖SAでネット確認をしたところ、志賀高原の山ノ内町と群馬県高山村を繋ぐ県道66号線が昨年10月の台風で不通になっていた。慌てて長野
県道路管理署に電話したところ、高山村からは笠ヶ岳まで通行可能とのことで、長野東ICで降り、群馬県側から66号線に入って、山田牧場などを通過し、昼
過ぎに笠ヶ岳登山口に到着した。昨年、長野県では台風19号で千曲川が氾濫し、大きな被害を受けたことを思い出した。登山口の標高は1910メートル、た
った166㍍登れば良いので余裕たっぷりである。他に3台の車が停まっていた。
早速準備をして登山開始。峠の茶屋は本日は休みのようだ。まずはササの生い茂る木段の道を登っていく。最初は緩やかだがだんだん傾斜が厳しくなって
いく。やがて通常の登山道になり、さらに行くとロープが現れ、岩場となる。ひと汗かくと話声が聞こえてきて、そこはもう山頂である。
 狭い山頂には大きな岩が有り、ケルンが積んである。その大岩の横にはかすかに笠ヶ岳神社と読める標識板が有る。大岩の上から眺めると北アルプスの山
狭い山頂には大きな岩が有り、ケルンが積んである。その大岩の横にはかすかに笠ヶ岳神社と読める標識板が有る。大岩の上から眺めると北アルプスの山
々が勢ぞろい。槍、針ノ木、乗鞍、鹿島槍、五龍、白馬などが一望できる。時間はたっぷりあるので単眼鏡を出してゆっくり山座同定を楽しむ。1時間ほど山
頂に留まり、その後下山開始。あっという間に登山口に着き、まだ時間が有るので横手山に向かう。ナビでは3キロ、3分の表示だが、山ノ内町方面は通行
止めなので、大きく迂回して292号線に入った。若い頃、毎冬3度ぐらいずつ志賀高原にスキーに通った。真っ白な銀世界の中を、麓の渋・湯田中温泉から丸
池、蓮池、発哺と各スキーゲレンを通過、目的地の一ノ瀬スキー場を目指した。現在、志賀・草津高原道路は火山警戒警報レベルが2で、夜間(夕方5時か
ら~翌朝8時まで)通行止め、昼間も歩行者、バイク、自転車などが通行不可となっている。横手山に到着したのが午後3時、スカイレーターの係員に3時
40分までには戻ってくるように言われ、慌ててスカイレーターとリフトを乗り継いで山頂へ。山頂にある「日本一高所のパン屋」でパンを買って、笠ヶ岳を眺め
ながら食べた。20分ほど滞在して下りリフト、スカイレーターを乗り継いで4時前に駐車場に到着。すぐに志賀・草津高原道路のゲートを通り抜け、赤茶けた平原をしばらく走ったが、途中検問が有り万座
方面に迂回させられた。軽井沢を抜けて上信越道、関越道を通り、8時過ぎに帰宅した。
今回は今までで最も楽な三百名山であったが、冷涼な空気の中、、笠ヶ岳山頂から北アルプスの山々をゆっくり眺め、また、若い頃に何度も訪れた志賀高原を思い出し、有意義なひと時を過ごすことが
できた。
トップページに戻る