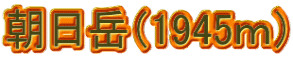
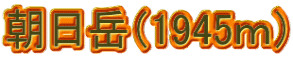

丂丂揤岓偑晄埨掕偱梊掕偟偰偄偨墱嶰奅妜傗敨惙嶳偺搊嶳寁夋偑師乆偲棳傟丄俉寧偺廔傢傝偵嬤偯偄偰偒偨丅揤岓偺惏傟娫傪尒偮偗丄扟愳楢曯偺挬擔妜偵搊傞偙偲偵偟偨丅杮棃側傜乽攏掻宍僐乕僗乿偲尵傢傟傞扟愳妜仺堦
丂僲憅妜仺晲擻妜仺挬擔妜仺妢儢妜仺敀栄栧仺搚崌偺僐乕僗偑堦斒揑偩偑丄僐儘僫偺偙偲傕偁傝嫹偄嶳彫壆偺廻攽傪夞旔偡傞偨傔丄挬擔妜僺僗僩儞偲偄偆僐乕僗傪慖戰偟偨丅挬擔妜偼扟愳楢曯偺搶晹偵偁傝丄搾瀢慭愳尮
丂棳偺嵟墱偵戕偊傞柤曯偱丄椗慄偐傜偼扟愳妜搶柺偺堦僲憅戲丆桯僲戲摍偺戝敆椡偺娾暻傪挱傔傞偙偲偑偱偒傞丅
丂丂[峴掱]
丂
丂丂丂丂丂丂丂丂2021擭8寧28擔乮搚乯
丂丂丂丂丂丂丂帺戭9丗30仺楙攏IC仺娭墇摴仺悈忋IC仺15丗00柉廻乽側偐偠傑乿攽
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂29擔乮擔乯
丂丂丂丂丂丂丂乽側偐偠傑乿4丗45仺5丗00搚崌挀幵応5丗10仺7丗19徏僲栘戲偺摢7丗38仺8丗19敀栄栧8丗30仺9丗15妢儢妜9丗27仺9丗56戝塆朮巕10丗06仺10丗34挬擔妜嶳捀11丗01仺11丗31戝塆朮巕11丗41仺12丗11妢儢妜12丗40仺
丂丂丂丂丂丂丂13丗20敀栄栧13丗36仺14丗12徏僲栘戲偺摢14丗32仺16丗19搚崌挀幵応16丗30仺悈忋IC仺娭墇摴仺楙攏IC仺20丗05帺戭丂丂丂
丂 丂[嶳峴擔帍]
丂[嶳峴擔帍]
崱夞丄嵢偼媫搊偺楢懕妿偮僐乕僗僞僀儉10帪娫50暘乮擔杮嶰昐柤嶳丂嶳曕偒僈僀僪丂JTB乯偲偄偆偙偲偱嶲壛偤偢扨撈峴偲側偭偨丅扨撈峴偼擇昐柤嶳傪廔偊偰嶰昐柤嶳偵庢傝
妡偐偭偰弶傔偰偺偙偲偱丄撿傾儖僾僗偺鈺箠x埲棃偲側傞丅傂偳偄曽岦壒抯偺巹偵偲偭偰偼摴柪偄偑嵟戝偺儕僗僋梫場偩偑丄岾偄丄崱夞偺僐乕僗偼柧椖偱丄懠偺搊嶳幰傕戝
惃偄傞偺偱怱攝偟偰偄側偄丅
丂1擔栚偼柉廻偵摓拝偡傞偩偗側偺偱備偭偔傝弌敪丄廰懾偺娐敧傪偄偮傕偺攞偺帪娫傪偐偗偰敳偗丄僠僃僢僋僀儞僞僀儉傛傝偐側傝憗偔廻偵摓拝偟偨丅搚梛擔偵傕偐偐傢傜偢懠
偺媞偼偍傜偢戄愗忬懺偱偁傞丅偺傫傃傝夁偛偟偨偑丄晄巚媍側偙偲偵傎偲傫偳柊傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅
 丂梻擔偼11帪娫偺挿挌応丄偟偐傕塣揮偟偰婣傜側偗傟偽側傜側偄偺偵丄徟傟偽徟傞傎偳栚偑嶀偊偰偟傑偭偨丅傛偆傗偔抁帪娫柊偭偰栚妎傑偟偺壒偱婲偒丄廻偺彈彨偝傫偵尒憲
丂梻擔偼11帪娫偺挿挌応丄偟偐傕塣揮偟偰婣傜側偗傟偽側傜側偄偺偵丄徟傟偽徟傞傎偳栚偑嶀偊偰偟傑偭偨丅傛偆傗偔抁帪娫柊偭偰栚妎傑偟偺壒偱婲偒丄廻偺彈彨偝傫偵尒憲
傜傟偰5帪慜偵弌敪丄15暘屻偵搚崌挀幵応偵拝偄偨丅偐側傝偺悢偺幵偑挀幵偟偰偄傞丅偡偖偵弨旛傪偟偰曕偒巒傔偨丅嶐擔丄搊嶳岥傪妋擣偺嵺偵傕傜偭偰偍偄偨搊嶳撏傪億
僗僩偵擖傟丄庽椦懷偵擖偭偰偄偔丅僕僌僓僌偱媫側旜崻摴偵弌傞丅偙傟偐傜墑乆偲娾崿偠傝丄崻偭偙偑棈傑偭偨曕偒偵偔偄摴偑懕偔丅揤婥偼敄撥傝丄嬻婥偼傑偩椻偨偄偺偱丄愨
岲偺搊嶳擔榓偱偁傞丅傂偨偡傜懌傪慜偵弌偟丄俀帪娫嫮偺恏書偱徏僲戲偺摢偵摓拝丅堦屇媧擖傟傞丅扟愳妜偺堦偺憅戲偺戝娾暻偑敆偭偰偄傞偑丄巆擮側偑傜嶳捀晅嬤偼擹
偄僈僗偑偐偐傝丄慡懱憸偑傛偔暘偐傜側偄丅師偵敀栄栧偵岦偐偆丅業娾偑憹偊偰偒偰僋僒儕応傗儘乕僾偑壗搙傕尰傟傞丅堦偮堦偮傪怲廳偵墇偊傞偲敀栄栧丅攏掻宍偵暲傫偩
嶳乆偑夃傫偱尒偊傞丅扟愳妜偺愥宬偑傾僋僙儞僩偲側偭偰偄傞丅廻偱梡堄偟偰傕傜偭偨偍偵偓傝傪怘傋傞丅儁僢僩儃僩儖偼俇杮丄枩慡偱偁傞丅敀栄栧偐傜妢儢妜傪栚巜偟偰杒偵岦
偐偆丅

丂峴偔庤偵偼妢儢妜丄彫塆朮巕丄戝塆朮巕偺椗慄偑懕偄偰偄傞丅挬擔妜偼傑偩堿偵塀傟偰偄傞丅妢儢妜偺埰晹傑偱壓傝丄僒僒傗掅栘偵暍傢傟偨摴傪搊偭偰偄偔偲妢儢妜嶳捀丅
丂墦朷偼棙偐側偄偑椢偵暍傢傟偨嶳乆偑惔乆偟偄丅嶳捀捈壓偺埰晹偵娵偄壆崻偺旔擄彫壆偑偁傞丅係乣俆恖擖傟偽堦攖偲偄偆彫偝側傕偺偩偑丄偄偞偲偄偆偲偒偼棅傝偵側傞
丂僒僒偺惗偄栁傞憪尨偵強乆崅嶳怉暔偑巔傪尰偡丅僴僋僒儞僼僂儘丄儈儎儅傾僉僲僉儕儞僜僂丄僴僋僒儞僐僓僋儔丄僞僇僱僶儔側偳擌傗偐偱偁傞丅懅傪抏傑偣側偑傜彫塆朮巕
丂戝塆朮巕傪墇偊丄嫹偄椗慄偺娾応偺搊傝壓傝傪婔搙偲側偔孞傝曉偟丄傛偆傗偔挬擔妜嶳捀偵摓拝丅僈僗偑棳傟丄偁偭偲偄偆娫偵曯乆傪塀偡偑丄傑偨丄偡偖偵惏傟傞丅桞丄巆擮
丂側偙偲偵扟愳妜搶柺偺戝娾暻偺忋晹偼僈僗偵暍傢傟偨傑傑偩丅旜悾偺鄿働妜傗帄暓嶳丄墇屻偺嬵働妜傗拞僲妜偑巔傪尒偣偰偄傞丅婰擮幨恀傪嶣偭偨偺偪壓嶳偵偐偐傞丅
 婣傝偺峴掱偼挿偄偺偱偺傫傃傝偼偱偒側偄丅桞丄傑偩屵慜拞側偺偱帪娫偵梋桾偑偁傞丅攏掻宍偺廲憱楬忋偵偼扨撈峴傗僌儖乕僾偺搊嶳幰偑師乆偲傗偭偰棃傞丅戝塆朮巕丄
婣傝偺峴掱偼挿偄偺偱偺傫傃傝偼偱偒側偄丅桞丄傑偩屵慜拞側偺偱帪娫偵梋桾偑偁傞丅攏掻宍偺廲憱楬忋偵偼扨撈峴傗僌儖乕僾偺搊嶳幰偑師乆偲傗偭偰棃傞丅戝塆朮巕丄
彫塆朮巕傪墇偊偰妢儢妜偱戝媥巭丅怱攝偟偰偄偨塃旼偑懡彮捝傒弌偡丅嵍旼偲僟僽儖僗僩僢僋偱偐偽偊偽壗偲偐側傝偦偆偩丅妢儢妜傪壓傝丄敀栄栧偺媫搊傪怲廳偵搊傞丅敀栄
栧嶳捀偵偼懡偔偺搊嶳幰偑媥懅偟偰偄傞丅偙偙偱傕彫媥巭偟偰孅怢傪孞傝曉偟旼傪儕儔僢僋僗偝偣傞丅偝傜偵徏僲栘戲偺摢偱嵟屻偺彫媥巭傪庢傝丄搚崌搊嶳岥偵偼16帪夁偓偵
摓拝偟偨丅娾偁傝丄崻偭偙偁傝丄抜嵎偁傝偺挿偄挿偄壓傝偩偭偨丅幵偱拝懼偊丄偡偖偵婣戭奐巒丅娭墇摴偺愒忛崅尨SA偱梉怘傪庢傝丄偦偺屻丄100僉儘梋傝憱偭偰婣戭偟偨丅
丂媣偟傇傝偺扨撈峴丄昗崅嵎1700嘼偲偄偆懱椡彑晧偺擄僐乕僗偱偁偭偨偑丄揤岓偵宐傑傟丄壗偲偐柍帠偵忔傝愗傟偨偙偲偵戝曄枮懌偟偰偄傞丅扟愳楢曯偺戝娾暻丄偦偺暻傪
崗傓婔嬝傕偺愥宬丄僒僒偑暍偆椢偺憪尨丄懌尦偵嶇偔崅嶳怉暔丄偄偢傟傕偑挿偔婰壇偵巆傝偦偆偩丅
丂丂
丂僩僢僾儁乕僕偵栠傞