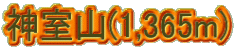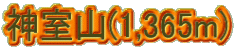
 「百名山」では近畿の山として大台ヶ原、大峰山八経ガ岳に登ったが、今回は奥駈道の核心部で
「百名山」では近畿の山として大台ヶ原、大峰山八経ガ岳に登ったが、今回は奥駈道の核心部で
ある釈迦ヶ岳と、小辺路にある山で、平家の公達平維盛の落ちた先である伯母子岳に登ることに
した。
奥駆道とは、修験者が修行のために天狗のような速さで駆け抜ける吉野から熊野までの道であ
る。また、小辺路とは、京都から熊野参詣のための道の一つで、他に大辺路、中辺路がある。い
ずれも山自体としては標高的にも峻険さにおいても大したことはないが、近畿地方は1000年もの
間日本の政治経済の中心であった地であり、歴史ロマン豊かな数々の伝説に溢れた地でもある。
その地域に接し、ある時は修行の場、ある時は戦の舞台となったのが今回登るである。
「行程」
2008年5月5日(月)
自宅5:00→羽田空港6:40→関西空港8:21→橋本10:05→釈迦ヶ岳登山口13:15→14:55山頂15:05→16:35登山口16:45:→19:00民宿「よしの屋」
6日(火)
「よしの屋」6:10→伯母子岳登山口7:10→9:13山頂9:37→登山口11:10→伊丹空港18:00→羽田空港19:15→20:45自宅

「登山日誌」
ゴールデンウイークの後半なので、道路はどこも渋滞することを予測して、できるだけ目的地に
近いところまで電車を利用した。今回は始めて関西空港を利用し、そこから橋本まで南海電車を
使い、そこでレンタカーを借りた。十津川沿いの国道を走り、その後林道を2時間ほど走って、釈迦
ヶ岳登山口に到着。駅で購入した柿の葉寿司で昼食を済まし、登り始めたのは登山としてはかな
り遅い13時過ぎだった。登山口の標高は1,320mであり、山頂までの標高差は約500m、ゆったり
とした足取りで登り始めた。ササを刈り払った道で歩きやすい。天気は曇りで今にも雨が落ちてきそうである。30分ほどで1,432mピークに到着。ここから稜
線歩きとなる。道は緩やかで完投とは異なる山の雰囲気を楽しみながら高度を上げていく。1,432mピークから30分で古田の森に着く。ここら辺りはトウヒが
が目立つ。足下にはバイケイソウの緑の葉がササ原にアクセントを添えている。突如
静寂の中ピーという甲高い鳴き声が響いた。前方に2頭のシカがいてこちらをじっと見ている。カメラを向けるとさっと逃げていった。
「深山堂」の標識を過ぎ、湿地を抜けると千丈平、更に行くと奥駈道と合流する。そこから15分で釈迦ヶ岳の山頂に到着。青銅の釈迦如来像が出迎えてく
れる。明治時代に鬼雅という強力が一人で担ぎ上げたと言われている。等身大であり一人で担ぎ上げるのは大変だったと思うが。
ガスがかかり視界がほとんど無く、大好きな山座同定はできないので、早々に下山にかかる。登りやすい道は当然降りやすい。走るように下って、1時間
40分で登山口に着いた。
その後、林道、国道、林道と乗り継いで宿泊地「よしの屋」に19時に着き、早速山菜中心の夕食をごちそうになった。
オーナーの吉野さんはここらあたりの自然保護の中心となっている方で、植林帯の手入れが不十分なことに心を痛めていた。木の葉で色々な曲を演奏し
てくれ、我々にもそのやり方を教えてくれた。宿泊客の中に大学の先生がいて、自分が始めてスギの花粉を数えたと言っていた。色々な方の色々な話しを聞
けるのも200名山の旅の楽しみである。
 翌朝吉野さんご夫妻と記念写真を撮った後、平維盛の終焉の地と言われる平部落に入り、川原
翌朝吉野さんご夫妻と記念写真を撮った後、平維盛の終焉の地と言われる平部落に入り、川原
樋川を渡って熊野参詣道小辺地にある大股登山口に7時に到着。準備を整えた後伯母子岳山頂
を目指した。
釈迦ヶ岳より400m以上標高が低いので、里では八重桜が満開であり、登山道は広く明るく、太陽
の日射しに照らされた新緑が眩しいくらいである。スギやヒノキの美しい樹林帯を昨夜の吉野さん
が話していたことを思い出しながら登っていく。非常に歩きやすい道で、近隣の小学生が集団登山
をしているそうだ。右手に見える夏虫山との分岐点を過ぎしばらく行くと、道は下りに転じる。更に
行くと護摩壇山との分岐点がある。アセビとホオの雑木林を15分ほど登ると伯母子
岳山頂に到着する。
 山頂からの眺めは素晴らしく、昨日登った釈迦ヶ岳や弥山が影絵のように青空に浮かんでいる。
山頂からの眺めは素晴らしく、昨日登った釈迦ヶ岳や弥山が影絵のように青空に浮かんでいる。
帰りは1時間半で降りてきて、その後野迫川温泉で汗を流し、橋本でレンタカーを返却、今度は伊
丹空港から羽田に戻ってきた。
今回の釈迦ヶ岳と伯母子岳はどちらも登りやすく下りやすかったが、その山麓や登山道には日
本の古代や中世の歴史を支えた自然があり、その息づかいが感じられた登山であった。
トップページに戻る。