 登山案内(河口湖口)
登山案内(河口湖口)
(Update:2000/08/03)
<登山準備>
・服装 −帽子は必需品。靴もトレッキングシューズの様な"軽登山靴"を用意しよう。
靴底の柔らかいものは疲れるし、スニーカーだと靴自体が保たない
事がある。上着は、"重ね着"で調節できる様なものを。日の出前の
山頂は、風が吹くと真冬以下の寒さに感じる。ご来光登山の場合
"防寒具"は絶対に必要。岩場から手を守る"軍手"も寒さに有効。
・持ち物−水。下山時を考慮すると1人1リットル以上は持っていきたい。
夜間登山なら懐中電灯&予備電池は必要。登山時のカロリー補給用に
"バナナ"か"ウィダーインゼリー"の様な食品を。チョコレートも良い。
それから"ゴミ袋"。ゴミは絶対に持ち帰ること。
・その他−携帯電話は"DOCOMO"に限り全エリアで使用可能。
煙草は5合目以上では売っていないし携帯灰皿を持っていない
人は吸っちゃ駄目。天候により、砂埃が舞い上がるので、
コンタクトの人はゴーグル等の砂よけがあると泣かずにすむ。
また"マスク"(手ぬぐい等で代用しても可)も砂塵対策に効果的。
足首への砂利の浸入を保護する"スパッツ"もあった方が便利。
<富士スバルライン>
中央高速"河口湖インター"を出て右折。その先の立体交差を下らずに
左側へ進んですぐの交差点を左折する。後は道なりに真っ直ぐ進めばよい。
途中の料金所で、往復分の料金を支払う。(ハイウェイカードの使用不可)
5合目までは約30km、40分位。途中に休憩所があるので、一息入れて
景色を眺めて見ては。
<5合目>
5合目の1km位手前に差し掛かると、道の両端に「登山者用駐車場」という
標識が目に入る。しかし、下山後の1kmはかなり厳しいものがあるので、
渋滞を我慢しても一番奥の駐車場に入れることをお奨めする。
登山開始2〜3時間前の到着を目安にすると良い。はやる気持ちを
押さえて、仮眠や腹ごしらえ等、のんびりと過ごせば、2時間ぐらい
あっという間。すでに標高2304mなので、身体を高度に慣らせる
効果もある。また、外に出ると少し肌寒いので薄手の上着等で調節しよう。
信心深い人は、小御岳神社に行って安全祈願をしておこう。神社は登山口に
向かって、左側手前のお土産屋の間にある。駐車場からは徒歩3分程度。
山頂から手紙を出す人は、絵はがきを買って宛名書きをしておくと良い。
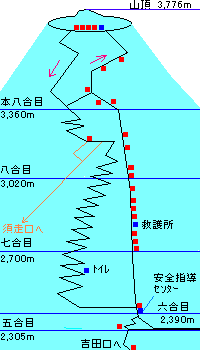 <登山開始〜6合目>
<登山開始〜6合目>
最初は拍子抜けするけど緩い下り坂。眼下に広がる景色を眺めながら、
急がずに歩こう。また、7合目の途中までは馬や車が通ることもあるので
要注意。馬の"落とし物"が多数存在するので、くれぐれも踏まないように。
やがて分岐が現れる。右手の岩肌に沿って登っていくのが"河口湖口"の
正規の登山道だが、真っ直ぐ行っても"吉田口"の登山道に合流できる。
6合目の手前で合流するが、"吉田口"に向かうと"佐藤小屋"の焼き印が
押せるメリットがある。(但し遠回りになることは言うまでもない。)
ここからは上り坂。"準備運動"のつもりで、呼吸を整えながら登ろう。
30分程で、安全指導センターに到着する。ここが6合目。ここでは
登山案内を配っている。もうしばらく登ると6合目唯一の小屋"穴小屋"に
到着。ここまでは序の口。まだ85mしか上っていない。
<6合目〜7合目>
穴小屋を過ぎると、比較的単調な上り坂が続く。山小屋も無くただ黙々と
登るのみ。次の山小屋を目指すあまり、オーバーペースにならないように
1ターン毎に立ち止まって息を整えるくらいの感じでダラダラ登ろう。
この辺りでは、まだ気温も高いのでちょっと登るとすぐ汗をかく。
十分に水分を補給することと、休憩したときの体温調節には注意する。
休憩時は山側に沿って、他の登山客の邪魔にならないように。
<7合目〜8合目>
7合目の"花小屋"からは山小屋群が続くので、次の山小屋を目指しては
"休憩"位のペースで登ろう。この辺は"岩場"が続く。比較的登りやすいが
岩に手を掛けて登るような箇所もあるので、軍手をしっかりはめて。
また、高山病の症状が現れ始めるのもこの辺りから。呼吸が乱れたり、
頭痛や目の前がチカチカしてきたら、すぐに休む。しばらく経っても
症状が治まらないようであれば、救護所へ行くか即下山する。
もし、症状が治まるようであるなら、少しペースを落としてゆっくりと
登山を続けてみよう。決して無理は禁物。中止して下山する勇気も必要。
"東洋館"が、ほぼ海抜3,000m地点。登り始めて695m。まだ半分以下。
<8合目〜本8合目〜8合5尺>
8合目の"蓬莱館"を過ぎてからは、延々と"8合目"が続く事となる。(-_-;)
足元は"小砂利"。6〜7合目と同様の単調な上り坂が延々と続くが、
かなりの急勾配になっている。"富士山ホテル"までが、この登山道の一番の
難所というか辛い所。水分・カロリーの補給を十分に行いながら焦らずに
ダラダラ登る。もちろん高山病にも注意して、休憩もこまめに。
"御来光館"が、8合5尺。ここが最後の山小屋なので、しっかりと
休憩を取っておく事をお奨めする。ここで海抜3,450m。
 <8合5尺〜山頂>
<8合5尺〜山頂>
平成元年の登山時は9合目にも山小屋が合ったような気がしていたのだが?
ねこの金剛杖には"標高3,600m"という"謎の焼き印"が確かに押されている。
9合目を過ぎると、再び"岩場"をよじ登る事となる。
かなり狭い所があるので、休憩を取る際は他の登山客の邪魔にならないように。上方からの
落石にも十分注意する事。明るければ、山頂は間近に見えているはずだが
慌てずに足場を確認しながら慎重に登る。不意に足場が階段に変わったら
ついに河口湖・吉田口の頂上。大きな"鳥居"と"こま犬"が迎えてくれる。
その先に"久須志神社"と、頂上の山小屋群(4件位)が併設されている。
日の出はAM4:40前後。山小屋を背にした方向が御来光の位置。
AM5時頃から久須志神社も開く。金剛杖の"頂上御朱印"はここ。(300円)

←河口湖口山頂(久須志神社=東北奥宮)

富士宮口山頂(頂上奥宮)→
 <お鉢巡り>
<お鉢巡り>
コンディションさえ良ければ折角だから火口一周を散策しよう。
お鉢巡りは時計回りがルール。休憩無しで一周約70分。
河口湖口山小屋群から約20分歩くとNTTの出張所がある。
その先に見える富士宮山小屋群には、浅間大社頂上奥宮と
富士山頂郵便局がある。(写真→)
ここから手紙を出すと"山頂限定"の消印が押されるので、
是非記念に 投函する事をお奨めする。
(郵便局の営業は7/10〜8/20、AM6:00〜PM2:00)
もしコンディションが悪く、お鉢巡りができなくても
山頂の山小屋に頼めば投函を代行してくれるのでご安心を。
(切手を貼ってあれば、手数料1枚50円)
 さらに進むと、"富士山測候所跡"がある剣が峰。(3,776m)
さらに進むと、"富士山測候所跡"がある剣が峰。(3,776m)
"馬の背"と呼ばれる手前の坂はかなり急で、しかも滑りやすいので慎重に。
天気が良ければ、眼下に"駿河湾"を一望できる場合もある。
"剣が峰"を下っていくとすぐに、"大沢崩れ"の真上に立つことが出来る。
この先は特にイベントは無い。残り半周、滅多に見ることの出来ない
火口の様子や、アルプスの山々の景色を眺めながら河口湖口の山小屋群へと戻ろう。
なお、山頂のトイレは2カ所。両山小屋群にあるが富士宮側の方が多少きれい。
また"山頂限定"のお土産もある。少々お高いけど登頂記念になるので、
お財布と相談して是非購入することをお奨めする。
 <頂上〜須走口江戸屋>
<頂上〜須走口江戸屋>
下山開始前に厚手の上着は脱いでカバンにしまって置こう。晴れの日なら
すぐに暖かくなるので大丈夫。"砂塵対策"・"日焼け対策"もした方がベター。
登りと違い、下りは"オーバーペース"になりがち。重力に逆らうよう、杖を上手に
使いながらゆっくりと下りていかないと、最終的に"膝が大笑い"し出す。
また、下山道外への"落石"を防ぐ為にも"絶対に"走ったりしないこと。
(個人的に転んで怪我したくらいなら、別に何も言わないのだが…。)
山頂から須走口下山道との分岐点となる"江戸屋"まで約1時間弱。
ここを過ぎると、6合目まで山小屋は無い。水が切れてしまっている場合、
多少高いが飲み物を購入して置いた方が良い。
<江戸屋〜公衆トイレ>
約1時間30分ほど、延々と下り坂が続く。ペース配分に気を付けて、
なるべく休憩を取るように心がけよう。休憩を取る際は、カーブ等の
広い場所で。また上方からの"落石"にも注意が必要。
なまじ行く手が見えてしまうために、その道のりの長さにうんざりして
くるが、登った距離と同じだけ下りがあるのは世の常。遙か下方に見える
"白い屋根"を目指して、黙々と下る。ここで間違えてはいけないのが、
そこが"終点"では無いと言うこと。やっとの思いで"白い屋根"の一段上の
カーブにたどり着いたそこには、"衝撃的"な事実を記す看板がある。
「ここから6合目まで1.4km(約30分)」…ぐうの音も出ない。(;_;)
あきらめてトボトボと再び歩き出す。
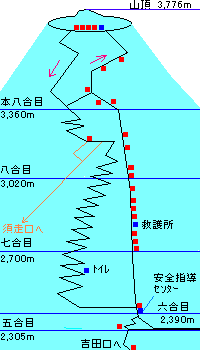 <公衆トイレ〜6合目>
<公衆トイレ〜6合目>
再び歩き始めてからしばらくすると、今までとは違って真っ直ぐな下り坂に
変わる。この辺りは地面が固く、とても滑りやすい。踏ん張りの利かなく
なった足にはとてもこたえるものがある。"落石避け"のトンネルが2つ程
連なっている。コンクリートは少々歩きづらいものがあるが、危険防止の
ため、我慢してトンネル内を歩こう。2つ目のトンネルの出口付近で、
最後の休憩を必ず取る事をお奨めする。残った水を飲み、チョコ等を食べ、
長かった下り坂の疲れから回復するまで、十分な休息を取ろう。
さもないと、その先に待ちかまえる"馬"の背中に揺られて、5合目まで
戻っていくあなたの姿が…。(別に利用しても良いですが…12,000円ですョ)
馬を横目に、さらに10分弱下り、ほんのちょっと登ると6合目の
"穴小屋"に到着。ここで登山道と合流。後は見覚えのある道を戻るだけ。
「久々の登りは新鮮!」なんて錯覚に陥る気持ちもわからなくは無いが…。
<6合目〜5合目>
約1.9kmの道のり。下りの階段や固い地面に足を取られながらも、なんとか
最初の分岐点まで到着。この辺りは"馬の落とし物"が多いことは前述した。
言うことを利いてくれない足が行き着いた先は…「ア゛〜う○ち!」なんて。
この先、登山時には"拍子抜け"だった下り坂が、ついに牙をむく事になる。
そう。帰りは当然の事ながら"上り坂"になっているのだ!
砂地の地面は残り少ない体力を容赦なく奪い取っていく。しかもダラダラと
した登りの終わりが見えない。途中、今度は"馬車"の誘惑が待っている。
こちらは1,000円なので、自分の体力と相談して利用しても良いだろう。
"終わりが見えない"と書いたが、実は坂を上りきったところがすぐ終点。
急ぐことが無ければ、後は気力を振り絞って歩くのみ。
<帰路>
駐車場は"無料"なので、焦って帰り支度をする必要もない。十分休んで
お土産等の買い物を済ませてから帰宅の途に付こう。途中、出来れば
"日帰り温泉"の様な施設を利用して、登山の疲れを癒して行くことを
お奨めする。特に"運転手"の方。"仮眠を取る"等の方策を取らないと、
"居眠り運転"を引き起こすので要注意。
とにもかくにも無理は禁物ニャ〜。

 戻る。
戻る。
 Home
Home
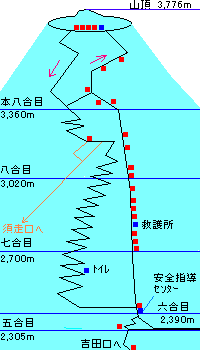 <登山開始〜6合目>
<登山開始〜6合目> <8合5尺〜山頂>
<8合5尺〜山頂>

 <お鉢巡り>
<お鉢巡り> さらに進むと、"富士山測候所跡"がある剣が峰。(3,776m)
さらに進むと、"富士山測候所跡"がある剣が峰。(3,776m) <頂上〜須走口江戸屋>
<頂上〜須走口江戸屋>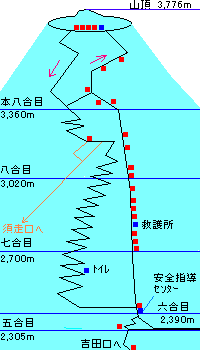 <公衆トイレ〜6合目>
<公衆トイレ〜6合目>