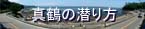
2.ダイビングコンピュータの利点 (潜水中で便利な機能)
お話が長くなってしまいましたが、これらを理解した上でダイビングコンピュータはどのようにして使用すればよいでしょうか。減圧症予防に関しての役割はダイブテーブルに譲るとして、その他の機能について有用な機能があります。
(1)高精度の水深表示
アナログ針式の水深計と比較して、ダイビングコンピュータの水深計の精度は高く通常10cm単位での表示です。そのため、アナログ式ではなかなか気づくことができないゆっくりとした水深の変化にも、ダイビングコンピュータなら直ぐに気づくことができます。こうした機能は、透視度が1~2m程度で周囲が全く何も見えない中で、速度を調整しながら浮上するような場合に力を発揮します。だからといってバッテリーが不要で耐久性の高いアナログ式の水深計が不要な訳ではなく、必ずバッアップとして併用する必要があると考えます。(バディーがバックアップという考え方は事故の元です。かならずバックアップも自分で用意しましょう。)
(2)潜水時間の表示
水深1.5m以深になると潜水開始として認識するなど、潜水開始を自動的に認識する機能があるものが多いです。ダイバーズウォッチの場合は、潜降開始時にベゼルを回しダイビング開始時刻をセットします。分単位で管理するダイバーズウォッチと比較して、ダイビングコンピュータの潜水時間は秒単位での管理ができます。但し、潜水時間についていも水深計と同様に、かならずダイバーズウォッチをバックアップとして併用しておく必要があると考えます。
(3)情報を一元管理できる
潜水中にダイビングコンピュータを確認すると、水深と潜水時間を同時に見ることができます。ゲージについている水深計を見て、ダイバーズウォッチの潜水時間を確認するという作業を、ダイビングコンピュータなら一度に出来るため、実際には両方をこまめに確認できることになります。
(4)安全停止の管理
6mまで浮上すると自動的に安全停止時間のカウントを始めます安全停止の残り時間をデジタルで表示してくれるのは大変見やすく、便利な機能と言えます。
3.ダイビングコンピュータの利点 (ログ機能として有用な機能)
ログ機能と言っても、一日の潜水終了後にログブックを書くのに便利と言う意味ではありません。ではどのような機能かを見てみましょう。
(1)潜水開始・終了時刻のログ
ダイバーズウォッチが潜水開始時刻と潜水中の潜水時間の管理が出来ても、潜水終了時刻と最終的な潜水時間はログ付けまでの間、記憶を頼りにしなくてはいけないのに対して、ダイビングコンピュータの場合は、潜水開始時刻と終了時刻をデータに残します。これは水面休息時間をダイブテーブルを用いて正しく計算し、次の潜水や高所移動の計画を立てるのに有用な情報を得ることができるということを意味しています。
(2)潜水時間のログ
マルチレベルダイビングを前提としているダイビングコンピュータでありながら、浮上完了時までをボトムタイムとしているのは、ダイビングコンピュータとしては自己否定してしまっていますが、ダイビングコンピュータで最も遅い組織が窒素放出を開始するまでの時間を潜水時間とするよりも、むしろこの方が正しい潜水時間と言えるのでこの値を潜水時間として考え、ダイブテーブルから潜水終了後の潜水記号を求めるのに有用な情報となります。
(3)平均水深
最大水深で箱型潜水をする場合のエアーの消費率(CR)は、初期残圧と最終残圧と最大水深から求めることができますが、マルチレベルダイビングの場合は、呼吸する圧力は変化しますから平均水深からでないとエアー消費率を求めることができません。ダイビングコンピュータの中には、平均水深をログに残す機能があるものもありますから、その場合にエアー消費速度が計算できることになります。
CRaverage=⊿Ptank×Vtank / (Tdive×Paverage)
CRaverage:エアー消費速度(ℓ/分)。一分あたりのエアー消費量
⊿Ptank :残圧変化(ゲージの初期残圧と最終残圧の差)
Vtank ::タンク容積(10リットルの場合が多い。タンクの刻印から調べます)
Tdive :潜水時間(ダイビングコンピュータやダイビングウォッチで計測したもの)
Paverage :平均圧力 Paverage= ((D平均水深/10)+1)
これは様々な理由で正確な値でない場合もありますが、参考となる値です。いつもと比べてエアー消費速度が早ければ、水中でのストレスが大きかったと考えることができます。いつもと潜る水深が違った場合では、潜水時間と残圧だけではストレスが実際にあったのかどうかを判断ができませんが、平均水深がわかれば、この潜水でエアー消費率がどうであったか、つまりストレスの多いダイビングだったかどうかを客観的に判断することができます。
またこの消費率が現実的に何の役に立つかですが、例えばストレスが多い潜水だった場合、U.S.NAVYの場合は通常のダイブテーブルは使えず、それ以降は減圧症にかかりやすいとして再潜水は行いません。そのような判断を各自が行う為の客観的な参考値になると言えます。初心者のころはまだ慣れていなくてストレスが多いはずです。であれば当然1本で終わりにする必要がありますし、ガイドであればゲストのエアー消費の状況を見て、無理をせずに1本で終わらせる判断も必要となります。つまり安全対策に有効活用が可能な定量的な数値データとなります。
4.最終警告機能としてのダイビングコンピュータ
(1)浮上速度の警告
浮上速度が10m/分を超えて速すぎる場合にはアラームが鳴るものが主流です。但し鳴ってからでは遅いですので、これは最終警告の機能という認識で使用する必要があります。疲労や体温低下などの厳しい状況での意識の低下などで浮上速度違反した場合などに指示をしますので、自分が危険な意識の状態になっているのを気づかせる、言わば意識のバックアップとしての機能と言うことになります。
(2)潜水時間超過の警告
潜水可能時間については臨床試験をされていませんので、「遊べる機能」という程度の認識にしておく必要があります。むしろダイバーが疲労や体温低下などの意識低下の際に潜水時間を超えても気づかない場合などに、アラームにより最終警告を出し気づかせるという機能という認識で使用します。Deco表示は最終警告表示と考え、潜水可能時間の表示は安全に潜れる時間ではなく、減圧症が更に深刻化するのを防ぐための最終警告までの時間という認識が重要です。

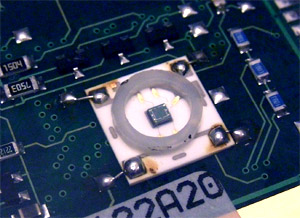
Mares製ダイブコンピュータの圧力センサー部
(1)残留窒素の計算精度の問題
減圧理論については別章で説明しますが、ダイビングコンピュータは、ダイブテーブルを作成する際に実験を行った結果から窒素吸収モデル曲線、窒素放出モデル曲線を作り、周囲の水圧を圧力センサーで計測し、水圧とモデル曲線を基にしてリアルタイムに残留窒素量を計算するというものです。しかし実際には体の中の窒素量そのものを測定しているわけではないですし、使用しているモデル曲線も精度は高くありませんので、それほど上手くいかないのが実態です。
ダイブテーブルでは、窒素吸収も窒素放出も1回ずつしか計算しませんので誤差も少なくて済みますが、マルチレベルダイビングになると何度も水深が変化し、そのたびに精度の低い計算式で繰り返し計算を行いますので益々誤差が蓄積されてしまう結果になってしまうという訳です。そこでなんとかしてより安全なモデル曲線を作ろうとダイビングメーカ各社が改良を加えていますが決定的なものはできていません。
TUSA IQ-700 実売価格 \20,000-
自分で電池を交換可能なので低コスト。
1.ダイビングコンピュータの使い方
(潜水時間の管理はダイビングテーブルを活用しよう)
ダイビング講習ではダイブテーブルを守るよう習いますが、実際にはダイビングコンピュータだけで潜ってしまうというのが実態です。しかしこういう状況に対して、 ダイビング器材メーカのタバタと東京医科歯科大学高気圧治療部は共同し、ダイビングコンピュータの潜水可能時間を信用してダイビングを行うことの危険性について次のように説明しています。「全国の減圧症患者数は、年間1000人近くいると推定されており、決して他人事では済まされない問題なのです。しかも、減圧症にかかった人の多くが、ダイビング中はダイブコンピュータを使用し、無減圧潜水時間を守っていることが分かっています。無減圧潜水時間を守っているのに、減圧症になってしまうことがある。これは一体、なぜなのでしょうか?」