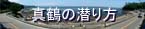

海で出会った生き物の中で一番危険な生物はと聞かれて、バディーと答えたという米国のダイバーの笑い話があります。これは形骸化した現在のバディーシステムの怖さを皮肉ったものだそうです。
二人のうち、スキルの低い人が自立して潜れる範囲でダイビングを行うというのがバディーシステムのルールと皆さんは習ったと思います。しかし実際はスキルの高いほうにあわせたダイビングが常習化してしまっています。逆にベテランダイバーについて潜ることを安全対策として推奨したりしている安全協会などがある程です。しかし頼られるほうにとっては単独潜水するよりも更に危険な状態になっており、本来矛盾した対策なのです。
ではガイドダイビングの場合はどうでしょうか。ガイドが顧客の安全の責任を持つというビジネスモデルは、同様に本来のバディーシステムをゆがめてしまっていると言えるでしょう。これについても実際には単独潜水よりも危険な状態でダイビングが行われていると統計結果は示しています。毎年のDANの統計を見ても、単独潜水事故件数が圧倒的に少なく、ガイドダイビングや講習中の事故が圧倒的に多いのが現実です。ガイドダイビングで自分のペースやスキル以上のところに連れられていくよりは、自らの責任で単独潜水で自分のスキルの範囲内で、自分のペースで潜ったほうが、まだ安全という状態にまでなってしまっているのが、残念ながら日本のダイビングの現状です。
しかしこれは何もダイビング業界側の問題だけでなく、実は消費者自身が自分のスキルの範囲を超えて、あるいは自覚せずにより素晴らしい体験をしたいとか、無意味にもより深度の深いところを体験したいなどを求めていることが問題を複雑化させています。消費者やダイビング業者の双方にとって都合の良い方向に安全対策がゆがめられて解釈されているからこそ、本当の原因究明がされず、事故も減らないのです。
本当は自分のエアーの管理ができないスキルの人にあわせたダイビングを計画する場合は、ダイビングを行わないという選択が必要です。しかしそれではダイビング業者も収益をあげられませんし、消費者側も要求を満たすことができません。双方の利害が一致して安全対策が歪められてしまうのです。OpenWaterDiverに要求される本来のダイビングスキルを身につけ、自らの管理を徹底し、自立することにより予防する事こそが事故発生件数を減らす最も有効な安全対策なのです。酸素プロバイダーが居ますとか保険に入っていますなどの事故後の対応ばかりを宣伝している中、平成21年になっても潜水事故件数は減少する傾向は見られません。
しかし上記のような事故後の対策は事故発生件数を減らすための対策にはなりません。また事故発生件数のほとんどがガイドダイビングやツアーダイビングであるにも関わらず、事故発生件数を減らす為の対策を「単独潜水の禁止」とすることが多いのですが、元々発生件数がほとんどない単独潜水事故を禁止するとしても、発生件数はもちろん減りません。これも実は上記と同様に、本来発生件数が多いガイドダイビングの事故、ツアーダイビングの事故の本当の原因を究明せず、ダイビング業者と消費者の双方にとって「単独潜水の禁止」とした方が好都合だったからに他なりません。
実際に潜水事故のデータを確認すると、平成17年のダイビング事故は、密漁や40mを超える大深度潜水という意図的な危険行為や違法行為を行うための潜水の2件を除くと単独潜水での事故発生件数は0件であり、逆にバディーシステムの形態を取りガイド潜水やツアーで潜水し、死亡したケースは17件、発生件数全体では30件となっています。この圧倒的な事故発生状況の傾向は、この年だけでなく例年、実は変わっていません。統計によっては単独潜水の事故が多いという説明をしている研究者もいますが、本当の単独潜水はほとんどなく、逆にガイドダイビングの事故で死亡すると、はぐれて単独潜水をしたからと結論づけられてしまうということを示しているに過ぎないようです。
これらの発生状況を確認してみると、そこから共通して言えるのは、バディーあるいはグループの内、最もスキルの低い人にあわせたダイビングが行われなかったということがあげられます。たとえガイドダイビングであっても、スキルの最も低い人に合わせた内容のダイビングにするという基本ルールは守らなくてはいけません。ダビングで事故にあわれた方が多くいらっしゃいますが、本来はガイドも、また他の参加者もその事故に遭遇された方に合わせたダイビングをおこなう必要があったはずです。しかしこの基本的で単純なルールは、現在の日本のガイドダイビングでは未だに守られないことが多いのです。消費者側のダイビング事故研究者も、ダイビング業界も、そしてダイビング関係の安全協会も利害が一致してしまい、本当の原因分析と対策には目を向けたくないのです。
年々、Cカード取得者数は減少の一途を辿っていますが、ガイドダイビングやグループダイビング、さらには講習中における事故が減少しないという事実は、事故発生率が増えていることを示しています。これまで発生した事故の原因究明や、そこから得るべき安全対策へのアプローチが誤っているからに他なりません。
本来、自分で管理して潜るダイビング、つまり本来のダイビングの形態であれば自らのスキルを超えたダイビングをしないところが、スキル以上のところにいとも簡単に連れて行かれてしまうことが常態化しているガイドダイビングやグループダイビング。それを安全対策であるとする安全協会のビジネスモデルに警笛を鳴らす時期に来ているのではないかと思います。
海で出会った生き物の中で一番危険な生物はと聞かれて、バディーと答えたという米国の笑い話をもう一度思い出してみましょう。琴ヶ浜ダイビングセンターは、こうした現状に問題提起をしています。琴ヶ浜ダイビングセンターではむしろ単独潜水を受け入れています。賛否があるとは思いますが、こうした現状の日本のダイビングの状態においては、むしろ自分の安全に責任を持つために自分のスキルの範囲で潜ることが許されるダイビング、つまり単独潜水を受け入れて欲しい、むしろ単独潜水によって安全対策を十分に取る自由を与えてほしいというニーズが高いからなのです。
2008年9月21日更新