(1)減圧症事故事例(下田海上保安部の発表を引用)を検証する
8月中旬、静岡県東伊豆において、事故者(女性、20代)は、引率インストラクター及び友人2名(男)の計4名にて3本の潜水(1本目潜水時間63分、最大潜水深度23m、2本目潜水時間60分、最大潜水深度25m、3本目潜水時間60分、最大潜水深度16m)を実施した。事故者は3本目の潜水終了後、東伊豆所在のダイビングサービスに戻り、風呂に入って休憩していたころ、下半身に軽い痺れを感じた。 同サービススタッフは潜水病の疑いがあることから、救急車を要請するとともに救急車到着までの約5分間、酸素投与を実施した。同サービスの酸素投与実施により症状が軽減、救急隊到着時には症状は消失していたが、救急隊員によりドクターヘリが要請された。ヘリ到着時には、既に事故者の症状は完全に消失し、自力歩行も可能な状態ではあったが、同ヘリにて大学付属病院へ搬送された。 事故者は、同病院医師から減圧症と診断、再圧治療により完治したことから退院した。事故者の既往症はなく、3本目の浮上時には水深5メートル付近にて10分間の安全停止を行った。 また、同行のインストラクター及び友人2名には潜水後の体調異変はなかった。引率のインストラクターはダイビングコンピュータで潜水及び休憩時間を管理していたが、同一日の繰り返し潜水と、各潜水時間が長い事から、当日の体調が万全でない事故者のみ減圧症が発症した。
この事故について検証してみたいと思います。まず一本目の潜水時間を見てみましょう。
1本目 最大水深23m、潜水時間63分
皆さんもご自身がお持ちのダイブテーブルで確認してみてください。ここではアメリカ海軍の標準減圧表で確認をして行きます。このアメリカ海軍の標準減圧表出確認すると、最大水深23mの無限圧潜水時間は40分となっています。つまり23分も超過していることになります。ではこの際の減圧時間を調べてみましょう。すると水深3mで23分間の減圧停止が必要とされています。5分の安全停止をしたとしても不足していることになります。それでもおそらくダイビングコンピュータではDecoは表示されていなかったはずです。これがダイビングコンピュータを使用して潜った場合の差で、これによって既に減圧症が発症してもおかしくない状態だったと言えます。(ちなみにこの水深と潜水時間の場合、3mでの減圧停止は23分間行わなくてはならず、それをおこなったとしても潜水記号はMとなります.しかし安全停止は3本目しか行っておらず、この一本目、二本目ともに行っていません。)
水面休息時間は不明ですが、更に二本目のダイビングを見てみましょう。
2本目 最大水深25m、潜水時間60分
最大水深25mの無限圧潜水時間は30分です。しかもこれは残留窒素がない状態においてです。既に一本目で無限圧潜水時間を越えていますが、ここで12時間の水面休息時間を取ったとしても、二本目だけでも無限圧潜水時間を越えています。たとえ正確に減圧潜水が行えていたとしても可能な潜水時間はマイナスです。
3本目 最大水深16m 潜水時間 60分
1本目、2本目、それぞれ残留窒素を考慮しないシングルダイブでも十分に減圧症が発症する条件がそろっていますので、3本目は既に説明のしようがありません。
しかし問題はそれだけではありません。
結果として減圧症が発症してもおかしくない状況ですが、問題なのはこの事故レポートの最後にあります。
「当日の体調が万全でない事故者のみ減圧症が発症した」
減圧症が発症した当人の体調管理の責任になってしまっています。確かにダイビングは自己管理も徹底して行わなくてはなりませんが、このような潜水計画をした側に大きな問題があると言わざるを得ません。このようにダイビング事故は、事故の分析が徹底して行われず、公的な機関でさえもこのような解釈をしてしまうことが分かります。
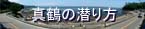
1.減圧症の事故分析 1
急浮上などの事故で最も致死性が高いのがエアーエンボリズムです。逆に減圧症の事故は、発症にタイムラグがあるため、減圧症に気づいていない方も多いのです。この減圧症を予防する為には、ダイビングコンピュータの潜水時間を見て潜るようなダイビングスタイルはやめ、ダイブテーブルによるダイビングに立ち返る必要があります。但しダイブテーブルの使用方法自体をインストラクターやトレーナーが間違って理解している場合も多く見られますので、問題は深刻です。このような状況でなされている日本のダイビングが安全であるはずもありません。
2.公的機関の発表の検証
潜水事故の分析をする際の事故例として、やはり公的な機関が発表する潜水事故概要が参考になります。海上保安庁が公開している事故例について、私たちが真摯に受け止め事故の再発防止に何ができるのかを考えたく思います。