第1部 暗黒騎士 Light in Darkness
第1章 星降草の夜
ヴァンは、ふた親の顔を知らぬ孤児だった。
光の王国アンディルの、うららかな春の朝、セフィアス神殿の白百合咲く門前に捨てられていた小さなみどり児だった。神殿にはみなし児たちを引き取って世話をしている養護院があり、彼のような子供は珍しくなかった。
ただ少しだけ、彼は他の子供と違っていた。彼を見つけた神殿の若い見習い巫女は、腕の中のみどり児が目蓋を開けたのを見て、思わず感嘆の声をあげた。みどり児の左の瞳は凍える冬の海のような深いサファイア
、右の瞳は夏の陽を映すトパーズの色だったのである。
彼はヴァンと名づけられ、その瞳の色から一部の口さがない者たちに『凶眼』などと呼ばれはしたものの、養護院や神殿の女たちに愛されて育った。この頃のアンディルは、老いた賢王アルフォンス・ハーン・セフィリアスを戴いた豊かな国で、時代はみなし児たちに優しかった。
そして、七度の春がめぐった。
ヴァンはひょろりと痩せた淡い金髪の少年に成長していた。雨であればこっそり神殿の書庫に潜り込んで、神々や英雄たちの活躍する物語を読み耽り、晴れた日には、同じ年頃の少年たちと野原を駆け回ったり、川で水遊びをするのが好きな、ごくありふれた少年だった。
そんな少年の日の春の夜、ヴァンは質素だが清潔な夜具の中で不思議な声を聴いた。
(──どこ?)
(どこにいらっしゃるの?)
(お祖父様……どこにいらっしゃるの?)
頭の裡に響いてくる、透きとおった哀しい声。
「誰?」
隣で眠る仲間を起こさないように、ヴァンは囁くような声で応えた。
(……お祖父様?)
「僕はおじいさんじゃないよ」
(お祖父様以外に、わたしの声が聴こえる人がいるの?)
「うん、聴こえてるみたい。なんだか不思議な感じ。……君は誰?」
(わたしはアイリア。あなたは?)
「僕はヴァン」
(ヴァン? そちらに行ってもいい?)
「構わないけど、どうやって?」
ヴァンが応えると、すぐ目の前にぼんやりと仄白い光が現れた。
「うわっ!」
ヴァンは思わず声をあげる。
(大きな声を出しちゃだめよ。他の人たちが目を覚まさないように、外に出ましょう)
アイリアと名乗った光は、蛍のようにすうっと飛んで、扉のほうへとヴァンを誘う。ヴァンは少し戸惑った。
(ヴァン……やっぱり怖い?)
闇の妖魔かも知れない──ちらりと思ったが、仄白い光は清浄で、ヴァンは惹かれるようにアイリアの後を追った。先を行く光は音もなく扉を通
り抜け、続くヴァンは扉をそうっと開けて、夜に足を踏み入れた。
神殿の庭園へと続く草むらには、夜に咲く星降草の薫りがたちこめていて、ヴァンは甘く薫る夜気を思いきり吸い込んだ。夜露に濡れた白く小さな星形の花が、夜着からのぞく足首に触れるのがくすぐったい。中空に浮かぶ月は細く昏く、星の瞬きがよく見える。
すべるように前を行く仄白い光が動きを止めると、光の中にぼんやりとした影が形をとりはじめた。声もなく見つめるヴァンの前に現れたのは、長い黒髪にこぼれそうなほど大きなエメラルドの瞳の少女だった。
「君が……アイリア?」
ふわりとした白い軽やかな衣裳をまとった少女を見て、物語に出てくる妖精のお姫さまみたいだ、そうヴァンは思った。
(来てくれてありがとう、ヴァン)
アイリアはスカートをつまんで優雅にお辞儀をした。 ヴァンはどうしたらよいか分からず、小さく頭を下げた。
「あの……さ。アイリア、君、透けてない?」
おそるおそるヴァンが尋ねる。
(心だけで飛んできたから。わたしの身体はお部屋にあるわ)
アイリアはにっこりと笑った──哀しみの滲んだ微笑み。
「……ね、さっき、君、泣いてなかった?」
(うん……お祖父様の声が聴こえないの)
アイリアは星降草を踏むことなく、その上にふわりと座ってうつむいた。大きな瞳からまた涙がこぼれ落ちる。
「ごめん、泣かないで」
思わずヴァンはアイリアの頬に手を伸ばしたが、するりとすり抜けてしまう。
(わたしこそ、ごめんなさい。わたしのほうからヴァンを呼んだのに、また泣いちゃって)
アイリアはひろがった袖で涙をぬぐった。
「お祖父さんが好きなんだね」
ヴァンが言うと、アイリアはこくりとうなずいた。
(わたしの声をちゃんと聴いてくれたのはお祖父様だけなの。お父様にも聴こえているはずなんだけれど、やめなさいって仰るだけ)
そう言ってから、アイリアはうつむいていた顔をあげてヴァンを見た。
(怖がらずに聴いて応えてくれたのは、あなたがふたりめよ、ヴァン)
「へえ。嬉しいな」
(わたしも嬉しい)
星降草の咲く草むらで、少年と少女はくすくすと笑った。
(ヴァン、あなたって……)
アイリアが、自分の色の違う双の瞳をじっと見つめているのに気がついて、ヴァンは思わず目を伏せた。
(光と闇の瞳を持っているのね)
「えっ?」
(おかしいわ)
ふいに小さく呟いて、アイリアが辺りを見回すような仕草をした。
(……なんだか外が騒がしいみたい。ごめんなさい、わたし、もう行かなくちゃ)
そう言ってふわりと立ち上がる。
(また来てもいい?)
「もっ、もちろん」
心持ち頬を赤くしたヴァンの目の前で、アイリアは闇に溶けるように消えた。星降草のやわらかな甘い薫りの中で、ヴァンはしばらくの間、少女が消えた闇を見つめていた。涼しい夜風に、短めに切りそろえたヴァンの淡い金色の髪がさらさらと揺れる。自分の髪に触れて、小さな星の花を摘んでから──少女に触れようとして届かなかった指が、少しだけ哀しいのに気がついた。
ヴァンが、アンディル王アルフォンス・ハーン・セフィリアス崩御の報を知ったのは、明くる日の朝のことだった。
アンディル王崩御の報は、国内外に大きな波紋をもたらしたが、十歳にも満たない少年のヴァンにとって、当初は貴人の世界で起こった遠い出来事に過ぎなかった。しかし、
聡明なるアルフォンス王の死が、ヴァンにとって深い意味あいを帯びてくるのは、そう遠い未来のことではなかった──。
王都イシュルディアは、亡き王の死を悼んで哀しみの色をまとった。
街には半旗が重たげに翻り、道行く人々は喪服あるいはどこかに黒を意識した身なりをしていた。ヴァンの細い腕にも修道女の手で黒い布が巻かれ、日頃、白以外の
装束をまとうことのないセフィアス神殿の巫女たちでさえ、頭をすっぽりと覆う黒い薄物のヴェールを垂らしていた。
星降草の夜のあと、十四の陽と月がめぐったが、アイリアは現れなかった。
アイリアとは、もう二度と会うことはないだろう──ヴァンはそう思いはじめていた。アイリア・リーデル・セフィリアス──亡き王の愛孫にして、王太子ゼフィルスのたったひとりの王女の名をヴァンは知っていた。
少年が半ば諦めかけていた夜、待ち焦がれていた声が彼の名を呼んだ。
(ヴァン……聴こえる?)
「アイリア?」
自然にはずむ声を抑えて、ヴァンは応えた。
(よかった。やっぱり、あなたにはわたしの声が聴こえるのね。今からそちらに行ってもいい?)
「うん。僕が外に出るから、君も外で待ってて」
そう言って、ヴァンはそろりと夜に出た。星降草の季節は短く、この夜は競うように最後の花を咲かせていた。月光の下、小さな星形の花の儚い薫りがたちこめる。ヴァンははやる気持ちを抑えて、なるべく花を踏まぬ
よう気をつかいながら少女の許へと急ぐ。仄白く光る少女は、以前と同じ場所に頭からすっぽりとヴェールをかぶって座っていた。
(こんばんは。なかなか来られなくて、ごめんなさい)
「ううん……だって、君のお祖父さん、亡くなったんだろう?」
(うん……)
アイリアの言葉が途切れる。居心地の悪さを感じて、ヴァンは少女に言った。
「あの……さ。やっぱり、そのヴェールってずっとかぶってなくちゃ駄目かな?」
(……そんなことないんだけど。ちょっと恥ずかしくて)
アイリアはそう言って、ヴェールに手をかけてからためらった。
(笑わないで、ね?)
少女はヴェールをするりと外した。
「えっ? どうしたの? その頭」
思わず大きな声を出してしまってから、ヴァンはあたりを見回した。少年が驚いたのも無理はなかった。ヴェールを外して見せたアイリアの姿は、はじめて会った夜とはかなり違っていた。腰のあたりまで垂らしていた少女の長い黒髪は、耳のあたりから段をつけるように切られて、襟足が見えるほどに短くなっていた。
(男の子みたいかな?)
アイリアは悪戯っぽく笑った。長いヴェールに隠れて見えなかったが、装いも黒っぽい上衣と裾の窄まったズボンに白いシャツという、いかにも貴族の少年めいたもので、今夜のアイリアはとてもきれいな男の子に見えた。
「それも似合ってるけど。でも、どうして変装してるの? ……だってさ、アイリアは王女さまなんだろう?」
(……王女のはずなんだけど。お父様はたったひとりの世継ぎが女の子なのがお嫌みたい)
「お父様? じゃ、その変装って、次の王様の命令?」
(これは、わたしだとわからないように変装してるわけじゃないの。お父様が、公式行事には世継ぎとして相応しい姿で出席しなさいって仰って。それから男の子の衣裳を着せられて、髪もばっさり切られちゃった。これはこれで動きやすいし、剣術を習うのは面
白いからいいんだけど。でも、あれだけはちょっとね……本当に笑っちゃいやよ)
「えっ?」
アイリアは何もないところから何かを取り出す仕草をした。ヴァンには見えないが、アイリアのいる場所にはそこに引き出しがあるらしい。少年めいた少女は手にしたそれを、鼻の下にぺたりと貼りつけた。
(今日、僕は父上のご命令で、謁見の間中、これをつけていたんだ。どうだ、似合うかね?)
アイリアは低い声色を作っておどけてみせた。
「あの……それって、つけ髭?」
ぷっ、と思わずヴァンは吹き出して、堪えきれず笑い出してしまった。短い髪や少年の服装は意外に似合っていて、少女の端正な顔立ちを引き立ててさえいたが、鼻の下にちょび髭をつけたアイリアの顔は酷く珍妙で、お祭りで見る素人芝居のようだった。
「ごっ、ごめん。でもさ、冗談じゃなくて本当につけてたの? ものすごく変だよ、それ」
(やっぱりそうよね。わたしも鏡で自分の顔を見て笑っちゃったもの。でも、誰もヴァンみたいに笑わないの)
アイリアは恥ずかしそうにつけ髭を外して、小首を傾げた。
(おかしいのよ。みんな笑わなくなってしまって。いつも、ぴりぴり緊張してるの。お祖父様が生きていらした時は、こんなことなかったのに)
「……アイリア」
(宮廷中がおかしいけど、わたしにはどうすることも出来なくて……)
アイリアはうつむいて、しばらくしてから気づいたように顔をあげた。
(わたし、この前からあなたに甘えてばかりいるみたい。ごめんなさい)
「いいよ。僕には話を聴くくらいしか出来ないけど」
(ありがとう、ヴァン)
少女は小さな花が揺れるように儚く、微笑った。
ずっと、この少女のそばにいたい──そうヴァンは願った。決して触れることのできない少女だとしても。
アルフォンス王の葬儀は、崩御の一ヶ月後、王家の創始神を祀るセフィアス神殿にて、アンディルの王族諸侯ならびに諸外国の王侯貴族列席のもと、荘厳かつ厳粛に執り行われることとなった。 王太子ゼフィルス・カーン・セフィリアスは、亡き王の偉業を讃えるため、此度の国葬の儀について慣例より長期かつ壮麗なものにするとの勅令を下した。この令により新たに税が課せられ、民は窮屈な生活を強いられることになったが、長年の安寧な治世により賢王は人々に敬愛されていたので、不満の声はさほど上がらなかった。当時のアンディルは豊かな国家だったのである──まだ、この時は。
2004.6.8
written by Mai. Shizaka
background by Silverry moon light
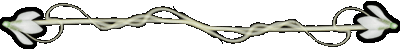
Copyright(C)2004-2005, Mai. SHIZAKA.
All rights reserved.

