中国メディア・東方早報は8日、発展途上国を中心に「日本式教育」への関心が高まっているとし、その特徴的なコンテンツとして運動会や学芸会、動物飼育の3点を挙げて解説する評論記事を掲載した。
記事は、今年8月に日本の文部科学省が「日本式教育」を海外に広めていく方針を発表したと紹介。そこには教材の編集、運動会、学芸会、動物飼育、学校給食、掃除当番、などのコンテンツが含まれているとしたうえで、なかでも日本の教育の特色が色濃く表れていると運動会と学芸会、小動物の飼育についてそれぞれ解説した。
まず運動会については、各学校が1カ月前から準備を始めるほど重視しており、その背景には「伝統的な人と人とのつながりが希薄化するなかで、学校を中心とする地域社会の連帯意識を強化する」目的があるとした。また、親と子、子どうし、保護者どうしの交流を促進するとも解説した。
さらに、学芸会・文化祭・学校祭については、生徒らが教室などに装飾を施し、日常とは異なる服装で演劇や模擬店といった活動を行うと紹介。「日常のルールを打ち破って自分たちをアピールする機会を与えることで、子どもの創意や個性を育む目的がある」と論じた。
そして、小学校で一般的に行われている小動物の飼育については、自然に触れさせる目的のほかにも、命を児童にゆだねることで責任感や生から死までのサイクルの認識を芽生えさせるために実施していると説明した。
子どものころの運動会や学芸会、文化祭といったイベントは、大人になっても特別な思い出として残っていることが多いのではないだろうか。それはみんなで何かを作り上げるという一体感や達成感によるものであるほかに、「脱日常」という要素もあるからだろう。もちろん、このようなイベントにいい思い出がない、という人も少なからずいる。
学校が単に教科書を学ぶ場ではなく、地域の連帯感を培うための存在でもあるとする分析は的確だ。この点において中国の学校が学ぶべき課題は多いように思えるが、いじめや学級崩壊が日常化している日本国内においても、もう一度「学校」の存在意義について考え直す時期に差し掛かっているかもしれない。記事は、「日本式教育」のポジティブな面について紹介する一方で、「決して完全無欠ではな」く、いじめなどさまざまな問題を抱えていることにもしっかり言及している。(編集担当:今関忠馬)
国内では教育崩壊、教育再生、などと揶揄される日本の義務教育だが海外ではめっぽう評判がいい。中国など「もしかしたら台湾・トルコをしのぐほどの親日国か?」と思わせるほどの大絶賛である。さらに学ぶ姿勢で分析するため、非常に客観的で正確なものが多い。上の記事などその代表である。
学校が単に教科書を学ぶ場ではなく、地域の連帯感を培うための存在でもあるとする分析
はもちろん的確だ。しかし運動会や学芸会を行うことで培おうとしているのはそれだけではない。
係活動を繰り返し行うことによる計画性や遂行能力の醸成、分業や協業になれること、責任をもって仕事を行うことや自分以外の係への配慮・協力。
勝負を競うことによる闘争心の育成、組体操などにおける忍耐力・胆力、その他基本的運動能力の伸長。
総じて個人の能力と社会性を、同時に鍛えようというのが特別活動のテーマなのだ。
ところが日本の一部では運動会や学芸会、修学旅行などは授業時間を削って行う教師と児童生徒の思い出づくりぐらいにしか思わない人々がいる。
彼らは言う。
「行事を精選し、授業時間の確保を!」
大人になって学問を背景に人生を送る人は少ない。
現在の私は、日本語(国語)は堪能なものの、英語・数学は中学校1年生並み、理科はそれ以下、音楽もカラオケぐらい、絵は数十年描いていない(だから描ける気がしない)。体育に至っては小学校4年生レベルか(?)。しかし生きていくに困らない。
勉強は(まったくできなくても困るが)トップレベルである必要はない。世の中のたいていの人々は私と同じ程度の学力で平和に、幸福に生きている。
しかし私が他人と協調できず、不道徳で、命を無残に扱える人間だったら、生きていくのはかなりしんどかっただろう。社会とうまく調和できない人間が平和に、幸福に生きることはできないのだ。
学校が何を大切にすべきかは、はっきりしている。
2015.12.17
中学生の「過労死」、中国で問題化
宿題大量、睡眠削り「寝たい…」
[withnews 12月16日]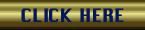
![]()
 (キースの逸脱)
(キースの逸脱)