2018.06.02
体操服の下に肌着禁止、小学校のルール変?
心配な親も
[朝日新聞 6月 1日]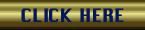
体操服の下に肌着は着てはいけない――。運動会シーズンが本格化するなか、小学校でのこんな「ルール」がSNSで話題になっている。学校側は、肌着を着たまま汗をかくと体が冷えるためだと説明するが、女児の胸など肌が透けて見えることを心配する親も。なぜ学校が子どものプライバシーにまで立ち入るのか、と疑問視する声もある。
疑問の声、ネットで拡散
「肌着禁止の理由ってなに?」「すれたら痛いし、意味が分からない」「これもう性的虐待では」……。5月半ば、ツイッターで女児の母親が懸念を投稿したのを機に、「うちの子も」といった声が拡散した。
「着替えるのに時間がかかるから、下着は脱いでいこうかな」。都内の母親(39)は5月初め、運動会の朝練習に出かける前に、小学4年の長女がつぶやいた言葉に驚いた。理由を尋ねると、長女が通う区立小では、体操服に着替える際に肌着を脱ぐことがルールになっていた。「女の子なのに、体操服1枚になるのは心配」と、担任に相談。校長にも、ルール化はおかしい、と伝えた。
担任は「汗をかくと体が冷えるから」と説明したが、校長は「汗臭くなるから」。結局、校長は「検討します」と応じただけで、今もルールの廃止にはつながっていない。
同じ学年の女子には、ブラジャーをつけている子もいる。また、インターネットのサイトには、体操服姿の女児の画像を集めたサイトも散見される。「子どもにとって、自分の発育は初めてのこと。大人が気づいて言わないと、子どもの体が無防備にさらされることになる。なぜ学校が、プライベートなところまで立ち入るのか」と憤る。
制服・体操服メーカーの菅公学生服(岡山市)が昨年3月、東京都と神奈川県に住む、小学生がいる母親1千人を対象に行った調査では、14・4%が「下着(ブラジャーや肌着)の着用が認められていない」と回答。1、2年生に限ると19・9%にのぼった。担当者は「下着が透けない体操服の需要を調べるために調査したが、下着の着用禁止がわりと多いなと感じた」と話す。
(後略)
学校というところは繰り返し職員が入れ替わってしまうので、校則一つひとつについてつくられた経緯とか理由を問われると困ることが多い。
その点「汗をかくと体が冷えるから」と即座に説明できた担任は偉いし、「汗臭くなるから」を理由に挙げた校長はさすが古株と誉めるしかないだろう。もちろん皮肉ではない。
一般に教師はやたら校則をつくってそれを振り回し、楽に児童生徒を指導したがっていると思われがちだがそうではない。校則はつくったら守らせなくてはならない。時間やエネルギーを使って子どもにあれこれ言わなくてはならない、そして子どもとの関係も冷える。
運動着の下の肌着のことなんか本当はあれこれ言いたくないのだ。面倒じゃないか。
ほんとうは、季節の変わり目に体育の授業が終わったあと、
「あ、だいぶ汗かいたな、冷えて風邪をひくといけないから予備の肌着に着替えよう」
そう自分から判断して着替えられる子、
「あ、オレ臭いぞ。こんな匂い振りまいて半日生活するのはマナー違反だ。家から持ってきたシャツに着替えよ」
そんなふうに配慮の行き届いた子、
すべての家庭がそういう子どもを育て、予備の肌着とともに学校に送り出してくれたらこんなアホな校則はつくらないで済んだ。面倒くさい指導もしなくて済むのだ。
ところが家庭はそういう立派な子どもを送り出す代わりに要求を出してきた。
「体育でびっしょり汗をかいたあとでそのままなんて、不衛生な上に不健康じゃないですが! 学校は何を考えてるんですか! 汗まみれの運動着や肌着を半日着たまま過ごすなんて意味が分からない。これはもう児童虐待ではないの? 汗をかいたら着替えるなんて当たり前でしょ。
ただし“体育のある日は毎回毎回着替えを持って行く”なんて、そんな面倒なことは真っ平ですからね!
あらかじめ肌着を脱いでおいて、体育が終わったらまた着る、それで十分じゃないですか、小学生なんですから。」
というわけで件の校則はつくられ、教師は「シャツは脱いでおくんだよ」と言わざるをえなくなった。
それが今や教師による「これもう性的虐待では」と非難される。
なかなかやっていられない世界である。
こうした校則を問題とする以上、朝日新聞は運動着の下の肌着を許可した場合、子どもが風邪をひいたり不衛生だったりするリスクを背負わなくてはならないことも説明すべきだ。さらに不衛生や不健康のリスクを回避する道は、運動中の肌着をやめるか、着替えを毎回持って行くか、二つに一つだと教えるべきである。
とにかく学校を非難すれば記事になるという態度はやめてもらいたい。
え? 朝日が非難しているんじゃなくて、「都内の母親(39)」をはじめとするツイッター住民が非難しているんだって?
そうだよな。マスメディアはいつでも「(非難している人がいるのは)事実だから」といって責任を取ろうとしない。
気楽な商売だ。
現場で必死に働く教員の爪の垢でも、煎じて飲めばいいのだ。
2018.06.28
「しつけ」の名で虐待
専門家「どの家でも起こりうる」
[朝日新聞 6月27日]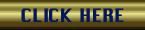
東京都目黒区の船戸結愛(ゆあ)ちゃん(5)が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死容疑などで起訴された父親は、当初の調べに「これまでしつけでたたいたことはある」などと供述していたという。しつけや「教育」という名を借りた虐待――。専門家は程度の差はあれ、どの家庭でも起こりうるとして、大人の自覚の必要性を訴える。
警視庁などによると、結愛ちゃんは自ら目覚まし時計をセットして毎朝午前4時ごろに起床。父親の雄大容疑者(33)に命じられ、平仮名を書く練習をしていた。しかし、1人で寝起きする部屋は室内灯がなく、薄暗い部屋で繰り返し文字を書いていたとみられる。
結愛ちゃんはノートに「きょうよりもっともっとあしたはできるようにするから もうおねがい ゆるして ゆるしてください」などと書き残していた。
「しつけ」の名の下に行われた虐待事件は頻発している。厚生労働省によると、2004年1月〜16年3月に虐待死した計653人の子どものうち、81人(12%)は主な虐待理由が「しつけのつもり」で、理由が明らかなケースで2番目に多かったという。特に3歳以上に限れば09年4月以降、「しつけ」で27人(28%)が死亡し、理由として最も多い。
青山学院大の古荘純一教授(小児精神医学)によると、「教育虐待」とは教育を理由に子どもに無理難題を押し付ける心理的虐待で、エスカレートすれば暴力も伴う。11年の学会で初めて報告された新しい考え方だ。「『しつけ』のため、というのは強い立場の人が自己を正当化する言葉。周囲の人も『しつけ』や『教育』と言われれば、虐待と気付きづらい」と話す。
(後略)
社会に衝撃的な事件が起こると必ずこういった扇情主義ははびこる。
曰く、
「誰でもいじめのターゲットになり得る」
「どんな子も不登校になる」
「非行に走るのは特別な子ではない」
そして、
「しつけ」の名で虐待 専門家「どの家でも起こりうる」
もちろん定義にもよるのであって、
「子どもを怒鳴っただけでも虐待だ」というレベルで話せば虐待はどの家でも起こりうる。しかし例えば高い木から飛び降りようとしている子どもに、
「やめろ!!」
と怒鳴って虐待だといわれてもかなわない。子どもの人権を守って命を守らないのは親のすることではないだろう。
わが子が人をイジメているのを見たら、私だったらとりあえず、
「何やってんだ、てめぇは!」
と怒鳴り上げると思うが、このとき指導されなければならないのはいじめをやったウチの子だろうか、それとも虐待親である私だろうか。
今の趨勢だといじめ問題は後回しにしても、まず私が糾弾され、処分を受けなければならない雰囲気だ。それが正常のことなのだろうか。
端的に言って、しつけを名目で行われる虐待は「どの家でも起こり得る」ことではない。しつけや「教育」という名を借りた虐待は「虐待」であってしつけでないことは、誰にだってわかるし普通の親は「虐待」なんかしない。
ただ記事にエスカレートすれば暴力も伴うとあるように、行き過ぎて歯止めがかからなくなる場合はある。
だから専門家は、どこまで行ったら「虐待」なのか、その目安を示さなければならない。
単に、
「行き過ぎた場合は虐待に当たりますよ」
なら素人にだって言える。
「しつけ」の名で虐待 専門家「どの家でも起こりうる」
こう言われて深刻に考えるのは子育てに自信のない誠実な親たちだ。虐待に近いことをしている連中や、実際に虐待を行っている親たちは何も感じない。
ひたすら真剣に考える真面目な親たちだけが自分の子育てを見直し、この教育は虐待ではないかと怯え、必要な指導を手控えたり児童相談所に飛び込んだりする。その結果ただでも忙しい児童相談所はさらに忙しくなる。
メディアはそこまで考えたのだろうか?
もう一度繰り返す。
「誰でもいじめのターゲットになり得る」
「どんな子も不登校になる」
「非行に走るのは特別な子ではない」
「しつけ」の名で虐待、「どの家でも起こりうる」
こうした見出しがどれほど大勢の親たちを不安に陥れ、追い詰めているか考えてみるといい。
|
![]()
 (キースの逸脱)
(キースの逸脱)