
1998年「教育条件整備の運動」レポート
教育活動を支援する、「学校総務部」を構築しよう!
1 はじめに
2
最大限の効果を上げる予算管理をめざそう
3 情報管理をめざした文書管理
4 学校の活力を引き出す学校総務部
5 まとめ
1 はじめに
(1)これからの学校に望まれるもの
学校にはさまざまな人が働いています。業種・職種に違いはあっても、学校教育を通して社会に貢献すると言う意味ではどの業種も平等であり、上下関係はありません。誰もが、プライドを持って職務をまっとうしているはずです。
地方分権の進展は、それぞれの自治体に今以上の業務の効率化と質の高い住民サービスを求めています。学校においても、協議、検討すべき課題をいくつも抱えつつ、さらに様々なニーズに対応していかなければなりません。そのためには、教職員一人一人が役割を果たし、組織の力が十分に発揮されることが必要です。
(2)学校総務部の役割
企業の組織で考えてみましょう。生産部門や販売部門、技術開発部門などのように、収益に直接つながる業務部門だけでは会社経営は成り立ちません。各部門が円滑に業務推進できるように支援し、経営を補佐する、総務部門が必要です。これらの役割から総務部門は、企業内サービス業ともいわれています。一般的に「ヒト・モノ・カネ・情報」の管理をとおして企業内サービスを行っています。
これを学校にあてはめてみると、学校における総務の役割とは「充実した授業や、よりよい教育活動が推進できるように支援することである」といえるでしょう。しかし、学校の校務分掌組織の多くは、業務を細分化して担当者を割りあてる方法をとっているために、業務の相互関連を意識しにくかったようです。特に事務部門・管理部門では、教育活動との接点を明確に表現することができませんでした。
学校総務部の構築を試みることで、「学校の業務はすべて教育目標に結び付いている」という視点を明確にし、教育活動を支援する事務改善はどうあったらよいかを考えていきたいと思います。
2 最大限の効果を上げる予算管理をめざそう
(1)教育活動と予算のかかわりについて職員の意識を高める
教職員の予算に対する意識をあらわすと、大体次のようになります。
・一生懸命やったんだから、どこかから経費は出してもらえるだろう
・予算がついたけれど、さあ何に使ったらいいのだろうか
市町村費も、児童生徒からの徴収金も、予算には枠があります。限られた条件の中で工夫をこらし、効果的な予算執行をしたいものです。計画性のなさや見通しの甘さは、場当たり的な予算執行となり、ともすると不正につながります。
まず、教職員の一人一人に公費について知識と関心を持ってもらいたいと考え、年度始めには予算の基本方針、学校配当予算を知らせるとともに、公費予算の分類、公費と私費の負担区分について資料を示すようにしています。(資料1省略)
また、より有効な活動計画であるかどうかより予算の有無が優先されるような教育活動の在り方は違うのではないか、それも少額で消耗品費だけを配分するのは意味がないのではないかと考え、公費予算の校内配分をやめました。
さらに、次年度の予算要求の資料を作成する際には、ほしい備品を記入してもらうだけではなく、活動を記入してもらうことで、前年踏襲ではない、より実態に即した予算計画になるのではないかと考え、予算見積書作成についての依頼文も工夫してみました。(資料2省略)
(2)予算事務担当者としての働きを考える
◇予算のプランニング機能とコントロール機能◇
組織の目標を設定し、それを実現するために戦略を練り、それを経費として数値で表すことを、「予算のプランニング機能」ということにします。
予算の裏付けの有無を理由に実行を制限することを、「予算のコントロール機能」ということにします。予算額や残額をタイミングよく示すことで、活動を促進したり抑制したりします。
予算を執行するとき、経費とその支出効果についてはあまり検討をせず、予算に対する執行率だけを問題として(コントロール機能)いないでしょうか。年度末に0清算するのは確かに予算事務担当者の腕ですが、それだけでいいのでしょうか。
学校では、「活動にはお金の動きが伴うものだ」という意識がまだまだ薄いようです。これからの予算事務担当者は、教職員の教育活動に対する思いや願いを引き出すような問いかけを、どんどん仕掛けて(プランニング機能)いってよいと考えています。
3 情報管理をめざした文書管理
(1)文書そのものを管理することより内容を管理する
これからの文書管理を考えるとき、情報公開やそれにまつわるプライバシーの問題、パソコンの普及などによる情報保管の多様性などのを視野に入れなければなりません。学校における情報管理はこれからどうあったらいいのでしょうか。
学校の意志がどのよう形成されるか、日々の教育活動に必要な情報がどのように流れ、共有されるのか。そのシステムは確立し、機能しているでしょうか。
(2)文書処理改善をとおして、情報の流れを整備する試み
現任校では、スチール書庫1個の文書棚がありましたが、その整理・保管・活用について、明確な役割分担がなかったことから、生きた文書管理とはいいにくい状況でした。文書係として、現状とその問題点・改善の視点を示し、年度末には当校版文書分類表を作成しました。(資料3)
受理文書、校内文書を問わず、日常の教育活動で頻繁に利用されるものを、文書棚に格納するようにしました。
文書管理を情報管理の一環ととらえたとき、完結した文書の整理分類方法を示すだけでは、総務の役割が十分果たせていないと考えました。次のことから、文書そのものの管理よりも、内容を管理する方向へ転換を図る必要を感じました。
・文書受理者がその情報を正しく理解しているかどうか、確認する必要があるのではないか
(提出期限・会議の期日の確認、全職員に周知すべき内容かどうかなど)
・作成する文書について、情報としての必要事項が盛られているかどうか、誰がどんな観点で
点検しているのかはっきりさせなくてもよいか
これらを明らかにするため「文書事務流れの改善について(お願い)」を提案しました。受理文書・発送文書についての流れを明文化し、校内文書の点検ルートには事務職員を加え、それぞれの役割を明確にしました。(資料4一部抜粋)
資料3一部抜粋
分類表作成の観点
・分類表が、次年度の活動に生きるように構成されているか。
・校務分掌の流れに沿うような分類であったか。
・持ち出したファイルが元の場所に戻しやすい工夫がされているか。
・綴った文書が来年度の参考資料となりやすい分類となっているか。
・ファイルの中身について周知されているか。
・個人のロッカーが、学校の文書に占領されていないか。
資料4一部抜粋
文書処理事務の流れの改善
(略)受理文書や教育委員会などに提出しなければならない文書については、おおむね円滑に処理されていますが、期限までに提出されたかどうか、内容に不備がないかなどを機能的にチェックを行う態勢ではありませんでした。そのために、各担当者の責任によるところが多かったこれまでの方法を次のように改めたいと思いますので、よろしくご協力ください。
1)点検機能について
校長 主に、学校から発信する文書として、ふさわしい内容かどうか確認する
教頭 主に、職員が意欲と責任をもって文書作成できるように手助けする
教務 主に、他の分掌や行事とのかかわりで不都合がないか確認する
事務 誤字・脱字がないか、年月日や曜日などに誤りがないかチェックする
2)点検経路について
各担当者→事務(誤字脱字があればここで担当者に返す)
→教務主任(他との係りで不都合があればここで担当者に返す)
→教頭→校長→各担当
なお、起案文書以外の文書はこれまで、それぞれの担当者で付箋などにメモ書きをつけて
まわしていましたが、統一様式をつくりましたので利用してみてください。
4 学校の活力を引き出す総務部
(1)組織の力は、一人一人の力
さるベンチャー企業の責任者が、近ごろのサラリーマンの“資質”を揶揄して、次のように
言っています。
1)明確に指示を出さないと仕事ができない。
2)細分化された仕事はできるが、仕事の全体観がない。
3)社内“政治”に敏感で、上司の顔色ばかり気にして仕事をする。
4)労働時間の多寡、努力の大小で評価されることを望む。
学校の教職員一人一人がそれぞれの立場で「学校をもっとよいところにするにはどうしたらよいか」ときちんと考えていける、そんな学校であってほしいという願いから、月に1度ちょっとかわった事務便りを発行しています。(資料5省略)
◆資質についての考察1 やり過ごしという能力 高橋伸夫(東京大学大学院経済学研究科助教授)
上司の指示命令とはいえ、重要度の低いものを上手にやり過ごすことで時間と労力を節約し業務をこなさなければならない。それができなければ「言われたことをやるだけで、自分の仕事を管理する能力がない」「上からの指示の優先順位付けができない」と低い評価をされる。
↓
まとはずれな指示、気まぐれな指示は、「やり過ごし」によって濾過され、上司に恥をかかせず低信頼性の表出を抑えて、組織行動の安定化をもたらす。
たまたま割り振りされていない業務があって、誰かがやらなければならないのだとしたら、それはりっぱな業務です。わたしの仕事ではないなどと、仕事を先送りにしたり放り投げたりするのは、ここでいう「やり過ごし」とは違います。だからといって、発生した順番にただ仕事をこなすのでは、忙しさが増すばかりです。
◆資質についての考察2 仕事の優先順位を意識する力
加藤スプリング製作所「タイムマネジメントで戦略的社員を育成」より

学校では、職種によって期待されている役割が違えば、優先しなければならない仕事も当然違ってきます。
例えば公開授業のあった昼休み、2時からの協議会のために授業記録を印刷しようとしていたH先生のもとへ、なにやら深刻な顔をして子どもがやってきたとします。「忙しいから、あとにして。」と、子どもを遠ざけてしまうえば簡単でしょうが、それでよいのでしょうか。その子にとって、一大事な出来事がおきているのかもしれません。ちょっと話を聞くだけてすむことなのかどうかも、分かりません。教師にとって優先順位の一番は、「子どもとどう向き合うか」であると思います。皆が忙しそうにしているからといって、だれもが今すぐ片付けなくてはならない仕事をしているわけではないのだ(!)と腹をくくって、借りだの貸しだのメンツだのは抜きに、印刷の依頼ができることこそベストだと思うのですが、いかがでしょう。
◆資質についての考察3 人の見方を変える軸
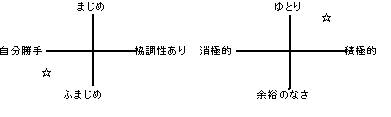
自分勝手でふまじめ、と思っていたが、見方を変えると
ゆとりがあって積極的、と見ることもできる。
「頭に来る奴だ」「気に入らないから協力しない」などと、感情に左右されて仕事を進めることが、果たしてよい結果を生むでしょうか。
(2)組織は仕事の集合体
予想していないことが起こったときにどのように対処するのか、という点で、組織としての在り方が問われます。
「学校は組織体である」「学校という組織体が教育をしている」などといういい方では、そこに属する個々の職員の顔が見えません。組織は存在しても、それを構成しているはずの職員だれもが傍観者で、無責任な冷たい感じがしてしまいます。
職員の顔が見えない学校は、ぞっとします。
緊急全県中学校長会議 義務教育課長指導要旨より H10.8 県教委
いじめ問題に限らず、生徒指導上の問題に対応する基本は、児童生徒理解で
す。学校が組織体である以上、組織として動くことは当然ではありますが、最
初から、「組織ありき」ではなく、生徒理解には教職員一人一人がそれぞれの
持ち場で、生徒の声にきちんと耳を傾けて対応をすることが最も大切であり、
教育活動の基本でもあります。
「組織は仕事の集合体である」このいい方には、それぞれの担当者が生き生きと仕事に向かっている様子が浮かびます。与えられた役割を単に“こなす”のではなく、一人一人が組織の目標に向かい、専門性を発揮し、行動している力強さを感じます。
学校は、組織体ではなく、さまざまな仕事の集合体です。
(3)組織での「ほう」「れん」「そう」の意味
具体的に、どんなことを「ほう」告し、なにを「れん」絡するか、どんなときに「そう」談するのか、共通理解がありますか。チームワークがよく、ざっくばらんに何でも話ができる雰囲気があれば、「ほう・れん・そう」にこだわらなくても、組織は円滑に動くでしょう。しかし、人柄やチームワークに頼っていたのでは、メンバーの交替とともに、ぎくしゃくする恐れもあり、組織としては感心できないと思います。
例えばこんな「ほう」「れん」「そう」
結果がどうなったか注目されているとき・・終了したことを報告する
皆の動きにかかわりのあることを・・・・・タイミングを逃さず連絡する
予想していた方向とずれを察知したら・・・すぐに相談する
(4)総務部の中の事務職員の専門性とは
間接的に教育にかかわりをもっているとはいえ、給与や、福利厚生(公務災害も含む)私有車公務使用申請などの手続きが、学校教育とどうつながるんだろう、と疑問に思ったことはありませんか。最初に述べたように、総務とは組織が円滑に動くためのサービス業です。こんなことを想像してみてください。転勤した先で手続きを知っている人がたまたまいなかっために、不利な扱いを受けてしまった・・・もし、そんなことがあっのでは、一生懸命仕事に打ち込もうとする気持ちもなくなるでしょう。
「知らなかったのでしかたがない」というのは、いい訳にはなりません。
公立学校に勤務する教職員は、地方公務員法、教特法をはじめ、拘束される法や条例が多岐にわたり、また、職種ごと微妙に扱いが異なっています。それぞれの法によってきちんと扱われること、これを、教職員の処遇を公平に保つ、と定義します。どんなとき何をよりどころに判断すればよいのか。それをしっかり押さえておくのが事務職員のもっとも重要な役割だと考えます。
5 まとめ
(1)学校総務部の課題
残念ながら、学校の中の限られた職員数では、「学校総務部」を固定した組織業務と考えることはできません。教職員の一人一人が総務的な役割を少しずつ分担しながら、教育活動を支援していく「しかけ」である、ととらえる必要があります。さらにそれが、単発的で単独な仕事とならないような、サービス提供のシステムとして確立していくことが今後の課題となります。その中核的な役割を事務職員が担っていく、それがわたしの理想とするところです。そのためには、企画運営の段階から積極的に教育活動にかかわりをもち、校長先生や教頭先生、用務員さん(管理員さん)たちとの連携・協働も考えていかなければなりません。
(2)学校総務部を支えるプロ集団とは
ところで、学校現場ではどの教職員であっても、学校で働くことにおいてはプロであるといえます。職種の違いからその専門性が異なることはあっても、それはただそれだけのことです。「教育の成果は、すぐにあらわれるものではない」とうそぶく人がいますが、それは本当でしょうか。どんな職業でもその道のプロというのは、素人が区別できない、わずかな差異さえ感じ取ることができるものです。また、一見似通って見える事柄を集めその違いをズバリ言う、プロの仕事とはすなわちそういうことです。これからの学校は、そんな人たちに支えられることになります。
専門性というのはその方面での知識の深さを指します。ですから、専門性による仕事の区分ははっきりしますが、プロの仕事といったとき、それは仕事の境界を意味していません。仕事は明確に区分できる部分とできない部分がありますが、「学校総務部」の考え方は、明確にできない仕事もその基本的役割をはっきりさせ、システムとしてのサービス提供をしよう、という意思表示です。
(3)「学校総務部」と「雑務」のかかわり
学校で発生する、区分が明確でない仕事を称して、わたしたちは「雑務」といい、排除する方向へ運動しがちです。しかし、それが学校の仕事の隙間業務であるのか、単なる個人的・私的なことの肩代わりなのか、という点に注目してみましょう。例えば、ヒトが替わっても残る業務なら学校にとってなすべき仕事であるし、ヒトの異動とともになくなる業務であれば私的な用務といえるでしょう。
学校の中の総務の機能を推進するには、雑務排除などと声高に叫ぶ前に、隙間業務なのか、単に公私混同しているだけなのかをきちんと見極め、学校業務には積極的に支援していく態勢をとりたいものです。
どの仕事を優先させるか、いかに専門性を発揮するか。教職員すべてが力を出し合い、協力し合う学校であってほしい、そんな思いを込めて、教育活動を支援する「学校総務部」について、今後一層の研究を深めていきたいと思います。
参考及び引用文献
変わる学校への職員会議運営の工夫・改善 大石勝男
飯田稔編著 東洋館出版1998
ホワイトカラーの生産性向上事例集 日経連広報部編 日経連広報部1993
MBA全集3アカウンティング フィナンシャル・タイムズ ダイヤモンド社1998
総務が変われば会社は伸びる 渡辺英幸著 日本経済新聞社1989
別冊宝島373号わかりたいあなたのための経営学・入門 宝島社1998
ワークスタイル革命 菅原眞理子編著 大蔵省印刷局1994
35歳までにプロフェッショナルになろう! 土井哲編 ダイヤモンド社1997
ほか