詩のページ その1
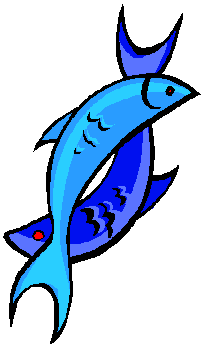
悲の壷
天井にいっぱい
小鳥が飛びかっている朝
寝台の中で私は悲の壷を割ってしまった
そんな壷は誰でももっているものだけれど
めったに割ることはないはずなのに
昨夜窓があいて誰かがなかを覗いたのは
やっぱりあれは兆しというものだったのだろうか
形のはっきりしない
魚類の魂のようなものが
あたりでピチピチ跳ねだした
私はあわてて拾い始めたけれども
仕舞い込むところといってポケットぐらいなもの
仕方なしにあきらめて煙草をふかして眺めている
人生にはこんな朝もあるものなのだ
************

手の神話
ふと見つめるひらいた手の
奇妙な母指球に驚いてはいけない
それがあまりに猿の手に似てみえようと
それがあまりにぎこちなく動こうと
私達はもともと花のようなものではなく
セミの抜け殻のようなものでもなく
あるとき急に意識にのぼる たとえば
地の隆起 岩の塊り 雲の膨らみ
あるいは古い松の幹に出たこぶのように
私達の住む世界へのさみしい愛の徴として
いつでも身近に息づいているものだから
それは根深い混乱に疲れ果てた日や
宿命を知ったとまどいに暮れる日を
耐えてゆくよすがとなるのだから
手というものの奇怪さを
嘆いてしまってはいけないのだ
************
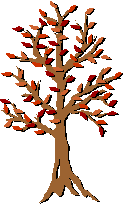
秋に
どんなに平衡が崩れても
私というぽっかりとあいた空間は
ちょうどみがいたひとつの林檎のような
つややかな充実でありたくて
秋の一日
風にしなうコスモスのゆるやかな振幅
壁の木目の不思議な幻想
鳩のような娘の歩調を習ってすごす
するといつかどこからか
冷たく澄んだ流れの音が
耳たぶの裏に聞こえてきて
私の時が少しずつ
去ってゆくのを教えてくれる
************

封印
幼い夢のなかにあった
波間や月のさざなみが
けしてこの世のものにはなれないように
頭のなかからはもう何千年
なにも生まれたことはなかったのに
天井の窓をみあげて
虫の歌をきいていると
やっぱり婚礼の前夜のように
沐浴し
耳の垢もきれいにとって
羊歯の葉のなかへ頭をさしいれる
まるく曲がった
馬のかたちになった背骨から
宇宙のいきづかい
ざらざらと
ながれだしてはくるのだけれど とても
夜を溶かしこむ音楽にはなりきれない
いまはもう
わざわざすこしものがなしい顔をつくって
目は種のかたちにみひらいて
耳介は花びらのようにひろげ
ちょっとステップ おどけて
踊ってみたりもする
************
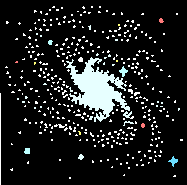
みえないいきものたちの天文学
水平線はみえるけれども
地平線はみえない
みえない地平線に平行に
どこまでも走って月をかすめた
ポップコーンみたいな星屑をふみつぶして
つるくさに似た時間記憶をのみこんだまま
直径十二キロメートルの重力場に身をなげてみた
どこまでもいっしょに旅しようねって
誓い合った妖精は木漏れ日のしたに
あの子の指先はクルクルまわって
他人の脳のなかに平気で宇宙を描く癖があった
r = aω のうずまきに
みずけむりの模様をつけて
これがあたしたちの瞑想かしらって
ふたりでウサギのからだを解剖したのは
月の裏の岩の陰
あの子の蛭のようなくちびるにキスしたいばっかりに
クローバーやら水晶形やら
くりかえしくりかえし変態をつづけて
時間の細い溝を走りぬけるのももう何万年
こんなふうにしていてうまく受精して
月日のめぐりにはなひらいて
ひかりのなかで爆発して蒸散する
成就
でもその確率はすごくひくいんだ
************
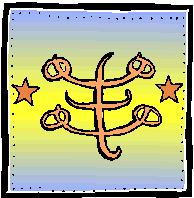
森の姫のジャーメ ビュー (jamais-vu)
やっぱり心臓は貝がら
いのちの出口
風の唇はなぜかしら?
宇宙から
あの森のなかをふきぬけて
一千年もこわれたままのこころからこころに
死化粧する頬紅のように
うっすらと血をかよわせる
木星のまわりをエイが巡る夜
海のなかには蛭が無限に生まれてあふれて
わたしたちの命は衰えたまま
急に
眠っていた海馬回に白鳥のゆうれい飛びかい
核酸があたらしい配列を求めて
まだまだ舞いあがることを忘れない
くりかえされぬものの予感が立ち上る
なまぬるいさざなみは
すこしだけ現在をくるわせ
過去を洗いながしてゆくと
砂のなかから肺魚が顔をもたげ
いるかの皮の内側へおちていった
冷たい流星の軌跡が描きなおされて
泡立つ悲しみがやっと
あなたのしろい首のあたりに
湧きあがってくるらしい
************
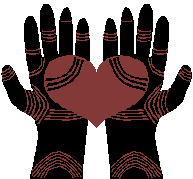
髪飾りの本質
あの夜 黙って話をきいていた
あのひとはふいに顔をくずしてほほえみ
ゆくえの知れぬ愛情をやさしく吐き出して
そのゆるやかにふくらんだくちびるや
なまあたたかい胸元や胸を
なにげなくテーブルの上にひろげていたけど
まもなく
そっと伸ばした
手のひらのくぼみに吸い取って
どこかへかくしてしまったのを
知っていたのはぼくだけだったのだろうか
あの夜は
頭の上の暗闇に小鳥たちがかけた
透明な唾液で藁と藁とをからめたはずの
巣の底にさえ穴があいてしまっていて
うつろう感情の底が定まらず
あのひとはきっと
人と人とが別れてゆくときの小さな嘘や
死の床に集まった家族の
暗い陰のうしろにある
青空の濃さが忘れられず
まるで微熱に病んだように
あんな魔術めいたことを愛したのかもしれない
あのひとがもしこの視界からしりぞいて
空の下のアネモネの茎の下の家族のもとへ
帰ってしまうのだとすれば
そのあといったいこの世界に
守るべき
なにが残っているのだろう
************
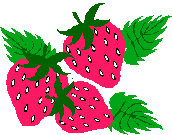
誕生日の贈物
いちごがりからの帰り道は
いつも水筒に水を満たしておこうねって
キツネが出るかもしれないし
もしかしたらおばけだって
切り株にすわって待っているかもしれない
車で通りすぎる道は
そこにまるで一度もいかなかったようだけれど
本当は何度も通り過ぎていた
そう知るためには窓を全部
あけて風を入れておかなくてはいけないね
そうすればきっと夜になってどこからか
寝台の上に蛇がでてきてくれる
蛇は私の指にからみついて
君にさえ言えなかったこと
いちごの酸味が本当は
泉にたまった恐竜の吐息だったとか
夕焼け空の水解物だったとか
いろいろなでたらめの香水で
長い話を夜明けまで囲んでくれる
象の鼻のなぞなぞは
どこの本にも書いてないから
蛇の首の巻きつけて
ひっこぬいて盗んできた
いちごの木につるしておこう
きっといつか干物になって
かたいなんだかわけのわからない
おばけにかわって
冷蔵庫のなかで
君の誕生日のごちそうになるかもしれない
************
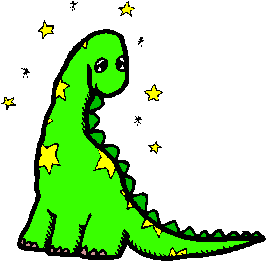
原宿の恐竜
メイプルリーフ金貨をポケットにつめて
並木通りの落ち葉を踏む
少女たちがピーナツをついばんで
指と風を遊ばせているように
そらにうかぶ水面にさざなみが立って
色彩が急に鮮やかさを増す
ブルーフォックスのコートが道路をわたり
マロニエの幹に文字が書かれる
そんなときポップコーンを食べながら
恐竜のことを考え始めた
今でも街を歩いているジュラ紀からの生き残り
倒れることを忘れてしまった奴
振り返る動作が正確でないから
変身することもできない
人の目を気にした肩をすりあげるしぐさで
本当は人間を馬鹿にしている奴
首が長いわりに腐りかけている自分の背骨がみえてない
僕たちはそんな恐竜をかわいそうに思って
博物館にいれてやるつもりだったけれど
奴はそんなこと予想もしていないようで
君がクラッカーの音に驚いて振り向いたとき
出し抜けにブティックから現れてみたり
雑踏にまぎれたアイスクリームを
なめて笑い声を上げたりする
灰白色の荒い肌はさすがに年代物で
少し水気を失っているくせに
案外若ぶった黒い帽子をかぶって歩いたりする
本当に好き放題な奴だけれど
目がいつもすきとおって明るいから
頭の中はからっぽに違いなく
その証拠には
スエヒロに入って水をたのんだら
あいつが出てきて水をおいていった
僕らは思わずキノコのように笑っちゃったね
************
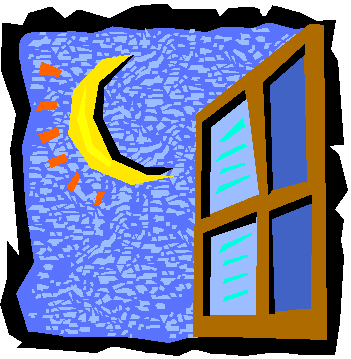
ピーターパンかな
いつかさっぱりと
消えてしまうことを思うと
この夜がいとおしくなる
窓を開けてこの世のうつくしいもの
すべてを迎えいれたい
星や森や君のイメージを迎えいれて
魚たちのように眠りたい
純粋になるなんてことはけっきょく
かぎりなく弱くなること
かぎりなく愚かになることだけど
炎のゆらめきのように純粋になって
この世の時間を生きていたい
君に伝える言葉さえなにもなくなって
君を思う想いだけは宇宙に広がってゆき
だから明日からもまた
この世の騒々しさを受け入れて
君のかんしゃくや怒りだって
愛していたい
************
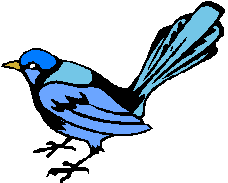
恋人
青いカナリヤのいるカフェテラスで
幽霊になった君と話していると
コーヒーが冷めるのも気にならないし
なにを話しているのか忘れてしまう
ガラス戸をとおして届く日の光だけが
まるで金砂かなにかのように
僕らの存在を祝福してくれるから
僕はしっぽを隠したまま
君の指を食べてみたりする
アボガドのような味の君の指は
食べても食べても生えてきて
いつもきっかり十本テーブルのうえに
美しくひろげられて
それは楽器の弦をひく指だから
人の心なんかよりずっとやさしく
僕の生命を危うくする
流星が口から飛び込んでおしりから出るまで
僕たちは宙に浮かんだ目で見つめ合って
恋なんて
プロントザウルスみたいな大昔の力を
剣状突起のあたりに感じている
だからもう君にしっぽがなくても
僕に心臓がなくても
この世界の意味は変わりはしない
************
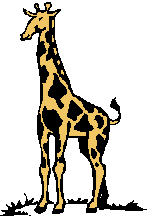
恋なんて知らない
そう言っていた君は今どこにいるのだろう
『象が動物園から出てくるとき
熊は山に帰りたくなる』
そんな呪文に感応して
CDプレーヤーはリピート機構を作動しつづけるけれど
音楽はいつだって果物みたいに
すべての感情の行き止まりを演出するだけさ
感情はいつも現実を裏切っていまう
でも僕はけっしてくたびれた天使のように
羽を折ったりなんかしないから
みててごらんこの詩のような乱雑が
いつの日にかあざやかな現実を呼吸して
空白のページのうえに
『リスに餌をやったのは
あの日つくったまずい料理の罪ほろぼしさ』
なんて書きつけながら
たとえばありふれた雨の一日をその出来事を
そっくりそのまま
一冊の詩集にしてしまう日がくるってことを
FOUR ROSES のボトルのふちに
僕が刻んだ君の名前は
いまでもあの棚にのっているし
あの店ではいつもあのウィスキーを飲んだから
あの場所に僕らが行かなくなったって
思い出はきっと4つのバラのなかに記憶されている
なんて信じ込もうとしている今の僕には
『縞馬が幸せに目をつぶっても
キリンはいつまでも空を見ている』
っていつか K.T. が言っていた
あんなわざとらしい言葉だって永遠さ