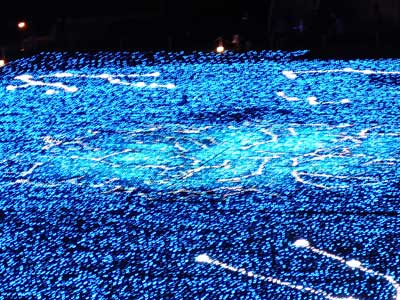わんだふるはうすcuisine francaise JJに行く
クリスマス・イルミネーション・ディナー編
東京ミッドタウンは、今年2度目のクリスマスを迎えています。「大切な人の幸せを願う誰もがサンタクロースである」というコンセプトのもと、自分の大切な恋人や友人や家族を想う、ミッドタウンに訪れるすべての人が幸せになりますように…。そんな想いを込めて今年もクリスマス・イルミネーションを中心とした様々なイベントを展開しています。2008年12月、東京ミッドタウンにあるジョエル・ブリュアンさんのお店「cuisine francaise JJ キュイジーヌ・フランセーズ・ジェイジェイ」をワンダフルハウスが訪ね、クリスマス・イルミネーション付きディナーを堪能してきました。メニューの数々を順番に紹介いたします。
 |
 |
| クリスマスも目前になり、ものすごい人出です…おおっ!あれは!?(^O^)\ |
キリコツリーです!\(^O^)/ |
| 東京ミッドタウンのメインツリーであるKIRIKO Tree。江戸切子をモチーフにした高さ8mのツリーは伝統と技術の結晶。音と光の演出で、月明かりや情熱的な炎などを表現しています。ツリーの中に入って上を見上げると、鏡面の世界が広がり、永遠に続く世界観を見ることができます。そして10分に1回、満天の星空が広がります。 |
 |
 |
| ん? あのイルミネーションは何でしょう?(^‐^)\ |
 |
 |
| シャンゼリゼ・イルミネーションです!\(^○^)/ |
| 日仏交流150周年を記念して、世界で最も美しいと言われるパリのシャンゼリゼ・イルミネーションが今年は東京ミッドタウンで見る事ができます。さくら通りと外苑東通り沿いの街路樹に約4万球のLEDを散りばめ、まるでシャンパングラスの並木を歩いているような、ロマンティックな空間になっています。 |
 |
 |
| 白い光が上から下へ…まるで雪が降っているようです。 |
おっ、2階建てバスです!(^O^)\ヤッホー |
| 見どころは、雪が降る様をイメージした「スノーフォール」。実際にパリで使用されていたLEDを譲り受けて飾り付けています。木に巻きつけるだけのイルミネーションが主流の中、シャンパン型に彩られた“デザインされたイルミネーション”を見ることができます。 |
 |
 |
| ん?人がたくさん集まっていますよ(^-^)\ |
あそこにもツリーがありますね。 |
 |
 |
| うわーっ! 銀河が浮かび上がったような…あれは何でしょう?(゚O゚)\ |
 |
 |
| あっ!真ん中に何か出ましたよ? |
 |
 |
| 星座に変わった! |
 |
 |
| また1つ星座が生まれました。 |
 |
 |
| 次々と星座が誕生しています。 |
| 2000m2にも及ぶ広大な緑地に出現した無限大の銀河…これはスターライトガーデンです。ガーデン全体にイルミネーションを展開。6つの冬の星座や銀河が浮かび上がり、幻想的な空間になっています |
 |
 |
| 次の星座は大きそうですよ。 |
| 6つの冬の星座(北斗七星、カシオペア座、ふたご座、ぎょしゃ座、オリオン座、おうし座)が次々に浮かび上がり、各星座の1等星は大きく明るくなっています。 |
 |
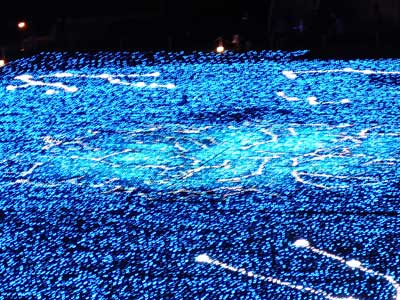 |
| ものすごい星座が誕生しようとしています。 |
 |
 |
| あーっ! 星が流れた!?(゚O゚)\ |
 |
 |
| こっ…これは?(゚O゚)\ |
 |
 |
| 流れ星です! |
 |
 |
| 回転しています! |
 |
 |
| 30分に1回、スペシャルコンテンツとして流れ星が立体的に流れるようです。 |
 |
 |
| う…美しい…(゚O゚)\ |
 |
 |
| うわーっ!強烈な光が!(>o<)\ |
 |
 |
| 芝生全体が一瞬、幻想的なブルーの光に包まれた後、流れ星と星座は消えていきました。 |
 |
 |
| おお…星が少しづつ消えていく…(゚O゚)\ |
 |
 |
| 星が全部消えて真っ暗に…ブラヴォー!\(^○^)/…素晴らしいショーでした! |
 |
 |
| ん?何か文字が浮かんでいますよ?(^-^)\ |
エアー・フランス! |
 |
 |
| そうだ、フランス料理を食べに行きましょう 〜/(^Q^)/ |
 |
 |
| 「こんばんは! 〜/(^O^)/」「これはこれはワンダフルハウス様…」 |
 |
 |
| 「今夜は寒いのを我慢してテラスでいただきましょう 〜/(^Q^)/」 |
 |
 |
| 「寒いので温かいスープをください!(^O^)/…そうですね…コンソメはありますか?」「メニューにはございませんが、スープ・オー・トリュフのベースとなるスープですので、いつでも御用意できます」「では、コンソメで!(^O^)/」「メインはどうしましょうか?本日はジョエルがワンダフルハウス様のために“ヴォー veau”を用意しておりますが…」「ヴォー?(゚O゚)\」「仔牛です」「いいですね!ローストにしてください!」「かしこまりました」 |
 |
 |
| 「ワンダフルハウス様、今、パラソル・ヒーターを点けますので少々お待ちください」「パラソル・ヒーター?」「ストーブでございます」 |
 |
 |
| 「おっ、ストーブが点きました!(^O^)\」 |
Amuse bouche
 |
 |
| 「ワンダフルハウス様、アミューズの“Poelee de seiche sauce tapenade 甲イカのポワレ ソース・タップナード”でございます」 |
 |
 |
| 「ソース・タップナード?(゚O゚)\」「タップナードとは、ケッパー、オリーブ、アンチョビ、ニンニクをミキサーにかけてピュレ状にしたもので、プロヴァンス地方の伝統的なソースです」 |
 |
 |
| 「タプナードという名前は、ケッパーを意味するTapeno(タプノ)に由来しています」 |
 |
 |
| 今の時期の身の分厚い甲イカは非常にジューシー。口の中に旨みが広がる最高の一品です(^Q^) |
 |
 |
| 「残ったタップナード・ソースは、バケットに塗ってお召し上がりください」「バケットにソースが染み込んで、生地がジューシーになって…言葉に出来ないほど美味です!(^Q^) |
 |
 |
| コンソメが運ばれてくるまで、先ほど見てきたキリコ・ツリーを紹介します。 |
 |
 |
| キリコ・ツリーは、今も伝統を受け継ぐ「伝統工芸士」の方々の協力を得て制作されています。様々な伝統の文様を基本に、新しい組み合わせや構成により、現代の江戸切子を創り出すことに成功しました。 |
| 秀逸の技と光の反射が織り成す東京都伝統工芸品「江戸切子」。江戸時代後期、江戸大伝馬町のビードロ屋、加賀屋久兵衛が手掛けた切子細工が今日の江戸切子の始まりと言われています。町民文化の中で育まれた江戸切子は、江戸時代の面影を色濃く残し、優れた意匠や技法の数々は、現代に至る160年以上もの間、切子職人たちによって受け継がれてきました。当時からよく使われた切子模様が一般的に「江戸切子」と呼ばれているものです。 |
 |
 |
| おっ、中に人が入っていますね(^-^)\ |
 |
 |
| ツリーの中に入って、“永遠に続く世界観”とやらを見てきましょう。 |
Soup
 |
 |
| 「お待たせしました。ワンダフルハウス様、“Consomme double aux xeres コンソメ・ドゥーブル・オー・ケレス”でございます」「コンソメ・ドゥーブル・オー・ケレス?(゚O゚)\」「ダブル・コンソメ・スープ シェリー風味でございます」「ダブルコンソメ?」 |
| ポテトチップスのコンソメパンチの味付けや、インスタントの固形スープとしてコンソメは生活に根付いた味であるといえます。しかし、本当の意味でのコンソメを知っている人は、果たしてどのくらいいるのでしょうか? |
 |
 |
| レストランのコンソメは、二重にダシをとるから「ダブル・コンソメ」「コンソメ・ドゥーブル」「コンソメ・リッシュ」などと呼ばれています。 |
Consomme double aux xeres
コンソメ・ドゥーブル・オー・ケレス
ダブル・コンソメ・スープ シェリー風味 |
 |
 |
| 大きな寸胴鍋に丸鶏と牛肉と牛骨と野菜を煮込んでブイヨンを作り、さらに牛肉と野菜を加えて煮込む…先に取ったブイヨンにブイヨンの材料を加えて煮るという手間のかかったコンソメスープ「ダブルコンソメ」。仕込みから完成まで丸2日かかる本物のコンソメの登場です。 |
La Soupe aux truffe noire du Perigord en croute
ぺリゴール産黒トリュフのスープ パイ包み焼き
8400円+サービス料10% |
 |
 |
| キュイジーヌ・フランセーズ・JJのコンソメ・ドゥーブルは、スープ・オー・トリュフ・アン・クルートのベースになってるスープなのです。スープ・オー・トリュフ・アン・クルートは、コンソメ・ドゥーブルにトリュフ、フォアグラなどの具を加えて作ります。 |