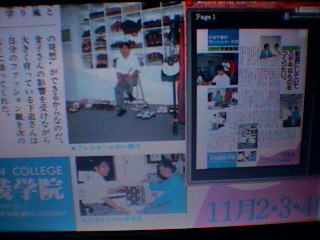
anan1984年11月2日号(452号)に掲載された文化服装学院の広告「小池千枝のファッショントーク 第29回」で、小池学院長(当時)と下迫さんが共演している。
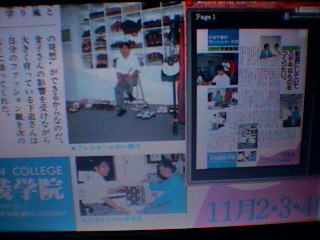
いまや青山・原宿に次ぐファッションの街となった代官山。静かな住宅地でもあるこの街の一画に、全国のファッション好きな女性たちを魅了し続けるピンクハウスのアトリエがある。
四年ほど前には十数人にすぎなかったスタッフが、現在ではおよそ六十人。この驚異的ともいえる成長を、目の当たりに見てきた人がいる。それが下迫秀樹さんだ。もちろん金子功さんと同様に文化服装学院の出身。
「入社した当時は、デザイン画を描くだけでなく、生地の選択とか発注も手がけた。とにかく毎日が初体験の連続で、何をどうすればいいのかもわからず、無我夢中だった。でも、いまにして思えば、そのころの経験が大きな力になっている」と話す下迫さんは、中学生のころからデザイナーに憧れていたのだという。そこで一流の先輩たちがいた文化服装学院へ。さらに小池千枝学院長の話が聞ける上に、ショーを手がけることができるということで、デザイン科への進学を決意する。
「小池先生からパリの最新ファッション情報を話していただいたりして、本当に楽しかったし、ためになった」またシンガポールヒルトンの要請で開かれたファッションショーに参加できたのも、文化服装学院に学んでいたからこそだと、下迫さんは話す。
「ショーは単に技術を発表するというだけでなく、いろんな意見をまとめてひとつのものをつくり出す。構成力を養う場でもある。クラス委員長でもあった彼は、それをうまくまとめあげた」と小池学院長は当時をふり返る。
イギリス・バリエラのテキスタイルコンクールで、金賞を獲得した実力をもつ下迫さんだが、「デザイナーになれる自信をもっていたのに、その一方ではいつもドキドキしていた」という下迫さんが念願のピンクハウスに就職できたのも、小池学院長の手助けがあったからだ。
「ただ就職できればいいというのではなく、学生それぞれの個性や感性が生かされる職場を探してあげるのも、私たちの大事な役割だと思う。その点、下迫君の作風は、ピンクハウスにぴったりのものだった」と話す小池学院長は、下迫さんのデザインは基本的な部分で、金子さんのものと共通しているという。ピンクハウス独特の女らしく優しいラインは、”ボディの発想”から生まれているものだというのだ。スタンには工業用とヌードのふたつがあるが、学院ではパターンメーキングが楽であるばかりでなく、繊細で美しいラインを出せるヌードスタンを使っている。これはパリへ留学していた小池学院長が帰国する際、初めて日本にもち帰り、改良を重ねて完成させたもの。金子さんにしろ山本耀司さんにしろ、あの美しいラインを出すのは、こうした学院独特の”ボディの発想”ができるからなのだ。金子さんの影響を受けながら大きく育っている下迫さんは自分のファッション観を次のように語ってくれた。
「大袈裟にしなくても、オシャレでステキなものがあると思う。僕自身も、普通にしててステキだといわれたい。結局は、こうした何気ない美しさが僕のファッションであり、ピンクハウスのムードなのだと思う。これからもそんなファッションづくりを進めたい」
金子功さんの一番弟子として、この(1988年)6月にデビューしたのが下迫さん。金子さんといえば、人を使わないことで有名なのだが、
「冗談ぬきで、金子さんのことが好きだった。真面目に服を作ってるという気がしたから。で、金子さんのところに入りたいなぁと思って。初めはいらないって言われました。でもデザイン画を見てもらって、ユリさんとかまわりの人がいろいろ言ってくれたおかげで。だから、あのとき嫌って言われたら、今の僕は、いないんです」
それが8年前(1980年)。最初はその金子さんと話ひとつできなくて、会社へ来ては黙ってデザイン画ばかり描いていた。やっと話ができるようになったのは、3か月後ぐらいとか。
「プリントのことをいろいろ教えてもらったし、吸収することが多かったから、毎日必死だった」
金子さんとふたりっきりの仕事場に、新しいデザイナーがひとり加わったのはやっと5年後だった。そして、下迫さんが金子さんに、自分のブランドを作るようにと言われたのが去年(1987年)の暮。
「正直言うと、心の準備はできてませんでした。金子さんとは絶対10年いようと思ってたから」
ピンクハウスが、別に新しいブランドを出すのも初めてのこと。Powderという名前は、下迫さんが考えた。
「また1から出直しというか、ちっちゃいという感じをつけたかった」
以来、金子さんからの指示はいっさいなし。嬉しかったのは、初めての展示会のとき、最後に見にきてくれた金子さんに「かわいいじゃない」と誉められたこと。感激した。
「デザインのことはいつも考えてる。寝るときも、浮かぶとパッと起きて描く。今の一般的なお洒落な人からみると、バカじゃない!?って言われそう」
学生時代は、プリントや色、レースなどにあまり興味はなかったのだが、だんだんそのよさもわかるようになった。ただし、Powderでは、自分を素に戻す意味で、モノトーンの作品を展開している。
「あんまり女、女してる服は嫌いです。何をセクシーというかは難しいし、着てる女の人にもよるけど」
スタッフは計4人、最低限でのスタートである。
「希望はやっぱり大きくなることだけど、いつも初心を思い出して、あまり勝手なことはしたくない」
ディスコが好きで、歳(?)のわりにはよく行くほう。ビール党。
コレクションとまではいかないが、帽子も好きで集めている。
Fashion Yearbook おしゃれ年鑑’88−’89秋冬編(1988年10月1日発行)より
| NEW! |
anan1989年8月18日号(687号)に掲載された文化服装学院の広告「小池千枝のファッショントーク 第76回」で、小池学院長(当時)と下迫さんが、5年ぶり、2度目の共演をしている。

「あなた、デザイナーでは誰が好きなの?」
いつになっても就職活動をスタートさせないので心配になった小池千枝学院長の問いかけに、その学生はピンクハウスの金子功さんだと答えた。学院長はその場で金子さんに連絡をとって、彼を採用してくれるよう頼み込み、その願いはかなえられた。
「金子さんは優しいから、きっと、断りきれなかったんでしょうね。いまだったら、とても無理なことですよ」
そして入社8年目の昨年、彼はピンクハウスの新ブランドであるパウダーをまかされるデザイナーへと成長した。下迫秀樹さんだ。
「いきなり机が金子さんと隣合わせだったんです。二人とも無口でしょ、ほとんど言葉を交わさない日々が半年くらい続きましたね。金子さんにしてみれば、何者なんだろう、この男っていう感じだったんじゃないですか」
笑いながら下迫さんは当時を振り返る。
”無言の行”の間、下迫さんはひたすら絵を描き続けた。絵がとてつもなく上手な金子さんに近づくためには、とにかくたくさん描くしか方法がないと考えたためだ。そうこうするうちに、
「そろそろ絵はたまった?」
と、金子さんが声をかけてくれるようになり、差し出した絵のなかから何点かが商品化され始めた。その際、ピックアップしたものに対して、金子さんは一切、手を加えなかったという。その人間の大きさを感じさせる話だ。
下迫さんが金子さんからファッションを学びつつ成長すると同時に、ピンクハウス自体も企業として飛躍的な成長を遂げていった。そうしたある日、仕事で大阪に出かけた金子さんは、下迫さんに次のように切り出した。
「6〜7年かけるつもりで、新しいブランドを手がけてみない?」
予想もしなかった話に、ありがたさを感じると同時に、正直、怖さも感じた。しかし、それが金子さんの言葉であったということが、下迫さんに決心を促した。ちょうど30才のときのことだ。そして、新ブランド設立の話が決まってからというもの、金子さんはよほどのことがない限り、下迫さんの部屋に足を踏みいれようとしなくなった。
「下迫は一本立ちしたんだから、あまり影響を与えないようにしようとしてくれたんだと思います」
「先輩と後輩とのこういう結びつきが、文化が誇る伝統のひとつなんですよ」
と、小池学院長はうれしそうに語る。
ピンクハウスの成長をその目で見てきた下迫さんは、小さな一粒の実を少しずつ育てていこう、そしてその感激をもう一度、味わおうと、新ブランド名をパウダーと決めた。
「僕は、真面目に服をつくることと、その大切さを金子さんから学びました。だから、このパウダーでも最初から最後まで手を抜くことなく、服づくりを進めていこうと考えています」
心身ともにリラックスできる服――それがパウダーだ。しかし、それを生み出しているデザイナーは、残念ながら現在のところ、リラックスからは程遠い状態のようだ。
「そういえば、このブランドがスタートして以来、服のことばっかりを考え続けてますね。好きな映画もなかなか観にいけないし。でも……」
でも、それを苦痛に感じたことはない。数多くいるファッションデザイナーのなかで、ブランドをまかせてもらえるデザイナーはごく少数だ。その一人になれたのだし、それよりもなにも、僕はこの仕事が本当に好きなのだから。
穏やかな口調のなかに、ファッションにかける情熱とひたむきさを感じさせる下迫さん。その活躍を期待しよう。